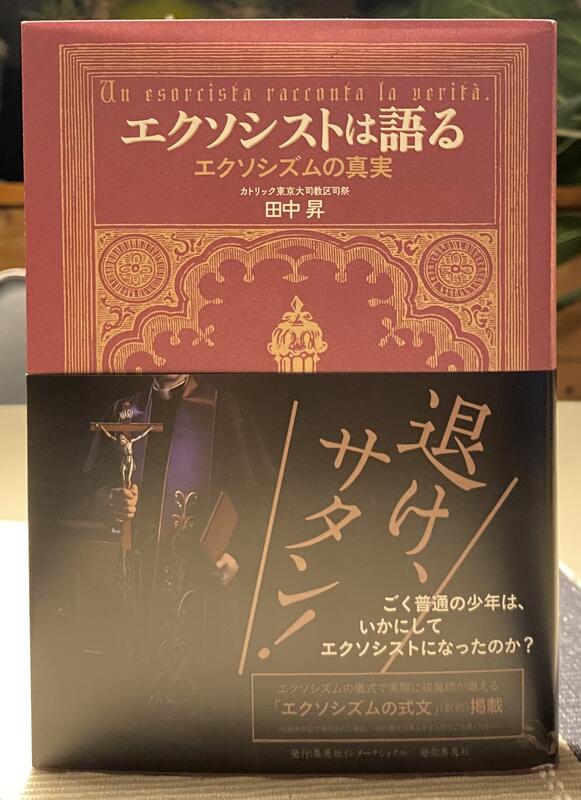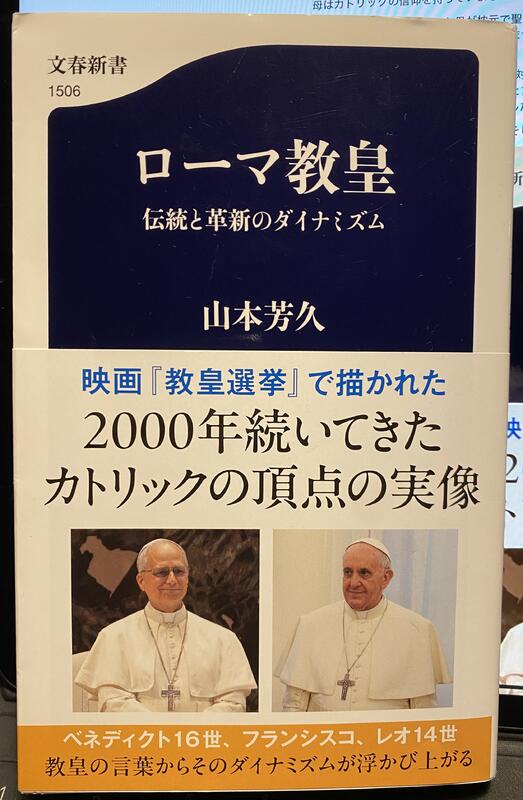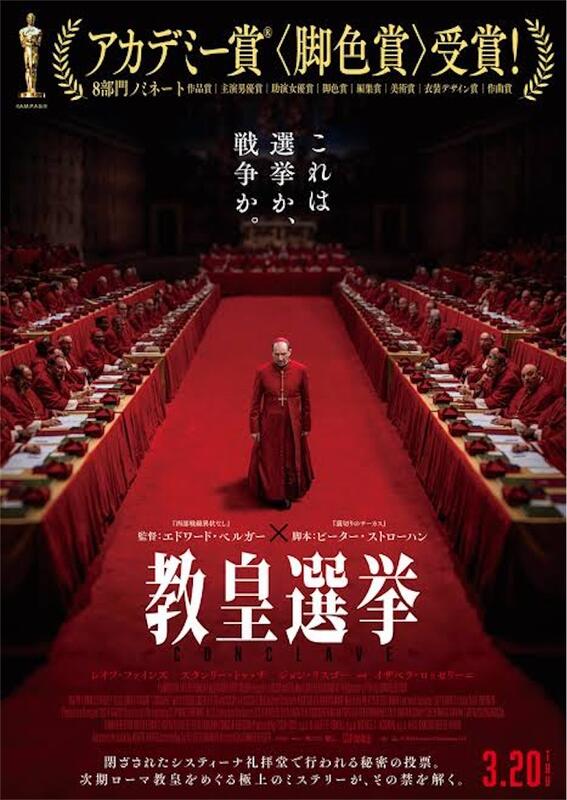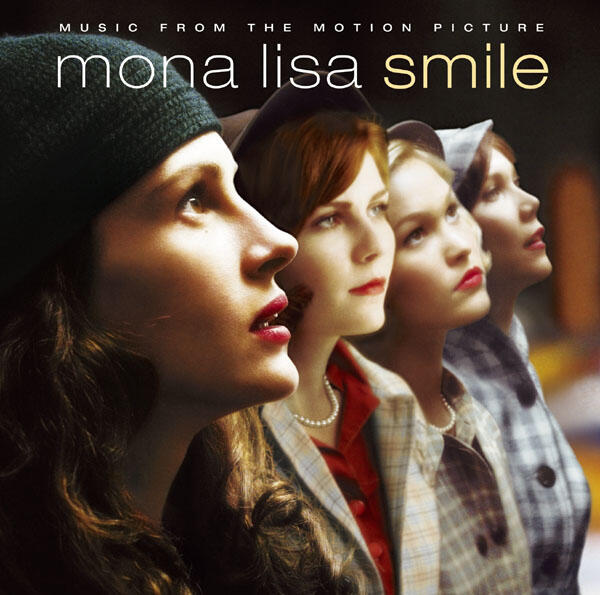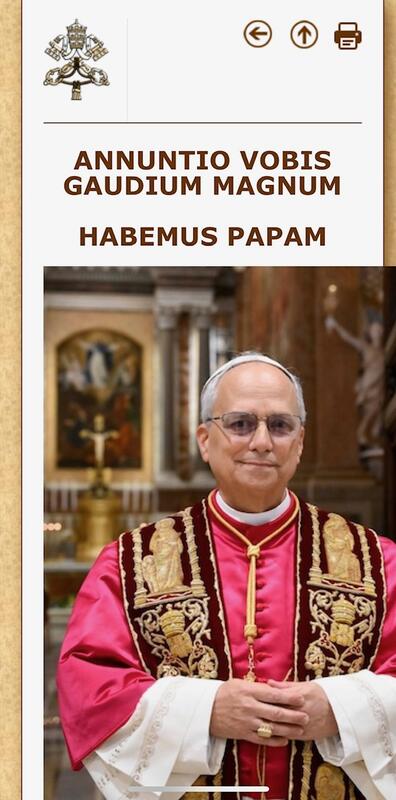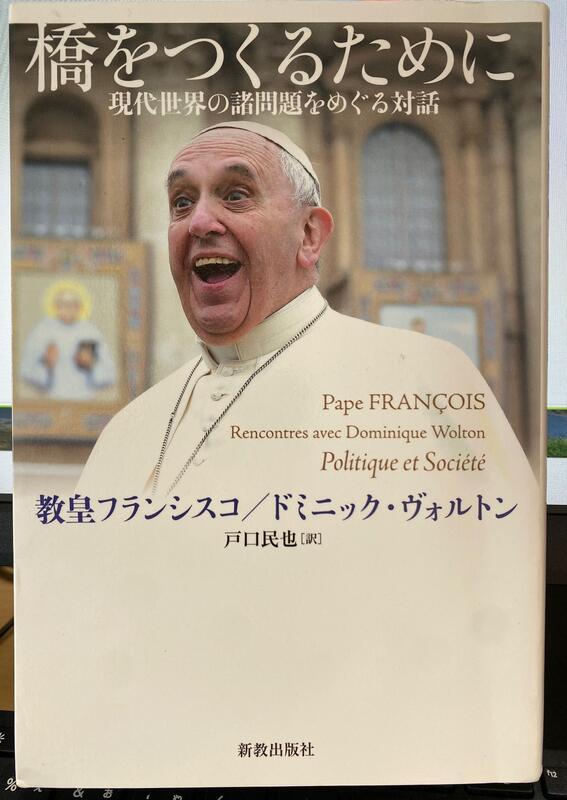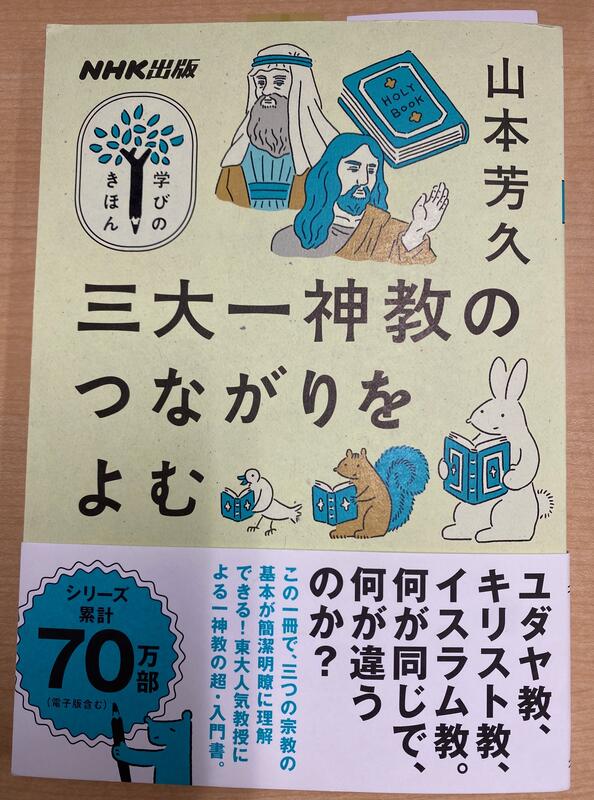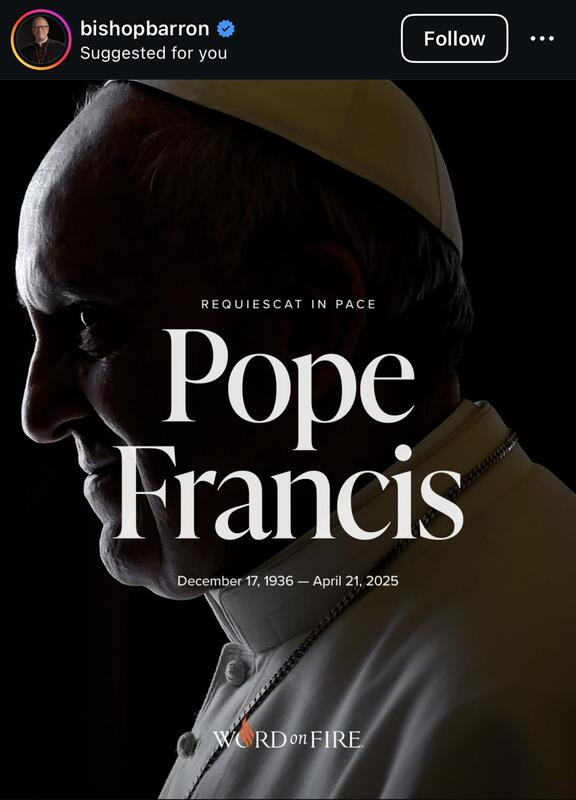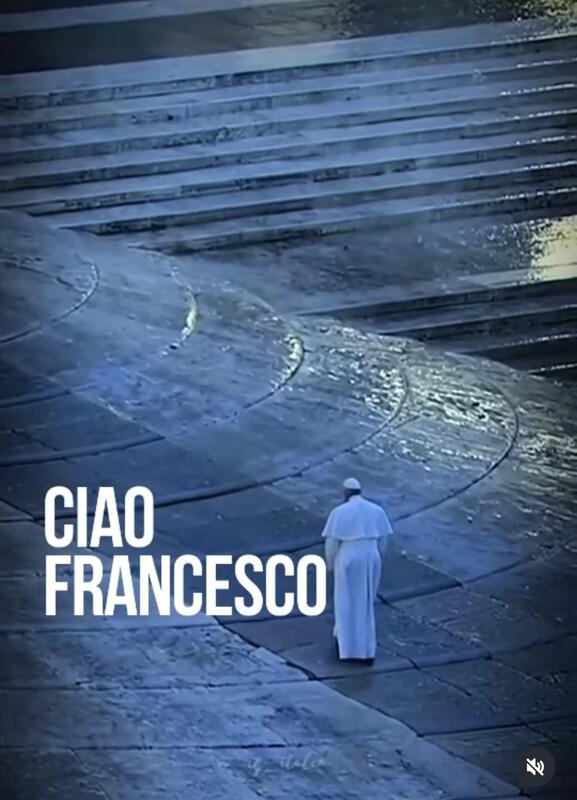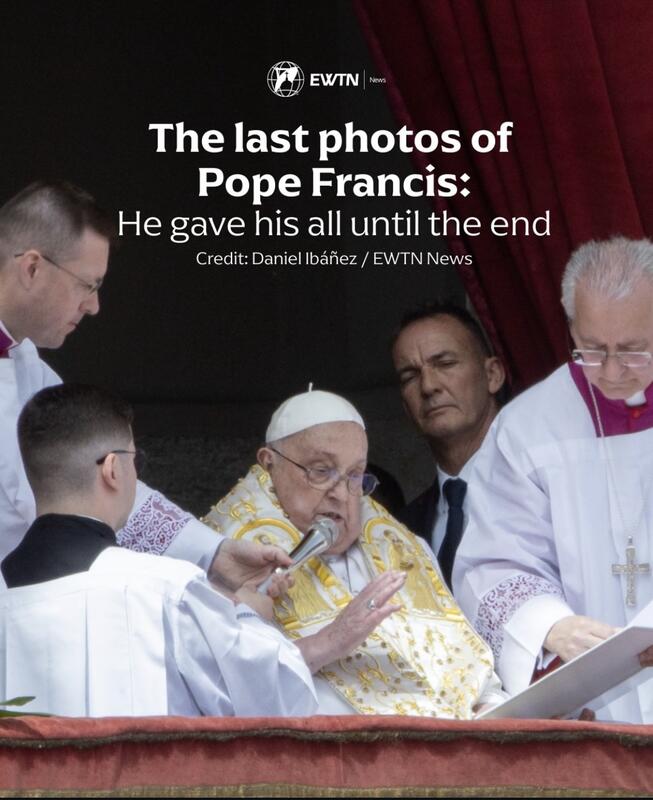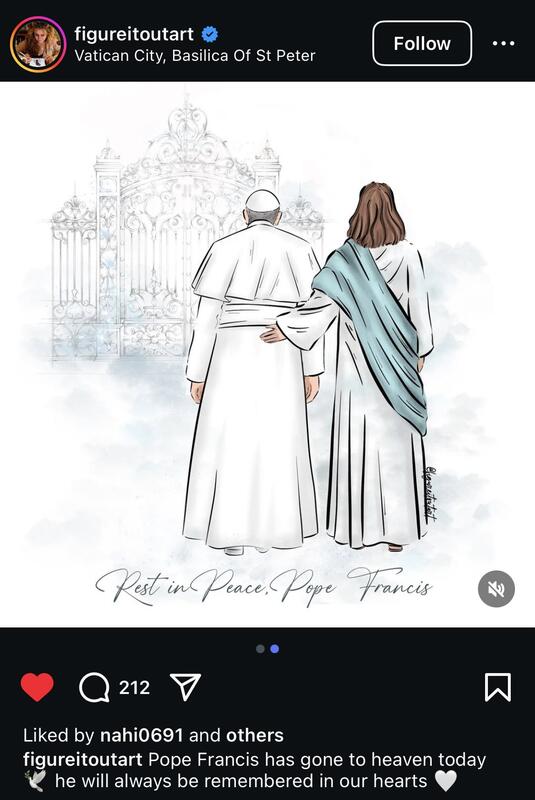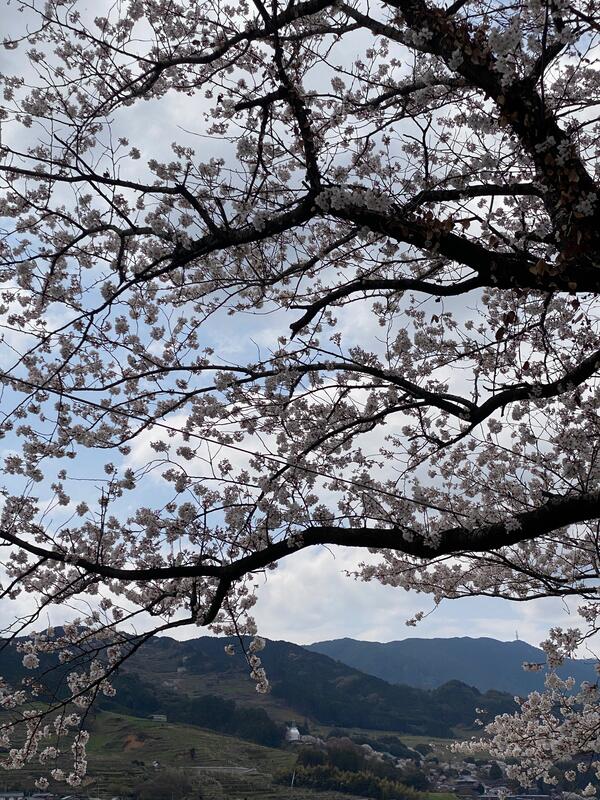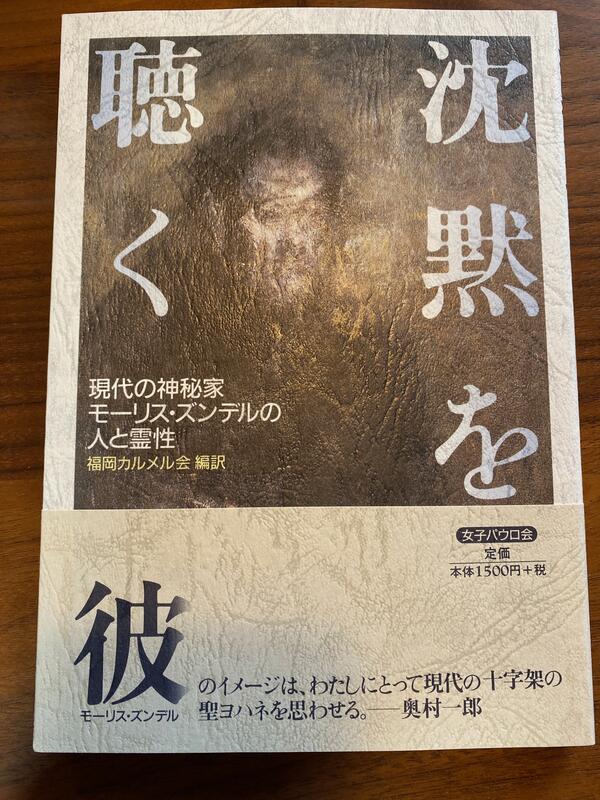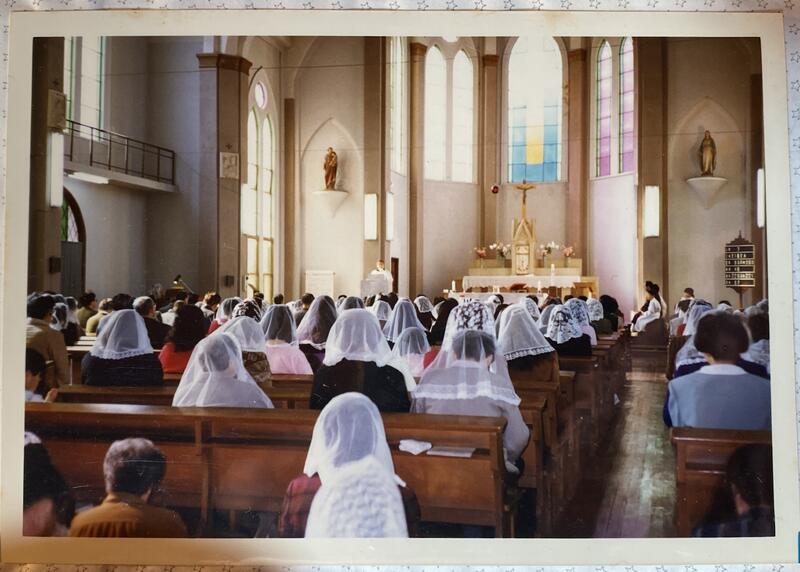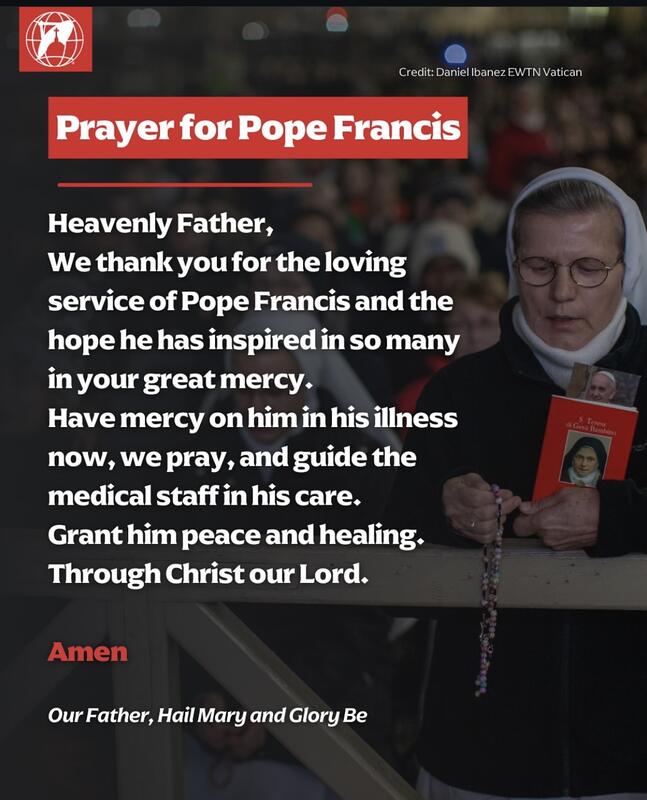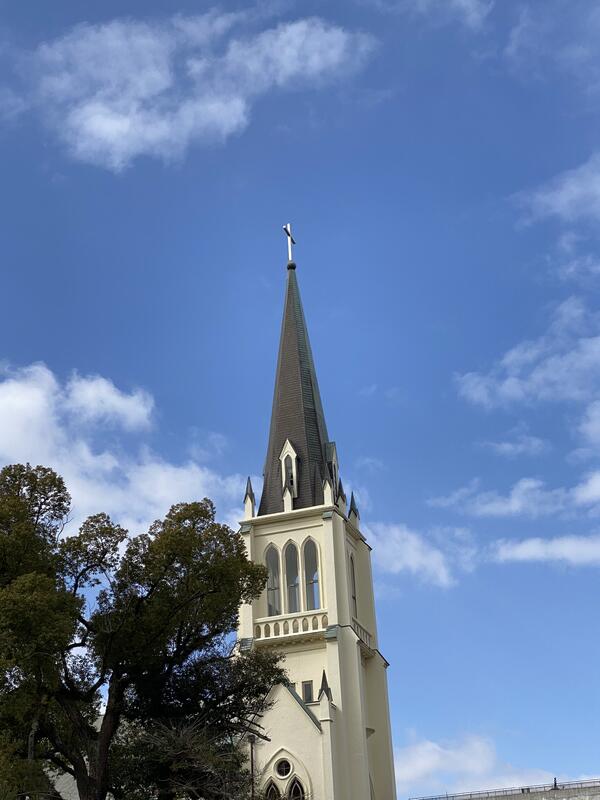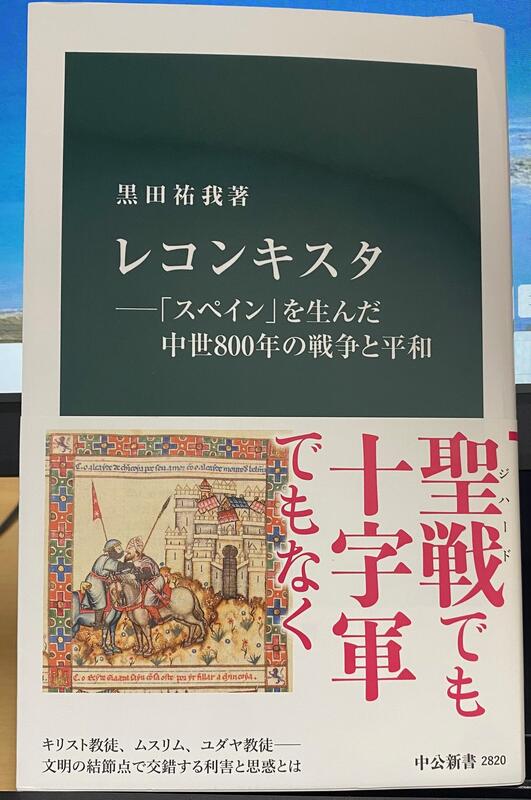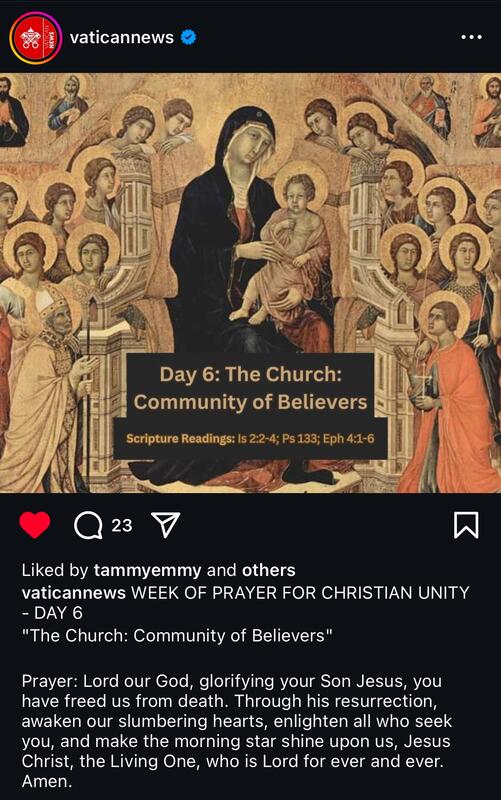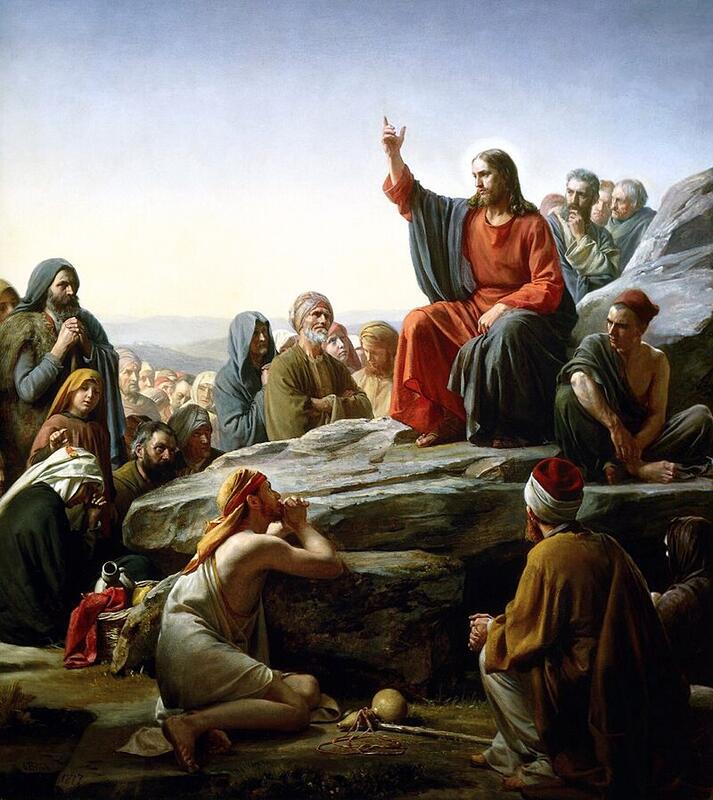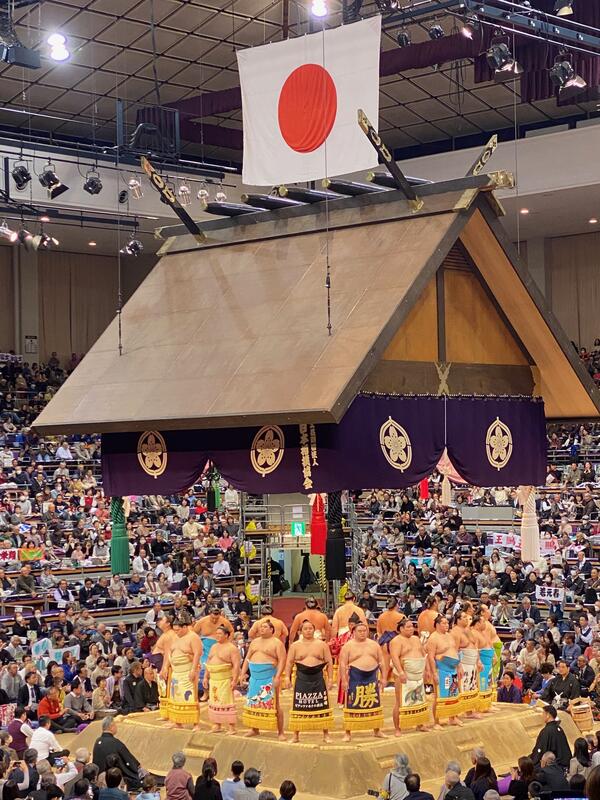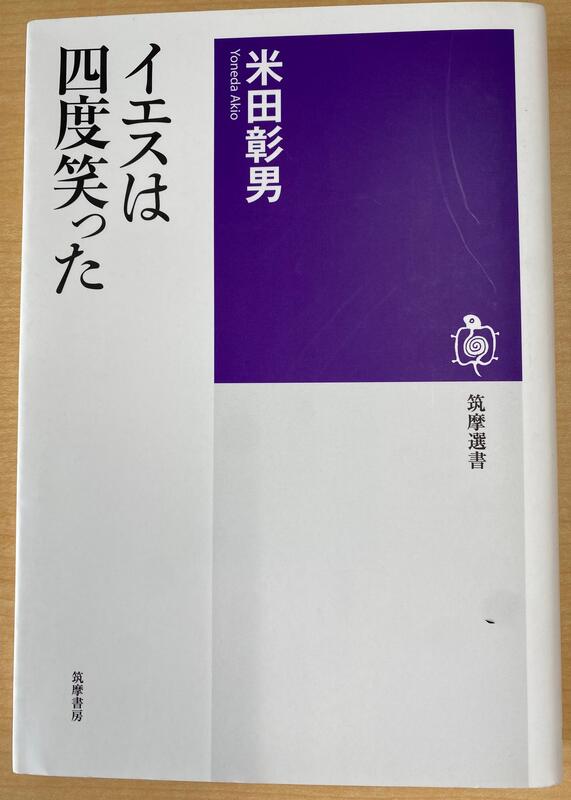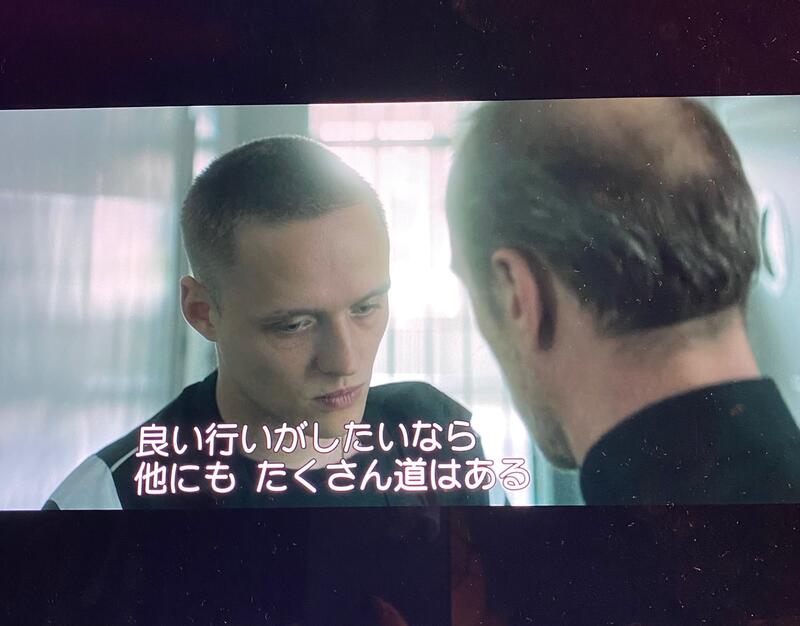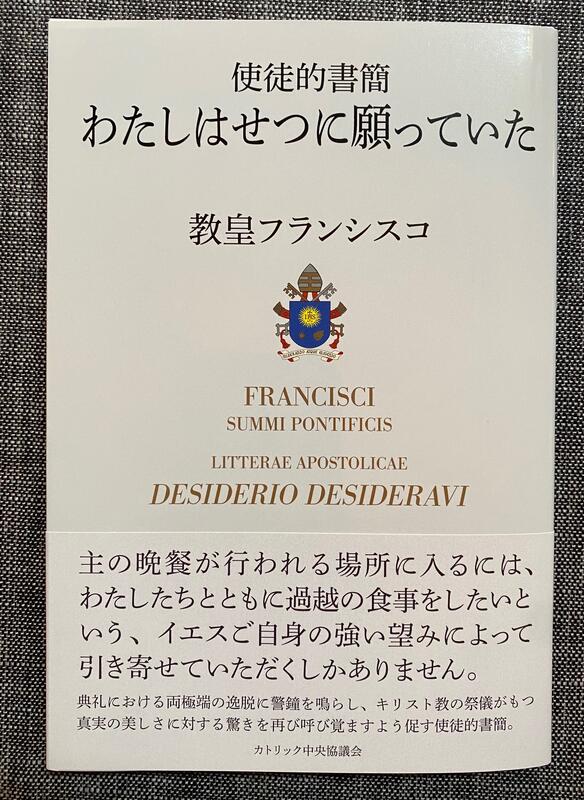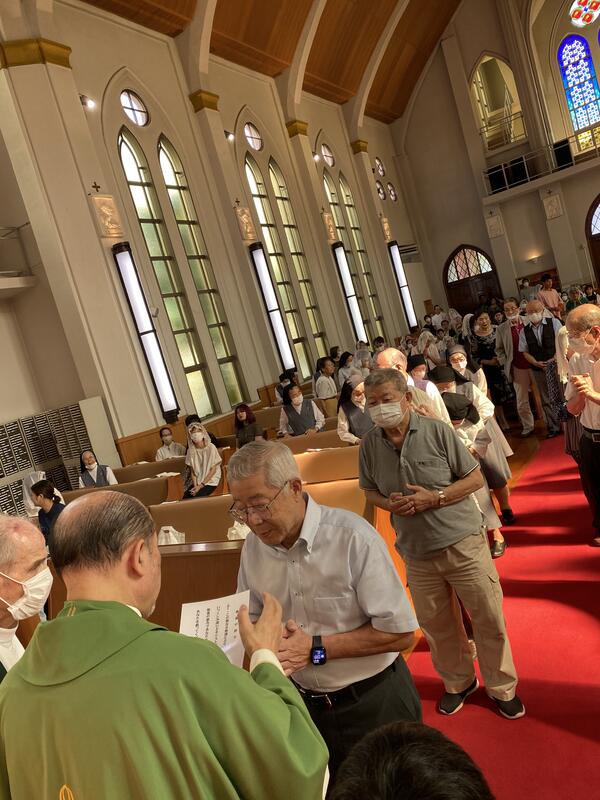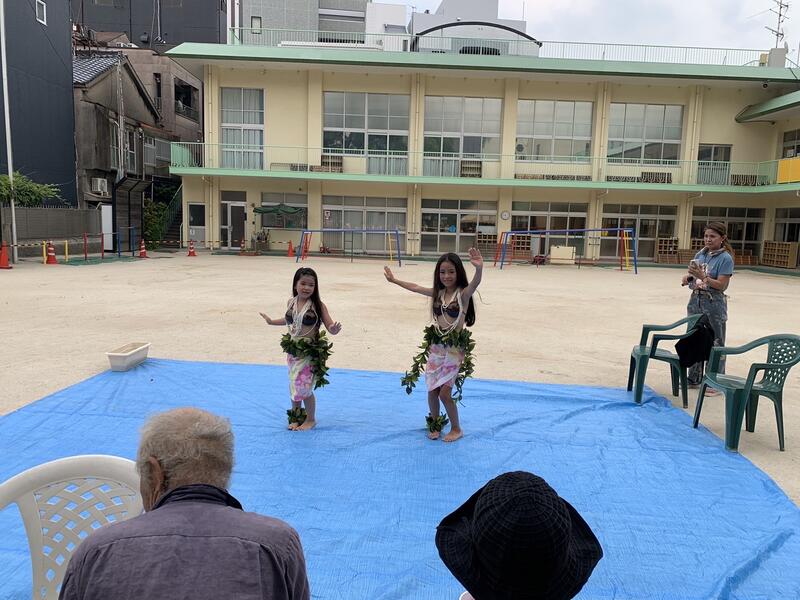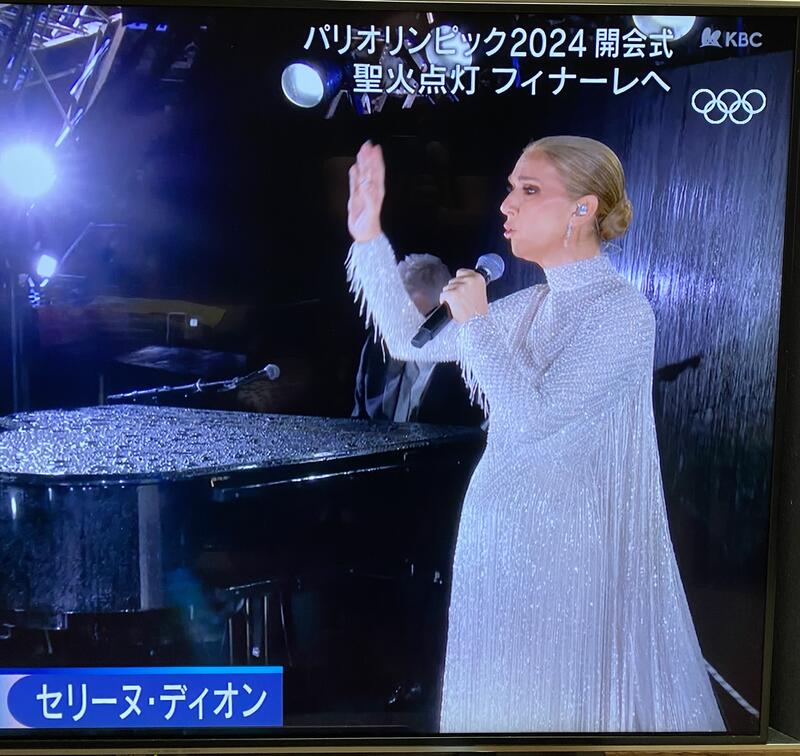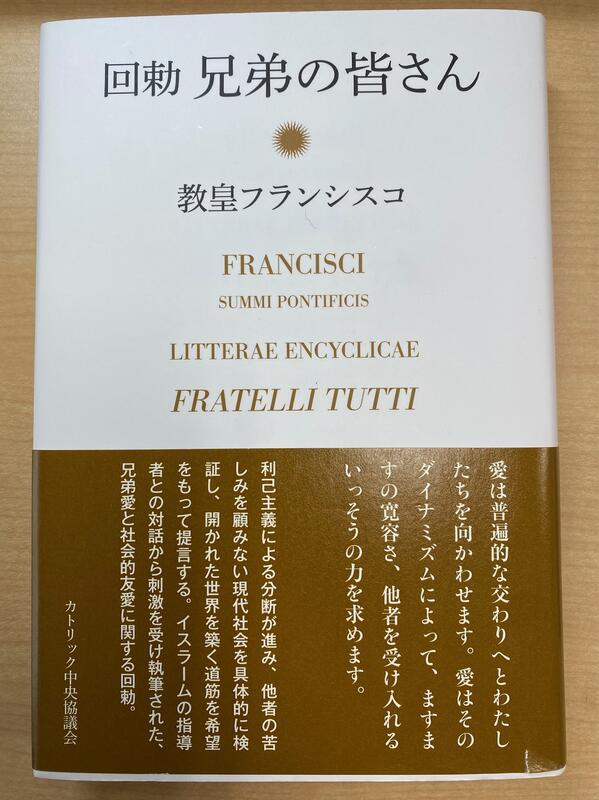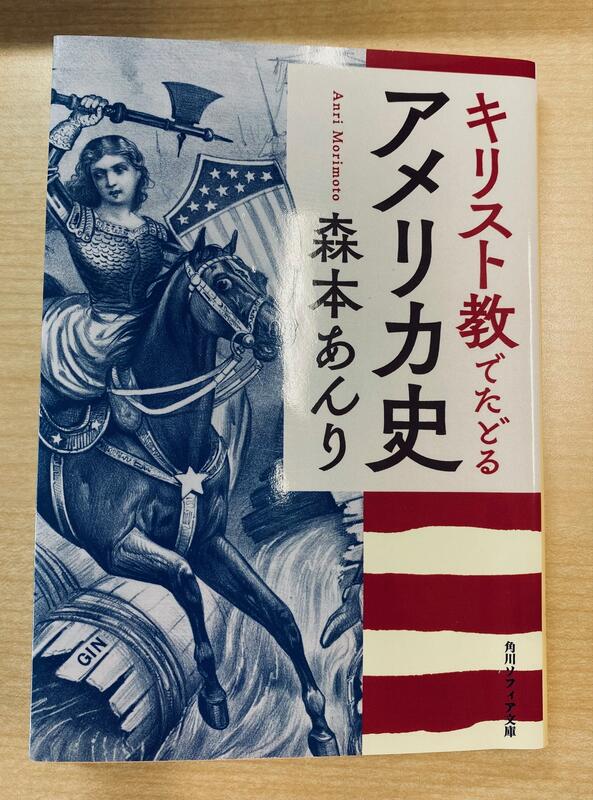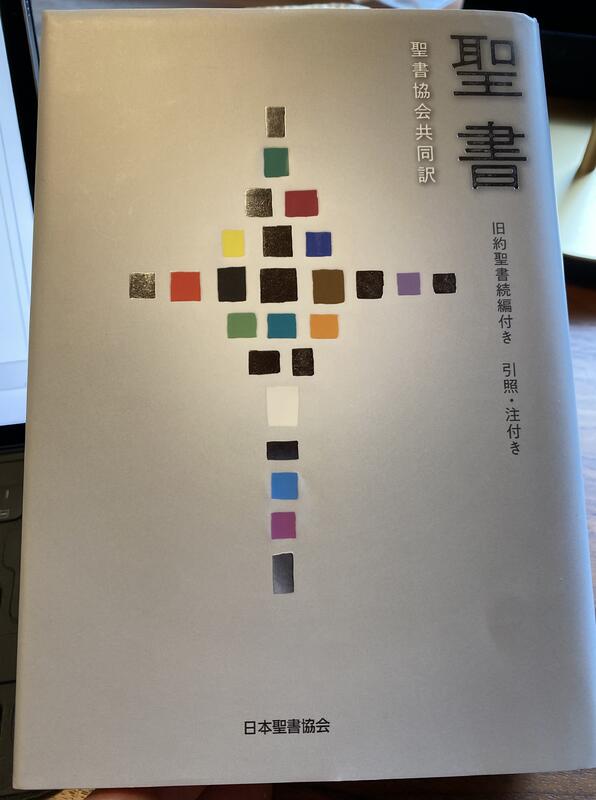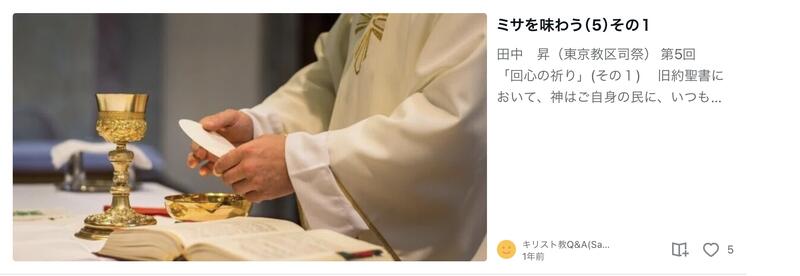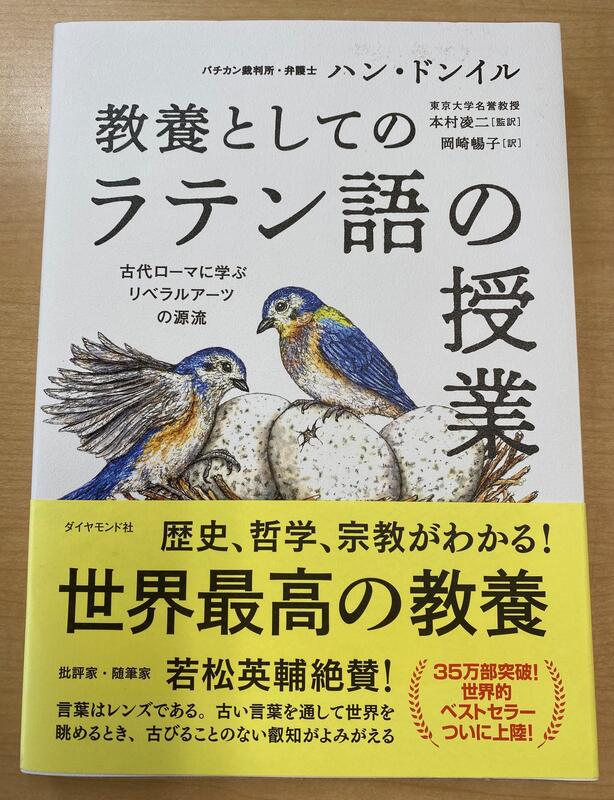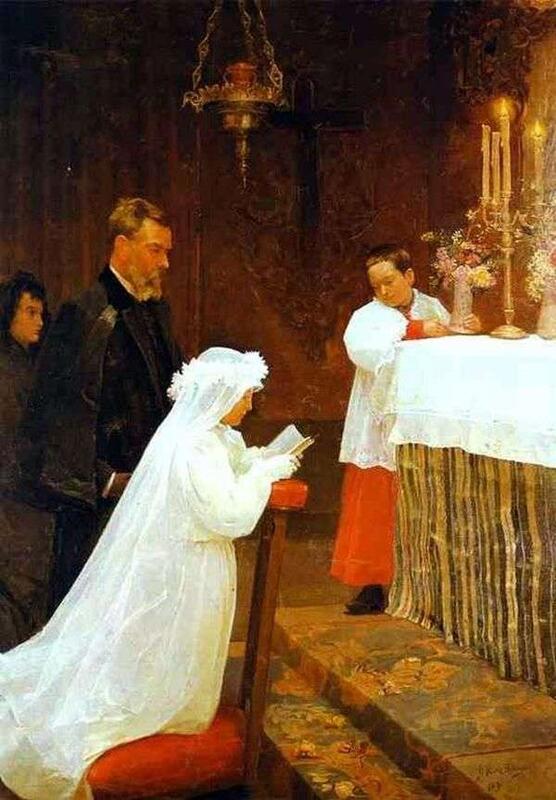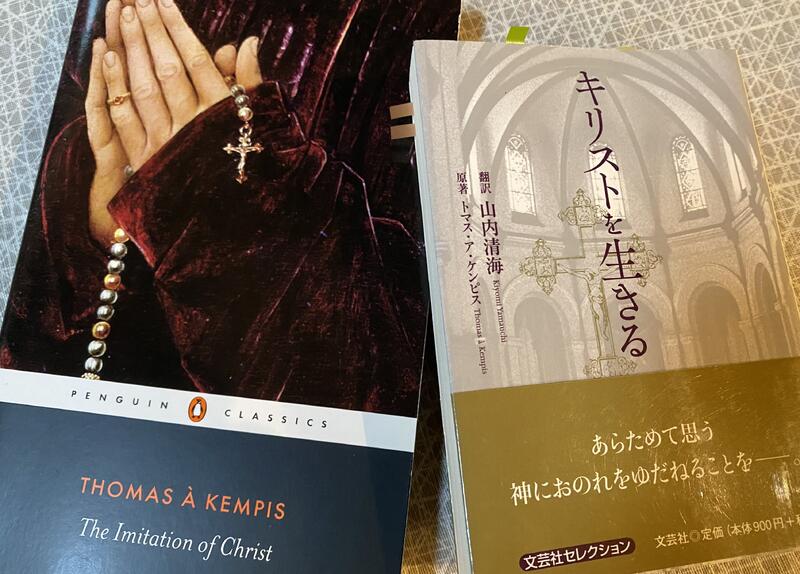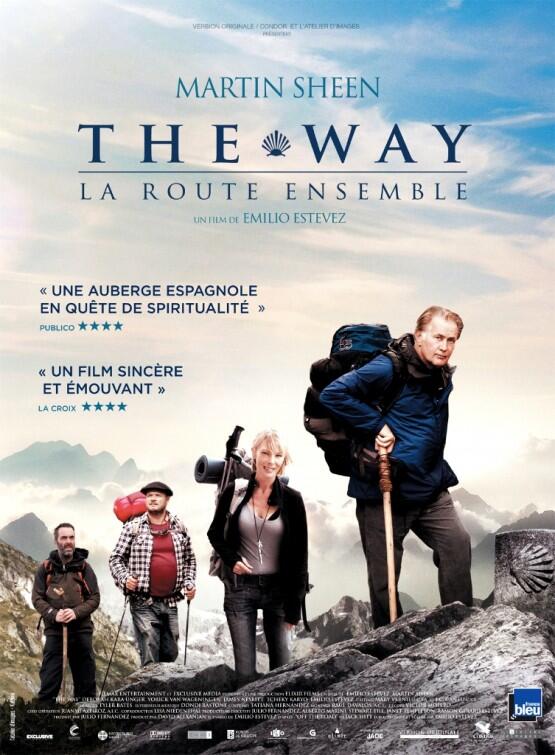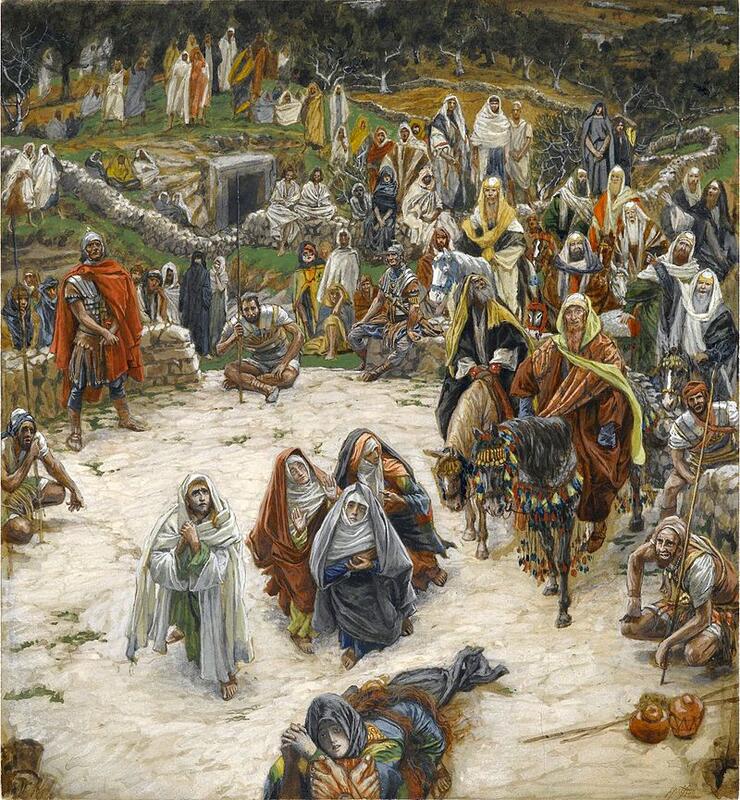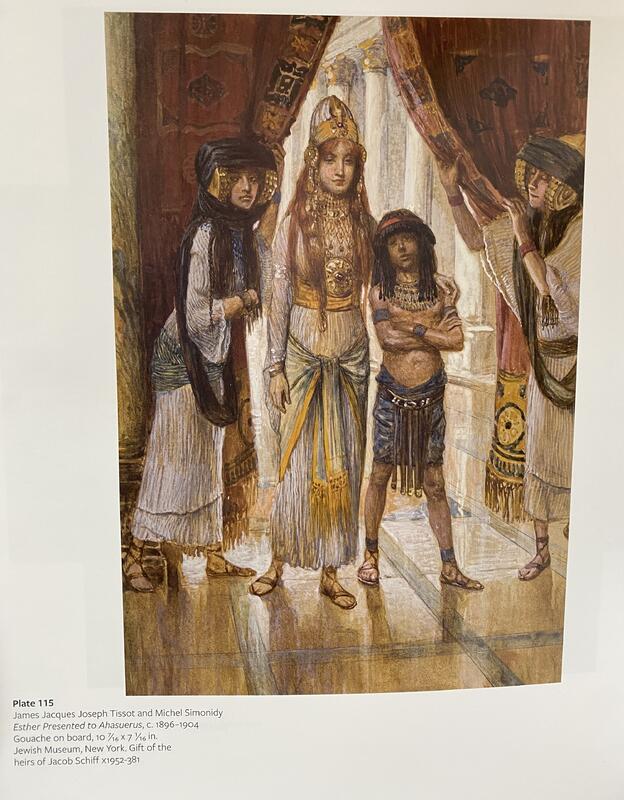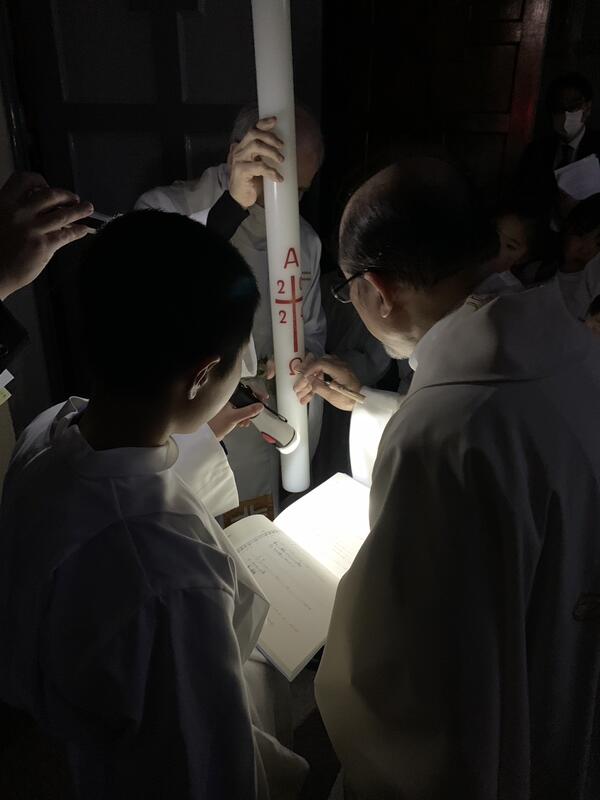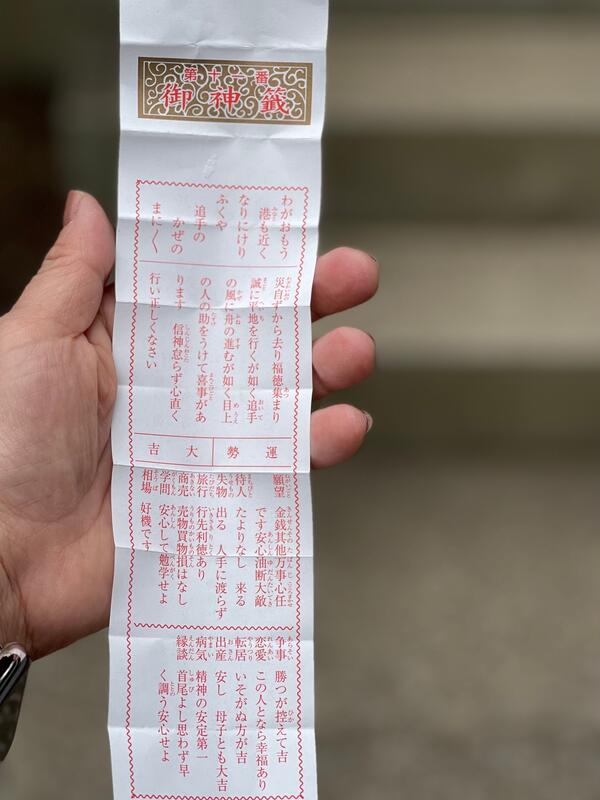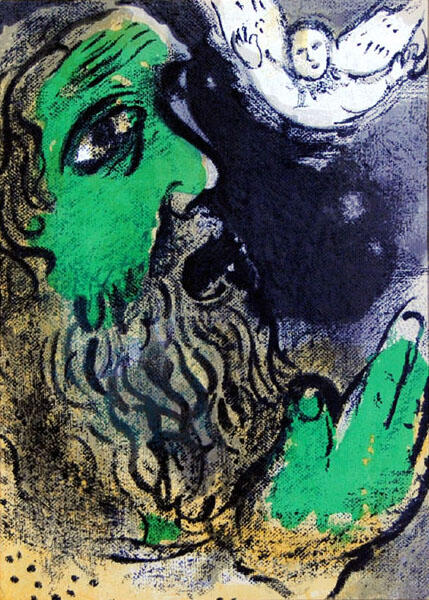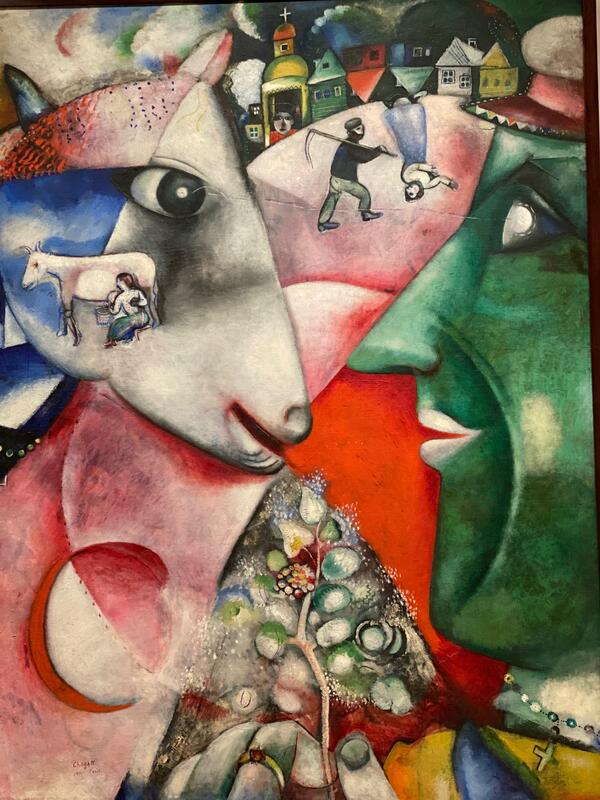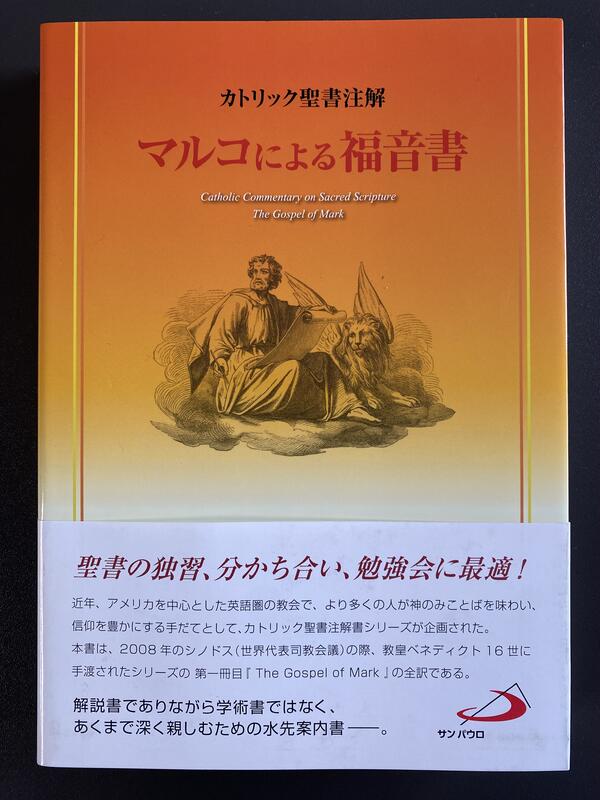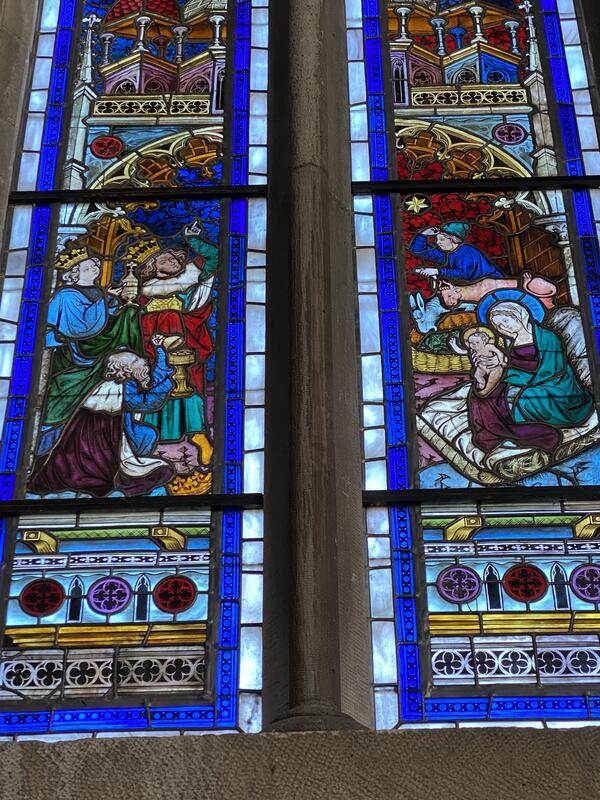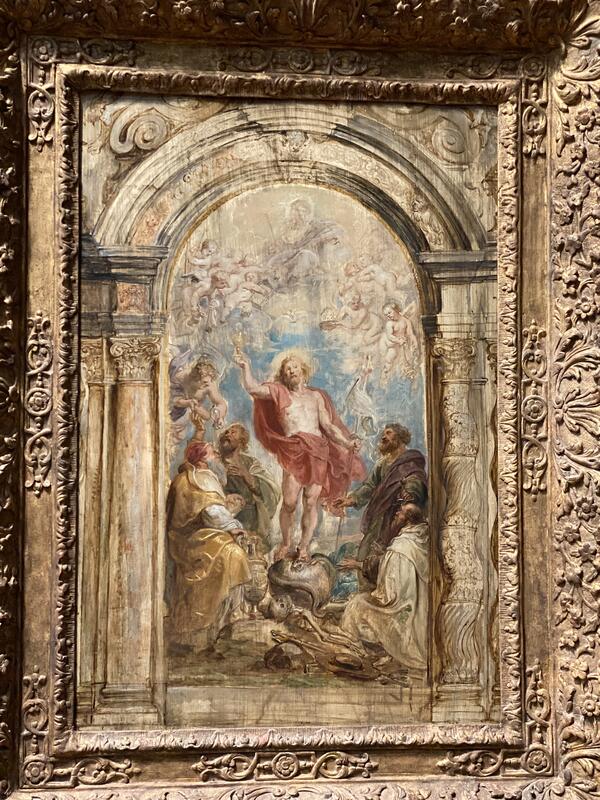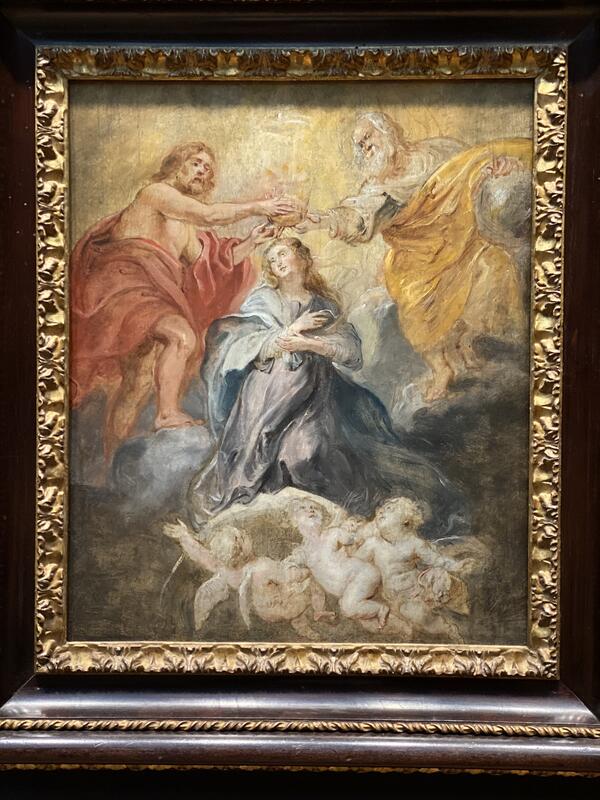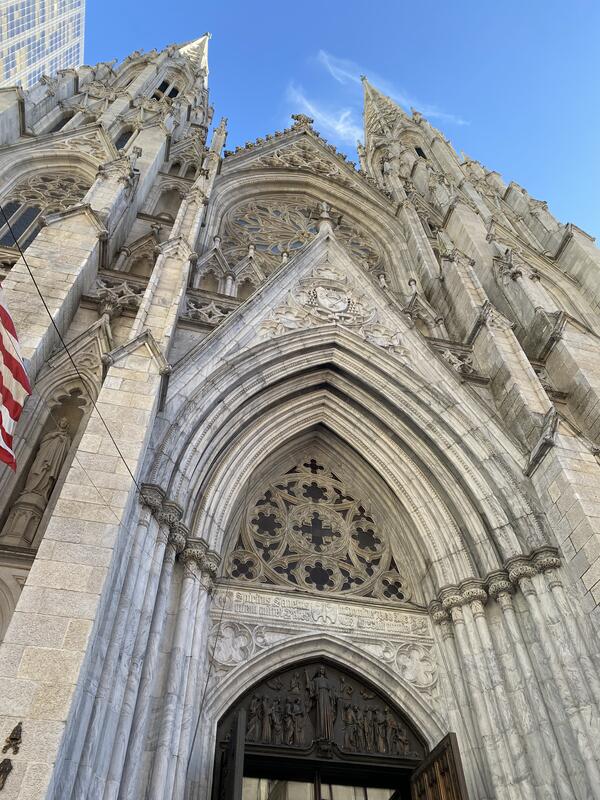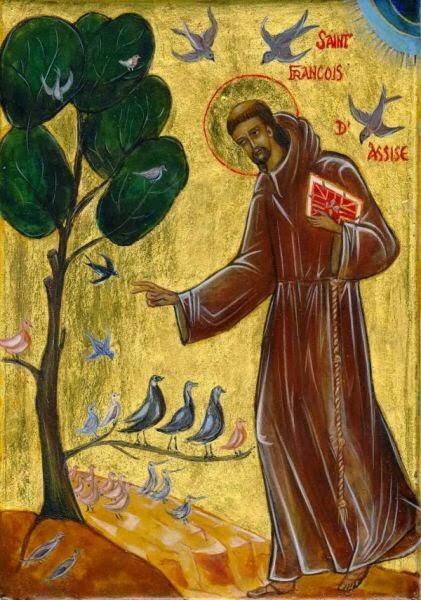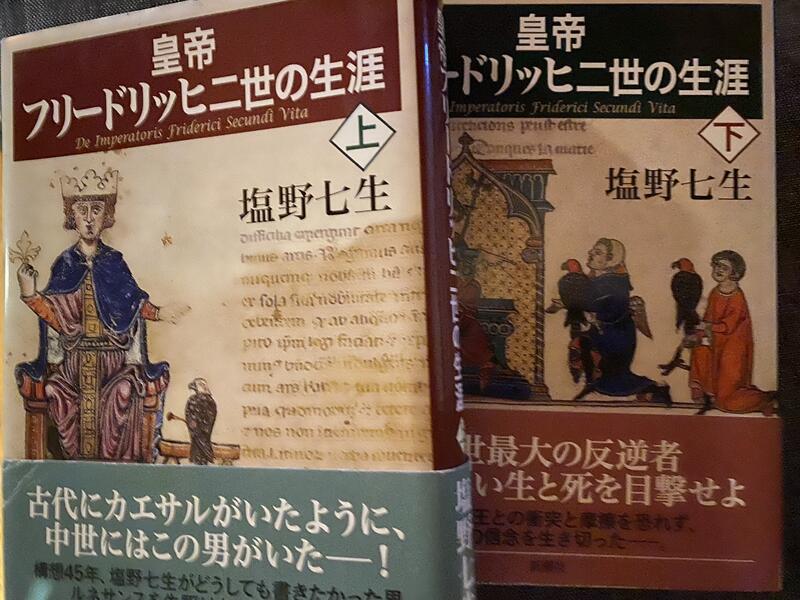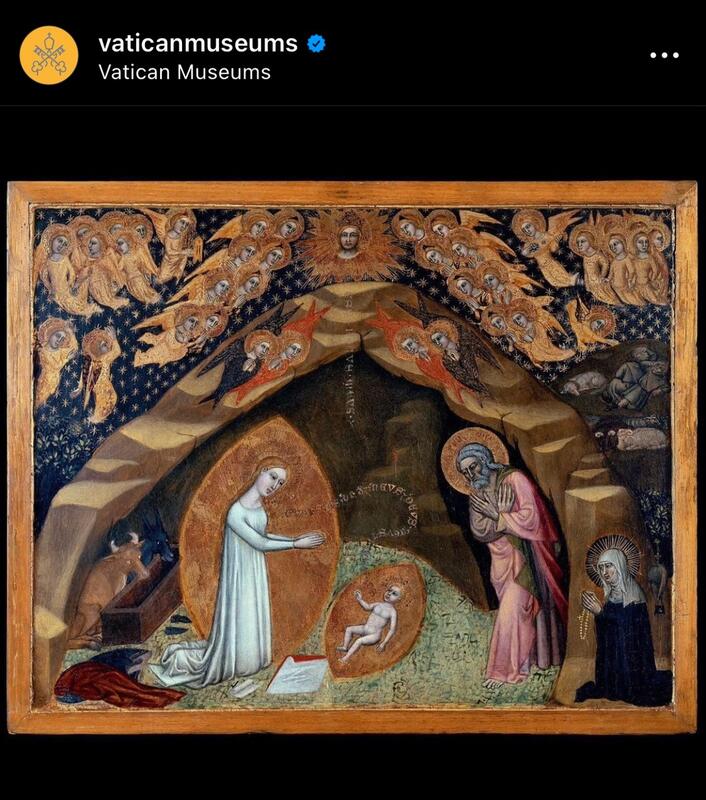行事風景
生きる者のための祈り
11/2死者の日が主日と重なりました。
宮﨑神父様がおっしゃった、「今日は自分の死について考える日でもあります」というお言葉が心にこだましています。
死者の月、自分を大切にしてくれていた方々のために祈るよう推奨されますが、今年はいつもと少し違う気持ちです。
11月になると、アウグスティヌスの「告白」のこの個所を読み返します。
おそらく、以前記事にしたことがあるのですが、それは母モニカの死に際の箇所です。
「わが子よ、私はといえば、この世の中にもう自分をよろこばせるものは何もない。
この世でまだ何をすべきか、何のためにこの世にいなければならないか、知らない。
この世ののぞみはもう十分にはたしてしまったのですもの。
この世にまだしばらく生きていたいとのぞんでいた一つのことがありました、それは死ぬ前に、カトリックのキリスト者になったおまえを見たいということだった。
神さまはこの願いを十分にかなえてくださった。
おまえが地上の幸福をすてて、神さまのしもべとなったすがたまで私は見たのだもの。
もうこの世の中で何をすることがありましょう。」
(「告白」第9巻第10章)
「このからだはどこにでも好きなところに葬っておくれ。
そんなことに心をわずらわさないでおくれ。
ただ一つ、お願いがある。
どこにいようとも、主の祭壇のもとで私を想い出しておくれ。」
(「告白」第9巻第11章)
この場面には、いつも胸が熱くなります。
「告白」を初めて読んだのは、10数年前だったと思います。
当時、母を亡くし、日々の暮らしや会社のことで途方に暮れていたわたしは、母の死について神様が与えられた意味を模索していました。
そしてしばらくして、モニカのように、自分たちの死について妹たちと話すようになりました。
決して悲観的な意味合いからではなく、モニカと同じ気持ちだということをお互いに語り合いました。
父とわたしたち3姉妹は、いつも天国の母に心配をかけるような人生です。
でも、本当に聞こえるのです、母がどっしり構えてこう言っているのを。
「神様のお導きを信じなさい、大丈夫だから」
人は常に死者を心にとめ、自らの関心と気遣いと愛情を通して、彼らにいわば第二のいのちを与えようと努めます。
わたしたちはある意味で彼らの人生経験を残そうと努めます。
そして、わたしたちは逆説的にも、彼らがどう生き、何を愛し、何を恐れ、何を望み、何を憎んだかを、まさに墓地に集まって彼らを記念するときに見いだします。
墓地を訪れて、亡くなった愛する人々のために愛情と愛をこめて祈るとき、永遠のいのちへの信仰を勇気と力をもって更新するよう招かれます。
そればかりか、この偉大な希望をもって生き、世にこの偉大な希望をあかしするよう招かれます。
これは、故ベネディクト16世のお説教でのお言葉の一部です。
モニカを亡き父の傍らに葬りたいと考えていたアウグスティヌスの気持ちは、母のためというよりも、「そうしてあげたい」という息子の愛の気持ちでした。
そして彼は、母の死に際して、彼女の生き方や愛、希望などについて思いを馳せる機会を与えられたのです。
死者のために祈ることは、生きる者のために祈っていることなのだ、と感じています。
死者の月にいつも以上に自分の死について考えています。
そして、それはすなわち、生かされている今をいかに大切にするか、ということだと痛感するのです。
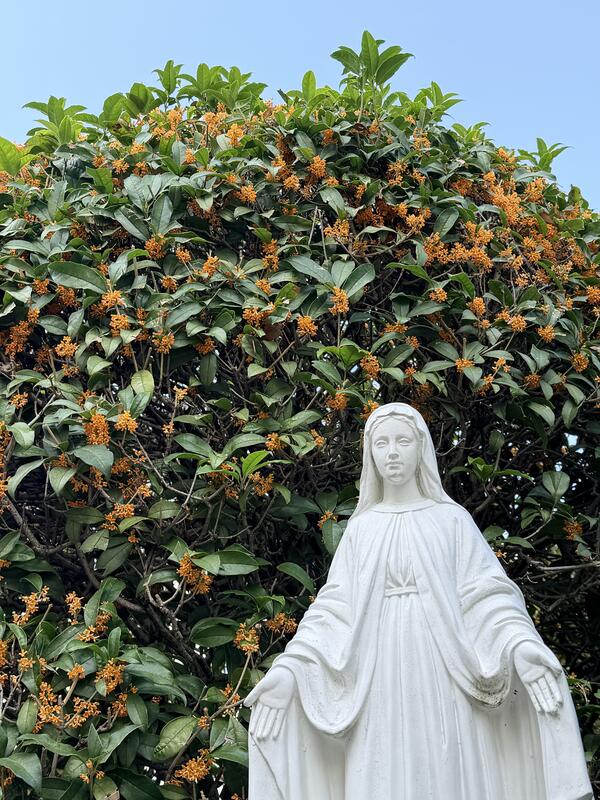
ヨハネのように
チンパンジーが道具を作り・使うことを発見した動物行動学の権威であり、自然環境の保護と次世代教育の重要性を説き世界中を飛び回り続けた女性、ジェーン・グドール博士が10/1に91歳で亡くなりました。
しなやかな強さ、決して諦めない精神、寛大さ、ユーモアを持ち合わせた人でした。
.
「誰にとっても不可能に見えることでも、諦めて受け入れるより戦っていたい」
「どうせ変わらない」と諦めるのではなく、「きっと変えられる」と信じて「行動する」こと。
「希望」が人々を動かし、団結させ、未来を変える。
上記の3つの言葉は、グドール博士のお考えを象徴するものです。
特に環境破壊が人間にもたらしている現状について、嘆くのではなく行動する必要について繰り返し講演で世界中に訴えておられました。
講演活動のために滞在していたホテルの部屋で静かに息を引き取られるまで、行動し、諦めずに希望を伝え続けていたのです。
わたしが大学に入学したころ、環境問題がさかんにクローズアップされ始めていました。
世界的な環境問題のNGOの日本支部のひとつの事務所に、18歳のわたしはボランティアとして足を運んでいました。
ある時、その団体の船が日本の船(捕鯨船だったと記憶していますが)にわざと体当たりして進路妨害したことがニュースになっていました。
わたしは「なぜあのような行動に出たのでしょうか、船が壊れて重油が漏れ出すほうが問題なのではないでしょうか」と質問してみたところ、「あれくらい強硬な手段を取らないと問題解決は前に進まないからね」との返答でした。
疑問と不安を抱いたわたしは、それ以来、お手伝いには行かなくなりました。
当時は、「あの団体のやり方はおかしい」と不満でしたが、その後環境問題について何も行動せずに諦めてしまった自分を、今は恥じています。
光は暗闇の中で輝いている。
暗闇は光に打ち勝たなかった。
神から遣わされた人がいた。その名はヨハネである。
この人は証しをするために来た。
光について証しをし、彼によってすべての人が信じるようになるためである。
彼は光ではなかった。
光について証しをするために来た。
すべての人を照らすまことの光はこの世に来た。
(ヨハネ1・5~9)
今に至るまで、その時代に必要な光(存在)が常に輝いてきました。
彼女もそのお一人だったと思います。
インタビュー動画『FAMOUS LAST WORD』がNetflixで配信されています。
「私たちは自然の一部であり、地球が暗い時でも希望が存在する」
「闇の時代に生きるわれわれには、希望がなければならない」
「闇の時代に希望の光をともすために、わたしはこの世に遣わされたと思っている」
彼女の言葉が胸を打ちまます。
このインタビューを観て思いました、彼女は現代のヨハネのようだわ、と。
わたしたちは、夜道を照らす月のように、他者を導くことができます。
迷っている友人、困っている隣人に寄り添うことができます。
イエス様と言う光で照らされたわたしたちは、その光を外に向けて生きるのです。
わたしを知りたもう者よ、御身を知らしめたまえ。
わたしが御身に知られているように、御身をわたしに知らしめたまえ。
わが魂の力よ。魂のうちにはいれ。
この魂を御身にふさわしきものとなし、御身がそれを汚れなく皴なく保ちうるようにせよ。
それこそはわが希望(のぞみ)。
そのためにこそわたしは語り、すこやかなよろこびをもってよろこぶとき、わたしはいつもその希望においてよろこぶ。
(アウグスティヌス「告白」第十巻 第一章)
わたしたち一人ひとりが、誰かにとっての希望、社会の中の小さな希望、家族の大きな光であり続けますように。
グドール博士について知るには、↓この記事がお薦めです。
https://www.vogue.co.jp/fashion/article/jane-goodall-the-book-of-hope
+++++++++++++++++
26日のミサの中で、4名の幼児洗礼式が行われました。
この子たちは、わたしたちの希望の象徴です。
本音の信仰
宮﨑神父様はよくお説教で、「行いの伴わない信仰」について喝を入れてくださいます。
『本音と建て前』を使い分けて隣人と関わっていないか、今一度よく考えてみなさい、と先日お話されました。
誰にでも「苦手な人」がいるかと思います。
以前、意見の食い違いがあり、わたしが一方的に嫌な気持ちになった人がいました。
それ以来、苦手な人だわと思っていた方と先日お会いする機会があったのですが、会ってすぐに「義足の調子が悪いですか?歩き方が前よりも悪くなっていませんか?」と声をかけてくださったのです。
あなたが馬鹿にされるとき、それは風となるのです。
あなたが怒るとき、それは波となるのです、
だから風が吹き、波が高まるとき、舟は危険に陥り、あなたの心は危険にさらされ、あなたの心は行ったり来たり激しく揺さぶられるのです。
馬鹿にされると、あなたは仕返しをしたいと思います。
しかし復讐は、難破という別の種類の災難をもたらします。
なぜでしょうか。
なぜなら、キリストはあなたの内で眠ったままだからです。
私は、あなたがキリストを忘れているということを言っているのです。
だから、キリストを目覚めさせなさい。キリストを思い出しなさい。
キリストをあなたの内に目覚めさせなさい。
キリストを心に留めなさい。
この方は一体どなたですか。風や波さえも彼に従うそのお方とは。
(アウグスティヌス『説教』より)
偶然、読んでいた本でこの箇所が目に留まりました。
(先週のyoutubeのビデオもそうですが、いつもこうして求めているものが与えられるのです!)
声をかけてくださったこともですし、わたしの足のことを以前から気にかけてくださっていたこと、その変化に気づいてくださったこと、とても嬉しかったのです。
建て前で信徒としてのお付き合いをしていくのは嫌でしたので、帰り際に話しかけて、いろいろとお話してみました。
いまさらながら(当然のことだったのですが)、わたしは馬鹿にされていたわけではないと分かり恥ずかしくなりました。
「言葉は、あなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある」。
これは、わたしたちが宣べ伝えている信仰を生み出す言葉です。
口で、イエスは主であると宣言し、心で、神はイエスを死者の中から復活させたことを信じるなら、あなたは救われるからです。
人は心で信じることによって義とされ、口で宣言することによって救われるのです。
(ローマの信徒への手紙10・8~10)
キリスト者であると自負し、毎週主日のミサに与っていたとしても、言葉と生き方に信仰が現れていないことが往々にしてあるのではないでしょうか。
言葉や行動に信仰がついていかない場合もあります。
クリスチャンらしい振る舞いはできても、心がそこに伴わないのです。
ミサ中に「主の平和」と笑顔で周囲とあいさつを交わすとき、本音で本心からそうしていますか?
福音書朗読の際に額・口・胸で十字をきるとき、頭と言動で福音書を賛美することは本音ですか?
「わが愛する子らよ、わたしは主においてあなたがたに挨拶を送る。
わたしは主に祈り求める。
主があなたがたをすべての災いから守ってくださるように。
主が、ヨブのような忍耐と、ヨセフのような恵みと、モーセのような優しさと、ヌンの子ヨシュアのような戦いにおける勇気と、士師たちのような優れた知識と、ダビデ王とソロモン王のような敵を屈服させる力と、イスラエルの民のような地に実りをもたらす力を、あなたがたに与えてくださるように。
主が、手足の萎えた体をいやしてくださったように、あなたがたのすべての罪をゆるしてくださるように。
主が、ペトロにしたようにあなたがたを荒波から助け、パウロや使徒たちにしたようにあなたがたを苦難から救い出してくださるように。
主があなたがたを、主のまことの子として、すべての災いから守ってくださるように。
そして、そのみ名によって、魂と体の益となるために、あなたがたが心から求めるものを与えてくださるように。アーメン」
ガザのバルサヌフィオス(パレスチナのバルサヌフィオスとも表記される)は6世紀に生きた隠者で、ガザの修道院の院長でした。
識別の知恵に優れていたので、修道士や聖職者、信徒が教えを乞うために訪れました。
上記の祈りは、ある一人の修道士が自分と仲間のために祈ってくれるように、バルサヌフィオスに願った際の答えです。
人のためにこのような気持ちで祈ることができるか、立ち止まって考えさせられる祈りのことばです。
天国はどこにあるか
10/19は世界宣教の日となっています。
日本の守護聖人であるフランシスコザビエル。
来航を記念して、大分市の遊歩公園内に建立された像です。
左手に十字架を持ち、右手を掲げたザビエルの像で、彫刻家佐藤忠良氏による1969年(昭和44年)の作品です。
背後には、世界地図のレリーフにザビエルのヨーロッパから日本にいたる航路を描き込んだモニュメントも設置されていました。
1549年に鹿児島に上陸したザビエルは、1551年に日本での宣教の許可を正式に「日本国王」からもらうために京へ赴きます。
天皇への拝謁は許可されず、山口へと退きます。
豊後国府内(現在の大分県大分市)にポルトガル船が来着したとの話を聞きつけたザビエルは、山口での宣教をトーレスに託し、1551年9月に豊後国に到着して守護大名・大友義鎮(後の宗麟)に迎えられ、その保護を受けて宣教活動をしました。
ザビエルの「山口問答」という出来事について知りました。
ザビエルが来日した1549年当時の神学では、「洗礼を受けていない人は天国に行けない」とされていました。
ある時、山口で宣教していたザビエルは、信者たちに「私たちの先祖は救われますか?」と聞かれました。
その質問に対してザビエルは、「救われない」と答えるしかありませんんでした。
ザビエルの死から400年後の第二バチカン公会議においてようやく、キリスト教以外の様々な宗教の真理についても認める、とされました。
つまり、キリストを信じる機会がないまま亡くなった人も、その生き方が神のみこころにかなうものであったら救われる、と教会憲章に明記されたのです。
カトリックの神学者たちは、天国が場所なのか状態なのかについて推測してきました。
ヨハネ・パウロ2世は、天国は「抽象的なものでも雲の中の物理的な場所でもない、聖なる三位一体との生きた個人的な関係である」と述べました。
先週、叔父が89歳で突然、天に召されました。
朝までいつも通りに過ごしていたのに、ソファに座ったままで、だったそうです。
カトリック信者ではありませんが、わたしは叔父も今は「天国」にいる、と信じています。
優しく穏やかで、勤勉な、家族思いの叔父でした。
先に「天国」に行った母が、「義兄さん、ようこそ!」と出迎えている姿が目に浮かぶようです。
天国、とはどこにあるのか。
うまく表現できませんが、答えを偶然youtubeで見つけました。
守護天使
秋は一番好きな季節です。
この季節は窓を開けて、朝の澄んだ、ひんやりした空気を吸い込むと、それだけで「今日はいい日になる」気がします。
ここで何度か引用したことのある本、メアリー・ヒーリー「マルコによる福音書」の解説を翻訳したのは、東京大司教区の田中 昇神父様です。
その田中神父様は、日本で唯一のエクソシストです。
悪魔による憑依現象は現代ではほとんどが精神疾患とされていますが、それでもカトリック教会は人や場所への悪魔の憑依を認めています。
エクソシズムは、悪霊に取り憑かれた人、ないし悪霊の誘いを受けている人が、神の絶対的な支配を認め、信仰を荘厳に宣言するものであり、本来的には悪魔に誘惑されている人の心と身体、その人の全体を神に向け直すことを教会が助けることによって救いをもたらすものであると言えるのです。
(「エクソシストは語る-エクソシズムの真実」田中 昇神父 著より)
旧約聖書には、悪魔憑きのエピソードはありません。
その存在を感じさせるものは登場しますが、悪霊に憑かれた人や病気の原因が悪魔や悪霊のせいにされている例は描かれていないのです。
悪魔のねたみによって死がこの世に入り、悪魔の仲間に属する者が死を味わうのである。
(知恵の書2・24)
一方、新約聖書には、イエスが悪魔や悪霊を人から追い払うシーンが数多くあります。
ナザレのイエス、かまわないでくれ。
我々を滅ぼしに来たのか。
正体はわかっている。神の聖者だ。
(マルコ1・24)
イエス様が地上にやってきた以上は、この世はすでに神の支配が始まっていることを悪霊は理解していました。
イエス様を神だと認識しているのです。
弟子たちは当時、イエス様のことをまだよく理解していなかったのに、悪霊・悪魔のほうがイエス様の存在を恐れて命令に従っています。
田中神父様は本のなかで、「彼らはもともと神に近い存在、天使であったから」だと書いています。
悪魔ももともとは神が創った天使でした。
天使の本来の役割は、神への賛美と奉仕です。
しかし、あるときから高慢と嫉妬のために神に反逆する天使たちが現れました。
彼らは神に罰せられ、天界を追放されます。
その追放された天使たち、すなわち堕天使たちが悪魔や悪霊だとされています。
神は被造物である天使にも堕落し神に反逆する自由意志をあたえているのです。
(173頁)
バビロン捕囚期以後に、異国からの宗教感覚がユダヤ教徒に浸透していく中で、悪魔とその働きが信じられるようになっていったようです。
そして、イエス様が活動していた時代には、多民族からもたらされた悪霊に対抗する必要がある、とユダヤ民族は信じていたのです。
悪魔は、暴力によって人を傷つけるのではなく、人を欺き、そそのかして理性を狂わせ、神の愛と真理から遠ざけて破滅に向かわせるように誘惑する者のことです。
洗礼を受けたわたしたちは、キリストとともに悪魔に打ち勝った(1ヨハネ2・13)のですが、自らの不信仰・不従順によって悪魔に罪へと誘われないよう、いつも心がけておかなければなりません。
あなたが主を逃れ場とし、いと高き方を隠れ所とするなら、不幸はあなたに臨まず、災いはあなたの天幕に近づかない。
主の羽があなたを覆い、あなたはその翼のもとに逃れる。
主はみ使いたちに命じ、あなたの進むすべての道であなたを守らせる。
あなたの足が石につまづかないように、彼らは手であなたを支える。
(詩編91・4,9~12)
田中神父様は、神を信じているからこそ悪魔の存在も信じることができる、おっしゃっています。
わたしは、悪魔の誘惑を感じたことはありますが、天使の存在を感じたことはありませんでした。
みなさんはご自分の守護聖人をお持ちですか?
ザビエルがキリスト教布教の許可を得たのが1549年9月29日。
この日は聖ミカエルの祝日だったことから、ザビエルは大天使ミカエルを日本の守護聖人にしたそうです。
(そのザビエルを、日本は自分たちの守護聖人としたのです)
余談ですが、妹の洗礼名はミカエルで、結婚した相手(アメリカ人)はマイケルという名前です。
わたしは特別に守護聖人を意識したことはないのですが、先月末からのいくつかの心配事が立て続けに2つ解決に向かってきたのは、天使の守護があるのではないか、と感じているところです。
日々の祈り、神様と母の導きのお恵みだけでなく、聖霊が道を示し、わたしの周りを天使が守ってくれているような感覚があるのです。
++++++++++
この本はタイトルがどうも引っかかっていて、(失礼ながら、出版社の売るため戦略に感じられて、、、)ずっとAmazonのカートに入れっぱなしでした。
ですが、やはり気になって購入して読んでみて良かった!
第1部は田中神父様のエクソシストとしての活動やエクソシズム、悪魔について、第2部としてご自身の召命と神学校時代、ローマ留学時代について、現在のキリスト教の問題点についてじっくりと書かれています。
読書の秋にお薦めの一冊です。
今、ここで
先週は、集会祭儀司会者養成講座の2回目が大名町教会で開催され、参加しました。
今回はレナト神父様による、「みことばの食卓」と題された講義でした。
実に、神の言葉は生きていて、力があり、どんな両刃の剣よりも鋭く、魂と霊の、また、関節と骨髄の分かれ目まで指し通し、心の思いや考えを見分けることができます。
(ヘブライ4・12)
この聖句にある通り、福音書(聖書)は読み物ではなく『みことば』であることを意識しなければならない、とお話がありました。
わたしたちが祈るときには神に語りかけているように、読むときには神が自分に語りかけておられるのだ、と。
聖書朗読とは携帯を持ち歩くようにみことばに同伴されるもの、つまり自分の置かれている生活の中で実践するようにみことばが日常に結びつかなければならない、ともおっしゃいました。
みことばを日常生活で実践する、とはどういうことなのか、考えてみました。
+
ラテン語「ヒック エット ヌンク」(hic et nunc)という言葉をご存じでしょうか。
直訳すると「ここで、今」(here and now)という意味です。
過去は変えられないし、未来はまだ先のことです。
今ここに集中すること、を意味しているそうです。
どうすることもできない過去を悔やみ、どうなるのか今は分からない未来に怯えるのがわたしたち人間。
人は「今ここ」を疎かにしがちではないでしょうか。
今日わたしが命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っているときも道を歩くときも、寝ているときも起きているときも、これを語り聞かせなさい。
(申命記6・6~7)
将来、あなたの子が、「我々の神、主が命じられたこれらの定めと掟と法は何のためですか」と尋ねるときには、あなたの子にこう答えなさい。
「我々はエジプトでファラオの奴隷であったが、主は力ある御手をもって我々をエジプトから導き出された。
主は我々の目の前で、エジプトとファラオとその宮廷全体に対して大きな恐ろしいしるしと奇跡を行い、
我々をそこから導き出し、我々の先祖に誓われたこの土地に導き入れ、それを我々に与えられた。
主は我々にこれらの掟をすべて行うように命じ、我々の神、主を畏れるようにし、今日あるように、常に幸いに生きるようにしてくださった。
我々が命じられたとおり、我々の神、主の御前で、この戒めをすべて忠実に行うよう注意するならば、我々は報いを受ける。」
(申命記6・20~25)
旧約の神は、「乳と蜜の流れる土地で大いに増える」と民に約束されました。
その条件は、エジプトから導き出された主を忘れず、主を試すようなことはせず、主の目にかなう正しいことを行い、常に幸せに生きることでした。
それは「約束の地」という文字通りの土地を所有できる権利ではなかったはずです。
与えられた土地で彼らがどう生きるのかを見ておられたのです。
「今日命じることを心に留める」「今日あるように幸せに生きる」、これが神様がわたしたち(イスラエルの民だけでなく)に教えてくださった生き方そのものなのです。
「今日」という日が過ぎ去らないうちに、毎日、互いに励まし合いなさい。
「今日、もし、あなたがたが神の声を聞くなら、心を頑なにしてはならない、神に背いた時のように」
(べブライ3・13、15、詩編95・7〜8)
「今日」「今ここ」は、神様が私たちに語りかけるあらゆる全ての瞬間のことです。
みことばを日々の生活の中で実践する、つまり「今、ここで」、今生きている瞬間を疎かにしない生き方が神様がわたしたちに求められていることなのではないでしょうか。
+++++++++++
大分教会と別府教会への巡礼に、久留米からバス2台で行ってきました。
大分教区の森山司教様は、司祭時代の最後の司牧教会である久留米の信徒からとても愛されています。
司教様と3人の司祭によるごミサは、わたしたちがどれほど恵まれ愛された信徒であるかを思い起こさせるものでした。
神様への応答
今場所の推しは、伯桜鵬です。
スポーツは、団体競技であれ個人種目であれ、ひとりで戦うものではありません。
例えば、相撲は部屋があり親方がいて、ともに稽古する同志がいて、指導してくれる先輩力士がいなければ、土俵で戦うことはできません。
教会の運営も、同じです。
ベネディクト16世教皇が書き上げ、フランシスコ教皇が手を入れて、2人のコラボレーションによって発表された回勅『信仰の光』の中には、次のような一節があります。
信仰は、招きに対する応答として表現されます。
わたしたちはこの招きの言葉を聞かなければなりません。
それはわたしに由来するものではないからです。
だから信仰は対話の一部であって、個人から生まれる純粋な告白だけではありません。
一人称で「わたしは信じます」と応答することができるのは、わたしがより大きな交わりに属しており、「わたしたちは信じます」とも言えるからなのです。
(第39節)
◇信仰とは、単なる個人の内面的確信ではなく、「共に信じること」から力を得ている
◇信仰は孤立した自己完結的行為ではなく、「他者との交わりにおいて」のみ本来の形を取る
◇信仰の本質は、「神からの招きへの応答」であり、共同体の交わりのなかで生きるもの
この回勅が出た11年前には、こんな風に自分の中に入ってきませんでした。
ベネディクト16世がわたしたちに伝えてようとされたことが、今のわたしには染みわたるような感覚です。
↑この写真、素敵だと思いませんか?
先月、教区100周年記念誌作成のための原稿と写真の提出を教区から求められていたので、もう一人の広報担当に「いいカメラ持ってるみたいだから、写真お願い!」と頼んで撮影してもらったうちの一枚です。
共に神様の招きに応えて働く仲間です。
愛する者よ、あなたは、年が若いということで、だれからも軽んじられてはなりません。
むしろ、言葉、行動、愛、信仰、純潔の点で、信じる人々の模範となりなさい。
わたしが行くときまで、聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさい。
あなたの内にある恵みの賜物を軽んじてはなりません。
その賜物は、長老たちがあなたに手を置いたとき、預言によって与えられたものです。
これらのことに努めなさい。
そこから離れてはなりません。
そうすれば、あなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。
自分自身と教えとに気を配りなさい。
以上のことをしっかりと守りなさい。
そうすれば、あなたは自分自身と、あなたの言葉を聞く人々とを救うことになります。
(テモテ4・12~16)
*フランシスコ会訳聖書の解説には、「当時、年が若い=30〜40歳までの者を指した」とありました!!(;'∀')
年寄りを責めてはなりません。
むしろ、自分の父親と思って勧めなさい。
また、若い男は弟と思い、年老いた女性は母親と思い、若い女性に対しては完全な純潔をもって、妹と思って勧めなさい。
(テモテ5・1~2)
あなた方の行うことはすべて、人間のためではなく主のためと思って、精魂をこめて果たしなさい。
(コロサイ3・23)
人の語るあらゆる言葉に、いちいち心を留めてはならない。
さもないと、あなたの悪口を言う僕の言葉を聞くことになるだろう。
あなた自身もまた、しばしば他人の悪口を言ったことを、あなたの心は知っているからである。
(コヘレト7・21〜22)
聖書には人生に必要な教えが全て網羅されています。
聖書を一人で読むだけではなく、ここにこうして紹介することで、読んでくださっている方々と分かち合っている気持ちになれます。
良いもの、素敵なこと、嬉しいことは、人と分かち合うことで数倍の価値になる気がするのです。
最初にご紹介した回勅『信仰の光』には、こうも書かれています。
信じる者は独りきりではないのです。
だから信仰は広められ、他の人を喜びへと招くことを目指すのです。
信仰を受けた人は、自分の「自我」が広がり、自らのうちに人生を豊かにする関係が生まれたことを見いだします。
7/27〜8/5まで、「青年の祝祭」ローマ巡礼に参加した彩天さんが、共に参加した友人と一緒に報告会をしてくれました。
彼女たちもまた、神様からの招きに応答し、共に交わり、共に信仰に確信を得た青年たちです。
++++++++++++++
教皇レオ14世は、9月17日、バチカンで行われた一般謁見の席で、パレスチナ・ガザ地区の情勢に言及された。
恐怖の中で生活を続け、受け入れ難い状況を生き延び、自らの土地から再び強制的に移動させられる、ガザのパレスチナの人々に、ご自身の深い寄り添いを伝えられた。
平和と正義の夜明けが一刻も早く訪れるようにとの、ご自身の心からの祈りに一致してほしいと、すべての人々を招かれた。
(バチカンニュースより)
皆で心を一つにして祈れば戦争が終わる、わけではありません。
戦争を始めるのも止めるのも、人間です。
皆で一致して心から平和を祈る、そのことに意味があるように思います。
1デナリオン
先週紹介した本から、もうひとつ。
マタイ20章にある、ぶどう園の主人と労働者の喩え話についてです。
1日につき1デナリオンで働くことを約束された労働者たち。
9時から働いた人だけでなく、5時ごろに雇われた人たちにも、主人は同じように1デナリオンを払うのです。
山本芳久さんの本には、教皇レオ14世はこの箇所についての説教で、気前の良い主人ではなく遅い時間まで広場に残されていた労働者に着目して話された、と書いておられます。
「彼らは、今日も仕事にありつけなかったという徒労感と無意味感、不安にさいなまれていたであろう。
ぶどう園の主人は、労働者を探すために、1日に何度も出かけるのだ。
わざわざ、5時にも。」
この疲れを知らない主人は、わたしたち一人ひとりの人生になんとしても価値を与えたいと望み、5時にも出かけるのです。
市場に残っていた労働者は、おそらくあらゆる希望を失っていたことでしょう。
それでも、なお彼らを信じていくれる誰かがいたのです。
人生で自分にできることはほとんどないように見える時でさえ、常に、人生にはやはり価値があるのです。
意味を見出す可能性は常に存在します。
なぜなら、神はわたしたちの人生を愛しておられるからです。
(2025/6/4、3回目の一般謁見講話より)
いつ働き始めても報酬が同じと分かっていたら、多い時間働く必要はない、と考えるのが普通かもしれません。
アウグスティヌスは説教の中でこのことに触れています。
「神の招きを感じたならば、呼ばれたときにすぐに行きなさい」
「いつ始めても報酬が同じだからといって始めるのを延期しているうちに、神からの招きに応答しないままに人生を終えることになってしまうかもしれない」
「いまここで神からの呼びかけに応え、あなたに与えられているかけがえのない役割を果たしなさい」
教皇様は、アウグスティヌスの言葉を引用しながらわたしたちに呼びかけられたのでした。
自分の日々の働きが無意味に感じることはありませんか?
家事、仕事、与えられた様々な役割をする中で、徒労感を感じる場面があるのは当然かもしれません。
来住英俊神父の9/8のnote、「年間第23主日の説教」の記事から少し抜粋してご紹介します。
洗礼を受けると予想しない苦しみを経験します。
次の例は、 教会で起こる典型的な苦しみではないかと思います。
最初は、キリストの受難に与ることを、ハードワークに耐えることと同一視しているものです。
頑張る覚悟はあるが、ある程度の評価と感謝を予想します。
そうなることもあります。
しかし、かなりの確率で周囲の人々は自分の頑張りを無視している、当然のことと思っているということに気がつきます。
不本意ではあるが、キリスト者なんですから、その無視に耐えようと思います。
しかし、その次に起こることは耐え難いものです。
自分は頑張っていると思っていたのが、他人から、周囲の人から批判されるていることに気がつくのです。
私は、いくつかの小教区でそういうことを聞きました。
それで教会に来なくなった人も結構います。
キリスト者生活をするにつれて、こういった予想もしない苦難を経験します。
「なんじゃ、これは!」と投げ出したくなります。
こんな取り扱いにも我慢しなければならないのかと思います。
ですから、キリスト者の旅路の途中で何度か、「腰を据えて考える」必要があるのです。
「 私はそれでも、この道を終わりまで歩む覚悟があるか。」
「自分の十字架を背負ってついてくる者でなければ、誰であれ、私の弟子ではありえない。」
わたしも、そして教会で役割を果たす誰もが、報酬(評価、感謝)を期待しているわけではありません。
もしも、報酬が与えられるとしたら、それはすでに与えられているからです。
それは、1デナリオンの価値以上の、信仰生活という人生に意味を見出すというご褒美です。
神様からの呼びかけを聞き、かけがえのない役割を果たすことができるという喜びを、いつも感じることができています。
終わりまで、腰を据えて考えながら導きに応えていきたい、それが全てです。
+++++++++++++++
ミサの中で敬老の祝福式が行われ、ミサの後にはささやかなお祝いの会を行いました。
先輩方の嬉しそうな楽しそうな様子に触れ、とても穏やかな気持ちで良い日曜日を過ごすことができました。
「落ち着かない心」
わたしが大きな病気をしたとき、若かったこともあり、全く心配もせず、おおらかに前向きに生きていました。
ですが、ふと思ったのです。
当時、家族はどれほど不安な気持ちで、心配をしながら落ち着かない暮らしをしていたのだろうか、と。
神よ、あなたの名によってわたしを救い、
あなたの力で守ってください。
神よ、わたしの祈りを聞き、
わたしのことばに耳を傾けてください。
神よ、わたしはすすんでいけにえをささげ、
いつくしみ深いあなたの名をたたえる。
神はわたしの助け、わたしのいのちの支え、
あなたはすべての苦しみからわたしを救われる。
(詩編54・3~4,8~9)
母はカトリックの信仰を持っていましたので、おそらく毎日神様に祈り、聖書を開いていたことでしょう。
化学療法の治療中は、いつも母が枕元で聖書を読んでくれていました。
吐き気がひどい中、内容は頭に入ってきませんでしたが、それでも素敵な音楽が遠くから聞こえてくるような心地よさを感じていたことは忘れられない思い出です。
当時、抗がん剤の治療を終えて1週間は絶対に外出禁止でした。(免疫が極度に落ちているから)
数度目の治療の後、お散歩に出ていい、と言われて出かけたのは、お向かいのビルにある本屋さんでした。
インターネットなど普及していない時でしたから、何か本を読みたかったのです。
ですからその時以来、聖書を開くこと、そして読書は、わたしの最高の癒しとなっています。
久しぶりに、素敵な本に出会いました。
8月20日に出たばかりの、山本芳久さんの新刊です。
レオ14世教皇のお人柄やお考えが、ようやくスーッと心に入ってきた気持ちになれました。
主よ、あなたは私たちを、ご自身にむけてお造りになりました。
ですから私たちの心は、あなたのうちに憩うまで、安らぎを得ることができないのです。
(アウグスティヌス「告白」第1巻第1章)
教皇就任ミサの冒頭にレオ14世が語ったのは、やはりアウグスティヌスの言葉でした。
わたしたちは皆、心の中に多くの問いを抱えて生きています。
聖アウグスティヌスはわたしたちの「落ち着かない心」についてしばしば語っています。
この落ち着かなさ、安らぎのなさは悪いものではありません。
わたしたちは、その火を消そうとしたり、自分が経験している諸々の緊張や困難を取り除いたり、麻痺させたりさえする方法を探すべきではありません。
むしろ、自分自身の心と向き合い、神がわたしたちの人生の中で、またわたしたちの人生を通して働かれること、そして他の人々にわたしたちを通して手を差し伸べることができることに気づくべきなのです。
(2025年6月14日シカゴでのビデオメッセージより)
わたしたちが抱えている、心の「落ち着かなさ」「安らぎのなさ」を悪しきものと判断して無理に克服しようとしなくていい、とおっしゃっています。
「落ち着かない心」「安らがない心」に促されるままに、自分の日々を深く歩むことが人生なのですよ、と。
他の人々に手を差し伸べることができるのは、自分が「落ち着かない心」を持っているからできるのだ、と。
このことを痛感する出来事がありました。
先週書いたように、色々と不安と心配事を抱えていて余裕のない心で過ごしていたのですが、もっと大変な心配事に覆われた友人がわたしを頼ってきたのです。
「うん、わかるよ、その気持ち」
と、彼女の話を聞き、心が軽くなるならこうしてみたらどう?と伝えることができました。
自分が落ち着いている時ならば、「え?なんでそんなこと心配してるの!?」と笑い飛ばしたアドバイスをしていたかもしれません。
わたしも今、心の「落ち着かなさ」「安らぎのなさ」の中にいるので、かえって一緒に落ち着いて語り合えた気がするのです。
代々に、主に寄り頼め、まことに、主はとこしえの岩。
そうです、あなたの定め道にあって、主よ、わたしたちはあなたを待ち望みます。
あなたの名と、あなたの名を呼ぶことが、わたしたちの魂の望み。
わたしの魂は、夜、あなたを慕い求め、わたしの中の霊はあなたを慕います。
(イザヤ26・4、8〜9)
あなたはわたしを健やかにし、わたしを生かしてくださいました。
あなたの愛は、滅びの穴からわたしの魂を守ってくださいました。
生きている者、生きている者だけが、今日のわたしのように、あなたをほめたたえるのです。
主はわたしを救ってくださる。
わたしたちは命の日々のあるかぎり、主の家で楽を奏でよう。
(イザヤ38・16〜20抜粋)
38章のこの箇所、これが生きる意味なのだ、と聖書の師匠から教わりました。
聖書の文章は、本当に美しいです。
落ち着きと安らぎをわたしに与えてくれます。
山本さんは、こう書いておられます。
世界の中で日々起き続ける様々な出来事に揺り動かされ、「落ち着かない心」を抱き続けながら、「一致」と「平和」を目指して生きる一人ひとり(キリスト者であれ非キリスト者であれ)によって築かれる、「多様性」を前提としたうえでの「一致」の世界。
それこそがレオ14世がアウグスティヌスに深く依拠しながら実現を呼び掛けている世界の在り方なのである。
教皇様のお話に、これからはもっと注目したいと思わせる本です。
信仰は希望
めずらしく、気持ちの落ち込みと不安に覆われてしまっていた1週間でした。
月曜日に一つ目の心配事
水曜日に二つ目の心配事
金曜日にそれらがさらに悪化
人にアドバイスするときには、「心配してもしょうがないから、神様のお導きを信じて!」などと立派な声掛けをしているわたしですが、まれにかなり深みにハマって這い上がれないこともあります。
20代初めの頃、人生の方向性を模索して悩んでいた時、いつもこの聖句を心に留めていました。
だから、あなた方も用意していなさい。
思わぬ時に、人の子は来るからである。
(マタイ24・42)
だから、目を覚ましていなさい。
あなた方はその日、その時を知らないからである。
(マタイ25・13)
聖書をちゃんと学んでいなかったので、本来の意味するところを理解してはいなかったのですが、このみ言葉は当時のわたしにとって「いつか、きっと必ず神様が道を示してくださるから、自分にできる努力をしながら待ちなさい」という意味だと勝手に解釈していました。
そして、それは今でも変わらない気持ちです。
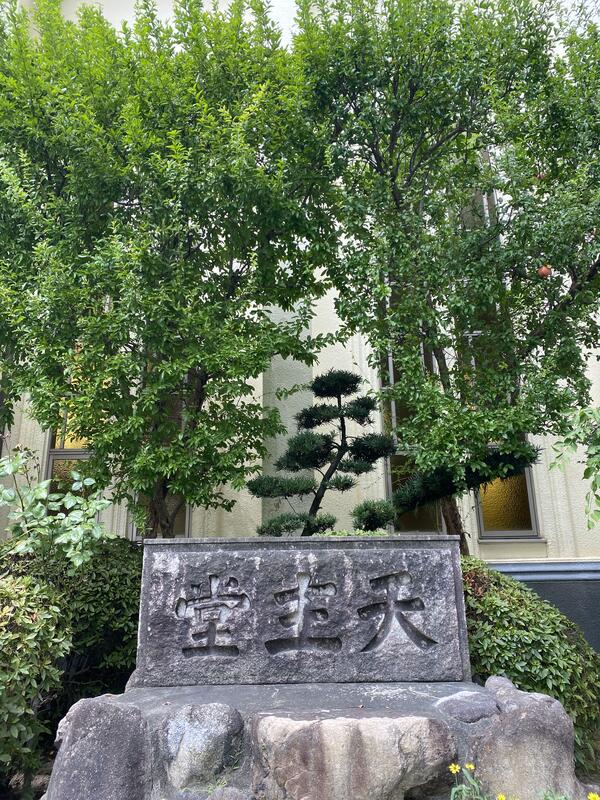
今わたしが抱えている不安は、祈り続ければ神様が解決してくださる、というようなことではありません。
わたしの人生に与えられた試練です。
「与えられた」というと神様の計らいのようですが、そして、「試練」というと神様に試されているようですが、こうした苦難はわたしたちが人生を歩むにあたって必要なことなのです。
痛みや苦しみ悲しみなどと対峙しながら人生を積み重ねる。
乗り越えられなくとも、その経験が人格を形成していく。
そして、日曜日に教会に行って、色々な方と言葉を交わし、担っている役割をいくつか実行し、 そうして神様からのメッセージを受け取りました。
兄弟のみなさん、わたしたちは、どんなに窮乏し、苦難の中にあっても、あなた方のお陰で励まされています。
あなた方の信仰のお陰です。
あなた方が主に結ばれてしっかりと立っているかぎり、わたしたちは、今、まさに生きていると実感するからです。
(1テサロニケ3・7〜8)
知っていたこと、わかっていたこと、つまり、神様は乗り越えられない試練は与えられないということ・そのために進むべき道をも同時に与えてくださるのだということを、日曜日に教会に行って思い出しました。
キリスト教でなくても、信仰という希望を持てることは最大の救いです。
月曜日から金曜日まで心配事に襲われても、日曜日には光を与えてくださる。
いつも、本当に不思議なのです。
日曜日に教会でいつもの席に座って祈り始めた途端に、神様と母がわたしに近づいてきてくれるのです。
毎週、わたしの横に座ってくれるのを感じるのです。
レオ14世教皇は、前教皇よりも説教の言い回しが少し難しく感じられますが、今回のこのお話は、今のわたしにとても深く刺さりました。
わたしたちも、御父のいつくしみ深いみ旨に身をゆだね、自分の人生を、与えられた善いものヘの答えとしていただけることを学ぼうではありませんか。
人生において、すべてをコントロールする必要はありません。
日々、自由をもって愛することを選択するだけで十分です。
試練の暗闇の中でも、神の愛がわたしたちを支え、永遠のいのちの実をわたしたちのうちで育ててくださっていることを知ること――これこそがまことの希望です。
教皇レオ十四世 2025年8月27日一般謁見演説より
それぞれ、個性
先週は、イエズス会の中井 淳神父様がミサを司式してくださいました。
そして、昨日はイタリア留学を終えて帰国された船津 亮太神父様が、留学仲間のベトナム人の神父様と共に久留米教会に早速来てくださいました。
当然のことですが、わたしたちと同じように、神父様方も色々な方がいらっしゃいます。
(もちろん、それが嬉しいことです。だって、どの司祭も同じようなタイプだったらつまらない。。。。)
わたしはそんなに多くの神父様を存じ上げているわけではありませんが、これまでお話しする機会のあった神父様は、どなたもとても魅力的な、そして個性的な方ばかりです。
1番最初の大きな出会いは、大学生の時に参加したイエズス会の黙想の家で指導してくださった神父様です。
身体の大きなスペイン人のおじい様で、わたしのことを「わが子よ、わが子」と、それ以来ずっと気にかけてくださっていました。
イエズス会の黙想会は沈黙の時間を大切にするそうですが、ギハーロ神父様は、他の参加者が部屋に戻った後にわたしを呼び寄せて、「どうして参加したのですか」と話しかけてくださったのでした。
洗礼を受けて間もない頃でしたので、神父様にはこういう方もいらっしゃるのか!ととても嬉しくなりました。
洗礼は体の汚れを取り除くことではなく、
正しい思いを保つ約束を神にすることなのです。
(1ペトロ3・21)
若い頃は、人と同じように行動してあまりはみ出さないように、と頭の中では考えていました。
ですがやはり、わたしは個性が強すぎるのか、あまり上手に人と足並みを揃えることができないことが悩みでもありました。
今やっと、「このわたしの個性は与えられたお恵み」と思えるようになり、ようやく自分に自信を持って生きていると公言できる気持ちです。
先週の中井神父様も、かなり個性的な方でした!
お話しされていた時に突然、「あんなこといいな、できたらいいな」と聖堂内を歩き回りながらドラえもんを歌い出し、「どこまでもドア〜〜〜!!」と。(^_^;)
何事?!と唖然とするわたしたちに、
「イエス様はわたしたちをどこにでも、ではなく、どこまでも連れて行ってくれる、どこまでも付いてきてくれるんです。
だから、イエス様はわたしたちの『どこまでもドア』なんですよ!」
主よ、あなたは、すべてにおいてご自分の民を高め、彼らに栄光を与え、彼らを見捨てず、いつでもどこでも彼らの傍らに立っておられた。
(知恵の書19・22)
そして、昨日の船津神父様。
侍者が鳴らす9時のベルと同時に祭壇に登場された神父様を見て、とても驚きました。
「え、男っぷりが上がってる!」
失礼ながら昔から存じ上げているので、その表情と佇まいが自信に満ちているというか、キリッとしたイケメン(本当に失礼)になられている感じがして、思わず涙ぐんでしまいました。
「3年前の5月に久留米教会で共にミサを祝い、その翌日からローマに3年間留学しました。
わたしは文字通りに旅をしていたわけですが、皆さんもそれぞれに人生を旅しておられたことでしょう。」
そうお話しされる神父様は、やはり変わらず誠実で、キリッとした優しさの方で、その上に何か確固たるものを得てこられた自信を感じさせる様子でした。

宮﨑神父様も、ジュゼッペ神父様も、とても個性的で愛すべき方です。
こうして、色々な神父様方と信徒仲間たちとの時間を共有できる日曜日は、素晴らしいお恵みの時間です。
応援する姿
15日のマリア様の被昇天の祝日、今年最後(希望)の40℃に迫る酷暑の朝でした。
この季節は、甲子園球児たちを応援するのが楽しみの一つです。
プロ野球も好きですが、大人の利害やスポンサーといったものがなく、純粋に野球に打ち込む彼らの姿は、本当に清々しくて気持ちの良いものです。
毎年、わたしがテレビで見て応援しているのは、グランドの選手だけでなく、スタンドで応援しているユニフォームを着た選手たちです。
スタメンに入れず、それでも満面の笑みを浮かべて全身全霊で応援歌を歌い踊る彼ら。
汗だく・泥だらけになってプレーする選手たちと同じように、彼らもまた、甲子園の舞台で精一杯に躍動しているのです。
さて、彼らは、ひたすら使徒たちの教えを守り、兄弟的交わり、パンを裂くこと、祈りに専念していた。
信じる人たちはみな一つになり、すべての物を共有にし、財産や持ち物を売り、それぞれの必要に応じて、みなにそれを分配していた。
また、日々、心を一つにして、絶えず神殿に参り、家ではパンを裂き、喜びと真心をもって食事をともにし、神を賛美していた。
彼らは民全体から好意を得ていた。
こうして、主は日々、救われる人々を仲間に加えてくださった。
(使徒言行録2・42〜47)
今年の甲子園でも色々と注目ポイントがありますが、話題として取り上げられているのが、県立岐阜商業の横山選手。
彼は、生まれつき左手の指が全て欠損しているのですが、レギュラーとして大活躍しています。
打席に立つたびにひときわ大きな歓声が上がり、投打に活躍する姿に大きな拍手が送られています。
「ハンデを持っているから注目されている。その分活躍したいし、勝利に貢献しなければいけない」とインタビューに答えていました。
以前も書いたことがありますが、教会とは、日曜日にミサに与るために来るだけのところではありません。
共同体を運営するために奉仕する、さまざまな役割を担う信徒の支えがあるからこそ、脈々と受け継がれてきたのです。
長年、お1人で納骨堂の管理をしてこられた方からその役割を引き継ぎ、今後の運営のあり方について打ち合わせをしました。
色々と提案をさせていただき、お話をする中で、「これまではお一人しか管理の仕方がわからなかったことも、こうしてわたしたちが引き継いで、そしてわたしもさらに引き継ぐ人を見つけていきますね」とお伝えしたところ、涙を浮かべて喜んでくださいました。
神を愛する人々、すなわち、ご計画に従って神に召された人々のために益となるように、すべてが互いに働き合うことをわたしたちは知っています。
(ローマ8・28)
わたしは与えられた恵みによって、あなた方1人ひとりに言います。
自分は当然このようなものだと思う以上に自分を過大に評価せず、神が各々に与えてくださった信仰の度合いに応じて自分を評価し、程よく見積もるようにしなさい。
(ローマ12・3)
わたしは植え、アポロは水をやりました。
しかし、成長させてくださったのは神です。
ですから、植える者も水をやる者も取るに足らず、成長させる神こそ大切な方なのです。
植える者も水をやる者も一致して働いていますが、それそれその働きに応じて自分の報酬を受けるのです。
わたしたちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。
(1コリント3・6〜9)
レギュラーになれなくても応援する姿に感動し、その彼らを応援したい
ハンデがあるから余計に応援したい
これまで担ってこられた役割を引き継ぐわたしたちを、応援してくださる先輩方がいる
野球も教会も、ある意味チームプレイです。
心をひとつにし、仲間を増やし、働き合って成長する。
各々に与えられたお恵みをそれぞれが最大限に発揮して、互いに応援し合う。
ちょっと強引かもしれませんが、連日の甲子園の試合を応援していると、教会での役割についてもっと役立ちたいという気持ちになったお盆休みでした。
++++++++++++++++++
17日のごミサは、イエズス会の中井神父様の司式でした。
その後に、ご自分の多岐にわたる活動についてのお話をお聞かせくださいました。
また改めて記事にしたいと思います。
危うい確信
Amazonプライムで配信が始まった映画「教皇選挙」を観ました。
この春に行われた実際のコンクラーベと相まって大ヒットしていましたので、ストーリーも結末も知っていたのですが、原作がゴシップ風のミステリー小説なので、実際のコンクラーベも枢機卿方もこうではないはず、、、というのがわたしの感想です。
菊池枢機卿が「現実とは違う」とブログに書いておられたのを思い出しました。
「ストーリーはちょっと荒唐無稽だなと思いますし、明らかに現実的ではないフィクションです」
https://bishopkikuchi.cocolog-nifty.com/diary/2025/05/post-7690d8.html
セットとして造られたバチカンの建物の迫力は圧巻でした。
それと、主演のレイフ・ファインズが演じる首席枢機卿が素晴らしく、演技だけでなく、役柄に秘められた落ち着きと責任感には救われました。
とても心に迫ったセリフがあります。
わたしは長年、教会にお支えしてきて、何より恐れるようになった罪が一つあります。
それは「確信」です。
「確信」は一致を拒む敵であり、寛容の大敵でもあります。
キリストさえ、最期には確信を持てず、十字架の上で叫びました。
信仰は生き物です。
疑念と手を取り合い、歩むものです。
もし「確信」だけで疑念を抱かねば、不可解なことは消え、信仰は必要なくなります。
あまりにも的を突いていて、忘れたくない、と書き留めました。
聖書の中で大好きな箇所(ヘブライ11・1)を思い返してみます。
信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。
(新共同訳)
信仰は、希望していることを保証し、見えないものを確信させるものです。
(フランシスコ会訳)
信仰とは、望んでいる事柄の実質であって、見えないものを確証するものです。
(聖書協会共同訳)
いつも思うのですが、この3種類の訳は微妙にニュアンスが違っています。
映画のセリフに1番ピッタリ当てはまりそうなのは、聖書協会共同訳のような気がします。
自分の信仰の弱さに落ち込み、告解したことを繰り返し、自分の望み(この世を旅する間は神様にいつも導かれてよりよく生きる)が叶えられると信じて祈り続ける。
望みは叶うとわかっていても、確信が持てずに祈り続ける。
これが、信仰なのではないでしょうか。
宗教学者の故・藤田富雄さんは、「信仰」の解説を次のように書いておられます。
信仰とは、自分にとって究極的な価値や意味をもっている対象と全人格的な関係を持ち、その対象に無条件に依存し献身する心的態度を言う。
経験できぬ不確実なものを主観的に確実であると思い込むことではない。
宗教的体験や儀礼を繰り返すことによって、しだいに人格の内部に一定の心的態度が信仰として形成される。
いわゆる無神論者とか、無宗教者と言われる人の中には、どのような宗教であれ、神を信じる人のことを「思い込み」だと決めつけている節があります。
無神論とは、神の存在を否定する立場で、つまりは神を意識しているのかも。
無宗教とは、神という問題に無関心な立場で、それでも儀式(葬儀、初詣など)はおざなりにしない人が多い。
映画「教皇選挙」では、数名の教皇候補と目される枢機卿たちの駆け引きが描かれています。
そこには、神様の存在も信仰も、別の次元に追いやられているかのようです。
まるで、信仰を持たない者がトップの座に就くことを最終目的としているような、水面下での権力闘争。
そして、そう描いた小説がヒットし、映画が世界的に評価されたということが何を意味しているのか。
つまり、その姿(高貴な聖職者でもやはり人間的野心に冒される)が多くの人の興味を掻き立てられる題材なのです。
興味深かったのは、主役の首席枢機卿が信仰の迷いを露わにしていたことでした。
冒頭に紹介したセリフにあるように、自分の信仰心に疑念を抱き続けている彼は、絶対に自分は教皇にはふさわしくないと言い続けますが、それでも、次々と候補者たちが脱落し、最後には自分に投票するのでした。
人間のもろさ、信仰の危うさという面を描いている点では、(偉そうな言い方ですが)この映画を評価することはできます。
+++++++++
↓ とても客観的な映画評論ですので、ご参考になさってください。
https://hollywoodreporter.jp/movies/108792/
神様との約束
パレスチナ自治区ヨルダン川西岸にイスラエルが建設してきた入植地。
ガザでの戦闘が始まって以降、ユダヤ人入植者によるパレスチナ人への暴力が増え、イスラエル政府はさらに入植者住宅を建設すると発表しています。
先週は、ヨルダン川西岸にあるキリスト教徒の村で、イスラエルの入植者によって襲撃があったとの報道がありました。
テレビでも、入植者の一人が「わたしたちが神から約束された土地なのですから」、と発言していました。
「入植地」とは、パレスチナ人から奪った土地に造成されたユダヤ人専用住宅地のことです。
西岸での入植地建設は国際法上、一般的に違法とされているものの、イスラエルはこれに反論し続けており、入植地はイスラエルとパレスチナの間で特に激しい争点となっている問題の一つです。
(BBCニュースの記事より抜粋)
https://www.bbc.com/japanese/articles/clyvzkqwpgjo
2019年にイスラエルに巡礼に行った時の写真です。
ここは入植地ではありませんが、このようにイスラエルの土地では、いたるところで植林が進められていました。
誰も住んでいない土地でも、岩場に水道のパイプが張り巡らされ、土地の緑化が進められています。
聖書には確かに、神様がイスラエルの人々を「誰よりも小さい民族だから」選ばれたのだと書かれています。
「乳と蜜の流れる土地」への旅を通して、神様が人々に慈愛の心を示されたエピソードは、旧約の中でも美しく、わたしたちがいつも神様の愛に守られていることを想起させてくれます。
あなたは、あなたの神、主の聖なる民である。
あなたの神、主は地上のすべての民の中からあなたを選んで、ご自分の宝の民とされた。
主があなたたちに愛情を傾けて、あなたたちを選ばれたのは、あなたたちがほかのどの民よりも数が多かったからではない。
事実、あなたたちはすべての民の中で最も数の少ない民であった。
しかし、主はあなたたちを愛し、また先祖に立てた誓いを守られたので、主は強いその手であなたたちを導き出し、奴隷の家から、エジプトの王ファラオの手からあなたを贖われた。
(申命記7・6~8)
イスラエルの地を神様がユダヤ民族だけに与えられた、というのは間違っていると断言できるでしょうか。
あるいは、その通りだ、と断言できるでしょうか。
トランプ大統領、プーチン大統領の言動を見ていて、「嘘つきだ」「信じられない」と思うのですが、当の本人たちは、自分は間違っていないという強い確信と信念があるようです。
創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記はモーセ5書といい、ここに書かれた教えをユダヤ教徒は大切に守っています。
イスラエルの人々(全員ではないでしょうが)、特に熱心なユダヤ教徒は、聖書に書かれているのだから、この土地は神様が自分たちに約束されたものなのだ、と信じて疑わないのです。
それ故、あなたの神、主こそが神であることを知りなさい。
主は誠実な神であって、主を愛し、その命令を守るものには、契約を守り、慈しみを千代にまで施されるが、主を憎む者それぞれに報いて滅ぼされる。
主を憎む者それぞれに猶予なく報復される。
(申命記7・9~10)
続きには、このように書かれています。
フランシスコ会訳では「主を憎む者」となっている言葉は、共同訳では「御自分を否む者」です。
このことばが何を言わんとしているのか。
ガザでのジェノサイドも、一方的な(暴力を伴う)入植地開発も、人道上は許されるものではありませんが、神様との約束を妄信的に信じる人々には、こちら側の正論を押し付けても通じ合うことは無理なのでしょうか。
人道に反することこそが、神様を否むことではないでしょうか。
神様がわたしたちに約束されたのは、世の終わりまでいつもわたしたちとともにいてくださる(マタイ28・20)、ということです。
これは、キリスト教徒だけの教えではないと思います。
+++++++++++
ここにきて、「パレスチナを国家として承認する意向がある」と表明する動きが出ています。
フランス、イギリス、カナダの表明に続き、他に数か国も追随するようです。
これまでの歴史と複雑な国際情勢の故、とはいえ、民族の尊厳を守り独立を決めるのが軍事力を持った西欧諸国という現実を、どう受け止めればよいのでしょうか。
8/6~15は日本カトリック平和旬間となっています。
わたしたちにとって戦後80年、ではありますが、世界では戦争は終わっていません。
教皇様の8月の意向は、「共存のために」です。
この祈りのことばが本当に素晴らしく、毎日全世界で唱えることができれば、と心から願います。
+基本の祈り
「共存することがより困難に見える社会が、民族的、政治的、宗教的、またイデオロギー的な理由による対立の誘惑に負けませんように。」
+黙想のための祈り
イエスよ、わたしたちの歴史の主よ、誠実な友、生ける現存よ、疲れを知らずわたしたちに会いに来られる方、あなたの平和を必要とするわたしたちがここにいます。
わたしたちは恐れと分裂の時代に生きています。
まるで自分たちしかいないかのように振る舞い、互いを隔てる壁を築き、自分たちが兄弟姉妹であることを忘れています。
主よ、あなたの霊を遣わしてください。
互いに理解し合い、耳を傾け合い、尊敬と思いやりをもって共に生きる望みをわたしたちの中に再び燃え立たせるために。
対話の道を模索する勇気をお与えください。
対立に兄弟愛の態度で答え、違いを恐れることなく他者に心を開く勇気をお与えください。
わたしたちを橋を架ける者としてください。
国境やイデオロギーを乗り越え、心の目で他者を見つめ、一人ひとりの中に侵すことのできない尊厳を認められるようにしてください。
希望が花開くことができる場所、多様性が脅威ではなく、わたしたちをより人間らしくする豊かさとなる場所を創造できるようにお助けください。
アーメン。
祈りの時間
NYと横浜から帰省している妹たち家族と過ごしていました。
思い出深い夏になりましたが、、、聖書を開く時間も余裕もありませんでした。
それでも、寝る前に今日1日の感謝と、家族のことを導いてくださっていることへの感謝の祈りだけは欠かさないように努めています。
普段は、静かな落ち着いた生活ができているので、神様と天国の母に話しかけたり聖書を開いたり、日常のちょっとした隙間に、そうした時間を持てるのですが、今改めて、子どもの面倒を見ているお母さんたちの気持ちがよくわかります。
久しぶりにごミサに与りました。
贅沢にも、妹・姪たちと毎日遊び疲れて、どうしてもリフレッシュのため、心と身体を落ち着かせるために教会に行って、ミサだけでなく、信徒仲間たちと会って話したかったのです。
今までなぜか気づかなかったのですが、ガラス越しに見える青々と茂った緑の木々さえも、今日は美しく感じることができました。
「日曜日のミサに子どもを連れた親の姿が少ない」
そういう声は、どの教会でも聞かれることかと思います。
特に、夏休みの子どもたちは忙しい!、ということを実感しています。
一度も姪たちを教会に連れて行けませんでした。
今回の国政選挙の結果を見ていて、感じたことがあります。
人々は「わかりやすさ」を求めているようです。
カトリックの教えは、信仰を持たない人にとっては難しく、ハードルの高いものに感じられている気がします。
ですが、この夏の日々の中で痛切に実感しました。
わたしたちキリスト者の信仰は、シンプルに「祈り」に集約されるのではないでしょうか。
わたしたちには、「祈りの時間」が必要です。
今日のごミサでは、宮﨑神父様が「祈りの時間」の大切さについてお話になりました。
洗礼を受けただけの人、普段教会に来ない人、日常の中で祈らない人、そういう人(わたしの妹)のためにも祈りを続けなければと決意を新たにしました。
神父様は、祈りは霊的呼吸だ、とおっしゃいました。
神を信じる者の信仰生活は、祈りによって支えられていることを忘れてはならない、と。
いつもは、ミサ前には入り口に立って皆さんをお迎えし、色々とお声がけするのですが、今日はしばらくじっと座って祈り、ロザリオを唱えていました。
それだけで、心の中のスポンジに水が染み渡る気持ちでした。
さて、イエスはある所で祈っておられた。
祈りが終わると、弟子の1人がイエスに言った、「主よ、ヨハネも弟子たちに教えたようにわたしたちに祈りを教えてください」。
そこで、イエスは仰せになった、「祈る時には、こう言いなさい。
『父よ、み名が聖とされますように。
み国が来ますように。
わたしたちの日ごとの糧を、日ごとにお与えください。
わたしたちの罪をお赦しください。
わたしたちに負い目のある人をみな、わたしたちも赦します。
わたしたちを誘惑に遭わせないでください』」。
(ルカ11・1〜4)
主の祈りも、ルカのこの言い回しが心に染み透ります。
祈る=神様と天国のみなさんに語りかける、感謝の気持ちを伝える、家族を導いてくださるよう願う、、、そうした時間を毎日、何度も持つことが、どれほど自分にとって必要なひと時かを改めて実感する夏になりました。
++++++++++++++++++++++++
日本カトリック司教協議会が推薦する映画「長崎〜閃光の影で」が8/1から全国で公開されます。
久留米では、Tジョイでご覧になれます。
思いやりの行動
トップページの画像を替えました。
少しでも涼しい気持ちになってもらえたら。
ディスレクシア(読字障害)という障害があります。
これは、知的能力や一般的な理解能力などに特に異常がないにもかかわらず、文字の読み書きに著しい困難を抱えるもので、学習障害の要因となることがあります。
トム・クルーズ、ジェニファー・アニストン、キアヌ・リーヴス、など、有名な俳優さんたちもこの障害を持つと告白している人が多くいます。
数々の大作を世に生み出してきたスティーブン・スピルバーグ監督は、60歳のころにディスレクシアと診断されたそうです。
文字が読めず授業についていけないため、小学校を2年遅れで卒業。
いじめを受け、「地獄のような幼少期」だったそうです。
今でも、脚本を読むのに人の2倍の時間がかかるそうです。
ブラッド・ピットは、相貌失認(そうぼうしつにん)や失顔症と呼ばれる、他人の顔が識別できない病気だそうです。
実際は会った人を覚えていたいのに、覚えられないことを恥ずかしく思っている、何度も会った人を認識できないので失礼な奴だと思われている、とインタビューで語っていました。
ディスレクシアや失顔症、いわゆる学習障害と言われる障害は、他者からは分からないものです。
社会生活に困難を感じるのは、身体に不自由があるからだけではないのです。
お前の友を虐げてはならない。
耳の聞こえない人を呪ってはならない。
目の見えない人の前につまずきとなる物を置いてはならない。
(レビ記19・13〜14)
忘れられない思い出があります。
昔、NYの地下鉄に乗って座っていたときに、見るからに身体が不自由そうな人が乗ってきました。
わたしはとっさに「ここに座ってください」とその人に席を譲ったのですが、わたしの動く様子から足が不自由だとわかったのか、離れたところに座っていた2人の人(別々のところに座っていた、どちらも若い人)が「わたしの席に座って!」と駆け寄ってきてくれたのです。
東京で電車に乗っていても、座っている人はとても疲れた様子で眠っているか、携帯を必死に見ていて気付いてもらえないかで、席を譲ってもらった経験はほとんどありません。
逆に、年配の女性から「若いんだから、座らないで席を譲って!」と怒られたことはあります。(笑)
外見でわかるかどうかに関わらず、ちょっとした気遣いが人の役に立つことを心に留めておきたいものです。
そして、いつも他者を思いやる行動ができれば、と思うのです。
寛大な人は満たされる。
人を潤す者は自分も潤される。
(箴言11・25)
ミサで先唱したり、質問を受けたり、初めての方をご案内したり、といつもお役目をいただいています。
「ごくろうさま。いつもありがとう。」
今まで何度、いろいろな方にこう言ってもらったことか。
ちょっとした気遣いを行動に移したことで、人から感謝(=気遣い)の言葉をもらえると、心が潤されます。
人は、その口から出る言葉によって、善いものに満ち足りる。
また、人は、その手の働きによって、報いを受ける。
(箴言12・14)
年齢のせいか、ときおり自分でも意味不明なイラ立ちが湧き上がることがあります(・・;)
そういうとき、「今日これから出会う人全員に優しく丁寧に対応する」と決めて過ごすようにしてみます。
そうすると、不思議なくらい相手からも気持ちの良い態度が返ってくるのです。
これはお薦めのリフレッシュの方法です。
もし、キリストに結ばれていることによって、それがあなた方にとって励ましとなり、また、神に愛されていることが慰めとなり、あなた方に、霊による交わりがあり、人に対する思いやりの心があるなら、どうか、互いに同じ思いを抱き、同じ愛をもち、心を合わせ、思いを一つにして、わたしを喜びで満たしてください。
各々、自分のことだけでなく、他人のことにも目を向けなさい。
(フィリピ2・1~4)
飛行機から見る空が1番好きです。
心が洗われる思いがします。
女性の生き方
早くも夏真っ盛りです。
夏の暑さは嫌いではありません。空が本当に綺麗ですから!
映画鑑賞も趣味のひとつで、これまでの人生でトップ3の映画のうちのひとつが「モナリザ・スマイル」(2003)です。
1953年、アメリカでもっとも保守的と言われる名門女子大で、ジュリア・ロバーツ演じる新任の教師は彼女たちに自立心を育てる教育をしようと奮闘します。
ですが、もともとエリートとの結婚が幸せだと信じて疑わない生徒たちは、その方針に反発します。
『Mrs.Degree』(ミセス学位)という言葉を聞いたことはありますか?
Mrs. Degreeとは、1950年代前後のアメリカ社会で、勉強やキャリアのためではなく結婚相手を探すために大学へ進学したとされる女性たちを揶揄する言葉です。
これは死語ではなく、超保守の男性にとっては、いまだに存在している概念なのです。
イエス様の時代、女性は数に数えられることもないほどの扱いでした。
それにも関わらず、マリア様は知的な女性として認識されていると思いませんか?
受胎告知の絵画では、ルネサンス期には聖書を手にする(読んでいる)マリア様の姿が好んで描かれました。
ロベール・カンパン《メロード祭壇画》
この絵の解説で、こう書いてあるものを見つけました。
「マリアが読むのを止めたテーブルの上の本が旧約の世界を象徴し、現在読んでいる本が新約の世界を表す」
「救世主イエス・キリストの誕生を告げる受胎告知の場面において、マリアはそれまで読んでいた旧約聖書から新約聖書に目を移し、旧約聖書の教えを表す机上の蝋燭はたった今役割を終え、今度は新たに恩寵の教えを表す蝋燭に火が灯されることを暗示している」
4世紀のミラノの司教アンブロジウスは、「マリアは身体だけではなく精神においても純潔である。心は謙虚であり、話すときには厳粛で、慎重さを備え、言葉を慎み、最も熱心に読書に励んだ」とお説教で語ったとされています。
マリア様が聖書を手にする絵画が描かれるようになった背景には、12世紀ルネサンスとマリア崇拝の発展、女性の宗教生活の拡大、書き言葉がラテン語から自国語へと移り変わっていく動きと並行した識字率の向上など、が原因として挙げられるそうです。
民衆のマリア信仰の高まりが、マリア様を人々の信仰生活の模範とみなす伝統と連動し、それによってマリア様が知性においても優れていたことが強調されるようになった、ということです。
こうした絵画を目にしたことがあったから「マリア様は知的な女性だった」と思っているのでしょうか。
そうではない、気がしています。
福音書には、マリア様の暮らしや立ち居振る舞い、発言などはほとんど記されていません。
それでも、カトリックにおけるマリア信仰(崇拝ではなく、崇敬)には、確固たるものがあります。
羊飼いたちは、この幼子について告げられたことを、人々に知らせた。
羊飼いたちが語ったことを聞いた人々はみな不思議に思った。
しかし、マリアはこれらのことをことごとく心に留め、思い巡らしていた。
(ルカ2・17~19)
わたしはこの箇所が大好きです。
マリア様が知的で素敵な女性だったのだろう、とわたしが意識しているのはこの箇所からです。
フランシスコ会訳聖書のルカによる福音書の解説には、このように書かれています。
本福音書では女性が大きな比重を占めている。
冒頭の1~2章ではマリアとエリザベトに中心的な役割が与えられているが、同じ姿勢が福音書全体に一貫している。
こうした女性への視点は、ルカの強調する普遍的な救いが民族的な相違のみならず、男女の性差をも克服するものであることを示している。
女性の生き方など関心の対象ではなかったであろう旧約の時代でも、聖書に登場する女性はみな個性的で知的だと思いませんか?
7/6は母の命日でした。
母は、わたしたち3姉妹の教育にとても熱心でした。
娘たちがそれぞれの能力を生かして活躍することを願って、いつも後押ししてくれました。
美人で、誰からも好かれ、与えられた役割に誠実に向き合い、病弱でしたが常に明るい人でした。
わたしにとって、亡き母はいまの人生の指針でもあります。
我が家のマリア様、だったと感じています。
++++++++++++++++
「モナリザ・スマイル」で生徒役を演じる若手俳優たちは、全員が今ではトップ俳優です。
とても素晴らしい映画なので、おススメです!
:参考:
https://catholic-nishichiba.com/priest-preaching/1397/
https://www.cbcj.catholic.jp/faq/maria/
歴史の積み重ね
話題の映画「国宝」を観てきました。
歌舞伎鑑賞が趣味のわたしは、推しの俳優さんや気に入っている演目があると、歌舞伎座まで出かけていきます。
「先代の勘九郎さんはやはり素晴らしかった」
「音羽屋は次の代も安泰だ」
などと、偉そうなことを友人と語り合ったりもしますが、あまり深くその家の歴史について考えたことはありませんでした。
この映画は、血筋か生まれ持った才能か、が大きなテーマですが、伝統を継承して歴史を積み上げていくことの重みをひしひしと感じさせられました。
伝統芸能は守るべきものが明確です。
歌舞伎俳優は男性だけですので、息子がいない場合は同じ家系の男子に名前が受け継がれます。
その子に才能があるかどうか、ではなく、とにかく精進させるのです。
キリスト教、特にカトリックにおいては、教皇様が変わっても教えが変わることはありません。
父親から息子へ継承されるような伝統を受け継ぐのが教皇の役目ではなく、わたしたち信徒の現世での最高の導き手なのです。
29日のごミサで、宮﨑神父様はこうおっしゃいました。
「何がこの時代に必要なのかを教えてくださるのも教皇様です」
いま、教区100周年記念誌に掲載する久留米教会のページの原稿を書いています。
そのために、教会の歴史について振り返ってみると、様々な発見がありました。
ご自分の教会の歴史について、考えてみたことはありますか?
「久留米の人は自分の街に誇りをもっている」
と、言われたことがあります。
適度に都会で、豊かな自然、山と川に囲まれ、農業が盛んで食べ物がおいしい。
歴史と伝統が街の随所に見られる。
水天宮の総本宮がある。
ブリヂストン発祥の地。
いくつも大学があるため若者も多く、大きな病院がいくつもあるので医療が充実している。
これが、久留米という街を語るときのモデル的説明文です。
医療の街のスタートには、カトリック教会が大きな役割を果たしていました。
久留米教会の歴史は、毛利秀包(ひでかね)が久留米領主であった時(1587~1600年)に始まります。
大友宗麟の七女を妻とし洗礼を受けた秀包は、宣教師の保護に努め、信者のために城のそばに教会堂を建立しました。
久留米地方のキリシタンは当時7000人に達していたと言われています。
浦上の信徒発見から13年後の1878年、大浦のプチジャン神父の命によりミカエル・ソーレ神父が久留米に赴任し、宣教を開始しました。
ソーレ神父は、仮教会だけでなく、信徒たちの病気治療のための診療所も併設しました。
神父の依頼で『マリアの宣教者フランシスコ修道会』のシスターが久留米に修道院を構え、診療所で働きながら、女性や障害者に生計の足しになるような手仕事を教えるようになりました。
次第に、病人の治療、子どもたちの信仰教育だけでなく、一般の病人や貧しい人も受け入れて、捨て子や孤児の面倒も見るようになっていきます。
このように、シスター方と信徒たちの診療所での働きは、地域に深く根差したものとなっていくのでした。
久留米市の医療、教育、福祉のまちが現在のように作り上げられていった一端は、こうした司祭、修道者、信徒の働きがあったからと言えるでしょう。
「わたしのこれらの言葉を聞き、それを実行する者はみな、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。
雨が降り、大水が押し寄せ、風が吹きつけ、その家を襲ったが、家は倒れなかった。
その家は岩の上に土台を据えていたからである。
しかし、これらのわたしの言葉を聞いても、それを実行しない人は、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。
雨が降り、大水が押し寄せ、風が吹きつけてその家に襲いかかると、家は倒れた。その倒れ方ははなはだひどかった」。
(マタイ7・24~27)
「雨が降り、大水が〜」という表現は、最後の裁きの日を表現しています。
久留米という街の根幹には、キリスト教という強固な岩のうえに積み重ねられた教会の歴史があることは間違いないのです。
街の歴史と信仰の歴史、ともに歩みを重ねてきたのだということを今回改めて知ることができ、とても満たされた気持ちになりました。
修道生活の真の完徳に輝いた聖なる教父たちの生きた模範を想い出しなさい。
そうすればわれわれは、われわれが行っていることが、どれほど小さく、ほとんど無に等しいことがよく分かるだろう。
彼らの生活に比べたら、われわれの生活がいったい何だろうか。
(「キリストを生きる」第1巻第18章1)
久留米教会は「至聖なるイエスのみこころ」に奉げられた教会です。
今年は27日(金)にお祝いのミサが執り行われ、春から聖マリア学院大学のチャプレンとして赴任されたケン神父様と一緒にお祝いすることができました。
(聖マリア病院には、大学も併設されています。)
久留米教会は、3名の司祭が導いてくださる、本当に恵まれた教会です。
キリシタンたちの信仰教育から始め、何もなかった地に教会を建て、地域のひとたちを巻き込みながら社会貢献を重ねていった先人たちの姿を思い浮かべています。
教会が、信仰の礎となった使徒の教えを受け継ぎ、その真理を世界にあかしすることができますように。
(29日の集会祈願より)
考える心
その人のことは、簡単なコミュニケーションからある程度わかるものです。
「コミュニケーションするということは、キリストが人間に対してしたように、身を低くすることです」
これは、前教皇フランシスコのお言葉です。
アメリカメジャーで活躍する大谷選手は、毎回打席に入る前に審判に挨拶する、唯一の打者だそうです。
多くの選手は最初の打席に入るときにキャッチャーに挨拶をしますが、大谷選手は毎回審判にも挨拶をするのだそうです。
さらには、相手チームのベンチにも試合前に挨拶をすると、アメリカのメディアが驚きをもって報じていました。
先週、デッドボールを受けた時、(監督は猛抗議で退場処分となりましたが)ベンチに向かって無事を強調し、「出てくるな」とばかりに手で制していました。
1塁に行き相手の選手と笑顔で会話する様子に、NHKの実況は「まるで親善大使のような」と表現していました。
大谷翔平選手、30歳です。
++++++++++++++++++++++++++
福岡教区青少年委員会では、11月に仁川教区への訪問が予定されています。
仁川教区の青年たちと共に交わり、分かち合い、信仰を強めることを目的とし、18~35歳までの信徒の募集を行っています。
久留米教会にも青年会があり、自主的にいろいろな取り組みをしています。
わたしが「青年」だったころには、そうした集まりはなかったように思います。
本当のことを言えば、その年代にはあまり教会に積極的に足を踏み入れてはいませんでした。
バチカン天文台のサマー・スクールに参加している若者たちとお会いになった教皇様は、学生たちに、「皆さんが体験することは、われわれ全体のためになるということを決して忘れないでください」と話され、自分が学んだこと、経験したことを、可能な限りできる方法で寛大に分かち合って欲しいと希望された、とバチカンニュースにありました。
[彼らは主から5つの能力の使用を授かった。
6番目として、知性が授けられ、7番目として、その働きを解く言葉が授けられた。]
主は彼らに判断力と舌と、目と耳とを与え、考えるための心をお与えになった。
主は知恵と知識で彼らを満たし、善と悪とを彼らに示された。
主は彼らの心に、ご自分への恐れを植えつけられた。
これはその業の偉大さを彼らに示すためである。
[主は人々にその不思議な業を代々に誇るようにさせられた。]
(シラ書17・5~8)
「今どきの若い者は、、、」という表現自体が死語ですが、わたしが20代だったころと今とではあまりにも社会の構造、価値観、生き方が違いすぎて、戸惑うことばかりです。
友人が自分の会社の広告原稿をChatGPTを使って作っている、と聞いて驚きました
ChatGPTでは、論文を要約させる、論文を解説させる、もちろん翻訳や書いた論文の校正もできます。
論文そのものを作成させることも可能、ということです。
・学会や大学によってはAI作成の論文は禁止されている
・下書きやサポート目的ならOK
なのだそうですが、自分で考えを巡らせて書き上げた論文なのか、コンピュータを駆使して創られた文章なのか、見極める先生方も大変なご苦労でしょう。
このページにこうして記事を書くときには、もちろんネットで情報を検索し、ネットのニュースも参考にします。
教皇様のXやインスタも見て、記事に織り込むこともあります。
そうやって、得た情報をもとに聖書を開き、心で感じたことを自分の頭で考えて書いています。
わたしは、自分の心で捉えたことを言葉にして書き留める、ことに喜びを感じます。
現代の学生たちが、自分の心と頭を十分に使えていない、とは思いません。
ただ、とても「控え目」な人が多い、と感じます。
一人1台のPCもスマホもなかったわたしが学生だった頃と比べて、心を鍛えて頭を働かせるチャンスがたくさん用意されています。
その機会を貪欲につかもうとするかどうか、なのでしょう。
神を知らない人々はみな、生まれつきの愚か者である。
彼らは目に見える善いものを通して、存在そのものである方を知ることができず、またその業に目を留めながら、その作者を認めなかった。
また、それらの力と働きに心を打たれる彼らであれば、それらを形づくられた方がどれほど力強い方であるかを、それらを通して悟ることができるはずではないか。
被造物の偉大さと美から推し量ることで、その造り主を認めることができる。
しかし、この人々の責めは軽い。
彼らは神を求め、見出そうと望みながら、迷っているのかもしれない。
彼らは神の業と慣れ親しんで、神を探し求める。
しかし、彼らは外観にだけ心を留める。
目に映るものがまことに美しいから。
(知恵の書13・1〜7)
目に見えない神を信頼し、見えない聖霊の働きを感じる わたしたちは、とても恵まれています。
「主は彼らに判断力と舌と、目と耳とを与え、考えるための心をお与えになった」
「被造物の偉大さと美から推し量ることで、その造り主を認めることができる」
自分の心で感じ取り、自分の頭で考え、行動することの大切さを忘れないようにしたいと思います。
初聖体を受けた時の気持ちを、彼らが忘れないでいてくれますように。
伝わる愛
宮﨑神父様の所属されている神言会の創立150周年を記念し、管区長のディンド神父様が久留米教会にミサを捧げにきてくださいました。
創立者である聖人の聖アーノルド神父と、聖ヨゼフ・フライナーデメッツ神父、お二人の聖遺骨が収められた十字架をお持ちになり、「神言会の司祭が働く教会に感謝するために訪問し、共にミサを」とおっしゃっていました。
ミサの司式中、言葉を発せられるたびに、正面ではなく全方向の信徒一人ひとりの方に目を向けてくださる様子にとても感動しました。

「愛とは何か。
トマス・アクィナスはいつものように簡潔に、『愛するとは、他者のために善を望むことである』と述べている。
したがって、神を自分の人生の絶対的な中心に据えることは、自分の人生を愛に適合させることを意味する。
あなたが贈り物として受け取ったものは、贈り物として与えなければならない」
ミネソタ州ウィノナ・ロチェスター教区バロン司教は、ご自分の出身校でもあるアメリカ・カトリック大学(CUA)卒業生へのメッセージでこうおっしゃいました。
アメリカだけではく、世界中の国が「自国を守るため」という間違った愛国心からくる政策を次々と打ち出しています。
先週は、ロサンゼルスで不法移民の摘発に抗議するデモ隊が治安部隊と衝突し、政府が州兵、さらには海兵隊まで派遣したことで事態がより悪化しました。
不謹慎な表現かもしれませんが、武装した警察や州兵が自国民に催涙弾を投げ、一部の暴徒化した人々が放火や略奪する様子を映像でみて、去年の映画『シビルウォー』が現実になったような錯覚を覚えました。
NYに住む姪(アメリカ国籍)の外国人のボーイフレンドは、トランプ政権の数々の政策(不法移民でなくとも強制送還された事例がありました)におびえ、旅行だとしてもアメリカから出国できずにいます。
教皇レオ14世は6/8、聖霊降臨祭のミサで行った演説で、世界各地でナショナリズムを助長してきたとする「排他的な思想」を拒絶するよう信者らに呼びかけました。
「心と思考の国境を開く」
「聖霊は境界を開放する」
「教会は人と人の間の国境を開き、階級や人種による壁を打ち破らなければならない」
などと述べられました。
パトリオティズムとナショナリズムは、根本的に全く違うものです。
ナショナリズムは、一国の文化、伝統、価値を重んじ、その国の利益と主権を最優先する思想です。
国の自主性と独立を強調し、外部からの干渉や影響を拒否します。
パトリオティズムとは、国や国民への敬愛の感情や態度を表し、他国への敵意や優越感を持たず、愛と尊敬の表現です。
ヨハネはイエスに言った、「先生、お名前を使って悪霊を追い出している人を見ました。その人はわたしたちの仲間ではないので、やめさせようとしました」。
イエスは仰せになった、「やめさせてはならない。わたしの名によって奇跡を行いながら、すぐにわたしをののしる者はない。
わたしたちに反対しない者は、わたしたちの味方である」。
(マルコ9・38~40)
この箇所は、信仰共同体の中においても外においても、他者に対して寛容であることの重要性を教えています。
ヨハネのように特権意識を抱くことは、信仰共同体にとって危険です。
イエスは、排他的な態度を改めるよう弟子たちに教え、信仰の多様な表現を受け入れる寛容さを促しました。
神の働きは私たちの枠を超えているという事実を認め、他者の信仰や行いを尊重する心を育てましょう。
サンパウロのホームページに寄稿されている福音解説には、このように書いてありました。
自国愛=排他的な愛国心、ナショナリズムによる世界のリーダーたちの政策が当たり前になりつつある現実は、キリスト教の精神からかけ離れています。
冒頭にご紹介した、トマス・アクィナスの『愛するとは、他者のために善を望むことである』という言葉を、いまこそ多くの人に伝えたい、そう思います。
サンパウロの神父様のコラムはこちら
https://www.sanpaolo.jp/category/column
++++++++++++
カンボジアから一時帰国している中島 愛さんが、現地での活動報告をしてくれました。
彼女の現地での様子がとてもよく伝わるプレゼンで、多くの信徒が耳を傾けていました。
共同祈願として、とても素敵な文面で祈りを捧げることができ、リンドー神父様と愛さん、お二方の愛を心の芯まで受け取ることができた日曜日でした。
様々な国で宣教をしている神言会の司祭、修道者のために祈ります。
これからも、それぞれの場所で創立者の精神を生き、み言葉を述べ伝えることができますように。
また、カンボジアでの宣教から一時帰国している中島 愛さんのために祈ります。
これからも健康のうちに現地の人々と、神様のみ手の中で過ごすことができますように。
ミサ、集う信徒
先週書いた、マルクス・アウレリウスの思想からもうひとつ、ご紹介したい哲学的考え方があります。
それは、「留保つき」の行動というものです。
結果が自分次第ではないこと、つまり、自分ではコントロールできないことを受け入れながら行動することを指します。
結果にかかわること、特に成功への期待を排除しながら行動する、ですが、結果への期待は自分の意志でコントロールできるので「留保つき」、と言うのです。
この考え方は、「成すべきことを成し、起こるに任せよ」「神の思し召しのままに」とも言い換えることができる、と本に書いてありました。
わたしはいつも、聖霊の導きを信じて神様に委ねると同時に、自分にできることは何かを考えて実行するように努めています。
この「留保つき」行動という考え方が、まさにそのことを表現していると思います。
このように行動すれば、人生に何が投げ込まれてもひるむことなく適応できます。
そして、たとえそれが失敗に終わったとしても、その経験を人生に生かしていける、と思えるのです。
経験豊かな人は知識をもって語る。
試練に遭ったことのない人は僅かなことしか知らない。
しかし、旅をした人は賢さを増す。
わたしは旅の折に多くのことを見た。
わたしの知識は語っても尽きるところがない。
わたしはしばしば死の危険にさらされた。
しかし、わたしはそれらの経験のお陰で救われた。
(シラ書34・10~13)
+++++++++++++++++++
昨日は、筑後地区の研修会が久留米教会で行われました。
テーマは「集会祭儀」
久留米教会はたいへん恵まれており、主日のミサは2人の司祭が執り行ってくださいます。
ジュゼッペ神父様はイタリアのミラノ宣教会の司祭で、聖マリア病院のチャプレンとして久留米に来られました。
(歳を言うと怒られますが)今年で89歳になられます。
宮崎神父様は、神言会の司祭です。
今年で74歳になられます。
先日のミサのお説教の際に、「わたしたちは二人とも歳をとっていますので、いつまでもいることはできません。そして、福岡教区には一人も神学生がいないという現実をよく考えてください。
召命のための祈りはもちろんですが、『集会祭儀』について信徒が理解しておくことが必要なのです」とお話になりました。
将来が不安になりますが、目を背けてはならない現実です。
お二人とも教区の司祭ではないし、ご高齢(怒られる)なのです。
集会祭儀とは、司祭が不在でミサをささげることが出来ない場合に、あらかじめ任命されて養成された信徒がミサの代わりに集会という形式で執り行う、みことばの祭儀です。
あくまでも、主日に感謝の祭儀を捧げることができない場合の補助的な祭儀ですが、実際に、全国にはこのやり方で主日のミサの代わりが行われている教会があります。
昨日の研修会では、田中重治神父様がこのテーマでお話をしてくださいました。
まず導入として、なぜわたしたちは日曜日に教会に集まるのか、ということからでした。
日曜日=主日とは、イエス様が復活なさった日曜日であり、わたしたちの前に現れてくださった日曜日である、ということを忘れてはならない、と。
日曜日、毎週わたしたちは復活祭、聖霊降臨祭を祝っているのだ、と。
キリストはご自身のことばのうちに現存しておられる。
聖書が教会で読まれるとき、キリストご自身が語られるからである。
教会が嘆願し、賛美を歌うとき、「二人または三人がわたしの名によって集まるところには、わたしもその中にいるのである」(マタイ18・20)と約束なさったキリストが現存しておられる。
(典礼憲章7)
集会祭儀が実際に福岡教区内で行われるようになるのは、まだ先のことでしょう、と田中神父様はおっしゃいました。
ですが同時に、一人の司祭が複数の教会で主日のミサを行っている教区があることも現実であり、その姿は望ましいものではないのだ、とお話になりました。
「日曜日に教会に行って聖体拝領することが目的ではありません。共同体が創られていくために、ミサを中心に司祭と信徒が集い、交わることが重要なのです。
ミサが終わって、すぐに次の教会へ司祭が奔走するようでは、それはなしえません。」
研修会に、20代の若い信徒の参加を強くお願いしました。
「あなたたちがわたしくらいの年代になった時に、久留米教会には司祭はいないかもしれないのよ!知っておいて欲しいの。」と。
集会祭儀については、また記事として書いてみたいと思います。
色々と考えさせられる、有意義な研修会でした。
お二人の大切な神父様に、まだまだお元気でいていただかないと!

困難の中に
『レジリエンス』
困難をしなやかに乗り越え回復する力のことをいう、心理学の用語です。
ローマ皇帝 マルクス・アウレリウスは、すぐれた哲学者でもありました。
彼の哲学(自省録)は、現代のわたしたちもすぐに実践できる現実的な教えが詰まっています。
痛みや病気に対処する方法について、マルクスは自省録のなかでこのように書いています。
病気になったときのわたしが、肉体的な苦痛について話すことはありません。
見舞客が来てもそんな話はしません。
話題はいつもどおり、哲学についてです。特に、哀れな肉体の中で起こる動揺を心に認めながらも、なぜ、特定の善を保っていられるかについて議論します。
ですから、わたしの人生は今まで通り順調に、そして幸せに進んでいます。
(『自省録』9-41)
マルクスの哲学では、痛みや病気、その他のどんな逆境に際しても、知恵の追及に集中することによってその精神的苦痛から解放されると説きました。
肉体的苦痛や症状について愚痴ったり、くよくよ悩んだりするのは時間の無駄だ、と彼は考えていました。
耐えられぬ痛みはわたしたちを死に導くが、長引く痛みなら耐えることが出来る
(『自省録』7-33)
苦痛に対するわたしたちの態度が動揺の大きさを決めている、とマルクスは言います。
痛みや病気そのものではなく、そのことに対する自分の考えや思いが、自分の現実となってしまうのです。
4月くらいから足の調子が悪く、しょっちゅう転んでいました。
そしてとうとう、5月の頭におかしな転び方をしてしまい、左手の親指を骨折しました。
家事ができなくなるから、とギブスで固定はせずに、痛みに耐えながら暮らしています。
転ばないように恐る恐る歩いていて、身体がこわばったようになって首と肩も痛めています。
ですが、わたしの心は沈むことはなく、晴れやかなままなのです。
大好きなシラ書の聖句が、今の気分を表現してくれます。
善きにつけ悪しきにつけて、人の心はその顔つきを変える。
楽し気な顔つきは、幸福な心の徴。
(13・25~26)
口を滑らすことがなく、罪の苦しみに悩まされることのない人は幸いである。
良心の責めに遭うことがなく、希望を失うことのない人は幸いである。
(14・1~2)
自分に対してきびしすぎる者が、どうして他人に対して親切にできようか。
(14・5)
食事を終えたとき、家族が「おいしかった!ごちそうさま!」と言ってくれると、痛みを忘れます。
病気でなかなかミサに来られない方に教会でお会いできると、嬉しくなります。
妹たち家族が楽しそうにしている様子を見聞きすると、安心します。
久しぶりに会った友人たちと近況報告をしあい、元気が出ました。
趣味を楽しむことができることに、感謝しています。
そしてさらに、2つの大きな出来事が、わたしの心を晴れやかにしてくれました。
このページを読むのを楽しみにしていて、いつも励まされている、というお手紙をいただきました。
お会いしたことのない方からのお手紙です。
そこに書かれたたくさんの素敵な言葉に、信仰で繋がる友情のような感覚を覚えました。
久しぶりに会った大学時代からの友人。
彼は講演で世界中を飛び回り、いつもキラキラしていると思っていました。
「急に体調が悪くなり、検査したら大きな病気が見つかった。来月手術するけど、どうせ入院するなら楽しんでやろうと思って、高い特別室を予約した!」と楽しそうに笑いながら話してくれました。
人間とは何ものなのか、彼は何の役に立つのだろうか。
その善、あるいはその悪は、どのような意味をもつのか。
人の寿命は百歳にまで及べばたいしたものである。
永遠の日に比べると、この僅かな寿命は、海の水の一滴、砂の一粒にすぎない。
それ故、主は人々を耐え忍び、その慈しみを彼らに注がれる。
主は人間のみじめな末路を見ており、知っておられる。
そこで、彼らにその赦しを豊かにお与えになる。
人の慈しみはその隣人に及ぶが、主の慈しみはすべての人に及ぶ。
(シラ書18・8~13)
日々の暮らしのなかで、抱えきれないほどのお恵みをいただいていることを、身体が不調なこの1か月ほどの間はいつも以上に感じ取ることが出来ている気がします。
健康で何も悩みのないときには、「もっと楽しいこと」「もっと良いこと」を追求してしまうのかもしれません。
マルクスは皇帝としての国務と哲学とに人生を捧げましたが、身近にいる人たちに愛される気さくで親しみやすい人物だったそうです。
厳粛ですが過度にではなく、謙虚だけど消極的ではなく、まじめだけど気難しいわけではなく、友人や家族と一緒にいることに大きな喜びを感じる人だった、と。
わたしは少し不自由なほうが、マルクスの言うようにお恵みの探究に心を研ぎ澄まして暮らせるようです。
これまでの人生で乗り越えてきたものと、徐々に蓄えてきた信仰心を通して、レジリエンスが身についているのかもしれません。
必要な助け
雨の季節が始まったような日も多くなってきました。
大相撲、今場所もかなり盛り上がり、毎日楽しませもらいました。
押し出しなどで力士が二人とも土俵から落ちた時、どちらかの力士が相手のことを気遣って手を差し伸べることがあります。
そこまで押さなくても、というくらい突き飛ばし、勝ち誇って興奮した様子の力士もいる中で、手を貸そうとする様子を見るととても嬉しくなります。
わたしは足が不自由なので、得することが多くあります。
どなたもすぐにわたしのことを覚えてくださる、どこでもどなたかが席を譲って座らせてくださる、など本当にたくさんあります。
旅行する際も、空港の方に駐車場まで車いすで迎えに来てもらい、搭乗口までスムースに移動でき、いつもとても助かっています。
助けが必要そうな人を見かけたら、躊躇しますか?
すぐに動くことはできますか?
自分が人の助けを必要としているとき、素直にそう伝えていますか?
わたしは自分がいつも周囲から助けられていることを実感していますので、そういうサインをかなり敏感に感じ取ることがあります。
その日、ある人々がユダヤから下って来て、「モーセの慣習に従って割礼を受けなければ、あなたがたは救われない」と兄弟たちに教えていた。
それで、パウロやバルナバとその人たちとの間に、激しい意見の対立と論争が生じた。
ファリサイ派から信者になった人が数名立って、「異邦人にも割礼を受けさせて、モーセの律法を守るように命じるべきだ」と言った。
そこで、使徒たちと長老たちは、この問題について協議するために集まった。
議論を重ねた後、ペトロが立って使徒たちと長老たちに言った。
「兄弟たち、ご存じのとおり、ずっと以前に、神はあなたがたの間でわたしをお選びになりました。
それは、異邦人が、わたしの口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためです。
人の心をお見通しになる神は、わたしたちに与えてくださったように異邦人にも聖霊を与えて、彼らをも受け入れられたことを証明なさったのです」。
(使徒15・1~8抜粋)
先週の朗読箇所のこの部分を読んでいて、「救い」とは「必要な時に与えられる助け」のことだ、と感じたのです。
割礼を受けて、律法を守った生活をしたうえでなければ信者として認められない、ということが議論されたと書かれています。
洗礼を受けていなければ救われないのか、という質問を受けることがあります。
そうではありません。
救いは、救われたと「信じる」から与えられたことが分かるものです。
神様が自分の祈りを聞き入れてくださったのだ、と素直に自然に受け入れることができる、それが信仰なのだと思っています。
救いは魔法のようにではなく、恵みと信仰が互いに織り成す神秘から来ます。
神が先に愛してくださることへのわたしたちの信頼と自由意志からの従順によっているのです。
教皇レオ14世 5/21のX(旧Twitter)
わたしが言いたいことを、偶然にもパパ様がXで明確にお伝えくださっているのを見つけました!!
神はわたしたちを救い、また聖なる招きをもって招いてくださいましたが、これは、わたしたちの業によるのではなく、神ご自身の計画とその恵みによるものです。
この恵みは、キリスト・イエスに結ばれているわたしたちに、永遠の昔から与えられ、今、私たちの救い主キリスト・イエスの現れによって明らかにされたものです。
わたしは信じてきた方をよく知っており、また、その方は、わたしに委ねたものを、「かの日」まで守ってくださる力があると確信しているからです。
(2テモテ1・9〜10、12)
必要な時に必要な助けの手が差し伸べられる、という神様への従順な信頼、それが信仰の恵みであることを忘れないようにしましょう。
++++++++++++++++++
万博に行った友人がリアルタイムで写真を送ってくれ、わたしも一緒に観ているように感じることができました。
1602~1604年制作のカラヴァッジョ「キリストの埋葬」
16世紀にミケランジェロが手掛けた石像「キリストの復活」
この2つが今回の万博で共に展示されていることに、深い意味を想います。
真実の種を蒔く
「デマを聞いた2人に1人はデマを正しい情報と信じた」「信じた人の4人に1人は知り合いにSNSで送った」という、総務省が行ったインターネット上の偽・誤情報の拡散に関する全国調査の結果がニュースになっていました。
菊池枢機卿は、ブログにこう書いておられました。
イタリアメディアを中心に、世界各国のメディアでは、様々な情報が飛び交っています。
なかには正確に、誰が何票得たのに、それがそのあとで大きく変わったのは、これこれこういう裏事情があったのだと、かなり断定的に書いているメディアがありましたが、わたしもそれを見ましたけれど、わたしが目の当たりにした事実とはかけ離れた数字だったので、何らかのストーリーを作るための推測の結果なのだろうと思います。
わたしたちのために聖霊の導きで新しく選出された教皇様、それが真実のすべてです。
何票で選出されたのか、といったことはゴシップの類の情報であり、わたしたちが心に留める必要はありません。
教皇レオ14世の誕生にあたり、日本カトリック司教協議会会長メッセージとして、菊池枢機卿はこう指摘されています。
枢機卿団は、教皇フランシスコの後継者を探しているのではなくて、使徒ペトロの後継者を捜し求めているのだということを、皆が心に深く留めていました。
枢機卿団が祈りのうちに求めたのは第二の教皇フランシスコの誕生ではなく、主ご自身から牧者となるように委ねられた教会を忠実に導く使徒ペトロの後継者でありました。
多くの枢機卿が、多様性を尊重しつつも、信仰における明白性を持って、教会が一致することの重要性を強調されました。
胸が熱くなるようなお言葉でした。
わたしたちは、新しい教皇様の選出を心から、祈りとともに待っていましたが、一般的には「映画のような」「隠されたドラマチックな展開」を期待していたのだとあたらめて感じました。
教皇レオ14世は、5/12に行われた報道関係者との会見での挨拶でこのようにおっしゃっています。
わたしたちは、進むことも報道することも困難な時代に生きています。
この時代はわたしたち皆にとって挑戦となりますが、わたしたちはそこから逃れてはなりません。
反対に、この時代は、わたしたち一人一人に、さまざまな役割と奉仕を通して、決して凡庸さに陥らないように求めます。
教会は時代の挑戦を受けています。
同時に、コミュニケーションとジャーナリズムも、時間と歴史の外に存在することはできません。
聖アウグスティヌスがこういってわたしたちに思い起こさせてくれるとおりです。
「わたしたちがよく生きれば、時代もよくなる。わたしたちは時代なのだ」。
わたしの父はよく「NHKでこう言っていたから、やってみる」(=NHKは真実しか伝えていないと信じて疑わない)という、素直な人です。笑
いつも、このページには私見を交えていろいろと書かせていただいています。
できるだけ、教皇様や神父様方がおっしゃったこと、書いておられる本の内容を軸にするようにしていますが、時々、真実をお伝えできていないかもしれない、と不安を感じることがあります。
ただひとつ、自信を持って言えるのは、丁寧に、心を込めて、学んだことをお伝えしようとしているということです。
ここを読んでくださる方にとって希望の種となる、信仰における真実を、わたしなりに蒔いています。
最後に、5/25の世界広報の日のために、故フランシスコ教皇が今年の1月にわたしたちに向けて伝えてくださったお言葉を抜粋してここに載せておきます。
わたしたちに希望が開かれ、注意深く、柔和で、思慮深く、対話の道を示唆するコミュニケーションの必要性が示されています。ですから皆さんを励まします。
ニュースのひだに隠された多くのよい物語を見つけ出し、それを伝えてください。
柔和でいること、ほかの人の顔を忘れずにいること。
あなたがたが働きを通して奉仕する人々の、心に語りかけること。
衝動的な反応によって、あなたがたのコミュニケーションが左右されないようにすること。
困難なときでも、犠牲を伴うときでも、実を結ばないように思えるときでも、いつだって希望の種を蒔き続けること。
傷を負ったわたしたちの人間性を回復させうるコミュニケーションの実践に努めること。
敵意のないコミュニケーションの証人となり、推進者となって、ケアの文化を広め、橋を架け、この時代の見える壁と見えない壁とを突き破ること。
わたしたちの共通の運命を心に掛け、未来の物語を一緒につづって、希望に満ちた物語を語ること。
第59回「世界広報の日」教皇メッセージ
https://www.cbcj.catholic.jp/2025/05/02/32234/
新しい時代
HABEMUS PAPAM(我らは教皇を得たり)
このラテン語は、新しい教皇が決まった時に枢機卿が宣言として唱える言葉だそうです。
ダマスコにアナニアという弟子がいた。
幻の中で主が、「アナニア」と呼びかけると、アナニアは、「主よ、ここにおります」と言った。
すると、主は言われた。「立って、『直線通り』と呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名の、タルソス出身の者を訪ねよ。今、彼は祈っている。
アナニアという人が入って来て自分の上に手を置き、元どおり目が見えるようにしてくれるのを、幻で見たのだ。」
しかし、アナニアは答えた。「主よ、わたしは、その人がエルサレムで、あなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか、大勢の人から聞きました。
ここでも、御名を呼び求める人をすべて捕らえるため、祭司長たちから権限を受けています。」
すると、主は言われた。「行け。あの者は、異邦人や王たち、またイスラエルの子らにわたしの名を伝えるために、わたしが選んだ器である。
わたしの名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを、わたしは彼に示そう」。
(使徒9・10~16)
わたしが受洗した時はヨハネ・パウロ2世でしたので、コンクラーベの様子を観たのは3度目でした。
これほどまでに今回の新教皇選出への関心が高かったのは、故フランシスコ教皇の世界平和の訴え、環境意識の向上につながる働きかけなどが、テレビやネットで広く、信徒以外にも響き、伝わったからではないでしょうか。
「聖霊の導き、教皇選出は自分たちの利害を越え、現代世界のなかでカトリック教会を誰に託すべきか真摯な祈りの中で決めるプロセスがコンクラーベです」と、イグナチオ教会の主任司祭の髙祖敏明神父さまがおっしゃっていました。
2011年のイタリア映画「ローマ法王の休日」では、コンクラーベの様子が少しコミカルな要素を入れて描かれています。
コンクラーベのシーンでは、枢機卿たちが「わたしを選ばないでください」と心の中で神に祈ります。
新しい教皇に選ばれた枢機卿が、就任あいさつに姿を見せないまま重圧から街へ逃げ出すものの、街の人々との交流を通して信仰心や教皇の存在意義を見つめ直していくという映画です。
ローマカトリック教会の教皇は、現代の世界政治の中で特殊な存在感をもつ、と感じる場面が多くあります。
社会学者のドミニック・ヴォルトンとの対話をまとめた本「橋をつくるためにー現代世界の諸問題をめぐる対話」のなかで、ヴォルトンは故フランシスコ教皇のことを「ラテンアメリカとヨーロッパの間に立つ、グローバル時代の最初の教皇」と言っています。
「彼の役割は、世界の政治指導者たちの役割とはまったく違うのだが、常に問題と対峙している」
「教皇がその肩に担っている責任の重圧を思うと、わたしはときとしてめまいを感じるほどだ」
とも表現しています。
本の中(対談)でヴォルトンが、「皆が言っています、カトリック教会は政治に介入している、と。あなたも、前任者たちも、なんにでもです。」と問いかけると、フランシスコ教皇がこうおっしゃっています。
「事前にさんざん反対されたところへも行きました。
たとえ安全上の問題があろうと、教会が何をすることができるかを言うためにです。
人々が平和に暮らせるようになるために、何をすることができるか?
わたしはいつも、学ぶために巡礼者として、平和の巡礼者として、そこに行くのだと言っています」
「福音宣教するということは、信者を獲得することではありません。
教会は、信徒獲得によってではなく、人を引き付ける力によって発展するのです。
政治が発展するのは人を引き付ける力によって、友情によってです・・・橋です、橋、橋なのです」
「フランシスコ前教皇のリベラルな路線を引き継いで、世界の人々を一つにするために『橋』を懸けてほしい」
そうインタビューに答えていた方がいました。
「フランシスコ教皇は教会改革を推進して保守派の反発を買い、同時に進歩派からは改革が十分に行われなかったという批判を受けていたため、プレボスト枢機卿はこのように分裂した教会で掛け橋役をする人物になる」、とイギリスのBBC放送が分析していました。
アメリカ大統領にトランプ氏が初めて選出され、オバマ前大統領の政策をことごとく廃止すると発言した時に、当時の久留米教会の主任司祭だった森山神父様(現・大分教区司教)がおっしゃいました。
「政治家は、政権が変わると簡単に政策の方向性を変えますが、カトリック教会の教皇は連綿とその意思を引き継いでいきます」
「私はあなたのための一司教であり、あなたと共にいる一人のキリスト教徒です。
対話と出会いの橋を架け、平和を実現できるよう助けてください」。
8日の選出後、初演説でのおことばです。
レオ14世、新しいパパ様のために祈ります。
現代に生きる信仰
故教皇様について、インターネット上にはさまざまなAIによる画像や動画がアップされています。
有名人が「わたしが謁見した時の写真」として掲載しているものの中には、真偽が疑わしいものも多くありました。
天国でイエス様(と思われる男性)や帰天した歴代の教皇様方と楽しそうに語らっている動画も数多くあり、観ていて少し怖さを感じました。
「そうであったらいいな」が、AIによって具体的な映像で見られるというのは、なんだか夢がないと思うのは時代遅れでしょうか。。。
+++++++++++++++++++
故教皇様の『実績』をさまざまに評価分析された記事や、次の教皇候補の枢機卿についての推測も盛んに書かれています。
前回の記事に書きましたように、他の宗教との対話を実際に推進されたことは本当に大きな功績だったのではないでしょうか。
第二バチカン公会議で取りまとめられた公文書には、次のようなものがあります。
(カトリック中央協議会が発行している、公文書改訂公式訳から抜粋してご紹介します。
数字は公文書のページ数です。)
教会はムスリムも尊敬の念をもって顧みる。
彼らは、唯一の神、生きていて自存する神、あわれみ深い全能の神、天地の創造者、人間に語りかける神を礼拝しているからである。
イエスを神としては認めないとしても、預言者としては敬っているし、その母である処女マリアをも尊び、時には彼女に敬虔に祈りさえもするのである。
(386頁)
この聖なる教会会議は、教会の神秘を探究しつつ、新約の民とアブラハムの子孫を霊的に結びつけているきずなに心を留める。
というのは、キリストの教会は、自らの信仰と選びの始まりが神の救いの神秘に基づいてすでに族長たちとモーセと預言者たちのもとに見出されることを認めるからである。
信仰によってアブラハムの子であるすべてのキリスト信者がこの同じ族長の召命のうちに含まれており、・・・・。
異邦人である野生のオリーブの枝が接ぎ木されたよいオリーブの木の根によって養われていることをも忘れることはない。
(387頁)
前者はイスラム教のことを、後者はユダヤ教のことについて書かれています。
イスラム教にはまずアブラハムを重視しているという共通点があり、イエスを預言者としては敬っていて、その母マリアも尊んでいます。
ユダヤ教については、キリスト信者は血縁としてアブラハムの子孫ではないにしても、信仰によってアブラハムに連なっているのだ、つまり旧約聖書と新約聖書は深い結びつきがあるのだ、ということです。
そして、公文書のこの続きには、「教会はさらに、教会の土台であり柱であった使徒たちも、世界にキリストの福音をのべ伝えた多くの弟子たちも、ユダヤの民の出身であったことを忘れない」と書かれています。
1962年~1965年に開催された公会議でこのように宣言されただけではなく、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教という3つの一神教は、さまざまな違いを抱えながらも、同じ原点を有するという大きな共通点を互いに認め合ってもいます。
そのことを、身をもって、実際に行われた対話をもってわたしたちに示して、あたらめて教えてくださったのが故教皇様でした。
わたしたちは、現代に生きるキリスト者として、他宗教への正しい理解とふさわしい言動を心がけるべきだと考えさせられました。
公文書のこの一文が心に強く訴えてきました。
人間の条件の秘められた謎は昔も今も人間の心を奥深く揺さぶるものであるが、人々はこの謎についてさまざまな宗教に答えを願い求めている。
たとえば、人間とは何か、われわれの人生の意義と目的は何か、善とは何であり罪とは何であるか、苦しみは何から起こりどんな目的をもつのか、真の幸福に達するための道とはどんなものか、死とは何であり死後の裁きと報いとは何なのか、最後に、われわれの存在を包むとともにわれわれの始まりともなりわれわれの行き先ともなっているあの名状しがたい究極の神秘とは何なのか、というように。
(385頁)
宗教を信じるということは、こういうことなのだ、と改めて確信しました。
自分の幸せを望むためではなく、簡単に答えの出ない問について長い時間をかけて考え尽くし、丁寧に人生を生きていくこと。
信仰とは、望んでいることを確信し、見えない事実を確証することです(新共同訳)
信仰は、希望していることを保証し、見えないものを確信させるものです(フランシスコ会訳)
(ヘブライ11・1)
今回の記事は、山本芳久さんの新刊↓を参考にしました。
橋をかけた教皇
2022年6月に作成された遺言に、教皇様は自らの遺体をローマ中心部のサンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂に埋葬するよう書き残しておられました。
(歴代教皇が埋葬されてきたサンピエトロ大聖堂ではなく)
天井に聖母マリアの有名なモザイク画がある教会で、教皇様が2013年の就任翌日に訪れていた聖堂です。
(それからも、頻繁にこの聖堂で祈りを捧げておられたようです。
宮﨑神父様がローマを巡礼で訪れた際にも、他の巡礼者はほとんどいない中、教皇様が祈られていたところに遭遇されたことがあったそうです。)
お墓は簡素で特別な装飾をせず、自身の名のラテン語名であるFranciscusとだけ刻んで欲しいとの遺言でした。
https://www.cbcj.catholic.jp/2025/04/22/31968/ ←遺言
「私は神を信じていますが、カトリックの神ではありません。
なぜなら、カトリックの神などいないからです。
おられるのは神だけで、私が信じるのはイエス・キリスト、つまり、人間の姿を借りて、この世に現れた神です」
(教皇フランシスコ、2013年10月1日、イタリア紙『ラ・レプッブリカ』の取材)
帰天される前の日、御復活祭のミサでの様子です。
かすれた声を絞り出すようにして、世界中に向けてメッセージをくださった様子が忘れられません。
He gave his all until the end.
教皇様は最期まで、本当に全てをわたしたちに差し出してくださいました。
教皇様は本(『橋をつくるために』)の中で、こうおっしゃっています。
父なる神は御子を遣わされましたが、その御子は橋なのです。
イエス・キリスト自体が神から人に架けられた橋であり、キリスト者も他者へと橋を架けていく存在なのです。
Summus Pontifex
ラテン語で教皇を意味するこの言葉は、pons(橋)+facio(作る)が語源です。
哲学者の山本芳久さんによると、教皇様が宗教改革500周年の際にルター派のイベントに参加して共同宣言を出したり、ユダヤ教・イスラム教の指導者と積極的に対話を度々行ったのは、単なる「宗教間対話」ということだけではなく、橋を架けていくことがキリスト教の本質に属しているという理解があったからだ、ということでした。
カトリックが説く「一致」は、同一化ではなく、さまざまなものがそれぞれでありながら「共鳴」する状態を意味する。
「共鳴」はときに厚い「壁」の向こうにも響く。
「壁」と「橋」はフランシスコの信念を理解する上で、鍵となる言葉だといってよい。
「壁」をなくし、「橋をかける」こと、それがキリスト者の考える「一致」にほかならない。
(若松英輔 著「いのちの巡礼者 教皇フランシスコの祈り」より)
27日のミサでは、宮﨑神父様が2019年の長崎でのミサの思い出をお話しされました。
「朝からの大雨と寒さで、皆震えながらミサが始まるのを待っていたのを覚えているでしょう。
ところが、いざ教皇様が登場される時間になると、雨は止み、青空が広がり、汗ばむほどの陽気になったのでした。」
天国での永遠の安息をお祈りします。
ありがとうございました。
御復活のちから
主の御復活、おめでとうございます。
世界中で、西方も東方も、すべてのキリスト教の教会で同じ日に御復活が祝われた今年は、特に考えるとことろがありました。
最も古いマルコ福音書の注解書には、次のように書かれている箇所があります。
「イエスは、自ら罪を負うことでわたしたちの罪を取り除いたように、自らの顔を覆うことでわたしたちの心の覆いを取り除き、唾を吐きかけられることでわたしたちの魂の表を洗い清め、自ら頭を殴打されることで人類すなわちアダムの頭を癒し、自ら平手で打たれることで、彼はわたしたちの手と唇を通して最高の賞賛という喝采を受けました。
自らの十字架によってわたしたちの苦悩を取り除き、自ら死ぬことによってわたしたちの死を滅ぼしました。
彼が受けた侮辱は、私たちの恥辱を取り除きます。
彼が縛られることで、わたしたちは自由の身となりました。
彼が頭にいばらの冠をかぶることで、わたしたちは神の国の栄光を手に入れました。
彼が受けた傷によって、わたしたちは癒されました。
彼が葬られたことで、わたしたちは復活します。
彼が陰府に下ったことで、わたしたちは天に昇るのです。」
死者の中から復活し、今現在もわたしたちのそばで生きておられるイエス様。
イエス様の受難を黙想することは、その苦しみのすべての瞬間に思いを馳せ、ご自身を与えてくださったことが今の現実のわたしたちの人生を変えてくれる力となっていることを認識するために有効です。
聖週間の始まりに、とても心が苦しくなる出来事が二つありました。
知り合いの音楽家が、交通事故で楽器の演奏はもうできないほどのケガを負ってしまいました。
同じ歳で、とても活躍している方でした。
友人の子どもが難病を患っていることを知らされました。
治療法が見つからず、検査しては新しいお薬を試す、の繰り返しの日々で、友人は精神的に参ってしまっています。
2人の気持ちを考えると心が苦しく、胸が張り裂けそうです。
もしキリスト教の信仰を持たない方であっても、神様は背中に手を当てて、「大丈夫だよ」と言ってくださる気がしています。
聖年の御復活には、いつも以上に力強いわたしたちへの励ましが与えられると信じたいのです。
この季節に、このタイミングで二人の苦難を知り、わたしが今できることはないか考えて過ごしています。
音楽家として再起できないこと、病気とともに生きていくこと、に対してはわたしは何もできません。
ですが、友人として、寄り添う以上のことはできるはずだ、と思っています。
「寄り添っているよ。」
「いつも祈ってるよ。」
「神様に委ねれば大丈夫よ。」
そういう励ましは、一方的なものに過ぎないと思うのです。
実際にできることは何かを考えて行動することも、やはり時には必要です。
さて、十一人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスがお示しになった山に行った。
そして、イエスを見て伏し拝んだ。しかし、疑う者もいた。
イエスは弟子たちに近づき、次のように仰せになった、「わたしは天においても地においても、すべての権能が与えられている。それ故、あなた方は行って、すべての国の人々を弟子にしなさい。父と子と聖霊の名に入れる洗礼を授け、わたしがあなた方に命じたことを、すべて守るように教えさなさい。
わたしは代の終わりまで、いつもあなた方とともにいる」。
(マタイ28・16〜20)
降りかかる災難や苦難の中にある人は、神の存在もお恵みも癒しも、信じられずに疑うことがあるでしょう。
その時こそ、そこに寄り添うわたしたちが、諦めずにイエス様の教えを実践する時なのではないでしょうか。
「友のために自分の命を捨てる」
自分自身、心も時間も割いて、友のために生きる時間を作ることを決意した聖週間でした。
これは、わたし自身に与えられた神様の御復活の大きなちから、だと痛感しています。
++++++++++++
復活徹夜祭には3名が、復活の主日には6名の子どもが受洗し、久留米教会の一員として新しく生まれ変わりました。

”しるし”としての教会
いよいよ、聖年の年の聖週間が始まります。
滑り込みで告解、赦しの秘蹟に与ることができ、心が晴れやかになった日曜日でした。
13日の受難の主日、300名を超す参列があった久留米教会のミサの様子です。
先日、福岡教区の各教会の広報担当者の集まりがあり、参加しました。
福岡県、佐賀県、熊本県で構成される福岡教区ですので、遠方から出席された方も多く、各教会の広報の取り組みについて発表がありました。
その中で、ある方が「誰のために広報をするのか。誰のための広報誌、ホームページなのかをちゃんと考えて運営しなければならない」という趣旨のことをおっしゃいました。
私自身の発表の際には、「久留米教会の広報誌は、信徒のために作っています。ホームページは、久留米教会やカトリックの信仰に興味を持って検索してくださる方に情報を発信するために、と運営しています」と発言しました。
ところが、先週の記事を読んだ方から、「難しくてややこしいことを書かれるので、ついていけません、、、。」という感想をいただいたのです。
あなた方は世の光である。山の上にある町は、隠れることはできない。
ともしびをともして、升の下に置く人はいない。燭台の上に置く。
こうすれば、家にいるすべての人々のために輝く。
このように、あなた方の光を人々の前に輝かせなさい。
そうすれば、人々はあなた方の善い行いを見て、天におられるあなた方の父をほめたたえるであろう。
(マタイ5・14~16)
イエス様は、誰にでも理解できるように、喩えを用いてその教えを人々に伝えました。
おそらく、モーセ5書や守るべき(と当時されていた)律法はすべて頭に入っていたでしょうが、そのような小難しいことは話されずに、暮らしに根付いた喩え話をされました。
「カトリックとはどんな教えなのだろう」
「久留米教会はどんなところだろう」
そう思ってネットで検索してくださる方が、わたしの書いた「ややこしい」文章を読んで、教会に行ってみようと思えるはずがありませんね、、、。
反省です。
イタリア語の“アジョルナメント(aggiornamento)”という言葉をご存じでしょうか。
ヨハネ23世教皇が使用された言葉で、「時のしるし」を見極めて教会の教え、あるいはあり方を「現代に適したものにすること」を意味しています。
教皇様によれば、世界は刻々とそして大きく変化しているのに、カトリック教会は旧態依然、閉塞状態にある。
だから、「キリスト教の教えのすべてが、現代に、人から新たな熱意と明るいおだやかな心をもって迎えられる」(第2ヴァチカン公会議開会演説)ために、教会の窓を大きく開いて、今の時代にもっと「適応」する必要がある、ということでした。
第2ヴァチカン公会議は、1962~1965年に開催された会議です。
それから60年経った現在、わたしたちの信仰は今の時代に適応し、教会が開かれているでしょうか。
少なくとも、広報の役割を任せていただいているからには、久留米教会の”しるし”=開かれた信仰の場であることが伝わるようにもっと研鑽をつまなければ!
先週ご紹介した本の中で、ズンデル神父様はこのようにおっしゃっています。
人間社会の中での主の現存の継続、そのしるし、それを伝えるもの、これが教会である
キリスト教というものが、教会という形で私たちのあいだに住まわれる主の真の現存だからである
大切なのは私の救いではなく、私たちの手の中に託された神のいのちなのである。
キリスト者の召命は神の顔となること。
教会とは私たちであって、自分が生きた福音となる責任を感じながら、一人ひとりが他の人々にとって神の顔となるように努めるなら、今日の世界には喜びがあるであろう。
わたしたち一人ひとりが教会のしるしとなる、それがキリスト者の目指す生き方だということなのだと思います。
四旬節に思う
今年は朝晩の肌寒さがまだ続いていることが幸いし、桜を愛でる期間が長いので、我が家から見える耳納連山の中腹のいたるところにピンク色に染まった箇所が楽しめます。
イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が激化していた昨年、アメリカ各地の大学キャンパスでは、学生らが敷地を占拠し、ガザでの戦争に抗議する動きが盛んに行われていました。
そしてその後、大統領が変わり、激しい抗議行動が起きた名門大学を標的に、連邦資金を剥奪する大統領令が出されました。
さらに移民局に対し、グリーンカード(永住権)所持者を含め、デモに参加した外国人学生を国外退去させるよう指示しています。
政府の助成金の停止を言い渡されているのは、名門のプリンストン大学、コロンビア大学、ペンシルベニア大学、ハーバード大学
https://japanese.joins.com/JArticle/332014
これまで守られてきた権利がいとも簡単に壊されています。
国益最優先という標榜の下、無駄を無くすために数万人単位で連邦職員が解雇されています。
世界では、民間企業のアメリカへの投資を中止する動きも始まり、報復の応酬が活発化しそうです。
変わらないと思っていたことが、こうも簡単に、大きく右に舵を切る様子をニュースで見聞きするたびに、イエス様の時代にインターネットが存在していたらどうなっていただろう、と想像します。
さて、過越の祭りと除酵祭が、二日後に迫っていた。
祭司長や律法学者たちは、策略を用いて何とかイエスを捕らえ、殺そうと謀った。
しかし、彼らは、「祭りの間はいけない。民衆が暴動を起こすかもしれない」とも言っていた。
(マルコ13・1〜2)
当時、過越祭の間の町の人口は通常の3倍ほどになったようです。
ユダヤ人たちの民族意識が最高潮に達するこの時を、あえて意図的にイエス様はご自分の使命の頂点の時として選ばれました。
(カトリック聖書注解「マルコによる福音書」メアリー・ヒーリーより抜粋)
情報があまりにも早く伝わるために起こること(例えば、韓国の大統領の罷免の裁判の際のデモ)を見ていて、イエス様のことを考えていました。
もし、あの時代に、イエス様が人々に語られた数々の言葉があっという間に世界に伝播していたら、いま私たちが信じているキリスト教はすぐにその流行が途絶えたのではないか、と思うのです。
使徒たちの命がけの宣教、初代教父たちの命を削るほどの奮闘。
2000年以上の歳月をかけて熟成され、イエス様の語られたことの本質を研究してきた学者だけでなく、信徒一人ひとりが教えを生活の中で昇華させてきたのが、現代のキリスト教です。
先日のサンパウロの出張販売で見つけた、この本を今読んでいます。
出だしから、目が覚める思いでした。
ズンデル神父は、50年ほど前に亡くなられたスイス人司祭です。
1930年代にはあまりに独創的すぎたその神学的思想、司牧の仕方などで、教会側からはほとんど無視され、同僚司祭たちからもつねに疑いの目で見られていたそうです。
何冊かの本を出されたのですが、この本は、彼の思想を一冊にまとめたものです。
少し、抜粋してご紹介します。
(紫の文字が本からの抜粋です)
「確かに、神のうちにはイエスの死の原因となった現実が永遠に存在しているはずです。
そしてある意味で、死ぬのは神であり、苦しむのは神であると言えるのです。
主のご受難にふさわしい次元を与えるためには、苦しむのは神であり、死ぬのは神であると言わねばならないのです」
公教要理にはこうあります。
「キリストは、その人性において、苦しみ、そして死んだ。
神性においては、苦しむことも、死ぬことも全くできなかった」
この箇所に照らしても、ズンデル神父の思想が当時は異端のように感じられていた、と本に書いてあります。
本のなかで解説を書かれている方は、こうおっしゃっています。
存在論的に言って、神は死ぬことはできない、それは確かです。
しかし、その死ねない神が死んだ、のがキリストの受難のことです。
愛の神秘です。
もし、人間キリストが死んだ、というだけのことなら、神秘でもなんでもありません。
ソクラテスも釈迦も、孔子も、すべて偉大な人が皆死にました。
その人たちの偉大さは「生き方」にありました。死んだことではありません。
もっと長く生きて、豊かな教えを説いてくれたほうがよかったと言えます。
これに対し、キリストの場合は違います。
そこでは、死そのものが生の無限の重味をあらわす神の愛の神秘となります。
ズンデルは、このことを明確に言ったまでです。
「死ぬのは神」という、この単語だけ見ると混乱するような思想に、目が覚める思いがしたのです。
キリスト教の教えの本質は、2000年前から変わらないはずです。
「神はあのときに死んだ」ということ。
わたしたちは、「復活された神」にいまこの瞬間も守られているということ。
イエス様の神としての死が意味することについて、四旬節のこの時こそとくに黙想したいと思います。
お恵みを受け取る
もう2週間以上も体調がすぐれず、風邪やコロナでもなく、黄砂と花粉が原因と思われる、むせかえる咳に悩まされています。
聖書を開いて今週の記事を書く、という気持ちの余裕がありませんでした。
それでも、毎日の小さなお恵みを見逃さずにノートに書き留める習慣は、忘れずに続けていました。
「主に感謝せよ、主は恵み深く、その慈しみは永遠」。
主に贖われた者は言え。
主は彼らに敵対する者の手から贖い、もろもろの国から、東と西、北と南の海から集められた。
彼らが悩みのあまり主に叫ぶと、主は彼らを苦しみから救い出された。
主はまっすぐな道に彼らを導き、人の住む町にたどりつかせた。
主の慈しみと、人の子らへの不思議な業に感謝せよ。
主は渇ききった魂を満ち足らせ、飢えた魂を善いもので満たされた。
(詩編107・1〜9)
お恵みノートは、20年近く続けている、わたしの習慣です。
お恵み=良かったこと、嬉しかったこと、幸せを感じたこと、思いがけない喜び、など、1日にひとつもなかったことはありません。
そんなことがお恵み?と思われるかもしれませんが、小さな喜びや幸せを受け取ると、「神様、ママ、ありがとうございます」と思わず呟くのも、わたしの長年の習慣なのです。
先日書いた、職場でのストレスの原因の人が、「お昼に食べて」とたこ焼きを買ってきてくれました。
(さすがにわたしへの態度が悪かったことを反省したのか!?)
洗濯機が壊れ、新しいのを買うしかない、と家電店に行ったら、「もったいないので修理したほうがいい」と思いがけない提案をされ、年度末の繁忙期にも関わらず迅速に対応してもらえました。
体調を崩していることを知った教会の方が、栄養ドリンクとケーキを届けてくれました。
別の教会の方も、「道の駅であなたが好きなお野菜(セリ!!)見つけたから」と色々なお野菜を買ってきてくれました。
こうしたわたしなりのお恵みを見逃さずに受け取ることで、心のキャパシティのうちの不安・悲しみ・寂しさが占める割合を減らすようにしています。
弱った手を強くし、
ふらつく膝をしっかりさせよ。
心に不安を抱く者たちに言え、
「強くあれ、恐れるな。
見よ、お前たちの神を。
神の報いが来る。
ご自身が来られ、お前たちを救ってくださる」。
(イザヤ35・3〜4)
体調がすぐれないと、どうしても気持ちまで落ち込んでしまいます。
自信をなくし、心に占める不安や心配事の割合が大きくなるのを感じます。
それでも、神様が毎日の暮らしの中にもお恵みを与えてくださっていることを感じることができる、それ自体がお恵みだと思えると、元気が出るのです。
教皇様の体調が心配です。
教皇様は、回心し、悔い改め、神のいつくしみを受け入れるべき時であるこの四旬節に、自分たち自身がまず何よりも神のゆるしの対象であることを忘れないように、と指摘されています。
宮﨑神父様がお説教でおっしゃいました。
「赦してもらうのだから、自分も人を赦さなければなりません。
隣人を赦して受け入れること、放蕩息子のたとえの“兄の心“を持たないこと。
特にこの四旬節は心がけてください。」
自分が日々受け取っているお恵み、神様がわたしたちの日々の罪をも赦してくださるというお恵みを、もっと深く噛み締めたいと思います。
信仰を噛みしめる
わたしは、33年前の御復活祭に受洗しました。
今年が33回目の四旬節です。
その年の3月22日に、まだ桜の便りはなかったような気がします。
33年前、久留米教会での御復活祭の写真です。
.
先週の来住神父様のnoteには、こう書いてありました。
「私が洗礼を受けたのは1981年です。
今年が43回目の四旬節です。
43年のうちに、良くも悪くも平穏であろうと思っていた人生が意外に難しいとわかって来ました。」
来住神父様は、洗礼を受けていたから、聖書を読んでいたから、自分に降りかかった苦しみの意味を考えざるを得なかった、とおっしゃっています。
受洗を控えた方が、「まだ悩んでいる」「疑問がたくさんある」「心が定まっていない」、といったことをおっしゃるのを聞いたことがあります。
わたしが洗礼を受けた時、受洗への迷い、信仰・聖書への疑問など、持ち合わせるほどに考えもしていませんでした。
周囲から、「あなたは神様の子だ」「インマヌエルだ」と何度も言われて(調子に乗り)、洗礼を受けることは「正式な信仰の始まり」のような気持ちでした。
来住神父様が書かれているように、わたしもこれまでの年月、人間として成長していく過程に信仰と聖書があったことは何よりの救いでした。
神様に「どうしてですか?」「どうしたらよいですか?」と訴えることができた、そう言える対象は、最高の相談相手でした。
主に信頼し、主を望みとする者は祝福される。
その人は水辺に植えられ、流れの方にその根を伸ばす木。
暑さが来ても恐れず、その葉は青々としている。
旱魃の年にも心配はなく、実を結ぶのをやめることはない。
心はあらゆるものに勝って偽るもの、たばかるもの。
誰がこれを究めえようか。
わたし、主が心を調べ、思いを吟味する。
各々をその振る舞いに応じて
その行いの実に応じて報いるために。
(エレミヤ17・7~10)
(アンダーラインの箇所、聖書教会共同訳の聖書では、「主である私が心を探り、思いを調べる。おのおのが歩んだ道、その業が結んだ実に応じて報いるためである」となっています。)
信頼して望みをかけることができるよりどころがある、それが信仰の醍醐味です。
しっかりと根をはり、葉を青く茂らせ、実を結ぶように、心と心の芯(はらわた)を強く整えてくださる神様。
憂いを和らげてくださる神様を信頼する以外に、人生に降りかかる様々な問題を解決する術を知りません。
とはいえ、わたしがちゃんと聖書を読むようになったのは、この15年ほどです。
信仰について噛みしめて核心を持てるようになったのは、この10年ほどです。
いつもここに偉そうなことを書いていますが、書きながら噛みしめることが、ここ数年のわたしの信仰の基盤になっているのです。
自分が今歩んでいる道が実を結ぶように、と心がけながら。
あなたの立てた決心を思い起こし、十字架上の救い主の面影を、常に自分の眼前に置きなさい。
イエス・キリストのご生涯を思うなら、大いに恥じるべきことがあるはずである。
なぜなら、あなたは長い間、神の道に入っていながら、未だに、イエスに自分を一致させようと、真剣に努力していないからである。
彼の聖なるご生涯とご受難とを、熱心に、注意深く黙想するキリスト者は、自分に有益で必要なものを、そこに多く見出すであろう。
イエスにまさる何かほかのものを探す必要はないはずである。
(「キリストに倣いて」 第1巻第25章6)
3/20長崎・浦上教会での司祭叙階式には、久留米教会からバスで34名が参列しました。
久留米で司牧実習をしてくださったホンさんの、晴れやかな、新しい出発の日でした。
来月の御復活祭で洗礼を受けることになっている方が、中村大司教から祝福をいただいた時に、「よくいらっしゃいました」と声をかけられたそうです。
「祝福が心に染み渡りました」と感激されていました。
わたしたちキリスト者には、このように、信仰を噛みしめる幸せな瞬間があります。
愛する者よ、あなたの魂が幸いであるのと同じように、万事において恵まれ、また、健やかであるようにと祈っています。
兄弟たちが来て、あなたが真理のうちに歩んでいることを証ししてくれたので、わたしは非常に喜んでいます。
事実、あなたは真理のうちに歩んでいます。
わたしにとって、子供たちが真理のうちに歩んでいると聞くことほどうれしいことはありません。
(3ヨハネ1・2~4)
この聖句は、友人がわたしの誕生日プレゼントに添えて送ってくれた箇所です。
こうして信仰の分かち合いができることも、幸せなお恵みです。
ストレスと向き合う
今年の四旬節にあたっての教皇様のメッセージ、この一文が目と心に留まりました。
「この四旬節、神がわたしたちに求めるのは、生活において、家庭で、職場で、小教区や諸共同体において、他者とともに歩めているか、その声に耳を傾けられているか、自己中心的になったり自分の必要だけを考えたりする誘惑に屈せずにいられているかということです。」
https://www.cbcj.catholic.jp/2025/02/28/31569/
皆さんは、どのようなことに、どのようなときにストレスを感じますか?
わたしは最近、いろいろなことにストレスを感じて疲れてしまっている気がしていましたので、ストレス度自己テスト、というのをネットで見つけてやってみました。
日常生活でのストレス、職場でのストレスの2つのパターンでテストしてみたのですが、「あなたは『軽度のストレス状況』(多少のストレスはあるが、大きな問題はない)にあるようです。」という結果でした。
ようは、自分で「自分はストレスを感じている」と思い込んでいるだけで、心とからだには大した不調はない、ということがよく分かったのです。
つまり、「自己中心的になったり自分の必要だけを考えたりする誘惑に屈していた」ということを自覚しました。
⚫︎人々を不安にするものは、事柄それ自体ではなく、その事柄に関する考え方である
⚫︎自分ではどうしようもない物事は軽視せよ
⚫︎自由に生きていくうえで重要なことは、自分がどのような人間かをしっかりと把握し、自分の強みに磨きをかけることだ(日々、内省すること)
古代ローマの奴隷出身のストア派哲学者、エピクテトスの残した格言です。
古代ローマの人々も、やはり人間関係や仕事のストレスを抱えていたと思われます。
⚫︎ストレスを感じているのは、自分の意に沿わないからなのではないか、と立ち止まって考えてみる
⚫︎夢に出るほど考えたところで、明日何かが変わるわけではない
⚫︎今日の自分の言動は本当にあれで良かったのかを毎晩反芻し、明日はよりよく過ごすこと
エピクテトスの言葉に沿ってみると、うまくストレスと向き合える気がしてきました。
主よ、わたしたちを思い起こし、この悩みの時、あなたご自身をお示しください。
わたしに勇気をお与えください。
すべての主権を統治する方、神々の王よ。
主よ、あなたの手をもってわたしたちをお救いください。
わたしをお助けください。
わたしはただ一人、わたしにはあなたのほかに誰も助け手はおりません。
すべてに勝って力ある神よ、絶望のうちにある者の声を聞き、悪を行う者の手からわたしたちをお救いください。
また恐れからわたしをお救いください。
(エステル記C 23,25,30)
ストレスを感じていると思う時は、神様への信頼が損なわれている時かもしれません。
わたしのストレスの多くは仕事に関することですが、いつも結局はこう自分に言い聞かせて落ち着くようにしています。
「母が感じていたストレスに比べたら、こんなことはちっぽけな悩みに過ぎない」
わたしたちは四方八方から苦しめられていますが、行き詰まりはしません。
途方に暮れますが、望みを失いはしません。
迫害されますが、見捨てられはしません。
打ち倒されますが、滅びはしません。
わたしたちは、いつもイエスの死に瀕した状態を体に帯びています。
それはまた、イエスの命がこの体に現れるためでもあります。
実に、わたしたちは生きていますが、イエスの故に絶えず死の危険にさらされています。
イエスの命が、わたしたちの死すべきこの身に現れるためです。
そこで、死がわたしたちの内に働いでいますが、命があなた方の内に働いていることになります。
(1コリント4・8〜12)
パウロが献身的に働いていた宣教活動において受けた苦しみは、そのことを通してイエス様の死が働き、自分自身と信徒たちにイエス様の命を現すための犠牲だったのです。
地下鉄サリン事件から30年です。
事件から25年後の2020年に最高裁で判決が確定し、オウム真理教の後継団体「アレフ」が支払い義務を負う賠償金約10億円が未だに支払われていないことをニュースで知りました。
東日本大震災から14年です。
福島原発の廃炉への工程が予定通りに進んでいないことも懸念されます。
物事の解決には、なんと時間がかかるのだろうかと痛感させられます。
30年前のテロの犠牲者のご家族、いまだ後遺症やトラウマに悩む方々。
帰還者が想定通りに戻らず、故郷の再生に不安を抱く地域の方々。
そのような方々の抱えるストレスを想像すると、日々のちっぽけなこと(目をつぶればいいこと、気にしなければいいこと)にストレスを感じたわたしが恥ずかしくなります。
今週のお恵みは、ストレスと向き合う方法をこうして神様と母がわたしに気づかせてくれたことでした。
無償の愛
曽野綾子さんが帰天されました。
20代前半、いろいろ悩んでいた時期に曽野さんの本を読み漁っていたのを思い出し、いまでも大切にとってあった『天上の青』を読み返しました。
ヘブンリーブル―という鮮やかな青い朝顔に引き寄せられて、ふと、雪子の家を訪問するようになった富士男。
彼は、適当に狙いを定めた女性や子どもを次々に、大した理由もなく(本人には明確な理由があるのですが)殺します。
それでも、ふらっと雪子の家に来ては、お茶を飲み、お菓子を食べながら素直な様子でおしゃべりをすることが唯一の救いのような楽しみでした。
そして、ある事件をきっかけに富士男は逮捕されます。
(以下、紫の太文字は本からの抜粋です)
「今、良識ある行動というのは、一切黙っていることであり、宇野富士男に関することは総て忘れることだということは、わかっている。しかしそう思う傍ら、雪子はそのような自分の判断に恐怖を抱いた。
その人は確かにこの世にいるのに、その人の存在が都合悪くなると、あたかもその人がいなかったように無視せよ、と言う。
それが良識、というものなのだろうか。
それが、正しい、人間的な行為なのだろうか。
聖書の中には、イエスと悪人との関係がいくつも明瞭に記されている。
それはともすれば溺れそうになる感情の深淵から這い上がった上での悲痛なまでに理性的な選択だった。」
そうして、雪子は留置所の富士男に手紙を書くのです。
「この手紙は、あなたの手に届くのかどうか、私は知りません。差し入れということができるとも聞きました。
私にできることがあったら致します。
あなたには私など必要ないかもしれません。
しかしもし、何かの事情で、ご家族にそういうことがおできにならないような状況になった時は、私がしましょう。
あなたが、私の身内でしたらこう言うだろうと思います。
今いる所と時間を、どこであろうといつであろうと、自分を育てるために使ってください、と。
あなたが、ご自分を失われないことを祈っております」
どうしたらこのような気持ちになれるのだろうか、と初めて読んだ時は理解できませんでした。
さらに、雪子は富士男のために弁護士を見つけて費用を負担しようとします。
相談に行った教会の司祭からも、ごく普通に考えても死刑になる可能性が大きい人のために、なぜかなりの額のお金を払うのか、あなたの気持ちが何のためなのですか、と問いかけられます。
雪子の答えはこうです。
「同じ死刑になるのでも、それまでが、大切だと思うんです。
見捨てられて死ぬのではいけないんです、誰でも。」
雪子は帰り道、「あなたと神の間になにがあるか、ということだから」としか言ってくれなかった司祭のことを「何も進路を教えてくれなかった」と考えていました。
少し考えてから、司祭の深い配慮を感じるようになります。
余計な指示は出さずに、だたよく祈って決めるように、と背中を押してくれていたのだと。
こうしてずいぶん時間を置いて読み返してみて、最初は理解できなかった雪子の気持ちがすーっと心に入ってきたことに驚きました。
富士男は、いびつな愛情を雪子に抱いていますが、雪子は恋愛感情も明確な友情も感じているわけではありません。
20代のわたしには分からなかった、真の無償の愛を持って、最後まで富士男と誠実に向き合う様子に涙がこぼれます。
聡明な愛は、愛する相手の贈り物よりも、むしろ贈る者の愛を重んじる。
彼は価よりもむしろ愛情に注目し、愛する者の次に贈り物を置く。
崇高な愛をもつ人は、受けた贈り物に満足せず、あらゆる贈り物にまさって、神であるわたしに満足する。
(「キリストを生きる」第3巻 第6章 2)
ネタバレをしますが、留置所の富士男との文通の中で、彼は「たった一言答えを聞かせてほしい。愛していてくれるなら、控訴しない」と書いてよこします。
それに対し、雪子は「同じ時に生まれ合わせて、偶然あなたを知り、私はあなたの存在を悲しみつつ、深く愛しました」と返事を書くのです。
1994年にNHKでドラマ化されました。
雪子は桃井かおりさん、富士男は佐藤浩一さんです。
最後の「愛している」の重要なシーンで、ドラマでは「愛していません」と雪子は返信したのです。
インタビューで桃井かおりさんが、「聴衆を信じようよ、と監督と話し合い、原作・脚本と違うように変えた」とおっしゃっていました。
(このインタビューは衝撃だったので、よく覚えています)
当時は、桃井さんの考えも深くは理解できませんでした。
そして、愛とは親子の愛と恋愛のことだ、と思っていました。
色々な経験を積み重ね、信仰についても自問自答しながら生きてきた今、はっきりと無償の愛とはそういうものなのだと、今回読み返してみて素直に思えたことは、新たな発見でもありました。
・・・・・・・・・・・・
9日のミサでは、御復活祭で洗礼を受ける2名の方の洗礼志願式が行われました。
今年の四旬節は、教皇様のご病気への心配が拭えないままにスタートしましたので、とても嬉しいミサとなりました。
この道を歩む
フランシスコ教皇の病状について、先週は「午前中は治療を受けられ、午後は個室に付属した礼拝堂で祈り、聖体を拝領された。そして仕事上の作業に専念された。」という表現が続いていましたが、週末には人工呼吸器を装着されるまでに病状が進行しました。
山火事が広範囲で発生した岩手県大船渡市だけでなく、山梨県大月市、静岡県函南町でも山で火災が起き、甚大な被害が広がっています。
教皇様のためには「苦しみを少しでも早く取り除いてください」、山火事のことについては「地域の人々の不安を少しでも早く取り除いてください」と祈り続けています。
祈りの力を信じたい。
・・・・・・・・・・・・・
わたしとてみなと同じく死すべき者である。
土で形づくられた最初の人の子孫であり生まれ出で、同じ空気を吸い、同じ土の上に生み落とされ、みなと同じ産声をあげ、産着と心遣いに包まれて育てられた。
王の中でも、これと異なる出生の初めをもつ者はいない。
すべての人にとって命への入り口は一つであり、出口もただ一つである。
(知恵の書7・1〜6)
知恵の書は、紀元前2世紀ごろにエジプトで書かれた書である、とされています。
ユダヤ教徒、キリスト教のプロテスタントでは正典とは見なされていませんが、カトリックでは典礼にもたびたび用いられ、大切にされています。
「同じ土の上に生み落とされ」とは、誰が生まれ落ちても土のほうでは同じように感じる、という意味だとフランシスコ会訳聖書の注釈に書いてあります。
同じような産声をあげ、産着を着せられ、親だけでなく祖父母や兄妹などの心遣いに包まれて育つ子どもは、生まれた時はみな愛され、幸せな存在であってほしい。
そう、強く思います。
先日の教会委員会で「子どもたちが教会に来るようにするにはどうしたらよいか」という議題がありました。
結論は一つです。
家族が連れてくるしかないのです。
成人洗礼の信者は自らの意思で教会に行きますが、幼児洗礼の子どもたちの信仰は、ある程度の年齢までは親(家族)が導かなければならない、それは義務とも言えるのではないでしょうか。
アレクサンドリア生まれのアポロというユダヤ人が、エフェソにやって来た。
彼は雄弁家で、聖書に精通していた。この人は、主の道の教えを受け、霊に燃えて、イエスのことについて詳しく語り、かつ教えていた。
このアポロは、会堂で、大胆に語り始めた。それを聞いていたプリスキラとアキラは、彼を招き入れて、神の道をさらに正確に説明した。
アポロは神の恵みによってすでに信仰に入っていた人々の大きな助けとなった。
(使徒言行録18・24〜27)
アポロは、パウロの宣教を助けた大切な人物だと教わりました。
わたしたちがこの道、「主の道・神の道」=「キリスト教の信仰」を成熟させていくためには、助けてくれる人の存在が欠かせません。
わたしのために祈ってくれる人の存在、とも言えるでしょう。
「子どもたちが家族に連れられて教会に来てくれますように」という祈りは、なくてはならないものです。
昨日のごミサでは3人の男の子が侍者を務めてくれました。
侍者になりたい、と立候補してくれている子どもが数名いる、と聞いています。
ですが、ミサに与っている子どもの姿はほとんどありません。
しっかり腰を据え、またどっしり構え、絶えず主の業に励みなさい。
主と一致していれば自分の労苦は無駄ではないと、あなた方は知っているのですから。
(1コリント15・58)
先日、ある方が「教会に行くと信徒の皆さんがなんとなく微笑をたたえている、という姿がいい教会だと感じます」とおっしゃいました。
子どもたちにとっても、同じです。
主の道を歩む大人がその姿を見せること、良いものを入れた心の倉から良いものを出す(ルカ6・45)生き方をいつも心がけること。
子どもが来ない、と諦めずに、次世代の子どもたちのために教会=木の手入れの上手下手は実で分かる(シラ27・6)ことを肝に銘じ、手入れを怠らないようにしたいものです。
傲慢という自由
受験生の合格発表の様子をニュースで見ました。
姪はネットで発表を確認しているので、てっきりそれが主流かと思っていましたが、西南学院大学の発表はキャンパスの掲示板に合格者の番号が張り出されていました。
飛び上がったり泣いたりして喜びを表している受験生の姿、微笑ましくて。
わたしの合格発表は、郵送されるのが待ちきれなくて、東京にいる知人に大学まで見に行ってもらったことを思い出しました。
努力の成果を素直に喜べたあの頃が懐かしい。

毎日の聖書朗読の箇所、21日金曜日にはバベルの塔のくだりが読まれました。
この箇所は単に、人間の傲慢さと神の怒りが書かれている、と思っていました。
全地は同じ発音同じ言葉を用いていた。
東のほうから移り住んでいるうちに、シンアルの地に平野を見つけ、そこに住みついた。
彼らは互いに言った、「さあ、煉瓦を造ってよく焼こう」。
彼らは石の代わりに煉瓦を、漆喰の代わりにアスファルトを用いた。
(創世記11・1~3)
改めて、当時(紀元前3000年くらい?)の技術革新には驚きます。
フランシスコ会訳聖書の解説には、このように書かれています。
創世記の第一部は人類の起源を述べると同時に、人類に対する神の摂理を示している。
この型は歴史を通じて繰り返されることになる。
この型の循環は神から出る本来の善、人間から出る破滅的罪悪、神の善と慈悲による救いである。
この型は創世記全体を通じて展開され、イスラエル人がエジプトにおける奴隷の状態から解放される出エジプトの出来事の前置きともなっている。
第一部が現代的な意味において「歴史」として格付けられないことは確かであるが、神話でもないことも確かである。
主は人の子らが建てた町と塔を見るために降ってこられた。
そして主は仰せになった、「見よ、彼らはみな同じ言葉を持つ一つの民である。これは彼らの業の初めにすぎない。これからも彼らが行うと思うことで、成し遂げられないものはないであろう。さあ、われわれは降りていって、あそこで彼らの言葉を乱し、互いの言葉が分からなくなるようにしよう」。
(11・5~6)
「神から出る本来の善、人間から出る破滅的罪悪、神の善と慈悲による救い」という循環は歴史を通じて繰り返される、という解説には深く頷かされます。
善き者として造られた人間は自由意志で神に背き、罪を繰り返し、それでも見捨てない神、という循環です。
先日観に行った歌舞伎のストーリーは、簡単に書くと次のような感じです。
戦場で兵士の死体から金品を盗んで生計を立てていた主人公ライは、朧の森の精霊たちに「なんでも願いを叶えてやろう」と持ち掛けられます。
「王になりたい」というライに、「お前の命と引き換えに叶えてやる」と精霊たちが答え、ライは悪事の限りを尽くして王に上り詰めますが、、、。
人間の欲、傲慢さがこれでもか、と盛り込まれた演目です。
主人公は自分だけを信じていて、他者はあくまでも利用価値のある存在としてしか見ていません。
18歳の頃の自分には、傲慢さはなかったように思います。
神様に顔向けできないような罪も犯してはいませんでした。
信じられる対象(それは友人であり、カトリックの信仰であり)が次第に確立されていく過程、大人になるにしたがって少しづつ傲慢さを蓄えてしまったように感じています。
生活の知恵が増すに伴って、上へ上へと欲望を増していったバベルの人々のように。
人が信仰を持つようになるのは神様の働きかけによるものか、それとも人の自由意思によるものなのか、というキリスト教神学の「恩寵論」について、読んでいる本で知りました。
古代の教父たちは、神に似せて創られた人間の力を強調し、恩寵のみではなく、自由意志に基づく善の選択を説いています。
一方で、宗教改革をおこなったルターは「恩寵のみ」を力説し、人間の救済には神の働きしか作用しない、としました。
そしてトマス・アクィナスは、「恩寵と自由意志」がともに働くことで、神と人間の深い協働関係が構築されていくという立場でした。
トマスの研究で知られる山本芳久さんは、トマスの主張を次のように解説されています。
「人間が生まれつき固有に持っている『自然』だけでは、無限な幸福に対するあこがれは実現するのが難しい。
むしろ、実現する力は神の『恩寵』によって与えられる。
人間は幸福への憧れのようなもの、そして『恩寵』と協働する力ももともと持っているけれど、自分一人で実現するだけの力は持っていない。
信じられないほどの『恩寵』に参与させられることで、心底追い求めていたものが自らの思いを超えた仕方で現れ、実現する。」
歌舞伎の主人公ライは、自分のもともと持っていた能力しか信じておらず、神も仏も仲間すらも切り捨て、自分の命と引き換えに人生を上り詰めようとしました。
王になることこそが、自分にとっての最高の幸せだと信じて疑わなかったのです。
わたしたちキリスト者は、最高の幸せを求める信仰を生きています。
それは、究極には「永遠の命」のことですが、この世を生きる上での幸せは、神様からのお恵みという「恩寵」を絶えず受け取ることです。
傲慢なわたしをいつも見捨てず、「また!?」と思いながらも正しい方向へ導いてくださる神様の愛に、今日も甘えます。

進歩していく教会
書きたいことが溢れてきて、でも一旦落ち着かなければと思い適当に聖書を開いたら、この言葉が最初に目に留まりました。
「心を騒がせてはならない。
あなた方は神を信じなさい。
そして、わたしをも信じなさい」。
(ヨハネ14・1)
そして、昨日のごミサでは、宮﨑神父様の力強いお言葉にとても励まされました。
「わたしたちにとって、本当の幸せとは何か。
それは、神への信頼という信仰に満たされること。
つまり、諦めず、絶望しない生き方をすることです。」
この1週間は、心がざわざわする日々を過ごしていました。
人々の中に偏見や対立、旧態然とした考え方があることは、どの教会、いえ、どの組織にもあることなのかもしれません。
先日、歌舞伎を観に行きました。
歌舞伎といっても、演劇と融合した、全く新しいスタイルの演目です。
30年ほど前でしたでしょうか、テレビで、亡くなった勘三郎さんが息子たち(当時の勘太郎・七之助兄弟)に所作の指導をしているところを見たことがあります。
父から教わった後、勘太郎くんが「オッケーです!」と答えたところ、大きな張り手が飛んできました。
「古典芸能の稽古をしている時に、オッケーですとは何事か!!」と。
今回観に行った歌舞伎は、松本幸四郎さん(52歳)が座長です。
稽古風景の写真では、幸四郎さんは髪を赤く染め、歌舞伎役者の皆さんはジャージ姿でした。
インタビューで幸四郎さんが、「昔は役者が髪を染めたり、浴衣ではない姿で稽古をするなんて考えられなかった。歌舞伎界も柔軟になったなぁ、と思います。」とおっしゃっていました。
ユダヤ人たちは、イエスを迫害し始めた。
安息日にこのようなことをしておられたからである。
ところが、イエスは彼らにお答えになった、「わたしの父は今もなお働いておられる。だから、わたしもまた働く」。
このために、ユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。
イエスが安息日を破ったばかりでなく、神をご自分の父と呼んで、ご自分を神と等しいものとされたからである。
(ヨハネ5・16〜18)
イエス様は、当時は相当な異端児であったでしょう。
ユダヤ教徒の指導者たちが必死に守って、民衆にも厳しく教えてきたことを、簡単に破ったのです。
新しいもの、新しいやり方が必ずしも良いこととは限りません。
良いかどうかは、新しさにあるのではなく、柔軟な発想と行動力の中に現れるのではないでしょうか。
群衆の間では、イエスのことがいろいろと取りざたされていた。
「善い人だ」と言う者もいれば、「いや、群衆を惑わしている」と言うものもいた。
しかし、ユダヤ人たちを恐れて、誰もイエスについて公然と話す者はいなかった。
(ヨハネ7・12〜13)
キリスト教という宗教、カトリック教会という組織は、2000年以上前に確立されたものではありません。
罪深い歴史も、多くの失敗もありながら、今なお進歩し続けていると感じます。
特に、フランシスコ教皇になってからの時代は(情報が誰でも簡単に手に入るようになり)、現代社会と向き合う姿勢が内部の反発を招く様子も見てとれます。
慎重でありながらも、内外の課題に目をつぶらず、時には世界政治を動かすほどの影響力を発揮される教皇様は、信仰面だけでなく、リーダーとしてわたしたちの手本ではないでしょうか。
他の教会のある年配の信徒の方とお話ししていたら、「教会のことをいろいろ一人でしていて大変だ。青年向けの事業をやっても、うちの教会には若者はいないので誰も参加できない。」とおっしゃいました。
確かに、高齢の信徒が多い教会なのかもしれません。
ですが、本当に、誰も後任がいないのでしょうか。
一人も若い信徒はいないのでしょうか。
変わることを拒絶しているだけかもしれない、と考えてみる必要はないでしょうか。
久留米教会では、長年、納骨堂の管理を一人の信徒(80代後半)に任せきりでした。
「誰か若い人に代わってもらいたい」とおっしゃり、何人かの方に依頼してみました。
先日、ようやく「やります」と言ってくれたのは、20代の女性2人でした。
本当に、とても嬉しい出来事でした。
わたしたち強い者は、強くない人たちの弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。
わたしたち一人ひとりは、互いにキリスト者として造り上げられるのに役立つように、隣人を満足させるべきです。
忍耐と励ましの源である神が、あなた方に、キリスト・イエスに倣って互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。
それは、心を合わせ声をそろえて、わたしたちの主イエス・キリストの神であり父である方をたたえるためです。
(ローマ15・1〜2、5〜6)
失敗を恐れず、前に進むために、与えてもらった役割に責任を持つ。
教会のために、集うキリスト者のために、そして、自分自身のために働く。
そうしたことができるのは、聖霊が背中を押してくれているからなのだ、と強く再認識した1週間でした。

人間の本質
見なければいいのに、つい見てしまうのが「ネットニュース」と「SNS」
報道という言葉とは程遠い、質の低い(取材に基づかず、噂と想像と憶測とが入り混じっている)内容を見聞きするたびに、これは一種のいじめに近い気がするのです。
「いじめ」には、言葉、態度、精神的、暴力など、いろいろな種類があると定義されています。
判断基準は非常にシンプルで、「身体的・精神的にかかわらず、いじめられた本人が苦痛を伴うかどうか」です。
そして、被害者がいじめを受ける「きかっけ・動機」はあるものの、「原因」は見当たらない(少なくとも本人に心当たりはない)という特徴が、多くの場合に言えることです。
わたしも子どもの頃、心当たりなくいじめのようなことをされた経験があります。
いじめは、子どもの社会にだけある問題ではありません。
大人の社会のほうがむしろ、陰湿でしつこく、凶暴性を帯びているように思います。

イエス様の公生活は、苦難の日々だったと言えると思います。
ご自身が、「人々は理由もなく私を憎んだ」と言われています。
「これは一種のいじめ状態だったのだ」、とプロテスタントの牧師さんが書いておられるコラムがありました。
イエス様は「理由もなく憎まれ」、ユダヤ社会という閉塞集団の中で「いじめによる殺人」のような状況に追い詰められたのだ、そんな状況でも、イエス様が閉塞感や絶望感に蝕まれなかったのは、上の世界を見ておられたからなのだ、と。
わたしたちのように、目に見える世界に翻弄されることなく、この世界を創られた、神だけに目を向けておられたのです。
神よ、わたしを救ってください。
水はわたしの首にまで達しました。
わたしは泥の深みに沈み、そこには足を掛ける所もありません。
わたしは水の深みにはまり、渦に巻き込まれました。
わたしは叫び疲れ、喉は嗄れました。
わたしの神よ、目は待ちわびて衰えました。
故なくわたしを憎む者は髪の毛よりも多く、わたしを欺く者は頭の毛よりもおびただしい。
(詩編69・2〜5)
だまし打ちを仕掛ける敵を喜ばせず、故なくわたしを憎む者が、目くばせし合うことのないようにしてください。
彼らは平和を語らず、国のうちに穏やかに住む者を欺こうと企みます。
(詩編35・19〜20)
ほかの誰も行わなかったような業を、わたしが彼らの間で行わなかったなら、彼らには罪はなかったであろう。
だが、今、彼らはその業を見たうえで、わたしとわたしの父を憎んでいる。
しかし、これは、『人々は理由なしにわたしを憎んだ』と彼らの律法に書かれている言葉が成就するためである。
(ヨハネ15・24~25)
人を憎んだり恨んだりするのは、ある種、人間の本質的なものかもしれません。
ガザで起きている惨劇は、ジェノサイドです。
ハマスから奇襲攻撃を受けたイスラエルがガザ攻撃を激化させたのに伴って、欧州や北米、オーストラリアなどでイスラエルへの批判とともに、反ユダヤ主義の動きが目立つようになっています。
また、アメリカ大統領の「ガザを所有」「住民を全員他国に一時的に移住させる」といった、トンデモ発言が新たな火種となっています。
実行されることはないでしょうが、この発想自体がジェノサイドです。
わたしがあなたと争う時に、正しいのは、主よ、あなたです。
それでも公正について、わたしはあなたと話したい。
なぜ、悪人の道が栄え、不忠実の極みの者がみな、安穏としているのですか。
あなたが彼らを植えられ、彼らは根を張り、成長して実を結びます。
あなたは彼らの口には近いのですが、腹には遠いのです。
主よ、あなたがわたしを知り、わたしを見、わたしを試みられると、わたしの心があなたとともにあることがお分かりになります。
(エレミヤ12・1〜3)
アウシュビッツの解放から1/27で80年となり、各国の首脳を招いた式典が開かれました。
当時を語ることができるホロコーストの生存者が減り、記憶の継承が課題となる一方、若者の間ではSNSを通じて「否定論」(ホロコーストは実際にはなかった、という考え)が広がっているそうです。
現在でもフランス語やスペイン語の聖書で、「焼き尽くす捧げ物」がホロコーストと表記されているものもあります。
奉納者が内臓と四肢を水で洗うと、祭司はその全部を祭壇で燃やして煙にする。
これが焼き尽くす献げ物であり、燃やして主にささげる宥めの香りである。
(レビ記1・9)
生存者の方の訴え、「人間は忘れる。だからわたしは何度も言う。二度と同じ悲劇を繰り返すなと」「憎しみは憎しみを生むと警告する義務がある」という言葉は、非常に重いものでした。
人を憎み、恨み、相手を傷つけ、そして報復する。
負の連鎖が繰り返される中で、祈りの力はどこまで立ち向かえるでしょうか。
・・・・・・・・・・・・
詩編13『痛みに耐えかねた人の祈り』
主よ、いつまでですか、とこしえにわたしをお忘れになるのですか。
いつまでみ顔をお隠しになるのですか。
いつまでわたしは魂を悩ませ、心に痛みを抱けばよいのですか。
いつまで敵がわたしについて勝ち誇るのですか。
わたしの神、主よ、わたしを顧みて、わたしに答え、目に光を与えて、死の眠りに就かせないでください。
「わたしは勝った」と敵に言わせず、わたしの倒れるのを見て、敵を喜ばせないでください。
わたしは、あなたの慈しみに寄り頼み、わたしの心は、あなたの救いを喜びます。
わたしは歌います、主に。
恵みを与えてくださった主に向かって。
閉ざされた信仰
中世のスペイン王国・ポルトガル王国で、ユダヤ人でユダヤ教からキリスト教に改宗した人々のことを、「コンベルソ」(新キリスト教徒)と言います。
イベリア半島(現在のスペイン)は、ヨーロッパの中で最もユダヤ人が住む地域でしたが、キリスト教国とイスラム教国のせめぎあいの中で翻弄され、レコンキスタの最中に即位したカトリックの国王の迫害を逃れるために、多くのユダヤ人がキリスト教に改宗しました。
そのような中、1478年にローマ教皇の許可を得てドミニコ修道会が異端審問制度を始めます。
この異端審問所は、ユダヤ教徒やイスラム教徒に対してではなく、新キリスト教徒の中の背信者を取り締まるために設けられたのです。
1492年、国王はついにユダヤ教徒追放令を出し、キリスト教に改宗しないユダヤ人は国外に退去することを命じました。
ちなみに、レコンキスタとは、イスラム教徒から不当に領地を占領されたとして、その支配に抵抗するカトリックを信仰するスペイン人による領土奪還のことです。
レコンキスタ、とは19世紀に作られた造語で、当時の人々はそのような自覚(我々はスペイン人である、イベリア半島は統一すべき、というような)はなかったようです。
アメリカの新政権が打ち出した政策、「犯罪を犯した不法移民を国外退去か、グアンタナモの収容所に入れる」は、もちろん根本的には全く別のものですが、どこか似たような政策に感じます。
中世の当時、「スペイン」というひとつの国は存在せず、キリスト教・ユダヤ教・イスラム教という宗教カテゴリーごとに連帯するわけでもなかった。
当時の人々は各々の思惑を持って懸命に生きたのであって、その割り切れない生き様を単純化してしまってはならない。
国家や民族、信仰や善悪といった、後世の人々が創り出した「フィクション」で単純化して線引きすることが、どれほど多くの悲劇を生み出してきたか、そして生み出し続けているのかを、現代に生きる我々は痛感している。
「レコンキスタ ―「スペイン」を生んだ中世800年の戦争と平和」
黒田 祐我 著より
全く知らなかった、中世のスペインの歴史について、とても勉強になる本です。
そして、歴史上の大きな転換点には良くも悪くも、いつもカトリック教会(教皇)の深い関わりがあったことを、この本でも改めて認識させられました。
わたしは、聖書の基本理念はこの箇所に表されていると、いつも思います。
お前たちが自分の土地の刈り入れをするとき、お前は畑の隅まで刈り尽くしてはならない。
またお前の刈り入れの落ち穂を拾ってはならない。
お前のぶどう畑の実を取り尽くしてはならない。
お前のぶどう畑に落ちた実を拾ってはならない。
それらは貧しい人や他国の者のために、残して置かなければならない。
(申命記19・9〜10)
在留する他国の者や孤児の権利を侵してはならない。
やもめから衣服を質に取ってはならない。
エジプトで奴隷であったあなたを、あなたの神、主が贖われたことを思い起こしなさい。
畑で穀物の刈り入れをするとき、一束を畑に置き忘れたなら、それを取りに戻ってはならない。
それは在留する他国の者、孤児、やもめのためのものである。
そのように行えば、あなたの神、主はあなたのすべての業を祝福なさるであろう。
(申命記24・17〜19)
ミレーは、この申命記の理念を表したルツ記の場面を取り入れて「落穂拾い」を描いたと言われています。
これは、キリスト教の教えではなく、旧約聖書に書かれている「全人類」への教えではないでしょうか。
レコンキスタの時代も、現代も、自分たちがそもそも寄留者に過ぎないことを完全に忘れているのです。
もちろん現代社会は、各国が定めた法律に則って暮らす義務と責任をだれもが持っていますが、「メキシコ湾」か「アメリカ湾」か、そのようなレベルの争いが未だに繰り広げられているのが現実です。
問題が拡大したのはテレビ局のせい、山火事が大規模で長期間にわたったのは前政権の予算配分のせい(気候変動対策に予算を割きすぎたから)、旅客機に軍のヘリが追突したのはFAAがDEI(多様性、公平性、包摂性)の推進のために「重度の知的障害や精神障害を持つ人々の雇用を進めた」せい、、、。
(もちろん、大統領の根拠のない発言です)
紹介した本によると、10世紀のアンダルス(現在のスペインの一部)では、どれか一つに統合されることのないハイブリッドな社会でした。
公用語はアラビア語、日常言語はラテン語が俗語化したロマンス諸語、ヘブライ語もユダヤ人の儀礼言語として用いられていました。
イスラムが実質的に支配していた10世紀の後ウマイヤ朝は、ユダヤ教徒もキリスト教徒も、その庇護のもとで自らのアイデンティティを維持しながら、それぞれの分野で活躍していたそうです。
「多様性に根差し、宗教的寛容によって形作られた非凡なる中世文化」と書かれています。
2025年の今、そのような社会の形成を求めるのは理想主義すぎるでしょうか。
少なくともキリスト教を信仰するのであれば、信仰の根本を思い起こし、わたしたち一人ひとりがもっと寛容でなければならない、と痛感するこの頃です。
ミサ後の、わたしの大好きな光景です。
あちらこちらで、それぞれの日常を交換する信徒の皆さん。
わたしも、週に一度お会いする方々と言葉を交わす日曜日が大好きです。
女性の決断
めでたし聖寵充ち満てるマリア
主御身とともにまします
御身は女のうちにて祝せられ
御胎内の御子イエズスも祝せられたもう
天主の御母 聖マリア
罪人なるわれらのために
今も臨終のときも祈り給え
アーメン
わたしは、毎日の祈りはいまだにこの言い回しを使っています。
主の祈りもそうです。
(天にまします・・・・)
日々、誰に向かって、誰を想いながら祈りを捧げていますか?
神に祈るなら、神は聞いてくださる。
そして、あなたは自分の誓願を果たすことが出来よう。
(ヨブ22・27)
わたしは彼らが呼ぶ前に応え、
彼らがまだ語り続けている間に聞き入れる。
(イザヤ65・24)
映画「マリア」が、先月ネットフリックスで公開されました。
聖母マリアの幼少期から、聖家族のエジプト逃亡までを描いた物語です。
福音書(外典も含む)の記述にとても忠実でありながらも、新しい解釈を用いたストーリーです。
この映画では、ヨゼフ様も若い俳優が演じています。
「ヨゼフに声を与えて欲しい」と、親交の深かった司教からの言葉があったから、と監督がインタビューで答えていました。
カトリック信徒のダニエル・ジョン・カルーソ監督は、
「私はこの物語を伝えたいという強い意志があった。
マリアの物語は過小評価されていると感じた。
私たちはみなキリスト降誕の物語を知っているが、彼女の視点からこの物語を伝えるというアイデアにとても心を動かされた。
マリアの立場になって、幼少期からキリストの誕生、そしてその後まで、このすべてを経験するのはどんな感じだったか、この若い女性は逆境に直面し、疑いや恐れを抱きながらも、最終的にはこの美しい『フィアット(fiat)』、つまり神からの恩寵を受け入れた」
と語っています。
監督は、「私たちはマリア様に祈ることが大好きで、マリア様を執り成し手として受け入れている。」とおっしゃっています。
マリア様は、象徴的で、美しく、聖なる母であり、私たち皆が崇敬している存在ですが、同時に若い女性でもあったのです。
若いというより、まだ少女でした。
彼女はその中で大きな決断を下し、前に進まなければなりませんでした。
そして、若いヨゼフ様もまた、困難な決断を下したのでした。
フランシスコ教皇は、先週の一般謁見のお説教で、次のように話されています。
「マリアの心には信頼の光が灯った。
神に委ね、従い、自分を明け渡した。
マリアは御言葉をその肉に受け、こうして、一人の女性、人間にこれまで託されたことのない、最大の使命に飛び込んだのである。」
映画の中で、誠実なユダヤ教徒の両親ヨアキムとアンナへのお告げに従って、マリア様は幼少期から神殿の中で育てられます。(外典:ヤコブの福音書に沿っています)
両親、マリア様、マリア様を見初めて結婚を申し込むヨゼフ様は、大事な場面ではその都度、天使ガブリエルから導きを受けます。
わたしは「神様のお導き」を強く信じていますが、その「神様」とは、わたしにとってはイエス様だけを指しているのではない気がしています。
なにか、聖なるものの集合体とでもいうか、イエス様の足元に集うマリア様を始めとする聖なるかたまり(天国の母も含む)が頭に浮かぶのです。
イエスは、常に生きて、人々のために神に執りなしをしておられるので、ご自分を通して神に近づく者を、完全に救うことがおできになります。
(ヘブライ7・25)
わたしたちは神の前に確信をもっています。
それは、わたしたちが神のみ旨にかなうことを求めるのであれば、神は聞き入れてくださるということです。
わたしたちのどんな願いをも神が聞き入れてくださることが分かるなら、わたしたちが神に願い求めたことはすでにかなえられていることも分かります。
(1ヨハネ5・14~15)
ヘロデ王をアンソニー・ホプキンズ、マリア様・ヨゼフ様は若くて美しいイスラエルの俳優が演じていたのも素晴らしかったです。
(アンソニー・ホプキンズは映画「2人のローマ教皇」でベネディクト教皇を演じていましたので、そのギャップがすごかったし、マリア様は他の映画ではたいていヨーロッパの白人俳優が演じていますから。)
ヨーロッパ第2のカトリックメディア、ポーランドのカトリック情報局KAIの特派員であるJJ神父(パウロ・ヤノチンスキー神父、ドミニコ会)のnoteの記事を参考にさせていただきました
・・・・・・・・・・・・・
アメリカ大統領は、就任後にワシントン大聖堂で礼拝に参加することが慣例となっています。
聖公会のマリアン・エドガー・バディ主教が、就任したばかりのトランプ大統領に説教壇からLGBTQと不法移民のために訴えたことがニュースになっていました。
バディ主教は、「大統領閣下、どうか慈悲をお与えください」と静かに語り、米国全体で「恐怖」が感じられるとおっしゃっていました。
(当然、トランプ大統領や側近たちは不満そうな表情で、後日、謝罪を求める声明を出してた。)
奇しくも一致祈祷週間の中でしたので、世界中が注目する中でこうした発言をハッキリなさった女性の主教様の行動力には感服させられました。
「女性だから」「女性なのに」というのは不適切な時代ですが、やはり女性の決断力と行動力はものすごいパワーを持っている気がします。
https://www.afpbb.com/articles/-/3559308?pno=3&pid=doc-36V64DR_1_2395207_preview
時代に沿った祈り
今年のご復活祭はいつか、ご存じでしょうか。
なんとなく3月末から4月上旬、という固定概念がありますが、今年は4月20日とかなり遅いご復活なのです。
1/18から1/25までの期間は、キリスト教一致祈祷週間となっています。
1968年以来、教皇庁キリスト教一致推進評議会と世界教会協議会が、毎年テーマを決めてともに祈る期間として続けられてきたものです。
その冊子には次のように書かれています。
今年は、西暦325年に二ケアで最初の公会議が開かれてから1700年目にあたります。
この会議には、伝承によれば、318人の教父が出席しました。
そのほとんどが東方教会の教父だったようです。
教会は、異なる文化的・政治的背景の中で同じ信仰を共有することがいかに難しいかを経験し始めていました。
二ケア公会議は復活祭の日付の計算方法を定めましたが、その後さまざまな解釈が生じたことにより、東方教会と西方教会では大抵は異なる日に復活祭が祝われるようになりました。
わたしたちは、毎年共通の日に復活祭を祝う日が再び来ることを待ち望んでいますが、偶然にも2025年の記念の年は、同じ日にこの大祝日を祝うのです。
キリスト教一致祈祷週間は、二ケア公会議当時のキリスト教世界よりもさらに多様化している、現代の文化に沿ったかたちで再解釈する機会です。
聖年の今年に、二ケア公会議から1700年の記念の年に、なんということでしょう。
今年の四旬節は、こうした大きな意味があることを心に刻んだうえで過ごし、例年以上に有意義な日々としたいものです。
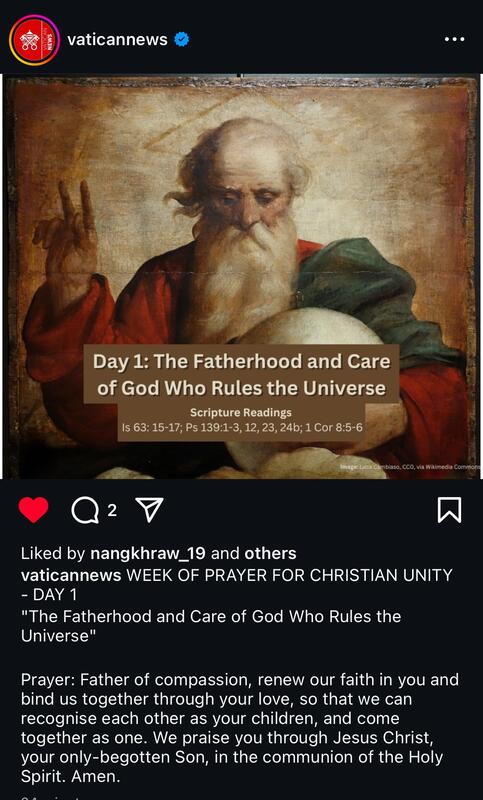
二ケア公会議までの数十年の間に、キリスト者は意見の相違による対立が深刻になっていました。
一致祈祷週間の冊子によると、次のようなことで対立が深まっていたそうです。
・父なる神との関係におけるキリストの本性
・復活祭を同じ日付で祝うこと
・ユダヤ教の過越祭との関係について
・異端とみなされる神学的見解にたいする異議
・初期の迫害時代に棄教した人を再び教会に迎え入れる手順
イエス様は、こうしたことについてひとこともおっしゃってはいなかったのに、、、、。
イザヤは言った、「ダビデの家よ、聞け。あなたたちは、人間を煩わせるだけでは足りず、わたしの神までも煩わせるのか。それ故、主ご自身が、あなたたちに徴を与えられる。
見よ、おとめが身籠って男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。
その子は、悪を退け善を選ぶことを学ぶまで、凝乳と蜂蜜を食べるであろう。
(イザヤ7・13〜15)
「聖書」(わたしたちが旧約と呼んでいるもの)は、当時のイスラエルの人々が待ち望んでいる救い主が必ず現れると言うことを預言しています。
その解釈がユダヤ教とは異なったため、「キリスト教」という新しい教えが確立されました。
わたしたちが信じている「カトリック」の教えも、この2000年以上もの間にさまざまに発展してきました。
わたし、主は、正義をもってお前を呼び、お前の手を取り、お前を守り、お前を民の契約、諸国の光とした。
見えない目を開き、囚われ人を牢獄から、闇に住む人々を獄舎から連れ出すためである。
(イザヤ42・6〜7)
主は仰せになる、「お前がわたしの僕として、ヤコブの諸部族を立ち上がらせること、イスラエルの生き残った者を帰らせることだけでは足りない。
わたしはお前を諸国の光とし、地の果てに至るまでの、わたしの救いとする」。
(イザヤ49・6)
この救いは、あなたが万民の前に備えられたもの、異邦人を照らす光、あなたの民イスラエルの栄光です。
(ルカ2・31〜32)
イザヤ書の中で、40〜55章の第2イザヤと呼ばれる箇所は、キリスト教ではメシア預言とされていて重視されています。
わたしたちの信仰の根底にユダヤ教の教え、旧約聖書があることを忘れてはいけないといつも思います。
つまり、西方教会も東方教会も、カトリックもプロテスタントも、大切にしている教えは同じ源流であることを忘れてはならないのです。
現代において、キリスト教のさまざまな宗派が一致して祈る、しかも同じ祈祷文を使って祈る期間が設けられていることは、本当に素晴らしいことです。
特に、今のように各地で世界を巻き込んだ戦争が起きている時には、なおさら宗派で争っている場合ではありません。
キリスト教一致祈祷週間については、↓こちらをご覧ください。
https://www.cbcj.catholic.jp/2024/12/19/31132/
・・・・・・・・・・・・・
かなり余談
西序二段70枚目の醍醐桜(16歳)は、円形脱毛症により髪がほとんど抜けてしまったため、きれいに頭をそり上げて今場所に臨んでいます。
相撲協会の「相撲規則」では、頭髪について「十枚目(十両)以上の力士は、出場に際して大銀杏(おおいちょう)に結髪しなければならない」と記載されていますが、厳密にこれに準ずるなら、スピード出世で今場所初めて大銀杏を結った大関大の里も規則違反だったことになります。
伝統を重んじる相撲界も「まげのない力士も個性だ」と、多様性を尊重する時代となったようです。
答えをさがすために
先日、ある教会の信徒の方といろいろなお話をするなかで、その方がこうおっしゃいました。
「家庭の問題について神父様に相談したけれど、求めているような答えをいただけなかった。
結婚していらっしゃらないし、お子さんもいないので、やはりそういう問題には、、、なのでしょうか」
神父様方にはたいへん失礼ながら、信徒がそういう疑問を持つのは仕方のないことかもしれません。
その際に、(若輩者で未婚で子なしのわたしが)このようにお答えしました。
「神父様は、神様とわたしたちを繋ぐ仲介者のような存在なのではないでしょうか。
問題の答えを求めるのではなく、自分で答えを見つけるきっかけを与えてもらえることを期待してはどうでしょう。」
わが子よ、もしお前が、わたしの言葉を受け入れ、わたしの命令を心に蓄え、知恵に耳を傾け、英知に心を配るなら、そうだ、もし知性を呼び求め、英知を求めて声をあげ、あたかも銀のように、知恵を求め、あたかも隠れた宝のように、知恵を探すなら、その時、お前は主を畏れることを悟り、神を知ることを見出すだろう。
主は知恵を与え、その口から出る知識と英知を与えてくださるのだから。
主は正直な人々のために健全な知恵を蓄え、誠実に歩む人々の盾となり、公正な人々の行く道を保ち、その聖なる人の道を守ってくださる。
(箴言2・1~8)
甲乙つけがたいのですが、箴言は旧約のなかでトップ3に入る、とても好きな聖書です。
その方にも、「箴言を読んでみてください、探している答えのヒントが見つかりますよ!」とお話しました。
わたしに耳を傾け、日々、わたしの門の戸口で見張り、わたしの門の柱の傍らで番をしている者は幸いだ。
わたしを見出す者は命を見出し、主の恵みにあずかる。
(8・34~35)
人の心は自分の道を思い巡らす。
しかし、その歩みを導くのは主である。
(16・9)
いつの頃からか、わたしは人に悩みを相談しなくなりました。
(もちろん、心を軽くしたくて愚痴を聞いてもらうことはあります)
たとえ似たような境遇で、似たような悩みを持っている友人であったとしても、必要としている(求めている)答えが同じだとは思わないのです。
◇ミサでの神父様のお説教に、必ず一つの(その時点でのわたしにとっての)キーワードを見出す
◇聖書を読んで心を落ち着ける&導きを探す
(それでもだめなら、ワインを飲んで早くベッドに入る!)
神は、わたしたちがどのような苦難にある時でも慰めてくださいます。
そこで、わたしたちも、自分たちが神から慰めていただくその慰めによって、あらゆる苦難の中にある人を慰めることができるのです。
わたしたちが苦しみに遭うとするなら、それは、あなた方が慰められ救われるためですし、わたしたちが慰められるとするなら、それは、あなた方がわたしたちも受けているのと同じ苦しみを耐え忍ぶにあたって、力を発揮する慰めがあなた方に与えられるためです。
(2コリント1・4~6)
パウロたち、初期の使徒たちが受けていた迫害、苦難を基にしたことばですが、現在のわたしたちそれぞれの悩み・苦しみに重ねて読んでみてはどうでしょうか。
悩み・苦しみは様々にわたしたちに降りかかってきます。
人生とは、そのようなことの連続ともいえます。
ミサの時に偶然となりに座った方も、おそらく何かを乗り越えた方か、現在悩みの中におられるか、だと想像してみるのです。
そうすると、自分は一人ではない、誰もが神様のお導きを探しているのだ、と思えるのです。
誰かに答えを教えてもらいたい、と思うのは自然なことです。
わたしたちキリスト者であれば、なおさら、神父様に助けを求めるでしょう。
亡くなった母が、当時通っていた聖書勉強会の神父様に悩みを打ち明けていました。
「わたしはまだ洗礼を受けていませんが、亡くなった義母と同じお墓に入りたくないのです。どうしたらいいでしょうか。」
その神父様は、秒速の返答でした。
「あなたの信仰はあなたの心のものです。
死んだ後の骨がどうなるかなど、心配する必要はありません。
あなたは今の信仰を大切にし、骨のことは残された家族に任せなさい。」
あっぱれなご回答に、母が大変喜んでいたのをよく覚えています。
わたしが人に相談しないのは、悲観的な意味ではなく、答えは外にはない、と実感したからだと思います。
そして、全ての思い煩いは神様の導きに委ねるしかないのだ、と痛感しているからです。
お前が呼べば、主は答え、叫べば、『わたしはここにいる』と仰せになる。
(イザヤ58・9)
「わたしが来たのは、あなたがわたしを呼び求めたからである。
あなたの涙、あなたの念願、あなたの謙遜、あなたの心の痛悔がわたしを動かし、あなたのもとに来させたのだ」。
(「キリストを生きる」第3巻第21章6)
『わたしはここにいる』とは、なんて心強いフレーズでしょう。
呼び求めれば近くに来てくださる、と知っていれば、これ以上に心強いことがあるでしょうか。
わたしは、人から悩みの相談を受けるのは好きです。
その方が、自分なりの答えを見つけられるよう、アドバイスができたら幸いだといつも思っています。
家庭における愛
新年あけましておめでとうございます。
お正月を家族とともに過ごす、というのは日本の良き伝統ですね。
我が家には中学生の甥が一人だけ帰省してくれたので、「初詣に行こう!」と教会に連れて行き、一緒に座って祈ることができました。
素晴らしい一年のスタートが切れた気分です。
今年はどのような一年にしたいですか?
今年の抱負、どのように考えていらっしゃいますか。
新年最初に、トビト記を読みました。
トビト(義人としてトビトと息子のトビア、その嫁のサラ)への神の絶えざる保護、苦難や迫害にあっても神に忠実に生きる姿が物語形式で描かれています。
わたしは4人の姪甥に、「人からして欲しいことを人にもしなさい(マタイ7・12、ルカ6・31)」と常々話しています。
トビト記には、その由来とも言える教えが書かれています。
目が見えなくなり、生きていることが辛く、死にたい、と嘆き暮らすトビト
嫁いだ夫7人が次々と亡くなり、何のために生きているのかわからない、この世から解き放って欲しい、と願うサラ
二人を繋いだのは、神の使いラファエルでした。
息子よ、日ごとに主を思い起こしなさい。
息子よ、できるかぎり施しをしなさい。
息子よ、すべてのみだらな行いから身を守りなさい。
息子よ、お前の兄弟たちを愛しなさい。
子よ、すべての行いに注意し、すべての振る舞いに節度を守りなさい。
お前自身が嫌うことを他人にしてはならない。
(トビト記4章抜粋)
この4章の教えは、現代でも親が子どもに伝えるべき全てではないかと思わされます。
兄弟、とは、この時代は親族(従兄弟など)を指しており、家族を大切にすることを意味しています。
ラファエルを伴ってトビアが旅に出る際、息子にこう語りかけるトビト
息子よ、旅に必要なものを整え、兄弟と一緒に出発しなさい。
天におられる神が、お前たちを守り、無事にわたしのもとに連れ戻してくださるように。
息子よ、神の使いが、お前たちとともにいて、無事に旅をすることができるように。
(5・17)
7人もの夫に(結婚したその夜に)死なれた娘サラがトビアと結婚することになり、翌朝トビアが無事に生きていることを知ったサラの父の祈り
「神よ、あなたは、あらゆる清く尊い賛歌をもってたたえられますように。
あなたのすべての聖者と被造物とが、いく千夜にわたって、あなたを賛美しますように。
主よ、彼らに憐れみと救いを与え、彼らの一生が喜びと憐れみに満たされますように」。
(8・15〜17)
二人の父の、こどもに対する愛情と神への賛歌が感動的で、ここも、現代の親のこどもへの願いの全てではないでしょうか。
サラの家での婚礼期間を終えて家に戻る際に、トビアが義理の両親へかける言葉も、親へのこどもからの愛の全てです。
「主がわたしに一生の日々、あなた方を敬う恵みを与えてくださいますように」。
(10・14)
ラファエルが神の使いであることを明かし、トビトたちに向けてこう言います。
日ごとに神を賛美し、かつ神に向かって歌いなさい。
(12・18)
ふと開いたトビト記には、わたしの今年の抱負の全てが詰まっていました。
家族への愛、親子の慈しみ合い、こどもへ伝えたい大切なこと、これがすべての家庭において大切にされれば。
改めて、家庭がすべての愛の根幹であることを、新年から再確認することができました。
・・・・・・・・・・・・・・
2025年の聖年は、次の教会への巡礼が推奨されています。
福岡教区 巡礼指定教会
浄水通 教会(福岡県)
大名町 教会(福岡県)
久留米 教会(福岡県)
小 倉 教会(福岡県)
佐 賀 教会(佐賀県)
島 崎 教会(熊本県)
八 代 教会(熊本県)
大 江 教会(熊本県)
久留米教会にも多くの方が巡礼に来られるかと思います。
初めて久留米教会に来られる方には、聖堂入り口に、「わたしたちのあゆみ(久留米教会の歴史)」「はじめて教会に来られた方へ(未信者向け)」という2種類のパンフレットと、12月に発行したみこころレターを置いております。
巡礼のスタンプラリーのためのスタンプも準備しております。
どうぞ、ごゆっくりお祈りください。
皆様にとって、2025年が希望豊かな一年となりますように。
・・・・・・・・・・・・
聖年の祈り
天の父よ、
あなたは、わたしたちの兄弟、御子イエスにおいて信仰を与え、
聖霊によってわたしたちの心に愛の炎を燃え上がらせてくださいました。
この信仰と愛によって、
神の国の訪れを待ち望む、祝福に満ちた希望が、
わたしたちのうちに呼び覚まされますように。
あなたの恵みによって、わたしたちが、
福音の種をたゆまず育てる者へと変えられますように。
この種によって、新しい天と新しい地への確かな期待をもって、
人類とすべてのものが豊かに成長していきますように。
そのとき、悪の力は打ち払われ、
あなたの栄光が永遠に光り輝きます。
聖年の恵みによって、
希望の巡礼者であるわたしたちのうちに、
天の宝へのあこがれが呼び覚まされ、
あがない主の喜びと平和が全世界に行き渡りますように。
永遠にほめたたえられる神であるあなたに、
栄光と賛美が世々とこしえにありますように。
アーメン。
聖年の日程表
https://www.cbcj.catholic.jp/wp-content/uploads/2024/04/JPN-CAL.pdf

祝福を受けたもの
あらためまして、主のご降誕おめでとうございます
久留米教会のミサにも、たくさんの方が参列されていました。
24日の1回目の夜半のミサは、おそらく1/4ほどが洗礼を受けておられない方だったかと思います。
始まる前に、「ミサの中で聖体拝領という時間があります。洗礼を受けている信者が小さなパンを受け取ります。まだ洗礼を受けておられないかたは、列に並び、ご聖体は受け取らず、司祭の前で頭を下げて祝福を授けてもらってください」とアナウンスをしました。
聖体拝領の際、改めて宮崎神父様が「洗礼を受けてない方は、聖体拝領が終わった後で列を作ってください」とおっしゃったのですが、「さぁ、祝福を希望する方は並んでください!」と言われたときにとても多くの方が列を作り、祝福を受けられていたのです。

(失礼ながら)聖体拝領の時とは違う宮崎神父様の嬉しそうな表情に、少し涙ぐんでしまいました。
「よく来てくださいましたね、ありがとう、祝福を受けてください!」
そういいながら按手されている気がして、心が熱くなりました。
田中昇神父様のnoteに、派遣の祝福について書かれているページがありました。
以下、少し抜粋してご紹介します。
祝福は、二者の間でやりとりされる一種のコミュニケーションであると言えます。
参加している会衆に向かって「全能の神、父と子と聖霊があなたがたを祝福して下さいますように」と祈ります。
それは、ミサを司式する司教や司祭にキリストの祭司として民に祝福を与える権能が付与されているからです。
もし教会におけるミサ聖祭で、司教あるいは司祭である司式者が神からの祝福を祈るのであれば、それは祝福を与える神とそれをいただく会衆との間の代理者・仲介者として彼らが立てられているからということに他なりません。
ミサ聖祭に参加した信者は皆、聖体によって「養われた者、豊かさをいただいた者、栄えにあずかった者」として、得たものを生活の場で表すように招かれています。
彼らは司式者の祝福によって自分たちの生活の場である家庭、職場、学校に送り出されていきます。
そこで、彼らは遣わされる場で「豊かさ」と「栄え」を福音宣教によって多くの人々に証しながら伝えて行く「使命」(Missio)を果たすわけです。
復活され天に昇って行ったキリストも、後に全世界に宣教に出かけていく弟子たちを、手を上げて祝福されました(ルカ24:50-51)。
それゆえ教会は、ミサの最後に、頂いた恵みを伝えるように、宣教に専心するようにと、貴い使命を受け、それぞれの生活の場に派遣されていく信者を祝福するのです。
Ite, Missa est(イーテ、ミッサ エスト)というラテン語は、字義的には簡潔に「(あなた方は)行きなさい!終了/解散・派遣です!」という意味で、それが日本語のミサ式文では、「感謝の祭儀を終わります。行きましょう(主の平和のうちに)」と訳されています。
私たちは目的なく散会させられるのではなく、使命を伴う散会なのです。
わたしたちは毎週、ご聖体をいただくだけではなく、派遣の祝福を受けているのだ、と改めて理解できました。
洗礼を受けているから、按手による祝福ではなくご聖体をいただける、ではなく、ご聖体をいただいた上にさらに祝福を受けて派遣されているのです。
主があなたを祝福し守ってくださいますように。
主があなたの上にみ顔を輝かせ、顧みてくださいますように。
主があなたにみ顔を向け、平安を与えてくださいますように。
(民数記6・24〜26)
元旦のミサで読まれるこの箇所は、司祭がわたしたちを祝福してくださる権能を授けられていることの証であるとされています。
『来る年も今年のようでありますように。
あなたの上に、平安がありますように。
あなたとあなたの家、あなたのすべてのものに平和がありますように』
(サムエル上25・6)
この箇所は、とても好きなのでいつも年末のあいさつとして用いてきました。
毎年、「わたしにとって今年は本当に素晴らしい一年でした、たくさんのお恵みをいただくこともできました、来年もよろしくお願いいたします」と言う気持ちから、この箇所を好んで人にもお伝えしてきました。
今年は、少し違った気持ちです。
元日に起きた能登半島地震、2日に起きた飛行機事故、クリスマスでさえ停戦がなされなかった戦争、これらを思い浮かべると、「来る年も今年のようでありますように」と言う気持ちにはなれないのです。
主よ、わたしの祈りを聞き入れ、わたしの叫びをみ前に至らせてください。
わたしの悩みの日に、あなたの顔を隠さず、わたしに耳を傾け、わたしが叫び求める日に速やかに答えてください。
(詩編102・1〜3)
天地を造られた主が、あなた方を祝福してくださるように。
天は、主に属するもの、地は、主が人の子らに与えてくださったもの。
わたしたちは主をほめたたえよう、今からとこしえに。
(詩編115・16、18)
来る年も、神様がわたしたち一人ひとりを正しく進むことができるように導いてくださいますように。
・・・・・・・・・・・・・・
29日、今年最後の日曜日は、ミサの最後にベトナムとフィリピンの皆さんが、「今年一年の感謝の気持ちを表したい」と聖歌を披露してくれました。
小道具を持参していらしたジュゼッペ神父様もイタリア語の聖歌を(負けじと)披露してくださり、心温まる最後の主日ミサとなりました。
希望のあかし
カトリック教会では25年ごとを聖年とする伝統があります。
2025年はその聖年にあたり、『希望』がテーマとして定められました。
希望はわたしたちを欺くことがありません。
わたしたちに与えられた聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれているからです
(ローマ5・1~2、5)
「希望を持つ」ことは、簡単なことではありません。
そして、希望こそが今、世界各地の紛争地の人々に必要とされています。
平和な地に暮らすわたしには、「希望が見えない」日々は想像すらできないのが本心ですが、過去には「希望を失いかけた」経験があります。
周囲には、「希望を望む」友人、知り合いがいます。
先の見えない悲しみ、不安、絶望感に取り憑かれた経験は、次に誰かを励ますことができるためだったのだ、と今は思えます。
来る年には困難な現状が打開されることを切に祈る人々は多いかと思います。
信仰がなくとも、なにかにすがる気持ちは、誰にも湧き上がる自然なものでしょう。
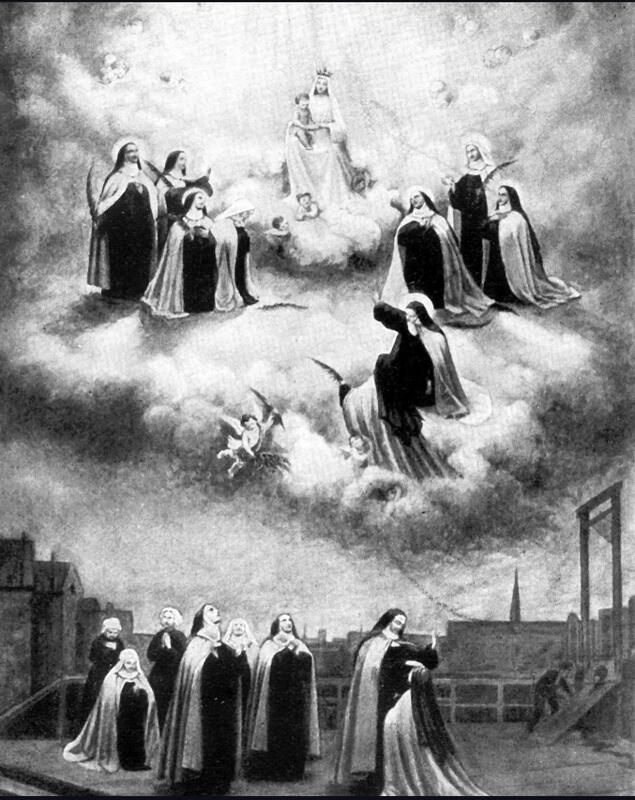
この季節、マリア様がもたらしてくださった希望は、わたしたちにとって最高の光であることを痛感します。
アベイヤ司教様は、聖年を有意義に過ごすために、次のような提案をされています。
1.普段より時間を割いてみことばを読み、そして、できれば、兄弟姉妹と分かち合う
2.ミサへ積極的に参加し、ご聖体によって養われるように心がける
3.神のゆるしを求め、周りの人々との和解を行う
4.さまざまな理由で苦しんでいる人々や差別を受け排除されている人々を心にかけ、具体的に寄り添うようにする
5.すべてのいのちを大切にする心を培い、環境問題に積極的に取り組む
6.聖年の伝統である巡礼のため、指定された教会を訪ね、神の国に向かって歩んで行くことを思い起こし、そのための恵みを願う
どれも大切なことですが、わたしは特に来年は、3「神のゆるしを求め、周りの人々との和解を行う」に取り組んでみようと決めました。
ここにどんな立派なことを書いても、わたしは出来ていないことが多く、人を心の中で排除することがあることを自覚しています。
来年こそは、わたしが関わる人を失望させることのないように努めたい、先週紹介した動画の女性のように、信仰を持っている証を周囲によい香りとして振りまきたい、そう思っています。
クリストフ・ピエール枢機卿がアメリカの聖体大会の講和でおっしゃった次の言葉は、年の瀬にあたってとても心に響きます。
「真の聖体的目覚めとは、秘跡に対する信心、礼拝、宗教行列、要理教育等を常に伴うことはもとより、単なる信心の実践を越えていくものでなくてはならない。
真の聖体的目覚めとは、自分の家族や、友人、自分が属する共同体だけでなく、他者の中に、すなわち、民族や社会的条件の違いや、考えや意見の相違のために、距離を感じている人々の中に、キリストを見出すことである。」
翻訳の文章なので、ややこしく感じますが、「距離を感じている人のなかにキリストを見出す」ことこそが、イエス様のからだをいただくキリスト者としての真の努力目標であるべきだ、あなたこそが「希望のあかし」となるよう努めなさい、とでもいうことでしょうか。
教皇フランシスコは、聖年を布告する大勅書「希望は欺かない」の最後に、こう述べられています。
次の聖年は、ついえることのない希望、神への希望を際立たせる聖なる年です。
この聖年が、教会と社会とに、人間どうしのかかわりに、国際関係に、すべての人の尊厳の促進に、被造界の保護に、なくてはならない信頼を取り戻せるよう、わたしたちを助けてくれますように。
信じる者のあかしが、この世におけるまことの希望のパン種となり、新しい天と新しい地(二ペトロ3・13参照)―主の約束の実現へと向かう、諸国民が正義と調和のうちに住まう場所―を告げるものとなりますように。
今より、希望に引き寄せられていきましょう。
希望が、わたしたちを通して、それを望む人たちに浸透していきますように。
わたしたちの生き方が、彼らに「主を待ち望め、雄々しくあれ、心を強くせよ。主を待ち望め」(詩編27・14)と語りかけるものとなりますように。
主イエス・キリストの再臨を信頼のうちに待ちながら、わたしたちの今が希望の力で満たされますように。
わたしたちの主イエス・キリストに賛美と栄光が、今も、世々に至るまで。
https://www.cbcj.catholic.jp/2024/07/24/30297/
「希望」の年である2025年に、ひとりでも多くの人が希望を見出せますように。
変わることを恐れない
いかがお過ごしですか?
待降節を落ち着いた、穏やかな心で暮らせているでしょうか。
宣言したわたしは、仕事でストレスを感じて疲れてしまっていますが、それでも毎晩「だいじょうぶ!」と気持ちをリセットするようにしています。
ご近所づきあい、職場の人間関係、家族との距離など、何かと頭を悩ませることがあります。
「誰一人として付き合いづらい人は周りにいない」、などという人はいないのではないでしょうか。
「何かを変えたいと思ったなら、その選択肢は自分にある。」
これは、フリーアナウンサーの内田恭子さんの言葉です。
ここ数か月にわたり、友人の職場での相談に乗っています。
友人は、「わたしは正しい、間違っていない。上司のやり方が間違っているので、おかしいことを見過ごすことができない。」と何度もわたしに訴えています。
自分が正しいかどうかを判断するのは、果たして「自分」でしょうか。
ほんとうに自分を正しく知り、自分を軽んじることこそ、最高の、そして最も有益な知識である。
自分を無に等しいものと見なし、常に他人をより高く評価することが、大いなる知恵であり、より高い完徳である。
たとえ、他人が公然と罪を犯し、あるいは何か大きな悪事を行うのを見たとしても、自分をその人よりも善人だなどと考えてはならない。
あなたは、自分がいつまで、そのような状態に留まり得るかを知らないからである。
われわれは皆弱い。
しかし、自分よりももろい者はほかに誰もいない、と考えなさい。
(「キリストを生きる」第1巻第1章4)
われわれは、自分自身を過大に信頼してはならない。
われわれは、しばしば能力と分別を失いがちだからである。
われわれの心の光はかすかであり、しかもわれわれはそれさえ怠惰によってすぐに失う。
われわれは他人のことになると、わずかなことでも咎めるが、しかし自分の短所については、たとえそれが大きくても見逃しがちである。
他人からいやな目に遭わされると、非常に敏感にこれに反応し、これを重視するが、われわれが、他人にどれほど迷惑をかけているかについては、なかなか気づかない。
自分の行動について、よく、正しく反省する人には、他人を厳しくさばく理由などないはずなのに。
(同、第2巻第5章1)
問題の答えを見つけたいときは、聖書とこの本を開きます。
トマス・ア・ケンピスの「デ・イミタチオネ・クリスティ」は、ルネッサンス以降、今日までのあいだ、聖書に次いで最も広く読み続けられているカトリックの信心書です。
日本でさえ、キリシタン時代(1596年)にはローマ字版日本語訳が存在していました。
わたしが愛読書として手元においているのは、2017年発行の、長崎司教区・山内清海神父様の訳本「キリストを生きる」です。
(他にも、「キリストに倣いて」と言うタイトルでいくつかの訳本があります)
自分を信じてくれる人が周囲にいるか、も大事ですが、自分のことをきちんと理解することが大人としての責任です。
自分は正しい、と確固たる自信をもって相手を変えようとしている友人には、何度も伝えています。
「人を変えるのではなく、自分が変わるのよ」
自分の正しさが相手にとっての正論ではない、ことは、おそらく誰もが知っていることではあるのでしょうが、理解できていないことが多いように思います。
ああ、主なる神よ、「正しい裁き手、罰することを怠らない神よ」(詩編7・12)、人間の弱さと悪を知っておられるあなたこそ、わたしの力、わたしの拠り所となってください。
自分の判断だけでは不十分だからです。
他人から非難を受ける時、わたしはへりくだって柔和に忍ばなければなりません。
もしそうしなかったなら、そのたびごとにわたしを赦し、(次の試練の時には)より以上の屈辱を忍ぶ力をお与えください。
なぜなら、自分が正しいと思って、自分でも知りえない心の秘密を弁護するよりも、あなたの豊かなお慈悲にすがって赦しを受けるほうが、わたしにとってずっと有益だからです。
「わたしは自分に何らやましいところはありませんが、だからと言って、わたしが義と認められるわけではありません」(1コリント4・4)
あなたの憐れみがなければ、「生ける人の中で、誰一人として、あなたのみ前にあって正しい者とは言えない」(詩編143・2)からです。
(同 第3巻第46章5)
わたしが友人にアドバイスしていることは、むしろわたし自身ができていない事でもあります。
友人とのやりとりを通して、こうして答えを探す中で、自分にも言い聞かせることができました。
と、ここまで書いたところで、15日はアベイヤ司教様の司式ミサでした。
そのとき、群衆はヨハネに「わたしたちはどうすればよいのですか」と尋ねた。
(ルカ3・10)
アベイヤ司教様は、こうおっしゃいました。
「わたしたちは変わらなければ、という思いがあったから、ヨハネの話を聞いて受け入れたのです。
今、わたしたちは待降節で神を迎えようとしています。わたしたちに必要な姿勢がこれなのです。」
アベイヤ司教様が、結論とも言える答えを教えてくださいました。
・・・・・・・・・・
インスタグラムで、街行く素敵な人に突然声をかけてインタビューする、という動画があります。
NYの街中を闊歩する女性に、「失礼ですが、とても自信に満ちて見えます。どうしてでしょうか?」と質問していました。
その女性の答えは、「ありがとう。たぶん、確固たる信仰を持っているからだと思う。」というものでした。
突然カメラを向けられて、「どうしてでしょうか?」などという質問をされ、(やらせかもしれませんが)「信仰を持っています」と、美しい笑顔で答えていた女性に感動しました。
さらに、「どうしたらあなたのようになれますか?」と質問され、「そうねぇ、もし興味があったら、教会に行くこと、聖書を読んでみることを薦めるわ!」とも答えていました。
(わたしがこういう記事を書いていることをAIに見抜かれて、わたしが喜びそうな動画を見せられたのかも!?)
彼女の口調は、決して押しつけがましいものではありませんでしたし、自信を持って答えた彼女は本当に素敵でした。
わたしも、そうありたいです。
自分を知ること
待降節第2の主日を迎えました。
クリスマスまでの日々、通常よりも丁寧に日々のお恵みを噛みしめて過ごすように心がけています。
長年書いている「お恵みノート」に、今日のお恵みを書くことだけでなく、何かにつけて「ありがとう」という言葉を発するようにしています。
どう生きるか。
普段から自分をしっかり持っていないと、余計なストレスを抱えてしまいます。
無駄に一喜一憂したり、不必要なヤキモキを感じて、気分が滅入る。
そういったこと、ありませんか?
最近は、ネットのニュース・情報、SNSで一方的に表示される広告から、不要な情報ばかり目にしてしまっている(&お買い物してしまう)ことに反省しています。
待降節の1か月だけでも、怒らず、イライラせず、穏やかに暮らすことに専念したい!
神と自分の惨めさとを当時に知ることなしに、イエス・キリストを知ることはできない
アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、キリスト者の神は、愛と慰めとの神である
みずからとらえた人々の魂と心情とを満たす神である
彼らに自分の惨めさと神の無限のあわれみとを内的に感知させる神である
彼らの魂の奥底で彼らと結びつき、彼らに謙虚と喜びと信頼と愛とを満たし、彼らをして神以外の目的を持つことができないようにさせる神である
(パスカル「パンセ」第8章より)
自分の「惨めさ」をきちんと理解しているでしょうか。
「惨め」という言葉はとても後ろ向きな、暗いイメージですが、ここでいう「自分の惨めさ」というのは、「自分の貧しさを知る」ことだと思うのです。
「心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人のものである」(マタイ5・3)は、わたしの大好きな聖句のひとつです。
わたしたちキリスト者はいつも「心が貧しい」状態を意識するべきだ、と思っているからです。
自分をしっかりと持つために、いつも自分を見つめ直して、正直に、謙虚に、奢らずに神様に向き合う姿勢を大切に、そう心がけています。
それが、「心が貧しい」ことの証だと思っています。
ブロッホ〈山上の垂訓〉
ローマ皇帝であり、ストア派の哲学者であったマルクス・アウレリウス・アントニヌスは、著書の『自省録』の中で幸福のためにどうあるべきかを、自分自身に話しかける形で書いています。
いくつか、心に響いた点をご紹介します。
・今すぐこの世から去る者であるかのように、考え、話し、行うこと。
・誰もがたった今しか生きていない。だから、今を大切に生きよ。
・善き者であることが可能なうちに善き者であれ。
・ひどい悲しみに気高く耐えることも幸運である。
・死ぬときは、吸った息を吐きだして大気に戻す。日々の呼吸も同じ。
・自分とともに生きるよう定められた人々には愛情を寄せなさい。
・自分の心を明るいものにしたいなら、ともに生活している人々の長所を思いなさい。
最後の2つは、特に気に入っています。
幸せのバロメーターは人それぞれです。
少なくともキリスト者であれば、自分の貧しさを自覚し、自分のことをきちんと理解することなしに幸せを感じ取ることはできないでしょう。
毎年この時期には、今年一年を振り返り、やり残したこと、ほおっておいたままのこと、気がかりで解決しておきたいこと、を整理するのが長年の習慣です。
皆様は、いかがですか?
今年はどのように神様と、自分と向き合いながら生きましたか?
不安や心配事を残していませんか?
自分のことを見つめ直し、できることには取り組み、神様に委ねるしかないことは明け渡すこと。
心晴れやかな待降節を過ごすことができますように。
神様の光
最近よく聞く、「ミニストリー」・「カテキスタ」という言葉があります。
英語の「ministryミニストリー」の聖書的語源は、ギリシア語の「ディアコニア」です。
「キリスト共同体である教会とその生活の中で奉仕する」ことを表す一般的用語として、主にプロテスタントの牧師職を指して使用されてきました。
ここから、この言葉の中核的意味である「奉仕」が意味を拡大され、キリスト教の「聖務」「宗教活動」などに広く用いられるようになっています。
月刊誌の福音宣教では毎月「チーム・ミニストリー」という特集が組まれ、様々な立場で教会での奉仕活動をされている方々が、zoom座談会形式でお話をされている記事があります。
11月号では、ある信徒の方がこうおっしゃっています。
かいつまんでご紹介すると、
わたしたちには信仰の喜びというのはあるはず。
教会に通い、日々を生きているのに、それを報告する場がない。
信仰を生きるうえで、「宣教者」として歩むうえで、抱いている思いや課題、喜びなどを分かち合う場が少ない。
わたしは、こうして毎週ここに書くことで、学んだこと、感じたこと、今考えていることをアウトプットでき、時折感想をいただくことで、深い喜びや豊かな交わりを得ることができています。
最近、ある信徒の方とミサの後にゆっくりお話をする機会がありました。
初めてでしたが、お互いに信仰について感じていることをじっくりと語り合い、聞き合い、ミサに与るだけでは得られない、豊かで優しい、穏やかな気持ちになることができました。
皆さんは、ご家族や信徒の友人などと、信仰で得た喜びについてお話されていますか?
「カテキスタ」とは、おもに洗礼を希望する方々に、キリスト教の概要や教理(カテケージス・カテキズム)などを教える教師のことです。
あなたは、年が若いということで、だれからも軽んじられてはなりません。
むしろ、言葉、行動、愛、信仰、純潔の点で、信じる人々の模範となりなさい。
わたしが行くときまで、聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさい。
あなたの内にある恵みの賜物を軽んじてはなりません。
その賜物は、長老たちがあなたに手を置いたとき、預言によって与えられたものです。
これらのことに努めなさい。そこから離れてはなりません。
そうすれば、あなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。
自分自身と教えとに気を配りなさい。
以上のことをしっかりと守りなさい。
そうすれば、あなたは自分自身と、あなたの言葉を聞く人々とを救うことになります。
(2テモテ4・13~16)
教皇フランシスコは、2021年に公布された自発教令「アンティクウム・ミニステリウム」の中で、信徒のカテキスタについてこのように書かれています。
受洗者一人ひとりの熱意を目覚めさせ、共同体の中で自らの使命を遂行するように召されているという自覚を再び燃え立たせるためには、実り豊かな形で現存し続ける聖霊の声に耳を傾けることが必要です
この教令は3年前に発布されたものの、いまだ正式な日本語訳が公開されていませんし、日本ではカテキスタの養成がまだ本格的に行われているとは言えないようです。
司祭の高齢化、新しい召命の少なさ、を見ても、わたしたち信徒がカテキスタとして養成されて研鑽を積むことは喫緊の課題です。
教会において様々な奉仕職を担っている信徒は、ある意味でカテキスタとも言えますが、自己流で務められるものでないことも事実です。
受洗者それぞれが受け取ったカリスマをもっと発揮するように、と教皇様はわたしたち信徒を鼓舞されています。
(教皇様のこの教令に関しては、福音宣教12月号でレナト・フィリピーニ神父様が詳しく書いておられます)
https://www.vaticannews.va/ja/pope/news/2021-05/il-motu-proprio-antiquum-ministerium.html
神はわれわれに隠れているが、神がぼんやりしてよく見えない原因は、いわば神が暗中に隠れているというように、神自身にあるのではない。
その原因はわれわれ自身のうちにある。
すなわち、われわれの精神の洞察力が弱いために、いなむしろ精神力がにぶいために、われわれは神の光に近づくことができないのである。
(カルヴァン「テモテへの第一の手紙注解」より)
待降節は、神様の存在を一番感じることができる季節です。
待降節の始まりにあたり、今年もアドベントクランツを作りました。
また、ヨゼフ会、青年会と日曜学校の子どもたちが協力して、プレゼピオの台座を設置しました。
様々な立場で「カテキスタ」として働くわたしたちの、教会における「ミニストリー」は、こうした場面でも現れます。
毎週ミサに与るだけでなく、一人ひとりが共同体の中で思いを分かち合い、自分に与えられている神様からの光(カリスマ)を発揮できますように。
毎週灯されるロウソクの光の中に、少しづつ完成していくプレゼピオの飾りの中に、神様の光を感じ取り、待降節=今年の残りの日々を心豊かに過ごすことができますように。
神への信頼
大相撲を観てきました。
毎場所テレビで楽しみに観ていますし、九州場所に観戦に行くのも年に一度の楽しみです。
驚いたのは、わたしが取った升席の前後左右は外国人ばかりだったこと。
お相撲の世界にも神様がいます。
「相撲の神様」と奉られているのは、野見宿禰(のみすくね)という日本書紀に書かれている人物です。
東京での大相撲本場所開催前には、日本相撲協会の理事長・審判部長らが出席して例祭が行われ、その新横綱の奉納土俵入りをニュースなどでご覧になったことがあるかと思います。
ここを読んでくださっている方は、洗礼を受けていらっしゃらなくても、信じる「神」を持っているか、「何か」信じるものを模索していらっしゃるのではないでしょうか。
結論から言うと、「信じている『神』がいることは、人間の究極の心の支えではないか」と言うこと。
わたしが望むのは犠牲ではなく、愛である。
わたしが望むのは焼き尽くす捧げものよりも、
人が神を知ることである。
(ホセア書6・6)
アメリカの精神分析の権威カール・メニンガー博士は、
「ユダヤ教の指導者、プロテスタントの牧師、カトリックの司祭は、大まかな原則で言えば、理論上の違いを一致させることが可能だが、ひとたび永遠の命に到達するための方法や決まりについて議論を始めると、絶望的なほど意見が相容れない。ここまでは問題ない。しかし方法や決まりとは何か、確実に知らないと、すべてが茶番になってしまう。」
と書いています。
一方で、ヒンズー教の聖者ラーマクリシュナは、
「神は、大志を抱く者一人ひとりに合わせて、時代や国に合わせて、異なる宗教をつくった。すべての教理は多くの道にすぎず、そのうちの一本が神そのものであることはない。たしかに、どれかの道を心から信じて進めば、神にたどり着くだろう・・・。アイシングをかけた歌詞は、縦から食べても横から食べてもいい。どちらから食べてもおいしいのだから。」
とおっしゃったそうです。
三笠宮妃百合子様がお亡くなりになりました。
101歳でした。
18歳で皇室に嫁がれ、5人のお子様に恵まれました。
三男の高円宮様は、2002年にスカッシュのプレー中に突然倒れ、47歳でお亡くなりになりました。
長男の寛仁親王は2012年に癌で、次男の桂宮は1988年に急性硬膜下血腫で倒れ、闘病を続けて2014年にお亡くなりになりました。
3人の息子と三笠宮様に先立たれた百合子様は、「お孫さんたちのことを気にかけていた」と新聞に書いてありましたが、「何か」を強く信じて、心の支えにされていたのではないか、と勝手に想像してしまいます。
先ほど書いた、お二人の見解は、現代にもそのまま当てはまります。
色々な信仰、信じる対象、確固たる信念があっても、わたしたちの心はいつも揺れ動きます。
いざというとき、困難に直面した時に、信じている「神様」「何か」を信頼し、身を委ねることができなければ、それは(メニンガー博士の言うように)茶番になってしまうでしょう。
先日お亡くなりになった詩人の谷川俊太郎さんは、直前まで朝日新聞に詩を連載されていました。
最後の詩は、こう編まれています。
感謝
目が覚める
庭の紅葉が見える
昨日を思い出す
まだ生きてるんだ
今日は昨日のつづき
だけでいいと思う
何かをする気はない
どこも痛くない
痒くもないのに感謝
いったい誰に?
神に?
世界に?宇宙に?
分からないが
感謝の念だけは残る
最期の時に、「何か」に感謝する気持ちを抱きながら過ごせる。
谷川さんが信じていらっしゃったものがなにかは存じませんが、この最後の詩を読めば、彼の人生が素晴らしい締めくくりであったであろう、と想像できます。
人よ、何が善いことか、
主が何を求めていられるかは、
お前に告げたはずだ。
正義を行い、慈しみを愛すること、
へりくだって神とともに歩むこと、これである。
(ミカ書6・8)
ここで言う「正義を行う」とは、公正な裁きと正しい人間関係を保つこと、を意味しています。
人との関りを正しく保ち
隣人への慈しみをいつも心に留め
へりくだる心を忘れずに
神への感謝のうちに
信頼して全てを委ねる
この箇所は、印刷して寝室の枕元に貼っておくことにします!

後悔を晴らす
次の日曜日まで、聖書週間となっています。
皆さんは、どのようなタイミングで聖書を開いていますか?
いつも何か、1冊の本を読むようにしています。
信仰に関する本でなくとも、気になった箇所があればそこに関連するかもしれない聖書の箇所を探します。
ニュースも、気になる内容があれば聖書にその応えがないか開いてみます。
わたしにとって、聖書を開くのは習慣となっています。
昨日お話しした方は、「眠れない時や、夜中に目が覚めてしまった時に、聖書を開いて読んでいます」とおっしゃっていました。
聖書を家で一人で読んでも、「理解」することは難しいかもしれません。
ですが、聖書を家で開いて斜め読みすることは、テレビをつけっぱなしにしておくよりもずっと善い「習慣」になるでしょう。
ぜひ、今週は心掛けてみてください。
・・・・・・・・・・
先週紹介した、米田神父様の『イエスは四度笑った』を読んでいて、ある記憶が蘇りました。
18歳、大学一年生の冬の忘れられない記憶です。
終電での帰りの車内。
満員でギュウギュウ詰めに近かったのですが、ドア付近にいた若い男性に、酔っていて立ったまま寝ていたおじいさんが寄りかかっていました。
若い男性は何度もおじいさんを押して自分から離していましたが、すぐにまた寄りかかってきます。
その時、駅に到着し、ドアが開いた途端、若い男性はおじいさんをホームに突き倒したのです。
降りる人も乗り込む人も、一様に驚いていましたし、近くに立っていたみんなが(わたしを含め)あっけにとられました。
そして、ドアは閉まり、何事もなかったように電車は動き出しました。
すぐに、一人の女性が大きな声でその男性に向かって「あなた、サイテー!!」と言い放ちました。
すると、2人くらいが続けて「ホントだよ、あのおじいさん、頭打ってケガしてたらどうすんだよ!」「サイテーなやつだな!」などと非難を始めたのです。
終電でした。
降りて介抱するか、乗らずにおじいさんを助ければ、帰りの電車はもうありません。
わたしも含め、誰もそうしなかったのです。
米田神父様は、こう書いておられます。
イエスが生涯かけて身をもって示したこと、それは人間性の回復である。
困っている他者、悲しんでいる他者に近づき、他者のために惜しみなく時間を空け、他者の必要をすべて満たしつつ、その人の友人になりなさい、という内容こそ、「よきサマリア人」の譬え話である。
18歳のわたしが、洗礼を受けていたら、ホームに突き倒されたおじいさんに駆け寄って、介抱したのでしょうか。
当時、「よきサマリア人」の教えのことをきちんと理解していたら、おじいさんを助けたでしょうか。
おそらく、出来なかったでしょう。
この後悔は、長い間ずっとわたしの心に刺さったままでした。
電車が動き始めてから若い男性の行為を非難した人たちとわたしは、全く同じなのだ、という恥ずかしい気持ちです。
「よきサマリア人」の話は、ルカ福音書だけに書かれています。
ですが、米田神父様によると、共観福音書すべてに出てくる「最も重要な掟は何か」(マルコ12・28,マタイ22・36)、「何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるか」(ルカ10・25)が前提となっている話です。
イエス様の時代、「隣人」というのははっきりとした概念があり、選ばれたイスラエルの民に属していて、ユダヤ教の掟に忠実で敬虔な仲間内のことを指していました。
ですが、この譬え話の結論としてイエス様が伝えようとしているのは、「隣人」の定義でもあるのです。
「隣人とはだれか?」と問われて、「隣人とは誰々である」と答えることは、隣人の枠を定めることになります。
イエス様は、まずその枠を取り払いなさい、とおっしゃっているのです。
枠や壁を打ち破り、苦しんでいる人、悲しんでいる人に自分から近づいていき、その人の隣人になりなさい、という教えなのです。
イスラエルよ、聞け。
わたしたちの神、主こそ、唯一の主である。
心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたたちの神、主を愛しなさい。
今日、わたしがあなたに命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちにそれらを繰り返し教え、あなたが家に座っている時も道を歩く時も、寝ている時も起きている時も、この言葉を語り聞かせなさい。
(申命記5・4〜7)
「第二の掟はこれである。
『隣人をあなた自身のように愛せよ』
この二つの掟よりも大事な掟はない」。
(マルコ12・31)
洗礼を受けたから、信仰を持っていると自覚しているから、「隣人を自分のように愛する」ことができるわけではありません。
人生の中で、幾つものつまずきを経験し、失敗を糧に進み、後悔を挽回すべく努力する。
そうした積み重ねによって形成されてきた、自分の人間性。
「酸いも甘いも」ではありませんが、若い頃には分からなかったこと、気づかなかったこと、出来なかったことを、人生を重ねるうちに理解し、自分の糧としていく。
今の自分の姿を、神様の前で自信を持って「努力していますので、これからもよろしくお願いします」、と言えるようにしたいものです。
先日、とても嬉しいお言葉をいただきました。
「いつも読ませてもらっています。
先日の記事で、とても救われました。
ありがとうございました。」
本当に嬉しく、「一人の方を励ますことができた」としたら、わたしの過去の後悔も神様に少しは許してもらえるかも、、、、と思えたのです。
・・・・・・・・・・・・
いつも、花壇を美しく整えてくださって、ありがとうございます。
イエス様のユーモア
突然ですが、大人に必要な、一番大事な人間性は「ユーモア」のセンスだと、常々思っています。
「ユーモア」とは、人を意図して笑わせる能力ではありません。
辞書によると、
広辞苑:上品な洒落やおかしみ
三省堂:人間味のある、上品な・おかしみ
大辞林:思わず微笑させるような、上品で機知に富んだしゃれ
大辞泉:人の心を和ませるようなおかしみ、上品で笑いを誘うしゃれ
などと表現されています。
「ユーモアは感情的なものであり、自分を客観視して笑いのめす余裕と、他者を完全に突き放すことなく、愛情によって自分と結びつける能力を兼ね備えてこそ、真のユーモアの持ち主になれる。
こうしたユーモアに欠かせない要素をイエスは誰よりも豊かに身につけている。
ユーモアとは、他者を思いやる懐が深い人間、他者のみならず自己に対しても寛大である人間のみが備え得る特性であり、人生の悲しみや苦しみを潜り抜け、汗と涙で生き抜いてきた者こそが身に帯びる感覚である。」
カナダとスイスで10年にわたって徹底的に聖書と神学の研究をされた著者の米田神父様は、この本のタイトルを「意表をついてみた」とおっしゃっています。
事実、わたしもタイトルに魅せられて(よく内容も知らずに)、この本を購入しました。
本の導入で、1970年代に発見されたグノーシス主義者による「ユダの福音書」(発見されたのは写本で、書かれたのは2世紀ではないか、とのこと)について紐解いています。
この福音書には、「イエス様が笑った」場面が4カ所あります。
カトリックでは異端とされた教義ですが、この中での最初のイエス様の笑いは、ミサを捧げている弟子たちを嘲笑した笑いです。
一世紀後半から始まった、正統派教会とグノーシス派との論争のなかで、イエス様は人為的に笑わされたのです。
ですが、米田神父様は「正統派による聖書の正典化に拍車がかかった」、「今日、不動の如く整理された聖書やミサ、教義の上にあぐらをかくのではなく、長い歴史の中での学問的論争を通じての一つの実りであることを認識」すべきだ、とおっしゃっています。
米田神父様が紙幅を割いたのはこの4つの笑いのことではなく、「大食漢の大酒飲み、取税人や罪人の仲間」と正典の福音書が記すイエス様の、ユーモアと隠れた笑いの読み解きのほうです。
その中でひとつ、最も心に響いた箇所をご紹介します。
だれも、織りたての布から布切れを取って、古い服に継ぎを当てたりはしない。そんなことをすれば、新しい布切れが古い服を引き裂き、破れはいっそうひどくなる。
また、だれも、新しいぶどう酒を古い革袋に入れたりはしない。そんなことをすれば、ぶどう酒は革袋を破り、ぶどう酒も革袋もだめになる。新しいぶどう酒は、新しい革袋に入れるものだ。
(マルコ2・21~22)
この箇所、わたしは全く誤解、というか、理解していなかったと自分で驚きました。
米田神父様によると、「古くて硬い入れ物に今まさに発酵中の新しいぶどう酒を注ぐと、その生命力、膨張力によって、古い革袋は持ち堪えられなくなる。
この比喩を通して、イエスの漲る生命力を指し示している。
今まさに新しく生まれつつある力が、古い殻を、古い体質を、古い壁を打ち破ってゆく、自分はまさにその力であるという、イエスの力強い積極的な意欲がここでは語られている。
マタイとルカは、「誰も、古いぶどう酒を飲んだ後で、新しいぶどう酒を欲しがりはしない。『古いものが善い』と言うからである」と付け加えている。
マルコが伝える真意を十分理解できなかったのかもしれないが、思わず笑ってしまう。
イエスなら言いそうな、まさにユーモアが感じられれる。
まあ、そうは言っても現実はそう甘いもんじゃないよ、そうはうまく行かないよ、と茶目っ気たっぷりに言い足したのかもしれない。」
その他にも、わたしたちがよく知っている福音書のエピソードを紐解いて、隠された(知らなかった)イエス様のユーモアが解き明かされていきます。
「米国の多様な社会を行き過ぎと感じる有権者は地方を中心に多い。
黒人かつアジア系の女性という多様性を体現するハリス氏の存在そのものが、保守層のみならず、無党派層の一部に忌避された面は否めない。」
読売新聞のアメリカ総局長が、記事にこう書いていました。
多様性を訴え続け、世界をリードしてきたかにみえた国の、これが現実です。
品がなく、他者を愚弄するユーモアのセンスの持ち主が勝つ、これが現実です。
(応援している方、ごめんなさい)
今週は、「ウィットに飛んでいる」「面白い」とは違う、「ユーモアのセンス」を身につけたい!と改めて決意を新たにしました。
・・・・・・・・・・・・・・・
10日のごミサは、3人の神父様と4人の侍者と、七五三のお祝い、という贅沢なお恵みの時間でした。
空から見ている
秋の空は本当に美しい
こどもの頃から、美しく晴れた空を見上げると、そこに神様がいらっしゃる気がするのです。
そして、上からわたしたちすべてを見ていらっしゃるのを、小さいころから感じていました。
アメリカメジャーリーグのワールドシリーズとプロ野球の日本シリーズ、同時日程だったので、朝と夜と、観るのが大変でした!
スポーツの秋、自分では全く運動をしないので、観戦するだけでも気持ちが高揚します。
野球選手が、バッターボックスに入る前に、バットに滑り止めのスプレーを吹きかける姿をご覧になったことがあると思います。
わたしが見てきた限り、普通、選手はそのスプレー缶をその辺に投げ捨てていますが、大谷翔平選手は違います。
使い終わった缶を、きちんと立てて、足元に置きます。
(このことに気づいたのはわたしだけではないはず。)
・・・・・・・・・・・
人の行いは、必ず誰かに見られているものです。
死者の月、いつもよりも天国の方々を身近に感じます。
とくに、母がわたしの仕事ぶりを見ている気がしています。
自分がどのような最期を迎えるか、想像したことはありませんか?
わたしの母は、若いころからとても病弱な人でした。
母を知っていた方は、「いつも明るく元気な人」だと思っていたようで、亡くなった後にその話をすると、誰もが「信じられない」と驚いていました。
しかし、義人の魂は神の手にあり、どんな責め苦も彼らに触れることはない。
彼らは愚かな者の目には死んだ者のように見え、彼らがこの世を去るのは災いだと思われ、彼らがわれわれから去っていくのは滅びだと思われた。
しかし、彼らは平和のうちにある。
主に寄り頼む者は心理を悟り、主を信じる者は愛のうちに主とともに住むであろう。
主に選ばれた者には恵みと憐れみとがある。
(知恵の書3・1~3,9)
病弱な母の元に、しょっちゅうホームドクターが往診に来ていた様子が、こどもの頃の記憶です。
最後の10年ほどは、月のうち1週間は寝込んでいました。
そんな母を、「かわいそう」な人だと思っていました。
遠藤周作さんのエッセイ『死について考える』に、興味深い箇所がありました。
以下、かいつまんでご紹介します。
わたしが大変面白く思うのは、釈迦とキリストの死に方が全くちがうことです。
お釈迦様は、お弟子や鳥や獣や虫たちにまで囲まれて、惜しまれて死んでいったわけですが、それが東洋的感覚で言ったら、死に際がきれいということでしょう。
しかし、キリスト教の場合は、キリスト自身が十字架の上で、槍で突かれて苦しんで、最後まで苦しみながら、一見絶望的に聞こえる言葉までくちにされました。
神よ我を見捨て給うやなどど。
これは、詩篇のなかの祈りの言葉で神を呪う言葉ではないのですが、非常に苦しんだ死に方です。
しかも、その死に方を聖書は肯定しているわけです。
そのうえ、キリスト教の信者は、そのイエスの死に自分の苦しみを重ねて考えるようになっています。
母は病気で苦しんで亡くなったのですが、信仰を持っていたので、間違いなく神様の元へ行くことができたと信じています。そして、身体は苦しんでいましたが、おそらく、最期まで家族の幸せを祈っていたであろうと確信しています。
さらに思うのが、母が亡くなった後により結束して強固な絆で結ばれたわたしたち家族は、母が天国から働きかけ、空から見守ってくれているおかげなのだ、ということです。
わたしがもし病気になって、地上での最期を迎える時も、病に負けても心は晴れやかでありたい、天国でもいつまでも家族のために祈り働き続けるのだ、と死者の日には毎年思っています。
天に属する体の輝きと、地に属する体の輝きとは違っています。
太陽の輝き、月の輝き、星の輝きは、それぞれ別であり、一つの星と他の星とでは輝きが違います。
死者の復活も、これと同じです。
蒔かれる時は滅び去るはずであったものが、復活する時は滅びないものとなります。
蒔かれる時は卑しかったものが、復活する時は輝かしいものとなります。
蒔かれる時は無力であったものが、復活する時は力あるものとなります。
自然の命の体として蒔かれて、霊的な体として復活するのです。
(1コリント15・40〜44)
遠藤周作さんは、このようにも書いておられます。
永遠に人間の同伴者となるため、愛の神の存在証明をするために自分がもっとも惨めな形で死なねばならなかった。
人間にむかって、ごらん、わたしがそばにいる、わたしもあなたと同じように、いや、あなた以上に苦しんだんだ、と言えぬからである。
人間にむかって、あなたの悲しみはわたしにはわかる、なぜならわたしもそれを味わったからと言えぬからである。
地上の生で苦しんだ人は幸いである
天の国にはその人たちの憩いが用意されているからである
(byわたし)
しっかり腰を据え、またどっしりと構え、絶えず主の業に励みなさい。
主と一致していれば自分の労苦は無駄ではないと、あなた方は知っているのですから。
(1コリント15・58)
わたしにとって、空から見てわたしを守り、働きかけ、導き、共にいてくれる聖霊は「母」なのです。
許される罪
いつの時代も、犯罪は存在し、犯罪を犯す者と被害者はなくなることはありません。
「闇バイト」という社会問題について、とても気になっています。
高額の報酬を餌に実行犯をSNSで募集する、という犯罪が横行しています。
お互いに素性の知らない者同士が集まり、強盗や窃盗を行い、離散していく。
計画者は指示するだけで手を汚さず、実行犯は使い捨て、という、信じられないような時代です。
逮捕されるのは、10代や20代の若者です。
『お金が手元に入ってきたら、罪悪感は消えていった』
『まともに働くことが馬鹿らしくなった』
『受け子だし罪の意識はあまりない』
この犯罪の一番の問題は、罪の意識が薄い(ない)、という点ではないでしょうか。
嘆きの壁、石の隙間に入れられた紙片には、祈りの言葉や宗教的メッセージが書かれています。
観光客は、単に自分の願い事を書く場合もあるでしょう。
実際にこの壁の前に立ってみて、そして祈りをささげる人の様子に触れて、人々は自分の罪を悔い改めているのではないか、と感じたことを今でもよく覚えています。
実際に起きた、司祭なりすまし事件をモチーフにして作られた映画「聖なる犯罪者」
(以前もご紹介していたかもしれません。。。)
犯罪を犯し、少年院にいるダニエルは、院内でのミサの侍者をしていました。
出るとき、ダニエルは司祭にこう尋ねます。
「神の元で働きたい。資格があれば」と。
しかし司祭はこう告げます、「前科者は、聖職者に就けない」と。
ダニエルは、司祭が病気で入院することになった教会で「代理の神父様」だと招き入れられ、静かな村の司祭代理の職にありつきます。
もちろん彼はカトリックの司祭教育など受けておらず、最初は、院内で見聞きしたことを見よう見まねで繰り返しているにすぎませんでした。
しかし次第に、これまでの司祭とは全く違い、熱く大胆に自分のことばで語る説教、形式を気にしない型破りなミサ、人々へ接するその様が、村人の「生」を呼び覚ましていくことになるのでした。
ですから、誰でもキリストと一致しているなら、新しく造られた者です。
古いものは過ぎ去り、今は新しいものが到来したのです。
これらのことはみな、神に由来しています。
神は、キリストを通してわたしたちをご自分と和解させ、また、和解のために奉仕する務めをわたしたちにお与えになりました。
つまり、神こそ、キリストにおいてこの世をご自分と和解させ、人々に罪の責任を問うことなく、和解のための言葉をわたしたちにお委ねになったのです。
(2コリント5・17~19)
主は憐れみに満ち、恵み深く、怒るに遅く、慈しみに溢れておられる。
主は永遠に責めることはなさらず、とこしえに怒り続けられることはない。
主は、わたしたちの罪に従ってわたしたちを扱わず、わたしたちの咎に従ってわたしたちに報いられない。
(詩編103・8~10)
前科のある人は聖職者になれない、という点がとても心に引っかかっています。
「罪を犯した人に石を投げられる者」はだれもいない、それがわたしたちです。
犯罪を犯し、罪を認め、報いを受けて悔い改めて社会復帰している人には、真の赦しは与えられないのでしょうか。
わたしは自分のうちに、すなわち、わたしの肉のうちに、善が住んでいないことを知っています。
善いことをしようという意志はありますが、行いが伴いません。
わたしは自分の望む善いことをせず、望まない悪いことをしているのです。
わたしが自分の望まないことをしているとすれば、それを行っているのは、もはやわたしではなく、わたしの内に住んでいる罪なのです。
(ローマ7・18〜20)
許される罪と許されない罪があるのでしょうか。
「わたしが悪かった、言いすぎた、申し訳なかった、ごめんね」、そう言ってくれた人を許しませんか?
罪を認め、裁判で決められた刑期を終えて、悔い改めた犯罪者は赦されませんか?
アメリカ大統領選挙に関するニュースを見ていて、こう発言している人がいました。
「犯罪歴のある移民は、国外に追放すべきだ」
あるのは「許されない罪」ではなく、「許さない罪」なのではないでしょうか。
「許されない罪」があるのならば、罪を認めず、反省も後悔もせず、悔い改める心すらない、そういう罪でしょう。
そういう罪人のために、神様が働いてくださいますように。
↓ 予告編をご覧ください。
きっと、映画を見たくなるはず!
静かな祈り
ある日の、教皇様のXのお言葉です。
戦争を望み、引き起こし、あおっては、無用に長引かせて、戦争から冷淡に利益を得る人々のためにともに祈りましょう 。
神がその人々の心を照らし、その目の前に自分たちが引き起こした数々の不幸を示してくださいますように。
読み間違い?書き間違い?かと思い、何度も読み返してしまいました。
「戦争から利益を得る人々のために祈りましょう」とは?と。
心のうちでお前の兄弟を憎んではならない。
必要なら同胞を戒めなければならない。
そうすれば、彼のことで罪を負うことはないであろう。
復讐してはならない。
お前の民の子らに恨みを抱いてはならない。
お前の隣人をお前自身のように愛さななければならない。
わたしは主である。
(レビ記19・17〜18)
下線を引いた言葉は、すべて同じ意味だと教わりました。
レビ記では、この単語はすべてユダヤ人を意味していますが、新約におけるイエス様の教えは、文字通りにすべての「隣人」へと広がります。
冷たい人、嫌なことを言う人、気の合わない人、、、
自分の周りに日常的に存在する、こうした人のために祈れますか?
わたしは全くできていません。
それすらできずに、教皇様がおっしゃる「戦争から利益を得る人のために祈る」など、到底できるはずはありません。
人のために祈るというのは、本当にハードルの高い教えです。
戦争は、旧約聖書のいたるところに書かれています。
神は人間たちの戦争に巻き込まれ、戦争に干渉したり、出陣の命令を下したりします。
これは、古代の中近東の考え方が反映されているのだそうです。
ヘブライ語で戦争を表す「ミルハマ」は、「敵対する」という意味の言葉が語源です。
また、ヘブライ語の「シャローム」という語は「繁栄・充足・平和」を意味します。
戦争に対立する言葉は、普通は平和ですが、ヘブライ思想において戦争は「シャローム」に対立するものではありません。
戦争と平和は、いずれも混とん状態や無秩序に対立するものです。
ですので、旧約における戦争は、混とん状態に対抗し、調和と秩序を取り戻すための手段である、という意味なのだ、ということです。
(トーマス・レーマー著「100語でわかる旧約聖書」より)
わたしが発見した次のことだけに目を留めよ。
神は人を正しい者に造られたが、人はさまざまな策略を探し求めたのだ。
(コヘレト7・29)
わたしはまた、日の下で見た。
必ずしも、足の速い者が競争に勝ち、強い者が戦いに勝つとは限らず、また知恵ある者がパンを、賢い者が富を、学識のある者が愛護を得るとは限らないことを。
時と災難が、すべての者に臨むからである。
誰も自分の時がいつ来るかを知らない。
(コヘレト9・11〜12)
コヘレトは、善人にも悪人にも同じように不条理なことが起こるが、それを神の手の中にある人生の一断面と捉えて歩んでいくことを説いています。
イエス様はそれを一歩進めて、善人にも悪人にも等しく同じ自然が与えられることに触れ、それを「敵を愛する」という教えの根拠としています。
ノーベル文学賞を受賞したハン・ガンさんは、受賞した後すぐに記者会見やお祝いの席を設けることを拒みました。
「今すぐスポットライトを浴びたくはないです、私は静かにしていたい。
世界に多くの苦痛があり、私たちはもう少し静かにしていなければなりません。
それが私の考えで、(それで父に)宴会を開くなと言ったのでした。」と取材で答えていました。
なるほど、と深くうなずけました。
敵、とまではいかずとも、「あの人」のために静かに祈ってみよう、そう思わされました。
///////////////////////////////////
不安定なお天気が続いていましたが、20日日曜日は秋晴れで涼しい一日となりました。
春に企画を始めて、試行錯誤しながら準備をし、ようやく皆さんとこのような時間を持つことができました。
企画した当初は、老朽化に伴い毎年あちらこちらを修繕し続けているため、教会の営繕費基金のためにバザーを、と考えていました。
ですがある信者さんから、「今日のバザーの目的は、信徒の親睦ですね!」と最高の笑顔で言われ、涙が出そうでした。
慣れない手つきでポップコーンと地鶏を焼いてくれた壮年男性陣
美味しいぜんざいを作ってくれた女性の会
バザー経験豊富でたくさんのアドバイスをくださったおばさま方
子どもたちのために遊びのコーナーを作ってくれた青年会
早朝からの設営を手伝ってくれた、若いベトナムのみんな
美味しいパンと飲み物を振る舞ってくれたフィリピンコミュニティ
たくさんの信徒の方々が、本当にたくさんの商品を出してくださり、カラッとした秋晴れの下、素晴らしい親睦のバザーとなりました。
久留米教会は、本当に恵まれています。
現代の徴
『シビル・ウォー』という映画が公開中です。(観てないけど)
アメリカで内戦が勃発したら、という衝撃作です。
近未来のアメリカが舞台で、連邦政府から19の州が離脱し、テキサスとカリフォルニアの同盟軍がホワイトハウスに侵攻するというストーリー。
今、世界では信じられないようなことばかりが起きている(報道されている)ので、この映画も将来ありえるのかも、と思わされます。
ガザの惨状を映像で見るたびに、奇跡でも起きない限りこの街の将来は絶望的だ、と思うのはわたしだけではないでしょう。
遠藤周作さんの『イエスの生涯』のなかに、こう書いてあります。
共観福音書やヨハネ福音書に記述されたおびただしいイエスの奇蹟物語は私たちに彼が奇蹟を本当に行ったか、否かという通俗的な疑問よりも、群衆が求めるものが奇蹟だけだったという悲しい事実を思い起こさせるのである。
そしてその背後に現実的な奇蹟しか要求しない群衆のなかでじっとうつむいているイエスの姿がうかんでいるのだ。
福音書が残しているこれらのイエスの悲しみの言葉にリアリティがあるのは、彼の前にあらわれる人間たちが「愛」ではなく、徴と奇蹟とを、現実に効力のあるものだけを願ったという事実に基づいて書かれたからにちがいない。
これらイエスの悲しみの言葉、とは、以下の2箇所を指しています。
すると、ファリサイ派の人々がやって来て、イエスに議論をしかけ、イエスを試みようとして、天からの徴を求めた。
イエスは心から深く嘆息して仰せになった、「どうして今の時代は徴を求めるのか」。
(マルコ8・11~12)
イエスはトマスに仰せになった、「あなたは、わたしを見たから信じたのか。見ないのに信じる人たちは幸いである」。
(ヨハネ20・29)
下線を引いた「天からの徴」とは、フランシスコ会訳聖書の注釈によると、衆目を見張らせるようなメシア的徴のことで、エリヤの時に天から火が降って犠牲を焼き尽くしたような奇跡を指す、ということです。
遠藤周作さんの仰るように、イエス様は「心から深く嘆息して」(フランシスコ会訳)、悲しみのうちにうつむいておられたことでしょう。
そして、今日の世界各地で起きている戦争や紛争をみて、今も悲しんでおられるでしょう。
教皇様は、先日談話を発表され、「戦争は敗北であり、武器は未来を建設するものではなく破壊し、暴力は和を決してもたらさない事実を歴史が証明しているが、我々は何も学んでいないようだ」、とおっしゃっていました。
イエス様が、病人を癒す奇跡というかたちで人々に徴をお見せになったのは、ご自分の権威を示し、証明するためなどではない、と教わりました。
そして、そう理解しています。
奇跡はイエスの神性を証明するために書き留められたのではありません。
イエスの神性を復活体験によって知った弟子たちが、導くために奇跡を行った旧約の神の働きの延長として、イエスの奇跡を語るのです。
これまでの歴史を導き続けた神が、今もイエスとなって導いている、との信仰告白として奇跡が語られたのです。
(雨宮神父「なぜ聖書は奇跡物語を語るのか」79ページ参考)
さらに、遠藤周作さんはエッセイの中でこう書いておられます。
イエスは、この結婚式ではじめて奇蹟を行った。
酒がつきたのを知った母マリアがそっとイエスに教えると、彼は甕に水を入れさせ、その水を葡萄酒に変えてみせたのである。
この奇蹟が象徴的だというのは、「水を葡萄酒に変える」ように、イエスはこの後、それまでの旧約的なユダヤ教の信仰を新約的な宗教に変えたことを、この物語が暗示しているからだ。
怒りの神、裁きの神、罰の神は、イエスによって愛の神、許しの神に変えられていく。
その旧約から新約への本質的な変化を、カナの奇蹟の物語は語っているのである。
イエス様が「どうして徴を求めるのか」、と仰ったときのことを考えています。
冒頭に、「奇跡でも起きなければガザに未来は見えない」と書きました。
戦争も冤罪もすべて、人間の仕業です。
神に祈って解決してもらう、奇跡を信じよう、ではなく、わたしたち一人ひとりが、あたらしい現代の徴として行動することが求められています。
日本被団協がノーベル平和賞を受賞したことは、何にも勝る徴でしょう。
68年も活動を続けてこられた被爆者の方々。
想いを引き継ぐべく活動をともにしている若者たちがいることにも、感動しました。
発表の映像を見ていて、「ヒダンキョウ」「ヒバクシャ」という日本語で委員長が語られたことにも感激し、誇らしく思いました。
受賞理由の骨子には、「被爆者の証言は世界で幅広い核兵器反対運動を生み出した」「平和に取り組んできた全ての被爆者に敬意」とありました。
彼らの活動も受賞も、奇跡ではありません。
現代世界を象徴する、新しい徴だと思うのです。
・・・・・・・・・・・・・・
13日は、宮﨑神父様の叙階45年、ジュゼッペ神父様の88回目のお誕生日という、素晴らしい日曜日でした。
幼児洗礼式も行われ、大阪に赴任する前のピーター神父様も来てくださり、侍者が5人もいて、久留米教会は恵まれた徴に溢れた日曜日でした。

沈黙のうちに
2024年10月の祈りの意向は、「使命を担い合う」ために。
教皇様は次のようにおっしゃっています。
わたしたちキリスト者は皆、教会の使命に責任を負っています。
すべての司祭が、すべての人がです。
信徒たち、洗礼を受けた人たちは、教会の中に、自分の家にいます。
そして、その家の世話をしなくてはなりません。
それはわたしたち司祭や修道者にとっても同じです。
一人ひとりが自分に得意なことをとおして貢献するのです。
わたしたちは教会の使命における共同責任者です。
わたしたちは教会の交わりの中で、参加し、生きています。
主なる神は言われた。
「人が独りでいるのは良くない。彼に合う助ける者を造ろう」。
主なる神はそこで、人を深い眠りに落とされた。
人が眠り込むと、あばら骨の一部を抜き取り、その跡を肉でふさがれた。
そして、人から抜き取ったあばら骨で女を造り上げられた。
(創世記2・18、21~22)
この箇所は、女性は男性の一部から造られたものであり、男性より劣っている、などという意味ではありません。
教皇様のお考えでは、こうです。
最初のアダムを深い眠りに落とされた後に、神が彼の脇腹からエバを引き出したように、十字架上での死の眠りに落ちた新しいアダムの脇腹からは、新しいエバである教会が生まれたのです。
(使徒的書簡「わたしはせつに願っていた」14)
わたしたちキリスト者は、いつも、旧約に書かれていることがどのようにイエス様によって成就されたのか、という並行的な読み方で聖書を理解する必要があります。
必要がある、というより、その方が何倍も、聖書を身近で面白いものに感じられるはずです。
新しいエバである教会の一員として、冒頭の10月の祈りの意向のように、教会に集うわたしたち皆が、その使命における共同責任者であることに誇りと喜びを感じることができますように。
教皇様の使徒的書簡「わたしはせつに願っていた」は、70ページほどの薄い本ですが、毎週ミサに集うわたしたちが理解しておくべき教えがぎっしりつまっています。
イエスは言われた。
「苦しみを受ける前に、あなたがたと共にこの過越の食事をしたいと、わたしは切に願っていた」。
(ルカ22・15)
過越の食事であるミサ、その『祭儀の美』としての典礼について、教皇様の教えが述べられています。
その中でわたしが特にご紹介したいと感じたのが、ミサにおける「沈黙」の重要性についてです。
洗礼を受けた時、代母であるシスターから「ミサ中に何度か『祈りましょう』という場面があるから、その時は目を閉じて頭を少し下げて、静かに祈るのよ」と教わりました。
ミサのなかでの所作については、以前このページに書いたことがありますが、わたしはミサの中で特に大切にしているのが、この『祈りましょう』の時間です。
会衆全体に属する儀式行為の中で、沈黙は絶対的な重要性をもっています。
感謝の祭儀全体は、それに先立つ沈黙と、展開する儀式のあらゆる瞬間を特徴づける沈黙に浸されているのです。
回心の祈りの中に、「祈りましょう」という招きの後に、ことばの典礼の中に、奉献文の中に、そして聖体拝領の後に、沈黙が存在しています。
典礼的な沈黙とは、祭儀の行為全体にいのちを吹き込む聖霊の現存と働きのシンボル(象徴)なのです。
だからこそ典礼的な沈黙は、聖霊の多面的な働きを表現する力を持っているのです。
沈黙はみことばを聞く心構えを呼び覚まし、祈りを目覚めさせます。
そして、沈黙はわたしたちを、キリストの御からだと御血への礼拝へと向かわせます。
これらすべての理由から、わたしたちは細心の注意を払って沈黙と言うシンボリック(象徴的)な動作をするように呼ばれているのです。
沈黙を通して、聖霊はわたしたちを磨き、形づくります。
(52)
ミサのなかでの沈黙は、ある意味で「間(ま)」とも言えるかもしれません。
展開する儀式、シンボリックな所作、みことばの連続の中に織り込まれた「間」。
聖霊の働きを、わたしたち一人ひとりが体感するための「間」。
形式的に祭儀を進めない(受けない)ように、ミサの先唱をする際にわたしが特に気を付けているのも、「間」です。
ひとつひとつの典礼が進むたびに、わたしなりにごく小さな時間を置くようにしています。
久留米教会では、ミサの5分前までロザリオの祈りを行います。
そして、ミサまでの5分間、それぞれが静かに沈黙し、祈っています。
ミサが終わると、(すぐに立ち上がって帰る方もいますが)ほんの少しの時間だけ、皆がまた座り、沈黙の時間を持ちます。
沈黙にはじまり、祭儀中に訪れる沈黙を守り、沈黙のうちに終える。
次のミサで、これまでよりもう少しだけ、この沈黙を意識してみませんか?
・・・・・・・・・・
上智福岡高校の生徒たちが、夏休みに行ったカンボジアでの研修の報告をしにきてくれました。
毎年実施されている研修だそうで、多数の応募者の中から選抜された12名が参加したとのことでした。
久留米教会から派遣されている中島 愛さんとの交流もあったようで、貴重な体験をした高校生たちの生き生きとしたレポートに、多くの質問が投げかけられました。

ひとつの生
明日から10月、ようやく秋を感じ始めたというのに、色々な教会の行事のことを考え、個人的な予定を立てていたら、もう今年は終わった気分です。
ステンドグラスから差し込む光も、柔らかで、あたたかく感じます。
イスラエルが展開する報復攻撃が、新たな局面に入っています。
自国民を殺害され人質に取られた報復にハマスを撲滅する、とガザ地区を集中攻撃していたのが、いつの間にか、ハマスを支援しているヒズボラをも撲滅する、という作戦も同時進行しています。
ヒズボラは先週、テルアビブ近郊にあるイスラエルの対外特務機関モサド(Mossad)本部を標的とした報復攻撃を行いました。
数日後には、イスラエルがヒズボラの本部を攻撃し、最高指導者を殺害したと発表しました。
互いに「血の復讐をする者」(申命記19・6)となり、やられたから何倍にもしてやり返す「復讐」の連鎖は、エスカレートする一方のようです。
紀元前18世紀に制定されたとされるハンムラビ法典の、「目には目を、歯には歯を」という同害復讐法は有名ですが、この法典は犯罪に対して厳罰を加えることが主目的ではありません。
(もちろん、目をやられたら目をやり返せ、という意味でもありません。)
ハンムラビ法典はその目的を、「全土に正義をいきわたらせるため、悪事を撲滅するため、強者が弱者をしいたげないため」としています。
財産の保障なども含まれており、奴隷階級であっても一定の権利を認め、条件によっては奴隷解放を認める条文が存在し、女性の権利が含まれている。
ハンムラビ法典は身分の違いによってその刑罰が異なるのに対し、旧約聖書の律法は身分の違いによる刑罰の軽重はない。
(Wikipediaより)
ハンムラビ法典は、次の序文から始まります。
敬虔なる君主で、神を畏れる朕ハンムラビをして国の中に正義を輝かせるために、悪者と奸者とを殲滅させるために、シャマシュ神のように黒い頭どもに向かって立ち昇り国土を照らすために、アヌ神とエンリル神とは朕の名をこう呼び給うた。
これは人びとの幸せを満たすためである。
世界の現代民法の根幹に影響を与えているとされるハンムラビ法典は、一般的に世間が持つイメージとは違い、弱者保護、人民の幸せを守るための法律なのです。
旧約聖書では、出エジプト記21章、レビ記24章、申命記19章の3か所に、この同害復讐に関する記述があります。
あなたの敵の牛あるいはろばが迷っているのに出会ったならば、必ず彼のもとに連れ戻さなければならない。
もし、あなたを憎む者のろばが荷物の下に倒れ伏しているのを見た場合、それを見捨てておいてはならない。
必ず彼と共に助け起こさねばならない。
(出エジプト23・4~5)
これは動物愛護の掟ではなく、たとえ敵であってもせめてこのぐらいのことはするように、そうすれば関係の改善の糸口が開けるかもしれないという意味合いがあると思われます。
イエスは単刀直入に「敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい」と言われます。
この場合、キリストが求めておられる敵への愛の根拠は、ただ父である神が「悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださる」かただからであり、目指すところは天の父の子となることです。
今道瑤子シスターは、「復讐」についてこう書いておられます。
あなた方も聞いているとおり、『あなたの隣人を愛し、敵を憎め』と命じられている。
しかし、わたしはあなたがたに言っておく。
あなた方の敵を愛し、あなた方を迫害する者のために祈りなさい。
それは、天におられる父の子となるためである。
天の父は、悪人の上にも善人の上にも太陽を昇らせ、正しい者の上にも正しくない者の上にも雨を降らせてくださるからである。
(マタイ5・43〜45)
30歳で逮捕されてから58年、1980年に最高裁で死刑判決が確定していた袴田巌さんが、9/26の再審によって無罪となりました。
袴田さんのニュースを見聞きするたびにいつも気になっていたのは、お姉様のひで子さんの存在です。
「人生を懸けてでも、弟の無実を証明する。それが自分の運命だと感じた。」という彼女は、御年91歳。
長年の拘禁生活で精神を病んでしまった袴田さん、弟の代わりに出廷したお姉様。
裁判長が判決を言い渡した最後に、「心身ともに健やかに、ひで子さんの健康を祈ります」と、時折言葉を詰まらせながら語りかけた、というニュースの記事を見て、心が痛くなりました。
この58年間という長い日々、取り返すことのできない人生について、判決が下りた今、どう考えておられるのだろうかと思いを巡らせています。
裁判を終えてインタビューに答えていらっしゃる様子、笑顔で何度も「ありがとうございました。」とおっしゃるお姿、「裁判長にねぎらいの言葉をかけてもらって、とてもうれしかった。皆さま、ありがとうございました」というお言葉。
わたしが彼女の立場だったとして、「うれしかった」「ありがとう」という言葉を発することができたか、、、、。
世界的仏教者のティク・ナット・ハンは、その著書『イエスとブッダ』の中で、このように言っています。
仏教徒はリインカーネーション(生まれ変わり)を信じています。
人間は幾度も生をくりかえすという考え方です。
仏教界では、リーインカネーションよりも、リバース(輪廻転生)という言葉のほうを好みます。
死後、あなたはふたたび生まれて、別の生を生きるのです。
キリスト教では、あなたの今の生は唯一無二のもので、このたったひとつの生があなたの救済の唯一のチャンスとなります。
あなたにあるのは、ただひとつの生だけです。
パウロ袴田さんとお姉さまに、この人生は過ぎ去ってしまったので、生まれ変わったら良い日々があるでしょう、などとは言えません。
「判決をもらって、58年なんか吹っとんじゃったみたいな気がする」とおっしゃっていましたが、お2人は、これからの人生をどのような思いでお過ごしになるでしょうか。
過ぎ去った日々を思い起こせ。
代々の年を顧みよ。
主は荒れ野で、獣の吼える不毛の地で、彼を見出し、彼を囲み、いたわり、ご自分の瞳のように守られた。
今こそ、見よ、わたし、わたしこそがそれである。
わたしのほかに神はない。
わたしは殺し、また生かす。
わたしは傷つけ、また癒やす。
(申命記32・7、10、39)
人生
2024年の全国の100歳以上の高齢者は、2023年から3000人近く増えて9万5000人あまりで、女性が8万3958人(全体の88%)、男性が1万1161人との統計が発表されました。
1924年(大正13年)は、シャネルがリップスティックを初めて発表した年であり、日本初の大規模多目的野球場である甲子園球場が竣工し、越路吹雪・淡島千景・竹下登・相田みつを・力道山などが誕生した年でもあります。
1924年生まれの山頭原太郎神父様は、9/20に100歳を迎えられました。
まだまだお元気で、相変わらずお茶目で、みんなの人気者です。
以前は時々久留米教会のごミサに来てくださっていましたし、現在は久留米の施設にいらっしゃるということもあり、久留米教会で100歳記念ミサを開催しました。
アベイヤ司教様、森山司教様を始め、神父様方が各所からお越しになり、盛大なお祝いのミサとなりました。
山頭神父様がお説教で、色々なお話をしてくださいました。
365日前の、まさに今日、救急車で病院に運ばれました。
悪魔にやられた、と思うほどの痛みに苦しみました。
そのちょうど1年後に、司教様から「ミサで説教をしなさい」と言われてこの場にいます。
神様がこうして、また司祭としての道に帰してくださいました。
今、聖母の家という施設で、なんでもやってもらえて何不自由ない生活をしているのに、やはり寂しいです。
ステーキもトロも、何にもいらない。
ただ、どこかの教会で信者と過ごして、ミサを捧げたい。
それだけが望みです。
カトリック教会は今、衰え始めているのかもしれませんが、イエズス様は全く衰えていません。
司教や司祭だけではなく、あなたたち一人ひとりにイエズス様が力を与えてくださっていることを忘れないでください。
・・・・・・・・・
人生100年時代、と言われて久しいかと思いますが、自分がまだ折り返したばかりなのかと思うと、、、、(;'∀')
人の生とは、語り尽くすことのできない、100人100様の生き様です。
お前は白髪の人の前で起立し、老人を敬い、お前の神を畏れなければならない。
(レビ記19・32)
白髪は栄光の冠。
それは正義の歩みによって得られる。
(箴言16・31)
ヤコブの家よ、わたしに聞け、イスラエルの家のすべての残りの者よ、母の胎にいた時からわたしに担われてきた者たち、腹にいた時からわたしに背負われてきた者たちよ。
お前が老いるまで、わたしはその者である。
白髪になるまで、わたしは担う。
わたしは造り、わたしは背負う。
わたしは担い、わたしは救う。
(イザヤ46・3〜4)
このイザヤの言葉は、こうして書いていて、涙が出そうになります。
あと残りの人生がどのくらい与えられるか、見当もつきませんが、背負って救って頂かなければ。
山頭神父様の人生は、県内各地から集まってくださった、この参列者の溢れんばかりの愛が物語っています。

時代に求められる資質
9/11に行われたアメリカ大統領選挙の討論会を観ました。
表情をほとんど変えずに、時にはイラついた様子で、(虚言も多かった印象ですが)相手を非難したり自身の主張を述べていたトランプ氏
一方で、相手の発言がひどい際には(それは、ほとんどの発言であり、わたしでさえ「根拠がなさそう」と思った)、口の動きは「It's not true.(事実ではない)」とあきれ顔をするハリス副大統領
ハリス副大統領は、トランプ氏には「事実を混同しない気質や能力」がないと主張していました。
兵庫県知事、2つの党の党首選のニュースも含め、最近のニュースは「誰が、どのような人がリーダーとして相応しいか」を考えさせるきっかけになっています。
リーダーにはいろいろな要素が求められますが、時代、国、現状によって、相応しいリーダー像は当然変わっていきます。
旧約に描かれたリーダーも、状況に応じていろいろなタイプがいます。
そこで、モーセとアロンは、集会の前から離れて会見の幕屋の入り口に行き、ひれ伏した。
すると、主の栄光が彼らに現れた。
主はモーセに次のように告げられた、「杖を取れ。そして、お前と兄弟のアロンは会衆を集め、彼らの目の前で岩に命じて水を出させよ。こうしてお前は岩から水を湧き出でさせ、会衆とその家畜に水を飲ませよ」。
モーセは主が命じられたとおり、主の前から杖を取った。
そして、モーセとアロンは集会を岩の前に召集して言った、「反逆する者たちよ、聞け。お前たちのためにわたしたちはこの岩から水を湧き出させることができるのだろうか」。
モーセは手を上げ、杖で岩を二度打った。すると、水が豊かに湧き出てきたので、会衆もその家畜も飲んだ。
(民数記20・6~11)
会衆たちにとって、モーセは自分たちを約束の地に引き連れてくれる、信頼すべきリーダーでした。
途中で「肉が食べたい」などと文句を言っても、こうして必要な時に水を豊かに湧き出させることができる彼は、主に導かれた理想のリーダーに映ったことでしょう。
ですが、この場面に続いて、主は怒りを露わにします。
「お前たちは、わたしを信じようとはせず、イスラエルの子らの目の前でわたしの聖なることを示さなかった。
それ故、お前たちはこの集会を、わたしが彼らに与えた土地に導くことはできない」。
主への信頼があれば、言われた通りに岩に命じればよかったのです。
そして、いらだって岩を二度も打つ必要はなかったのです。
その後、ほどなくしてアロンがホル山で死に、モーセもネボ山で召され(申命記32・48~52)、兄弟は約束の地に入ることは出来ませんでした。
「あなたの神、主が部族ごとに与えてくださる、あなたのすべての町に、裁き手と役人を任命しなければならない。
彼らは公正な裁きをもって民を裁かなければならない。
あなたは裁きを曲げてはならない。
人を分け隔てしてはならない。
賄賂を受け取ってはならない。
賄賂は賢い者の目を眩ませ、正しい者の言い分をゆがめるからである。
ひたすら正義を追い求めなさい。
そうすれば、あなたは生き永らえ、あなたの神、主が与えてくださる土地を所有することができる」。
(申命記16・18~20)
リーダーに求められるのは、いつの時代も「信頼」と「正義」
やはり、聖書にはすべての答えが書かれています。
・・・・・・・・・・・
WOWOWのドラマ「0.5の男」をネットフリックスで観ました。
(最近はネットフリックスで日本のドラマが充実しています!)
このドラマは、ざっと以下のテーマが網羅されています。
・引きこもり
・家庭内暴力
・いじめ
・職場でのパワハラ
・育休後の女性の働き方
・老後の暮らし方
すべて現代社会を反映している問題であり、その対策が国のリーダーに求められていることです。
なんだか、重くて暗い展開を想像されるかもしれませんが、俳優陣の演技の賜物もあり、軽快で明るく、ホロリとさせられる、とっても楽しいドラマでした。
この、現代の社会問題のすべてを解決するキーワードは、「家族」でした。
現実はそう単純なものではないでしょうが、親子の関わり方、兄弟姉妹の関係性、孤立した人への接し方など、いろいろな点において「知れてよかった」と思える内容でした。
人間関係の根本はやはり、家族なのです。
そしていつの時代も、やっぱり家族のリーダーは「お母さん」なのです!!
(このドラマ、かなりお薦めです!)
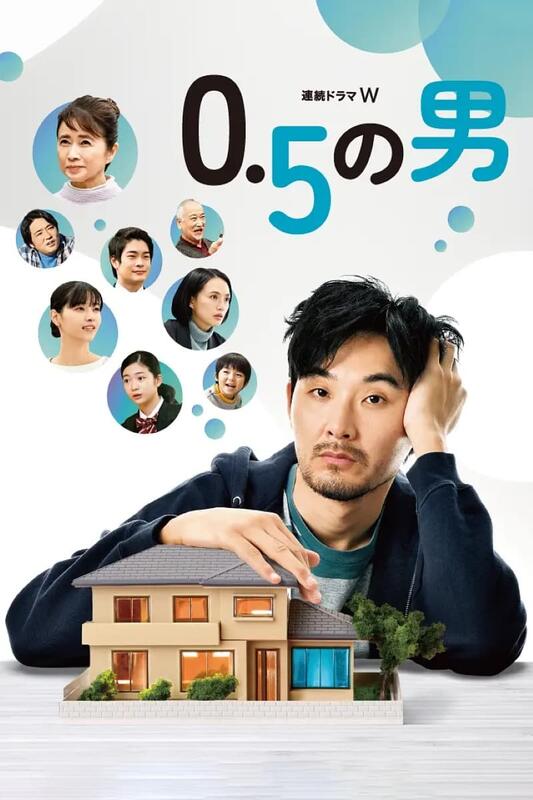
将来を見据える
8日のミサでは、敬老祝福式が行われました。
わたしにとっては、親と変わらない世代の先輩方ですが、友人のように仲良くさせていただいている方も多くいます。
そして、いつのまにか宮﨑神父様も、「敬老」の対象者に近づいていました。
・・・・・・・・・・
今読んでいる本に、ブッダの召命について書かれているくだりがありました。
若き王子ゴータマ・シャーキムニ、未来のブッダは、世俗を捨てるという考え方に染まっては困るから、老・病・死と出家は知らせないように、と父に厳格に守られ、大切に育てられていました。
3つの宮殿と4万人の踊り子をあてがわれ、現世の世俗的な喜びの世界を経験し尽くしていた若者は、違った経験を求めるようになります。
ある日、庭園に行こうと思った王子は、御者が用意した豪華な馬車で出かけます。
「王子に光を与える時来たり。しるしを見せねばならない」と神々は考え、仲間のひとりを身体の弱った年寄りに変え、未来のブッダに見せました。
王子と御者にしか見えていないので、王子は御者に尋ねます。
「この人は何だろう。髪までほかの人と違うが」
生まれれば老いが必ず訪れるものだと知った王子は、心をかき乱されます。
次に庭園に出かけた時は、神々は病人を、その次には死人を見せます。
そのたびに心を乱し、引き返す王子。
ある日、庭園に向かっていた王子は、神々が造った、丁寧にきちんと衣装をまとった僧侶を見ます。
「この人は何者だ」
「この世から隠遁した者でございます」
御者は、この世から隠遁することがどれほど素晴らしいことかを話して聞かせます。
この世から隠遁するというのは、未来のブッダを大変満足させる話でした。
神よ、わたしを守ってください。
わたしはあなたのもとに逃れます。
主に向かって、わたしは言う、
「あなたこそわたしの主、わたしの幸せ、あなたに勝るものはありません」。
(詩編16・1〜2)
わたしにも、「あぁ、あれが召命だった」と思い返すことができる出来事があります。
14年前、熱心にミサに通うようになったわたしは、昨日お祝いした先輩方が、ミサ前に準備で忙しく立ち回っていらっしゃる姿を遠目に見ていました。
それまで、たまに気が向いたらミサに行く、程度の信徒でしたので、教会の運営やミサの典礼準備など、全く知らなかった(関心を持っていなかった)のでした。
ある日、「あなた最近よく来てるわね。聖書朗読してみない?」と声をかけてもらいました。
それ以来、気にかけていただき、少しづつ色々な役割を任せいていただくようになりました。
先週のミサで、あらかじめお願いしていた聖書朗読者が5分前になっても現れず、急遽、夏休みで帰省していた大学生に「お願い、第2朗読、いまから!」とお願いしました。
その時、14年前の記憶が蘇ったのでした。
いま役割を任せてもらっているわたしたちも、将来を見据えて行動しなければ、と。
教会を繋いでいくためには、人の力が必要です。
建物を綺麗に整備して、傷んだ箇所を修理し、祭壇にお花を飾っても、教会という組織を動かして典礼の準備をする人材がなくては、信仰の場を将来に繋げていくことはできないのだ、と最近よく考えるようになりました。
信仰には、信徒の交わりという横軸がとても大切です。
そして、その交わる場が教会です。
以前のわたしのように、自分がミサに与ること以外に関心のない方も多いかと思うのですが、わたしが目をかけてもらったように、わたしも次の人材を見つけたい、と常々目を光らせています。
主よ、あなたはわたしの分け前、わたしの杯に受けるもの。
あなたこそわたしの行く末を決める方。
測り綱はわたしのために善い所に落ちた。
まことに、わたしが受けた譲りは素晴らしい。
わたしはたたえる、わたしを諭す主を。
夜には、心がわたしに教える。
わたしは常に主を思い浮かべる。
主がわたしの右におられるので、わたしは揺らぐことがない。
あなたはわたしに命の道を示してくださいます。
あなたの前には溢れる喜び、あなたの右には永遠の楽しみ。
(詩編16・5〜8、11)
気づいた時に、思った時に、こうして自分の背中を押すためにもここに書いています。
おこがましくも、勝手に身に負った使命感ですが、今神様がわたしたちをこうして働かせてくださっていることの意味を、見逃してはいけないと感じています。
典礼担当者が作ってくれた共同祈願の文が、まさに今の気持ちに合致していました。
今月、敬老の日を迎えるにあたり祈ります。
これまで、周りの方々のため、また教会のために、自分の時間、才能を惜しみなく使われてきたみなさんが、これからも健康に恵まれ、心身ともに元気に過ごすことができますように。
アーメン
聖書を楽しむ日
台風10号は、進路が刻一刻と予報から変わり、想定されていなかったであろう地域にも被害をもたらしました。
逆に久留米は、予想されていた暴風雨がほとんどありませんでした。
人間はコンピュータのデータ計算によって何事も予測できるようになったと思っていますが、自然の力はわたしたちの次元とは全く異なり、災害からは逃れることはできない、という無力さを痛感します。
教皇様の9月の祈りの意向は「地球の叫びのために」
私たち一人ひとりが、地球の叫びに、また、環境災害や気候変動の犠牲者の叫びに心の耳を傾け、私たちの住む世界を大切にする生き方へと導かれますように。
・・・・・・・
台風の影響を考慮して、金曜日は仕事を休みにしていましたので、ゆっくりと聖書を開いて読み返していました。
列王記のエリシャの召し出しと活躍のあたり、いつもワクワクさせられます。
エリヤはシャファトの子エリシャを見つけた。
彼は十二軛の牛を先に立て、畑を耕しており、自分は十二番目の牛とともにいた。
エリヤはそばに行き、自分のマントをエリシャに投げかけた。
エリシャは牛を残したまま、エリアの後を追って言った、「わたしの父と母に別れの口づけをさせてください。それからあなたに従います」。
エリシャは一軛の牛を取って犠牲としてささげ、牛の引き具を燃やして肉を調理し、人々に振る舞い食べさせた。
それから彼は立ってエリヤに従い、彼に仕えた。
(列王記上19・19〜21)
12という数字
自分のマントを投げる行為
牛を残したまま後を追う様子
両親への別れの口づけ
新約へのつながりを感じます。
列王記は、北イスラエルと南ユダ、両王国の王の不誠実さとその滅亡という悲劇的な史実を描いているのですが、その中に挿入されている、反バアル礼拝の主唱者である預言者エリヤと、その弟子エリシャの信頼関係が際立っています。
列王記下の2章では、エリヤが主に遣わされて遠くへ行くので、何度もエリシャに「あなたはここに留まりなさい」と言います。
ですがエリシャは、「生ける主と生けるあなたに誓って申します。わたしはあなたから離れません」。と何度も答えるのです。
イエス様から弟子が逃げるように離れて行った場面を思い起こすと、このエリヤとエリシャの場面はとても感動的です。
「わたしがあなたのもとから取り去られる前に、あなたのために何をすればよいか、言いなさい」。
エリシャは答えた、「あなたの霊の二倍の分け前を継がせてください」。
(列王記下2・9)
エリシャにはエリヤの霊が強く留まり、水が悪くて流産が多いと嘆くエリコの町で、水源の水を癒します。
(列王記下2・19〜)
この『エリシャの泉』は、聖書にある通り、今現在もきれいな水が湧き出で続けています。
2019年の巡礼の際に毎日書いていた記録を読み返してみると、コーディネーターの牧師さんから教わったことを、次のように記していました。
エリコは地中海の海面より250m低い。
亜熱帯的な気候と泉から、BC9000年頃から人類が定住した地として、世界最古の記録がある。
BC7000年の時代の城壁で囲まれた町の跡が発見された。
新約の時代のエリコは別の町。
1994年のオスロ合意でパレスチナ自治区となる。
日本のODA支援で、病院、学校、工場が建てられた。
悲劇を悲観的に捉えるのではなく、その不忠実さを悔い改めを呼びかけるためにあえて楽観的に締めくくられているのが列王記です。
こうして旧約聖書を読むことは、イエス様の教えの根本を知る、大切なことだと教わってきました。
巡礼の手帳の最初には、指導してくださった森山神父様(現、大分教区司教)が事前説明会でおっしゃった言葉を記していました。
わたしたちは、2000年後のキリスト教を受け取っている。
この巡礼は、2000年前のイエス様の言葉を受け取る旅。
新約に書かれたイエス様の言葉の元である旧約を理解し、イエス様と一人ひとりが出会う旅。
イエス様と近しくなるための巡礼の旅。
(2019・7・22コレジオにて)
旧約聖書を読みながら、イスラエルの風景を思い出す休日でした。
モチベーション
この夏の久留米の暑さは本当に異常でしたが、ようやく、朝晩がいくらか過ごしやすくなってきました。
先週18日の夕方、久留米教会恒例の夏の行事「納涼祭」が開催されました。
酷暑の中ではありましたが、多くの皆さんが協力し合い、夏の思い出深い時間を過ごすことができました。
・・・
社会学者・古市憲寿さんの「楽観論」という本を読みました。
その中にこう書かれています。
全く科学的根拠がなくても、ほんの些細なきっかけで人は自信を持ったり、幸せな気持ちになったりする。
結果として、その気分が仕事を成功に導くこともある。
社会学では「予言の自己成就」と言うが、たとえ間違った「予言」であっても、その内容によって人間の行動や意識が影響を受け、ついにはそれが現実となってしまうことがあるのだ。
「予言の自己成就」とは、根拠のない噂や思い込みであっても、人々がその状況が起こりそうだと考えて行動することで、事実ではなかったはずの状況が本当に実現してしまうこと。
例えば、自分は成功すると思う人は成功しやすく、失敗すると思う人は失敗しやすくなることなどがあります。
人から言われた些細な事、ちょっとした行き違い、などがきかっけで負のスパイラルに陥ることもあれば、努力が実ったと実感できること、美味しい食事、友人との楽しい会話などで力がみなぎるような気分になり、やる気が湧くこともありますね。
信仰も、ある意味「自己成就」的な要素を持っているのではないか、と思います。
信仰とは、願うだけ、祈るだけ、想像するだけ、ではありません。
求めるもののために、積極的な行動を起こす必要があります。
信仰生活は、「神様と向き合うことを縦軸とし、周りの人々とのつながりである横軸を深める」ことであると言われます。
そして、人生とは、自分と向き合い、周囲との関係性のなかで常に成長することで深まっていきます。
「わたしはお前たちに清い水を注ぐ。
そうすれば、お前たちは清くなる。
すべての汚れ、すべての偶像からお前たちを清める。
お前たちに新しい心を与え、新しい霊をお前たちの内に置く。
お前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。
わたしたちの霊をお前たちの内に置く。
そして、わたしの掟に従わせ、わたしの定めを守り行わせる」。
(エゼキエル36・25〜27)
わたしは、心が汚れていることを自覚しており、流言やテクノロジーといった偶像に時に支配されています。
心が石のようになり、他者を退け、批判することもあります。
そして、日々反省し、「絶対に神様がわたしを正しく、あるべき方向に導いてくださる」と信じています。
毎日の祈りで、呪文のように祈っています。
必ず祈りを聞き入れてくださる、と信じて、毎日をよりよく生きようと努めています。
谷は一面おびただしい骨で埋まり、しかもそれらは枯れきっていた。
主はわたしに仰せになった、「人の子よ、これらの骨が再び生き返ると思うか」。
わたしは答えた、「主なる神よ、それはあなたがご存知です」。
すると主は仰せになった、「これらの骨に向かって預言し、告げなさい。枯れた骨よ、主の言葉に耳を傾けよ。主なる神はこれらの骨に仰せになる。わたしはお前たちの中に息を送り込む。そうすれば、お前たちは生き返る」。
(エゼキエル37・2〜6)
適切な言い方ではないかもしれませんが、わたしにとって信仰は、人生のモチベーションを上げるために欠かせないものです。
ゼッタイたいじょうぶ
きっとたいじょうぶ
そう自分に言い聞かせるときに、祈りを捧げる対象があることは、本当に救いでありお恵みであると思うのです。
わたしのカトリックの信仰は、母から教わって始まりました。
神様が母を選び、そして、わたしをも選んでくださったのです。
キリストの良い香りでありたい、そう思って信仰を思い返し、今日もモチベーションを上げて、生きます。
永遠の父よ、約束された聖霊を待ち望むわたしたちの祈りを聞き入れてください。
多様な価値観が共存する世界の中で、救い主キリストを信じるわたしたちが、その信仰を誠実にあかししていくことができますように。
わたしが今すべきこと
お盆休みの間、皆さんも、ご家族が帰省されていたり、ご家族の元を訪ねて遠出されたりと、それぞれの過ごし方をされていたことでしょう。
お盆、というのは仏教に起源がある風習なのかもしれませんが、日本の夏の習慣として定着しています。
改めて家族のことを深く想う、日本の美しい季節です。
わたしも、横浜に住む甥を預かって、美味しいものを食べに行き、宿題を見てあげたりお買い物をしたり、と、楽しい時間を過ごすことができました。
子よ、すべての行いに注意し、すべての振る舞いに節度を守りなさい。
お前自身が嫌うことを他人にしてはならない。
(トビト4・14)
信仰を持たない家族に、自分の生き方を示して理解してもらうのは、そう難しいことではないと思っています。
わたしは、妹と、亡くなった母が信仰を持っていますが、姪・甥は洗礼を受けていません。
だからこそ、機会あるごとに、「人からしてほしいと思うことを、人にもしなさいね」と伝えるようにしています。
小さな頃から、機会があればごミサに連れて行き、一緒に祈って一緒に歌って、そうやって大きくなった姪と甥です。
カトリックの教義や信仰の意味については、おそらく全く理解していないでしょうが、わたしは彼らとミサの時間を共にすることが大切な喜びです。
聖母の被昇天の祝日のごミサに、甥を連れて行きました。
ジュゼッペ神父様のお説教は、今のわたしの心境を表してくださったような、とても大切な教えでした。
マリア様の被昇天については、聖書には全く書かれていません。
1950年に、教皇様が正式にカトリックの信仰として確立されました。
このことは、マリア様がわたしたちの父である神のお母様であることを、改めて「信じるべきこと」として宣言されたと理解するべきことです。
わたしたち信者は、胎内の子が喜んで踊ったように、いつも喜んでいなければなりません。
そして、周りの人も喜ばせなさい。
あなたが出会う人々に、あなたがもらっているお恵みを与えなさい。
そうすれば、イエス様があなたを通してあなたにも周囲の人にも、喜びを与えてくださいます。
わかりやすい、とても心に響くお話でした。
中2の少年にこのお話が響いたとは思いませんが、わたしが受けているお恵みを彼にもお裾分けしていることを、いつか気付いてくれたら、と思っています。
いつもこのことを基本として、わたしが家族の中ですべきことはなにか、を考えています。
こうして、聖書を開きながら書いている横で、甥はイヤイヤながら夏休みの宿題をしています。
この瞬間も、わたしにとっての思い出深いお恵みのひとときです。
すべての思慮深い人から助言を求めなさい。
そして、有益な助言を軽んじてはならない
いかなる時にも主である神をたたえ、お前の道をまっすぐにし、お前の歩みと計画とが栄えるように神に祈りなさい。
ただ主だけが、ご自分の欲する人にすべての善いものを与えてくださるからである。
(トビト4・18〜19)
受けているお恵みを家族にもお裾分けし、わたしの歩み(生き方)と計画(家族の幸せ)を神様が力強く導いてくださるように、と毎日毎日お祈りしています。
神様が、今もいつも、わたしたちの祈りを聞き入れ、導いてくださいますように。
自分の心で
今の期間は、カトリック教会の平和旬間(8/6~15)となっています。
平和の祭典でもあるオリンピックの期間中も、戦闘は止まず、ネット上では身勝手な正義感を振りかざす誹謗中傷がエスカレートしています。
根拠がなく真偽が定かではないのに言いふらされる、無責任なうわさのことを、「流言(りゅうげん)」と言います。
今回のオリンピックでは、ボクシングの女性選手2名は「性転換して女性になった男性」という流言が広まりました。
イングランド全土と北アイルランドの町や都市で現在も続く暴力事件は、7月末に起きたダンス教室で幼い子ども3人が殺された事件に端を発しました。
容疑者は小型ボートでイギリスに到着したイスラム教徒の亡命希望者だ、という間違った憶測と間違った名前がSNSで拡散されたことで、大きな移民排斥運動へと繋がったのです。
第17主日から第21主日まで、ヨハネ福音書6章のほぼ全部が読まれます。
「福音書のある一章を5回の主日に渡って読むことは、典礼暦年でこれ以外に例がありません。
ヨハネの6章が、いかに教会で重視されてきたかが分かります。」
と、来住 英俊 神父様がnoteに書いていらっしゃいました。
その後、イエスはガリラヤ湖、すなわち、ティベリアス湖の向こう岸へ行かれた。
大勢の群衆がついて行った。
イエスが病人たちに行われた徴を見たからである。
よくよく言っておく、あなた方がわたしを探し求めるのは、徴を見たからではなく、パンを食べて満腹したからである。
(ヨハネ6・1~2,26)
イエス様の時代にも、もちろん貧困はありました。
ですが、現代のほうが世界には大いなる貧困が存在し、富の格差は遥かに大きいのです。
パンと魚を食べて物質的に満足した群衆は、現代のわたしたちとも通ずるものがあるように思います。
今日食べるものに困っているわけではない人の方が、現状への不満や不安を大きく抱えているようにも思えるのが今の時代です。
イエス様を追い求めて付いて行った群衆は、イエス様の業の噂を聞き、実際に自分で確かめたかったのです。
少なくとも彼らは、自分の目で確信を得ようとしたのです。
貧困とローマの圧政から救ってくれると信じられていたメシアを、自分で。
流言などというものはなかったのでしょう。
インターネットがない時代は、可能であれば自分の目と耳で確認する、出向いて会って話す、これしかなかったのですから。
なぜ、ヨハネの6章がカトリック教会で重視されてきたのでしょうか。
改めて読み返してみて、今のわたしにはこの箇所が1番心に響きました。
弟子たちのうちの多くの者はこれを聞いて、「これはとんでもない話だ。誰が、こんな話を聞いていられよう」と言った。
イエスは、弟子たちがこのことについて不平を言っているのに気づいて、仰せになった、「わたしの話があなた方をつまずかせるのか。
それでは、人の子が元いた所に上って行くのを見るなら・・・・・
しかし、あなた方の中には信じない者もいる」。
このことがあって、弟子の多くはイエスに背を向けて去り、もはやイエスと行動をともにしなくなった。
(6・60〜66)
ここで書かれた「弟子」は、12使徒ではなく、イエス様の行われた徴を見てイエス様に付き従った群衆を意味しています。
わたしたちの多くは、この群衆と同じです。
自分の求めていたものとは違う
自分はこの人を間違っていると思う
自分のために何もしてくれない
目先の利益(ここでは満腹すること)が優先され、イエス様の伝えたかったメッセージを「とうてい受け入れられない」と拒絶する。
聖書とは素晴らしいことばかりを書いている書物ではない、とつくづく思います。
人の心の中をつぶさに表現し、「あぁ、わたしも同じだ」と身につまされるエピソードが散りばめられています。
それに気づくことができる信仰、それが、自分の心の中で行われる神様の業、徴なのです。
来年1月1日に記念される「第58回世界平和の日」のために教皇フランシスコが選んだテーマは、
「わたしたちの罪をおゆるしください。わたしたちに平和をお与えください」。
平和旬間の今こそ、そう祈りたいと思います。
いつも、不安、不満を探し出してばかりいるわたしたちをお赦しください。
すべての人々の周りに平和をお与えください。
強く賢く
毎年、「今年の夏は暑さが厳しくなります」「10年に一度の大雨」といったニュースを耳にしますが、今年は記録の残る126年間で「1番暑い7月」だったとか。
イスラエルのマサダ遺跡を歩いたときの気温を思い出す、猛暑を超えた酷暑の久留米です。
(マサダの山頂で、携帯の気温計は47℃だったのです!)
福音書には、イエス様のたとえ話に登場したり、男性使徒たちよりも重要な場面に遭遇する女性たちの姿が生き生きと描かれています。
イエス様は、女性の活躍の場は家に限定されるという考え方を覆すような教え、社会生活・信仰生活のなかにも女性の活躍の場があること、を示してくださいました。
女性がたとえ話の中で良いお手本として描かれ、イエス様の死に立ち会い、復活後に空になった墓を見つけたり。
イエス様の生きた時代は、女性は数に数えることすらされないような存在でしたのに、女性に対するイエス様の考え方だけでなく、福音史家の受けた教えがそれを物語っています。
(パンと魚の奇跡で、5000人が満腹したという数字は、男性だけの数でした。)
あなたがたは皆、真実によって、キリスト・イエスにあって神の子なのです。
キリストにあずかる洗礼(バプテスマ)を受けたあなたがたは皆、キリストを着たのです。
ユダヤ人もギリシア人もありません。奴隷も自由人もありません。男と女もありません。
あなたがたは皆、キリスト・イエスにあって一つだからです。
あなたがたがキリストのものであるなら、とりもなおさず、アブラハムの子孫であり、約束による相続人です。
(ガラテヤ3・26~29)
松田聖子さんのコンサートに行ってきました。
世界に遅ればせながら、女性でも目標のためにはどんな努力も惜しまない姿を日本でも見せつけた、初めての女性アイドルではないでしょうか。
一度狙いを定めると、目的を遂げるまでは決してあきらめない彼女の姿勢と行動力は、20世紀末の日本にあっては非難の対象でしかなかったように思います。
憧れの人と恋愛をし、アメリカデビューのためにすざましい努力をし、結婚、出産、離婚、恋愛、再婚、そして永遠のアイドルとしての存在。
もう25年も、ほぼ毎年コンサートに行っています!
62歳になった彼女は、わたしたちファンには今でも「聖子ちゃん」なのです。
彼女は、わたしたちにとってずっと、「尊敬の対象」です。
旧約聖書には、
ペルシャの王妃に選ばれたエステルが、ユダヤ人を救うために知恵と信念をもって行動する姿
ダビデに進言し、無益な争いをやめるよう思いとどまらせたアビゲイルの思慮深い行動
こうした、活躍する多くの女性たちの生き生きとした物語が多くあり、読んでいてワクワクさせられます。
彼女たちの物語は、信仰、指導、母性、勇気、知恵、そしてさまざまな人間の側面を示しています。
オンライン上の論文、『Woman of Faith in the Gospels』(「福音書に登場する信仰の女性たち」著者 ピーター・アムステルダム氏)には、このように書かれていました。
最初期の弟子全員がイエス復活の証人であり、十字架刑のあとにイエスが生きておられるのを見ましたが、最初の目撃者は女性たちでした。
墓が空であることを最初に発見したのが女性である、と福音書著者たちが告げているということは、福音書の記述が真実であることを示す、重要な根拠として挙げられることがよくあります。
1世紀においては、女性は一般に信頼できる証人とはみなされていなかったので、福音書の著者たちは、それが真実でない限り、最初の目撃者として女性に注目を向けたりはしないだろうからです。
・どうして使徒として描かれているのは男性12人に限定されているのだろう。
・そういう時代だったとしても、聖書に描かれている女性たちの方がずっと重要な役割を果たし、男性使徒たちよりもずっと強くて賢いように思うのに。
そう思っていましたが、この文章を読んで腑に落ちた気がしました。
誰が一番弟子かを争い、嘘をつき、一番大事な場面で逃げ、十字架につけられたイエス様の足元にすらおらず(いたのは一人だけ)、そうした弟子たちの不甲斐なさと比べ、女性たちの献身ぶりは際立っています。
同時に、その後の弟子たちを命がけの宣教に駆り立てたのは、自分たちの不出来さへの後悔と反動もあったでしょうし、女性たちの物心両面の支えがあってのことでしょう。
イエス様も福音史家たちも、男女の役割と能力、その影響をよく理解されていたのだわ、と思うのです。
パリオリンピックでは、 平均年齢が41.5歳で、自身らがつけたチームの異名「初老ジャパン」でも話題になった馬術が、92年ぶりのメダルとなる銅メダルを獲得しました。
「体力面では男性にかなわない女性であっても、馬との信頼関係を築き、馬に正しく指示することができれば、互角に勝負することができるのが馬術」ということで、五輪では唯一男女が同じステージで戦う種目でもあるのです。
わたしはフェミニストではありませんが、やはり、強く賢い女性が活躍する姿を見るのは嬉しいものです。
正しい行い
2022年末に、難病のスティッフパーソン症候群という神経疾患に侵されていることを告白し、現在も治療中のセリーヌ・ディオン
名前は知らなくても、彼女の歌声は誰もが聴いたことがあり、その伸びのある美しく力強い歌声には誰もが感動したことがあるはずです。
パリオリンピックの開会式で、観衆を前に久しぶりに歌声を披露してくれました。
彼女のドキュメンタリー映画が先月、Amazonでリリースされました。
自分を導いてくれる存在だった歌、声を奪われた心境を赤裸々に、涙ながらに語る彼女の姿は見ていてとてもつらくなりました。
ですが、彼女には「またステージで歌いたい」という強い強い希望があります。
https://www.vogue.co.jp/article/celine-dion-documentary-trailer-interview
このドキュメンタリーの中で、彼女が実際に発作を起こし、医療スタッフが治療をする場面があります。
全身の筋肉が硬直し、呼吸することすら辛そうでした。
幸い、彼女には24時間体制で付き添うチームがいますが、もし、目の前で人が倒れたりしたら、自分は何ができるだろうかと考えました。
佐賀・有田の救急救命士が、患者の家族(看護師)に処置を手伝わせたことで、地方公務員法違反の懲戒処分を受けた、というニュースがありました。
消防本部の見解は「偶然現場に居合わせた人が医療従事者だと告げてきたとしても、資格の証明が難しい。」。
宮﨑神父様がお説教で何度かお話ししてくださった、「善きサマリア人法(Good Samaritan Law)」について。
これは、アメリカ合衆国のすべての州で制定されている法律で、事故でケガをしたり、急病になった人を善意で助けた人に対し法的な保護を与えるもので、原則として、損害賠償責任を負わせないものとされています。
アメリカ以外にも、カナダ、オーストラリアなどでもこれに該当する法律が存在し、現在日本でも立法化すべきか否かという議論がなされているそうです。
昨年12月には、救護者保護に関わる合同検討委員会(日本賠償科学会 ・日本救急医学会 )が国に対して法整備を提言しています。
この提言書には、次の2つの理念の下に法整備をするよう書かれています。
(ア) 医療従事者は、日常的に社会において連帯する人々の突然の傷病や災難に対して、できる限りの診療にあたり、寄り添い、心の安寧の提供に努める。
(イ) 医療需給が不均衡な状況において、急病や災難による窮地の人々を救うために善意の行動をとった場合、できることを良識的かつ誠実に行った医療従事者に対して、行為の結果については責任を問わない。
欧米のようなキリスト教社会では、善きサマリア人のエピソードは説明するまでもないのでしょうが、日本ではほとんどの人が知らないかもしれません。
この提言では、医療従事者のみが想定されています。
だとしても、だれでも善きサマリア人のように行動することが求められいる、と思うのです。
そして同時に、倒れていた重症の人を遠巻きに避けて通った祭司とレビ人は、単に、無関心な非情な人だったのではないということも理解しておくべきでしょう。
(彼らは、律法に従って、血を流して倒れている人が死んでいるかもしれないため、触れると穢れて、自分の生活に支障が出ることを恐れたのです。)
助けなかった人を責めるものではなく、自ら進んで助けを必要としている人(それが敵対する相手だったとしても)に寄り添い、できることがあれば実行しなさい、という教えだと理解しています。
名乗り出て手を貸さなかった医療従事者を非難するのではなく、実践した人を守るための法律です。
冒頭に紹介した、セリーヌ・ディオン
彼女のドキュメンタリーを見た後でしたので、開会式の最後に『愛の讃歌』を高らかに力強く歌い上げる姿には、本当に驚かされ、力付けられました。
彼女の不屈の精神力は、オリンピアンと変わらぬものに感じられます。
https://news.yahoo.co.jp/articles/3891293d207727be35c5b9e80dba6ab41978f998
https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1275648?utm_source=yahoonews&utm_medium=related&utm_campaign=link&utm_content=related#goog_rewarded
・・・・・・・・・・・
気持ちがほっこりする記事を見つけました。
オランダで2000ユーロ(約34万円)入った財布を拾って警察に届けた30代の路上生活者のハジャーさん。
財布を拾って警察に届けたことがニュースとなった後、彼の生活を支援するためにオンラインファンディングを通じて一日で3万4000ユーロが集まったのです。
警察は「財布に身分証や連絡先がなく、持ち主にいかなる連絡も取れなかった」として、「特別なことをした地域住民に授与している『シルバー親指賞』と50ユーロ相当の商品券を彼に手渡しました。
さらに、誰も名乗り出なかった場合はお財布の2000ユーロもハジャーさんのものになるそう。
正当な理由
大相撲、楽しんでいます。
東十両7枚目の友風、という力士は、今場所から下の名前を友太(ゆうた)から想大(そうだい)に変えました。
右膝の大けがで4度の手術、5か月に及ぶ入院生活を経ても土俵に上がり続ける姿に、師匠が言った言葉が紹介されていました。
「お前は人とは違って壮大なことをやり続けている。それはすごいことなんだ。
しかも人の“想い”があって土俵に戻ってくることができた。
『想大』という名前にしたらどうだ」
力士として戦う姿の裏に、怪我とその後遺症による障害との闘いもあったのか、と思うと、より一層応援に力が入ります。

福音宣教の8・9月号のテーマは、『戦争をいかに防ぐか』です。
その中でも、神言会のハンス ユーゲン・マルクス神父様(前・南山大学学長)の「正しい戦争はあるか」というコラムが大変興味深く、そして、とても考えさせられるものでした。
神義論には興味がありますが、正戦論というテーマは初めて知ったことでしたので、驚きと共に読み進めました。
正戦論とは、戦争一般が正しいかどうかではなく、正しいと認められるため、戦争の開始と遂行はどのような条件が満たされるべきか、という考え方だそうです。
「災いだ、アッシリア、わたしの怒りの杖。
彼らの手にあるその棒は、わたしの憤り。
わたしは、神を無視する国に向かって彼を遣わし、
わたしの憤りの民から分捕り品を取り、略奪品を奪い、
彼らを巷の泥のように踏みにじるよう、命じる。
しかし、彼はそのように考えず、その心はそのように思わない。
まことに、彼の心にあるのは滅ぼすこと、多くの諸国を滅ぼし尽くすこと」。
(イザヤ10・5~7)フランシスコ会訳
この箇所では、神を敬わない国に罰を与えようとする神の意志が書かれています。
ところが、神が遣わしたアッシリアは、それ以上のこと、破壊して滅ぼし尽くすことしか考えていませんでした。
ニュースで見る、ウクライナとガザの映像、破壊され、根絶やしに滅ぼそうとされているかのような惨状と重なって見えます。
カトリック教会としては、第2バチカン公会議において、「平和的解決のあらゆる手段を講じたうえであれば、政府に対して正当防衛権を拒否することはできない」、とされているようです。
(難しい言い回しですが、ようは、正戦はありうる、ということでしょう。)
教皇様は今年の3月に、ウクライナの形勢が圧倒的に不利だとして「和解交渉のためにウクライナが白旗を揚げるなら、それこそ勇気のある決断だろう」と発言され、欧米の世論が猛烈な批判をしたことは記憶に新しいところです。
主がシオンの山とエルサレムですべての業を終えるとき、アッシリアの王の尊大な心が結んだ実と、その目に輝く高慢を、主は罰せられる。
なぜなら、彼はこう言っているからだ。
「私は自らの手の力で行った。
自らの知恵で賢く振る舞った。
私はもろもろの民の境を取り去り、その蓄えを奪い、力ある者のようにその住民をおとしめた。」
(イザヤ10・12~13)聖書協会共同訳
福音宣教のなかでマルクス神父様は、教皇様の発言の真意をこう書いておられます。
戦闘員と非戦闘員との区別がますます不明瞭になっていく中、自己防衛のために戦われる戦争もついに正当性を失う危険をはらんでいる、という警告も教皇は意図されていたかもしれない。
教皇が踏まえておられるカトリックの正戦論の趣旨は、第一義的には、戦争を正当化することではなく、避けがたい戦争による害を最小限度に減らす、ということである。
正戦論についていろいろ調べていると、2020年(日本語版は2021年)に発行された教皇様の回勅、「兄弟の皆さん」のなかに、そのことに関しての記述がありました。
久しぶりに読み返してみて、教皇様は2024年の現在も、恐らく全く同じように考えて上記のウクライナに関する発言をされたのだ、と確信が持てました。
問題であるのは、核兵器、化学兵器、生物兵器の開発と、新技術からもたらされる膨大で増大する手段によって、制御不能な破壊的軍事力が戦争に付与され、多くの罪のない民間人が被害にあっているということです。
ですからわたしたちはもはや、戦争を解決策と考えることはできないのです。
戦争によって手にされるであろう成果よりも、つねにリスクの方が大きいはずだからです。
この現実を見れば、「正戦」の可能性についてかたるべく、過去数世紀の間に合理的に練られた基準を、今日支持することはきわめて困難です。
二度と戦争をしてはなりません。
(第7章258)
わたしたちのように、戦争から遠く離れたところで平和に暮らしていると、どうしても現実的に深く考えることが難しい。。。
回勅の一番最初に、教皇様はこう書かれています。
「離れていても、一緒にいるときと同じように兄弟を愛する人は、幸せである。
身体的な近しさを超え、生まれや住む世界と言った場所を超え、一人ひとりを認め、尊重し、愛することを可能にする兄弟愛です。」
戦うのは自分自身の弱さとだけにし、周囲の人、特に子どもたちに対して優しい気持ちで接することに励みたいものです。
キリストは来られ、遠くの者であったあなた方に平和を、近くの者にも平和を、福音として告げ知らせました。
(エフェソ2・17)
神の方を向く
東京都民ではないのに、今回の都知事選挙はとても気になってニュースを追いかけていました。
バイデン大統領の進退も気になるこの頃です。
今年は、世界中で政治の流れが大きく変わっています。
というのも、EUの多くの地域で、極右とナショナリスト右派が躍進しているからです。
背景にあるのは、(2022年度は700万人がEU内に流入したという)移民問題、インフレ、環境重視の改革のコスト(環境保護を重要視する結果、電気代などが高騰)、などに人々が懸念を募らせているからだと言われています。
反移民、反環境規制、反EUといった主張を掲げる極右の躍進は、昨年11月のオランダの選挙で顕著に表れました。
ドイツ、ハンガリーでも極右政権が誕生しています。
先週のフランスの解散総選挙でも、結果及ばなかったものの、同様に極右政党が大躍進しました。
イスラエルは伸びほうだいのぶどうの木。
実もそれに等しい。
実を結ぶにつれて、祭壇を増し国が豊かになるにつれて、聖なる柱を飾り立てた。
(ホセア10・1)新共同訳
イスラエルは実を結ぶ茂ったぶどうの木。
その実が多くなればなるほど、彼は祭壇を増やした。
(同)フランシスコ会訳
イスラエルは多くの実を結ぶ、伸び放題のぶどうの木。
たわわに実るにつれ、祭壇を増やし
国が豊かになるにつれ、石柱を飾り立てた。
(同)聖書協会訳
この訳は、断然、聖書協会共同訳が勝っていますね!
わたしの素人考えではありますが、ヨーロッパをよりよい社会にするためにEUを結成し、移民を積極的に受け入れる政策を打ち出したのではなかったでしょうか。
環境を破壊し続けてきたのはわたしたちであり、そのツケを後回しにしないための政策は必要不可欠ではないでしょうか。
ユーロ安・円安、そしてインフレも、お金をゲームのように動かし、莫大な資金を出し合って戦争しているのは、わたしたち人間なのです。
クリスチャン・ナショナリズムというイデオロギーがあります。
彼らは、アメリカがキリスト教国家として建国されたと主張し、その政府と社会はキリスト教の価値観を反映すべきだと主張しています。
想像がつくと思いますが、ドナルド・トランプ前大統領を支持する人々です。
これまで人種差別的とみなされてきた欧米の極右は、近年は熱心にユダヤ人差別反対を叫んでいるようです。
それは、反ヘイトに舵を切った、というより、異人種・異教徒との共存を否定する考え方からのようです。
極右にとってイスラエルは、「イスラム勢力と戦う同盟者」であり、ユダヤ人差別反対はそのためのアピールだと言われています。
「南アフリカのアパルトヘイトが公式に消滅した現在、白人と有色人種・異教徒を、軍事力をもってしてでも分離する体制はパレスチナ占領地にしかない」と書いてある記事がありました。
人種、宗教の違いを根幹にしたヘイトクライムは、世界のいたるところで酷くなる一方ですし、政治もその方向を向いている(極右が主流になりつつある)という現実は、とても恐ろしいことのように思えます。
ホセアは、神と民の関係を夫婦の関係にたとえて巧みに表した預言者です。
不貞を働いた妻が、罰を受けた後に回心し神の愛を思い起こさせられる、という構成で編集されたのがホセア書です。
彼が活動したのは、BC750~725年ごろだと考えられています。
わたしは彼らの背信を癒やし、喜んで彼らを愛するであろう。
わたしの怒りは彼らから離れ去った。
わたしはイスラエルに対して露のようになる。
彼はゆりのように花咲き、
ポプラのように根を張る。
その若枝は栄え、オリーブの木のように麗しくなり、
レバノン杉のようにかぐわしくなる。
その名声はレバノンのぶどう酒のようになる。
わたしは緑の糸杉のようである。
お前を実らせるのはわたしである。
知恵ある者はこの言葉を悟り、賢き者はこれを知れ。
主の道はまっすぐで、正しい者はこれを歩む。
しかし、罪人はこれにつまずく。
(14・2~10)
青くした文字は、すべて神の愛の象徴である、と教わりました。
「お前を実らせるのはわたしである」
一口にキリスト教、と言っても、聖書の解釈も神に向かう姿勢も本当にさまざまであることを、世界情勢をみていると痛感させられます。
身勝手な大人の争いに巻き込まれて犠牲になる子どもたちのために祈ります。
子どもたちの巻き添えが、これ以上増えませんように。
身体と心に傷を負ってしまった子どもたちが、少しでも笑顔になれる時間が持てますように。
子どもたちが、神様の方を向いて、前を向いて生きていくことができますように。
・・・・・・・・・・・・・・
エルサレムにある、ユダヤ人とアラブ人の子どもたちが共に学ぶ学校についての、NHKの特集記事です。
周りが何と言おうとも、欧米の政治がどのような政策を行おうと、結局は当事者のこうした意識と行動が最高の成果を産むのだ、と思わされました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240708/k10014502391000.html
我が家の近くの、わたしが大好きな風景です。
筑後川と耳納連山と大きな空。
分かち合い
6/23にアベイヤ司教様をお迎えして、筑後地区の信徒を対象とした研修会が行われました。
研修会、というと一方的に「講話」のようなものを聞くだけ、の場合が多いかと思いますが、今回は司教様が二つのテーマで「さぁ、みなさんで今から分かち合ってください」という場面をくださいました。
教会では、「分かち合い」ということをよくします。
一般的には、「嬉しかったこと、喜ばしいことを分かち合う」こと(お祝いの会や贈り物)はしても、面と向かって人に「さぁ、分かち合いましょう」とは言う機会はあまりないのではないでしょうか。
(多分、ちょっと怪訝な顔をされます。。。)
東京大司教区のホームページに「分かち合いとは」というページがあり、そこにはこう書いてありました。
『分かち合いとは』
知識や考察、正しいとか間違っているという判断ではなく、今ありのままの自分が感じている、心の動き(喜び、悲しみ、怒り、恐れなど)や、気づきを分かち合うこと
互いに、ひたすら心をこめて聴き合うこと
肯定も否定もせず、解決も試みず、教えたり、指図したり、勧めたりもせず、ただ傾聴すること
『分かち合いの実り』
・「今、ここで」自分が感じていることを表現できると、自分のより深いレベルに気づく。
・話す方も聴く方も、お互いを鏡として、自分の価値観、何を大切にしているかが明確になる。
・相手の話を心をこめて聴くと、相手の心の動きに敏感になり、共感できる人になる。
・人との交わりの中で、互いに生かされていることがわかる。
アベイヤ司教様は、研修会の中でこうおっしゃいました。
シノドスのテーマであった「ともに歩む教会」を造り上げていくためには、信徒、修道者、司祭、司教が共に話し合い、それぞれの体験を分かち合うことは欠かせません。
実生活の体験を分かち合うことが大事です。
分かち合うことで、様々な気づきが生まれると同時に、お互いを知る事にもつながるからです。
しかし、残念なことに、小教区において「分かち合い」を避ける傾向や、人との付き合いが希薄になっている現状が広がっているようにも見受けられます。
久留米教会では、ピースナインの会やヨセフ会、女性の会といったいくつかのグループが活動していて、それぞれのグループでは毎月さまざまな分かち合いが行われています。
しかしながら、積極的に信徒が分かち合っているか、というと、コロナ前のようには活発ではないでしょう。
10年前(!そんなに前!)から8年間、聖書百週間で学んでいた時のグループでは、毎週聖書を分かち合っていました。
自分の感じたこと、疑問、好きな理由など、自由に全員で分かち合っていて、とても充実した日々でした。
そしていま、わたしはここにこうして書くことで「一人分かち合い」をしています。
書いたことについて、「わたしはこう思いました」といった「分かち合い返し」をいただくことがあり、それがとても嬉しいのです。
やはり、分かち合いは一方通行ではつまらないものです。
今ありのままの自分が感じている、心の動き(喜び、悲しみ、怒り、恐れなど)や、気づきを分かち合うこと。
イエス様の時代、ユダヤ人の多く住む地区にはたいていシナゴーク(会堂)がありました。
信心深いユダヤ教徒たちが集まり、祈り、聖書朗読、律法と預言書に関する教育が施されていました。
多くは文字が読めなかったため、シナゴークでの教えを忠実に守る人々にとっての礼拝は、大切な信仰の分かち合いの場でした。
初期の教会では、イエス様の教えの分かち合いがかなり活発に、というか、まだ新約聖書は存在していなかったのですから、信じる者たちが分かち合いをすることで信仰を保ち、伝えていたはずです。
こうして分かち合われた信仰が、脈々と受け継がれてきたのです。
イエス様が生まれ故郷のナザレのシナゴークで教えられた時、その教えは受け入れられませんでした。
マルコの5章の終わりまで、イエス様はガリラヤの至る所で神の国を宣べ伝え、癒し、悪霊を追い払い、亡くなった子どもを生き返らせ、勝利の行進のような様相で、満を持して故郷に戻られました。
ナザレは300人ほどしか住んでいない小さな村でしたので、奇跡を行いながら宣教していることも噂には聞いていたものの、小さい頃から知っている若造が偉そうに教えるのが許せない、気に入らなかったのもあったでしょう。
(わたしたちの日常にも、そうした気持ちが湧く場面があることは否定できないものです。)
宣教という分かち合いは、相手が心を開いていなければ受け入れられません。
信仰は、イエス様が心の中に入っていくための扉です。
しかも、その扉は内側からしか開くことはできません。
アベイヤ司教様が研修会でおっしゃいました。
「いろいろな理由で教会から離れてしまった人、それは、家庭の事情かもしれません、人間関係、信仰への疑問からかもしれません、そうした人々を裁いてはいけません。
その人たちとのつながりを考え直すことを話し合って欲しいと思います。」
教会から離れてしまった人を呼び戻せなければ、新しい人の心の扉を開くなどできないのかもしれません。
一人の信徒が、一人の離れてしまった人のことを心に留める。
できることをきちんと取り組みたい、と気持ちを新たにできた研修会でした。
歴史を理解する
本を読むのが好きな一番の理由は、「知る」ことができること。
最近のニュースサイトは、AIによってランダムに「好み」そうな記事が表示される仕組みになっていますし、そもそも内容の信憑性が疑わしいものが多い気がして、、、。
また面白い本を読みました。
アメリカの歴史はコロンブスがアメリカ大陸を「発見」した1492年から書き始められます。
(そう、学生時代には教わったのです。)
ですがこれは、あくまでもヨーロッパ的な見方であり、アメリカ大陸にはもともと先住民が暮らし、彼らはヨーロッパからやってきた彼らに、土地も彼ら自身をも「略奪」されたにすぎません。
コロンブスが「発見」したカリブ海の島々も、当時の教皇アレクサンデル6世の「認可」を得て、スペインとポルトガルで分け合っています。
その後もスペインは、南アメリカ大陸の地域をも征服し、現在のボリビアのポトシ銀山に眠っていた膨大な埋蔵量の銀山は、スペインの戦費を賄う重要な財源となったのです。
アメリカでは10月第2月曜日はコロンブス最初の航海を記念する『コロンブスデー』の祝日でしたが、近年はさまざまな都市がこの祝日を『先住民の日』に置き換えて、各地でコロンブスの像が取り除かれているようです。
同じ1492年、7世紀にわたってイスラム勢力の支配下にあったスペイン半島のグラナダが、レコンキスタ(失地回復)によってキリスト教徒の下に「取り戻され」ました。
当時、スペイン半島を支配していた連合王国は、統一するためにカトリックの信仰を利用しました。
ローマ教皇からの信認を得て、永年の戦いの末にイスラム勢力を「排除」し、それまでその地で共存していたユダヤ人にカトリックへの「改宗」を迫り、応じなかった10万人を「追放」することで、スペイン半島の統一を成し遂げたのです。
一方で、コロンブスの航海に同行したドミニコ会の修道士、ラス・カサスは、インディオを過酷に扱うコロンブスの一行を激しく非難し、自分たちと同じ人間である彼らの尊厳を守るようにと、教皇パウルス3世に訴えます。
アメリカのキリスト教の歴史も、わたしたちが学校で習ったような「メイフラワー号でアメリカ大陸に渡ったピューリタン」から始まるのではなく、敬虔なカトリック信者であったコロンブスと、その対応にあたったローマ教皇にその始まりがありました。
この本を読んで、歴史とは一方的な記述によって(征服者側=ヨーロッパの主観で)伝えられているのだ、と改めて強く感じました。
その意味でも、やはり新約聖書は、あらゆる方向からイエス様と弟子たちの様子を書き残していることがよく分かります。
怒ったり泣いたりするイエス様、疑って争って、イエス様の最期の時まで嘘をついたり逃げたりする弟子たちの姿、人の弱さと強さの両面を包み隠さず表現している聖書。
AIがわたし好みで表示してくれたニュースに、このようなものがありました。
米南部オクラホマ州のウォルターズ教育長は6/27、公立学校の授業で聖書を取り上げることを義務化すると通達した。
南部ルイジアナ州では教室に旧約聖書の十戒の掲示を義務付ける州法が成立しており、公立学校に宗教を持ち込む動きが広がっている。
通達は「聖書は必須の歴史的、文化的な規範だ」とし、授業で教えることで「生徒たちは米国にとって大事な価値観や歴史を理解できる」と主張
アメリカにとって大事な価値観や歴史を理解する、という、これまた一方的な考え方がいかにもアメリカらしいです、、、。
何事においてもそうだと思うのですが、背景を理解しておくことはとても大切です。
一側面からの見方で物事を判断してしまうのは、特に歴史に関してはとても危険です。
イスラエルとパレスチナのことについても本を読みました。
本に書いてあることが全て正しいわけではないでしょうが、それでも、歴史的な背景、これまでの長い経過を知ったうえでニュースを見聞きすると、物事の見方が変わります。
起きていることの背景をもっときちんと理解したい、とますます思うようになりました。
・・・・・・・・・・
わたしたちの信仰の大切な歴史のひとつである、今村教会
先日、どうなっているだろう、と気になって見に行ってきました。
耐震工事は遅々として進んでいないように見受けられます。
今村の信徒の方にお尋ねしたら、「工事が完了するまで10年はかかるそうです。聖堂の周囲の小屋などを取り壊すことから始めるようですが、まだそれも始まっていません。」とおっしゃっていました。
いつ起こるかわからない災害、特に大きな地震が来たら全て崩壊してしまいそうな様子です。
この美しい聖堂を久しぶりに見て、次の世代にも残したいと改めて思いました。
↓ 2019年7月7日、筑後地区の研修会で前田枢機卿をお呼びした時の写真です。
聖書の読み比べ
。
先日のミサのの朗読で、「あぁ、ここは素敵。帰って聖書を開いて前後を読んでみよう」と思う個所がありました。
家に帰って聖書を開くと、あまりにも訳が違うことに気づきました。
それで、わたしたちはいつも心強いのですが、体を住みかとしているかぎり、主から離れていることも知っています。
目に見えるものによらず、信仰によって歩んでいるからです。
わたしたちは、心強い。
そして、体を離れて、主のもとに住むことをむしろ望んでいます。
(2コリント5・6〜8 新共同訳)
そこで、わたしたちはいつも安心しているのですが、この体に住みついている間は、主のもとを離れているのだと知っています。
見えるものによってではなく、信仰によってわたしたちは生活しているからです・・・・。
わたしたちは安心しているのですが、体の住まいを離れて主のもとに住みつくほうがいいと思っています。
(フランシスコ会訳)
それで、私たちはいつも安心しています。
もっとも、この体を住みかとしている間は、主から離れた身であることも知っています。
というのは、私たちは、直接見える姿によらず、信仰によって歩んでいるからです。
それで、私たちは安心していますが、願わくは、この体という住みかから離れて、主のもとに住みたいと思っています。
(聖書協会共同訳)
読み比べてみて、いかがですか?
わたしは普段、フランシスコ会訳聖書を読んでいるのですが、この部分は断然、新共同訳の言い回しが好きです。
3つ目の聖書の文章はどうですか?
読みやすく、文章が綺麗だと思いませんか?
新共同訳の「わたしたちは、心強い」という部分は、英語聖書では「We are courageous.」です。
聖書と典礼で使用されているのは、新共同訳聖書です。
18年の歳月をかけて1987年に生まれた、現代日本の代表的翻訳です。
カトリック教会とプロテスタント教会の聖書学者の英知を結集した国内初の共同訳。
中央協議会の教皇メッセージ日本語訳は、新共同訳聖書を引用しています。
わたしが普段読んでいるのは、フランシスコ会訳聖書です。
これは、カトリックの聖書です。
(カトリックの学校時代から、この訳に親しんでいます。)
そして、1番新しい訳の聖書が、 聖書協会共同訳聖書。
次世代の標準となる日本語訳聖書を目指して2010年に翻訳を開始し、2018年12月に初版が発行されました。
カトリックとプロテスタント諸教会の支援と協力による共同の翻訳事業です。
国内の聖書学者および歌人などの日本語の専門家によって翻訳されました。
翻訳にあたり「礼拝での朗読にふさわしい」文章にすることを目的にして訳され、格調高く美しい日本語訳になっています。
翻訳の微妙なニュアンスの違いによって、頭と心にどのように入ってくるか、その違いをいつも感じています。
時には、「あ〜、やっぱり慣れ親しんだフランシスコ会訳がいい」と思うこともあれば、今回のように、「新共同訳の方がストレートに伝わるな」と思ったり。
それでも疑問に感じる時は、英語の聖書を開いて自分なりに納得したり、しながら読んでいます。
今回、聖書協会共同訳の聖書を手に入れたので、ますます読むのが楽しくなりました。
例えば、ガラテヤ6・9〜10の新共同訳
たゆまず善を行いましょう。
飽きずに励んでいれば、時が来て、実を刈り取ることになります。
ですから、今、時のある間に、すべての人に対して、善を行いましょう。
これに対して、フランシスコ会訳は次のとおり。
倦まず弛まず善を行いましょう。
飽きずに励めば、時が来たとき、わたしたちは刈り取ることになります。
ですから、機会のあるごとに、すべての人に、善を行いましょう。
さらに、聖書協会共同訳ではこうなります。
たゆまず善を行いましょう。
倦むことなく励んでいれば、時が来て、刈り取ることになります。
それゆえ、機会のある度に、すべての人に対して、特に信仰によって家族になった人々に対して、善を行いましょう。
「 たゆまず」ではなく、フランシスコ会訳の「倦まず弛まず」という言い方は、ひらがなで表記することの多い聖書の訳の中でも一際強調されたことを感じる表現です。
パウロが伝えたかったのは、「ずっと善を行いましょう」ではなく、「たるまずに(倦まず弛まず)、しっかりとして」善を行うように、なのだろう、とよく理解できます。
サンパウロ修道会の神父様の面白いコラムを見つけました。
パウロの勧めは、単に「時のある間に」とか、「機会が訪れれば」とかいう意味ではなく、まさに今がその「機会」、「特別な時」なのだから、という意味です。
わたしたちは、善を行うための「特別な時」、「重要な時」を実感し、行動に移すよう招かれているのです。
訳文の違いから聖書を味わい直す | 聖パウロ修道会 サンパウロ 公式サイト
第4回 機会のあるごとに、すべての人に、善を行いましょう――訳文の違いから聖書を味わい直す
https://www.sanpaolo.jp/14296
読み比べる読み方、これもまたお勧めです。
・・・・・・・・・・
聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたもので、人を教え、戒め、矯正し、義に基づいて訓練するために有益です。
こうして、神に仕える人は、どのような善い行いをもできるように、十分に整えられるのです。
(2テモテ3・16〜17 聖書協会共同訳)

つたわる言葉
中世ヨーロッパはラテン語が唯一の公用普遍語であったため、キリスト教ではラテン語を使ってその教えを広めていった、ということを以前書きました。
地方の話し言葉としてのラテン語は、ローマ帝国崩壊後は各地でそれぞれ独自の変容を遂げていき、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ルーマニア語などの言語が生み出されることになりました。
これらの地方に伝播されたラテン語(Vulgar Lain、俗ラテン語)と、その各地方の現地語とが時とともに融合し、各地で別々に発達し、ついに相互に通じなくなったのです。
「相互に通じなくなった」と聞くと、バベルの塔と聖霊降臨について思い浮かびます。
五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然、激しい風が吹いて来るような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。
そして、炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。
すると、一同は聖霊に満たされ、“霊”が語らせるままに、ほかの国々の言葉で話しだした。
さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰って来た、信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まって来た。
そして、だれもかれも、自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけにとられてしまった。
(使徒言行録2・1~3)
聖書は、冒頭からこのことを警告しています。
バベルの塔の話について考えましょう(創世記11・1―9参照)。
この話は、人間、被造物、そして創造主とのきずなをないがしろにしながら、天(=わたしたちの行き先)にたどり着こうとする時に起こることを描いています。
つまり、他者のことを考えずに、ひたすら上へ登ろうとするたびに、このようなことが起こるのです。
自分のことだけなのです。
わたしたちはタワーや超高層ビルを建てていますが、共同体を衰えさせています。
さまざまな組織や言語を統一化していますが、文化的な豊かさを抑えつけています。
地球のあるじになろうとしていますが、生物の多様性と生態系の均衡をむしばんでいます。
聖霊降臨はバベルの塔とはまったく逆です。
聖霊が風と炎となって天から降り、高間に閉じこもっていた共同体に、神の力を与え、すべての人に主イエスのことを伝えるためにそこから出るよう駆り立てたのです。
聖霊は、多様なものを一致させ、調和をもたらします。
バベルの話にあるのは調和ではなく、勝ち取るための前進だけです。
そこでは人は単なる道具、「労働力」にすぎません。
しかし、聖霊降臨においては、わたしたち一人ひとりが一つの道具、共同体の建設に全身全霊で参加する一つの共同体という道具なのです。
教皇フランシスコ、2020年9月2日一般謁見演説より抜粋
https://www.cbcj.catholic.jp/2020/09/02/21390/
言語だけでなく、互いになにもかもが通じなくなったかのような世界情勢です。
物理学者のアインシュタインと精神分析家のフロイトの往復書簡、『ひとはなぜ戦争をするのか』というものがあります。
ナチスが政権奪取する前年の1932年に、アインシュタインは「人間を戦争というくびきから解き放つことはできるのか?」というテーマでフロイトと書簡を交わしました。
それにたいしてフロイトは、「人間から攻撃的な性質を取り除くなど、できそうにもない!」と明言しました。
さらに、戦争とは別のはけ口を見つけてやればよいと言い、最期にはこう書いています。
「文化の発展を促せば、戦争の終焉ヘ向けて歩み出すことができる!」
二人ともユダヤ人で、亡命したためホロコーストの犠牲にはならずにすんだのですが、現在の世界に彼らが生きていたら、どんな発言が聞かれたでしょうか。
戦争に対する互いの主張が全く嚙み合わず、果たして何が正しく、何が正義だというのかすら分からない(理解できない)、現在の世界です。
そもそも、正しい戦争などというものはないでしょうが、、、。
争っている国同士は、言葉が通じない、のではなく、心をふさいでいるのだと思うのです。
種を蒔く人は、神の言葉を蒔くのである。
道端のものとは、こういう人たちである。
そこに御言葉が蒔かれ、それを聞いても、すぐにサタンが来て、彼らに蒔かれた御言葉を奪い去る。
石だらけの所に蒔かれるものとは、こういう人たちである。
御言葉を聞くとすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないので、しばらくは続いても、後で御言葉のために艱難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまう。
また、ほかの人たちは茨の中に蒔かれるものである。
この人たちは御言葉を聞くが、この世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望が心に入り込み、御言葉を覆いふさいで実らない。
(マルコ4・14~19)
今週もマルコが読まれています。
宮﨑神父様はいつも、「朗読される箇所の前後を読みなさい」とおっしゃいます。
聖書、特に福音書は、キリスト者でなくても、誰が読んでもその真意がつたわる言葉だと思っています。
自分の根とは何でしょうか。
揺るぎのない信仰への信頼、とでも言いますか、わたしたちキリスト者が持つべき理想ではないでしょうか。
お説教で、宮﨑神父さまはこうおっしゃいました。
「神からの恵みを、どう自らが成長させるかが大事です。
育てるのは神様ですが、手入れするのは自分です。
神様のお恵みに感謝し、努力する。つまり、不必要な雑草は時々自分で抜かなければなりません。」
メアリー・ヒーリーは、このくだりについての解説で、こう書いています。
「イエスの弟子たちが彼自身の苦しみの神秘を分かち合う上で体験する妨害や失敗は、その計画において予期せぬものではあっても、必要不可欠な部分なのです」
石だらけの人生で、深くはった根を持たず、茨の中に暮らすように心に隙間が多い自分である、と理解すること。
その上で、揺るぎのない信仰への信頼を渇望し、日々を新たに前進する。
神様に対して心をふさがず、「またやってしまった」と反省できることも、内的進歩のためには必要不可欠だと思います。
フロイトの言うように、心がささくれたようになった時には、美しい音楽を聴くのが一番の薬です。
普段クラシックを好んで聴かない方でも、これを聴けば喜びの気持ちが湧く、と保証します!
あなたとともに
バチカンの一般謁見での教皇様のお話しには、いつも心を打たれ、新しい気づきを与えてもらいます。
わたしたちがある人物について最初に知ること、それは名前である。
わたしたちはそれによってその人を呼び、認識し、記憶する。
聖三位一体の三番目のペルソナも名前を持っている。
それは聖霊である。
しかし、聖霊を指す「スピリトゥス」という呼び方はラテン語化されたものである。
最初に聖霊を啓示された人々が知った名前、預言者や、詩編作者、マリア、イエス、使徒たちが呼び祈った名前、それは風や息を意味する「ルーアハ」という名であった。
(6/5教皇フランシスコ水曜一般謁見でのお説教より)
主は皆さんとともに dominus vobiscum
またあなたとともに et cum spiritu tuo
昨年、ミサの式次第が変更になる前は、「また司祭とともに」と言っていました。
先日、友人から「本当は『あなたの霊とともに』と言うのが正しい訳なのよ」と教えてもらいました。
日本語で「主は皆さんとともに」と訳されている表現も、直訳では「主はあなたたちとともに」であり、それに対する会衆の応答が「またあなたとともに」なのだそうです。
主がイサクにかけた言葉「わたしがあなたとともにいる」(創26・3、24)
ボアズが自分の農夫たちへ「主があなたたちとともにおられるように」と言うと、彼らも「主があなたを祝福してくださいますように」と答える(ルツ記2・4)
大天使ガブリエルがマリア様へ「主はあなたとともにおられます」と告げる(ルカ1・28)
神がこのように人に語りかけられるいくつかの場面では、主ご自身か主の御使いが、「主があなたとともにいる」と確信を込めてその人物に語っています。
またあなたとともに et cum spiritu tuo
ラテン語が分からなくても、太字にしたところが英語のスピリットの語源であることには気付きます。
古典ギリシャ語 πνευμα (プネウマ)、ψυχή(プシュケー)
ヘブライ語 רוח(ルーアハ)
ラテン語 spiritus(スピリトゥス)
英語 spirit(スピリット)
(式次第が変わるときに「またあなたの霊とともに」とはならなかったのは、日本語の「霊」は人それぞれに様々な意味に受け取られるため、他の国々や他教派の式文を参考にして「霊」という言葉は使わないこととされたためです。
ちなみに、英語の式次第ではThe Lord be with you--And with your spirit となっています。)
東京教区の田中 昇神父様のnote(ブログのようなもので、色々なジャンルで書かれたコラム)に、「典礼における挨拶」というタイトルの文章が掲載されていました。
その中で、田中神父様はこうおっしゃっています。
「あなたの霊とともに」という表現は、聖書ヘブライ語においては「あなた自身」という意味に解釈することができます。
「あなたにも、神様がともにおられますように」という意味合い以上の何かが含まれています。
「あなたの霊とともに」ということによって、信仰者は、聖なる典礼の間、司祭叙階の際に与えられた聖なる力によって、「主があなたとともにおられる」と宣言するところの司祭を通して聖霊が特別な働きをしていることを認めているのです。
真の意味での司祭とは、ただ一人、キリストご自身のみです。
単なる「あなた」ではなくあなたをキリストの祭司とされた「あなたの霊」とともになのです。
田中神父様は、ここでも何度かご紹介している本、カトリック聖書注解「マルコによる福音書」メアリー・ヒーリー著の翻訳をされた方です。
その本のあとがきの中で、田中神父様はこう書かれています。
「マルコによる福音書」のオリジナルが、あえて復活したイエスとの出会いを書き残さなかったということ。
その理由として考えられるのは、福音書を始めて耳にした(恐らくローマの)教会の人々は、ガリラヤで復活したイエスにすでに出会っていて、あるいは復活したイエスに出会った人からその体験を伝えられていて、イエスの復活をあたりまえのように信じていたということです。
マルコは、今、わたしたちの生きている現実の中で、イエスはともにいて働かれているということを伝えているのです。
ですから、いつもマルコは福音が語られる時、イエスはそこでまさに語りかけているということ、そのイエスをいつも感じるように、いつもそんな風にイエスの前に自分たちが置かれているのだという感覚を伝えたいのではないかとわたしは思うのです。
「主は皆さんとともに」「またあなたとともに」
この1週間、この言葉について考えていて、「神様がともにいてくださる」というより、「風が吹くように、聖霊がいつもわたしたちのまわりに漂っている」、と理解するようになりました。
どこへ行ったら、あなたの霊から離れられようか。
どこへ行ったら、あなたの前から逃れられようか。
わたしが天に昇っても、あなたはそこにおられ、
陰府に横たわっても、あなたはそこにおられる。
わたしが曙の空に翼を駆っても、西の果ての海に住み着こうとも、
あなたの手はわたしを導き、
あなたの右手はわたしを離さない。
(詩編139・7〜10)
風は思いのままに吹く。
あなたはその音を聞くが、それがどこから来て、どこへ行くかを知らない。
霊から生まれた者もみな、それとおなじである。
(ヨハネ3・8)
「風」「霊」、つまりプネウマが、いつもわたしの頭のまわりに漂っている気がします。

言葉のなりたち
6/2のごミサでは、初聖体の子どもたちの晴れやかな笑顔がありました。
・・・・・・・
現代では誰も、話し言葉としては使っていないラテン語ですが、ヨーロッパの様々なは言語はラテン語から派生したものが多いだけでなく、わたしたちの今の生活の中にも、まだまだラテン語が存在しているのを感じます。
「謙遜」の徳は、様々な悪徳の中でも最も深刻な「高慢」の悪徳への偉大な対抗者である。
うぬぼれと高慢が、自分を実際以上のものに見せながら、人の心を膨らませているのに対し、謙遜はそれをあるべきサイズに戻してくれる。
わたしたちは素晴らしい被造物であるが、長所と短所によって限界づけられた存在である。
聖書はその始めから「塵(ちり)にすぎないお前は塵に返る」(参照 創世記3・19)と、わたしたちに思い出させている。
実際、ラテン語で「謙遜な」(humilis)という言葉は「土」(humus)から来ている。
それにも関わらず、人の心にはしばしば大変危険な万能という妄想がのし上がって来る。
(5/22教皇フランシスコ 一般謁見でのお言葉より)
実際に聖書がラテン語で書かれていたわけではないのに、こうして聖書の言葉を説明してくださるときには今でもヴァチカンの公用語であるラテン語の単語がでてきます。
なぜキリスト教ではラテン語が用いられていたのか、と調べてみましたら、ラテン語はもともとローマで話され、書かれていた言語であり、その後の中世ヨーロッパではラテン語が唯一の公用普遍語であったから、なのだそうです。
(とはいえ、映画「The Two Popes(二人のローマ教皇)」で、ベネディクト16世が生前退位をあえてラテン語で発表した際、その場にいた枢機卿たちのほとんどが何を言っているのか理解できなかった、というシーンが思い出されます。)
パパ様のインスタとXのアカウント名は、ラテン語の「フランシスコ」=Franciscusです。
ラテン語を勉強してみたい、と思い、数年前に一度本を買って読んでみました。
その時買ったのは、文法からラテン語を学ぶ、といったものでしたので、数ページで断念。
そして数年たった今、また興味が湧き、自分たちの生活にどのようにラテン語が潜んでいるかを知りたいと思い、ここのところ数冊のラテン語に関する本を読みました。
そのうちの一冊がこちらです。
ハン・ドンイル著「教養としてのラテン語の授業」
(最近の日本の本のタイトルの流行ですね。
本当のタイトルはなんだったのだろう、と思ってしまいます。)
これはもう本当にみなさんにぜひ読んでいただきたい、とても素晴らしい本なのです。
本の内容は、ラテン語を「学ぶ授業」ではありませんでした。
ローマ留学時代の悩める青年期のお話し、世界の若者たちに向けた人生論、といった講義内容にラテン語がちりばめらているのです。
(韓国の大学生への講義内容がベースですので、カトリックの信仰について触れられている箇所はあえて少なく、でもそれがかえって、内容をストレートに伝わるものにしていると思いました。)
いくつか、心に残った箇所をかいつまんでご紹介します。
①「時間」を意味するラテン語tempus(テンプス)
元の由来はサンスクリット語です。
(ラテン語の単語はサンスクリット語に起因しているものが多いのです。)
Time flies(光陰矢の如し)という英語の格言も、ラテン語の「テンプス・フュジット Tempus fugit」の翻訳にすぎません。
時間が矢のように過ぎていくことを表す格言ですが、もともとは「好機を逃すな」と言う意味で古代ローマの詩人 ウェルギリウスが使った表現です。
②beatitudo (ベアティトゥド)という、「幸せ」を意味するラテン語
beo (幸せにする、喜ばせる)とattitudo (態度、心の持ちよう)という言葉の合成語です。
つまり、beatitudoという言葉は、「態度や心の持ちように応じて幸せになれる」ということです。
自分の蒔いた種が、喜びや幸せとなって自分に返ってくることもあれば、苦しみや辛さとなって返ってくることもあります。
③「勉強する」と言うラテン語の動詞の原形は「ストゥデレ studere」
英語のstudyはこの言葉が語源です。
ラテン語のstudere の本来の意味は「専念する、努力する、没頭する」があり、心から望む何かに力を注ぐこと、それが「勉強する」という意味なのです。
自分に合った学び方を捜すことが勉強の第一歩です。
この過程を通じて、私たちは「自分」についても深く知ることとなります。
こうした訓練が、ひいては人間関係における自らの態度や話し方など、人生の多くのことを考えさせてくれます。
ルカ13章33節は、そんな人間の生き方を物語っています。
しかし、今日も明日も、またその次の日も、わたしは旅を続けなければならない。
この一節は、イエス様がファリサイ派の人々から、ヘロデが殺そうとしているから立ち去るように、とアドバイスを受けた時にお答えになる場面です。
ハン・ドンイルさんは、イエス様がおっしゃった『見よ、わたしは今日も明日も、悪霊を追い出し、病気を治す。そして、三日目にすべてを成し遂げる』。という旅の目的を、わたしたち一人ひとりの人生にも当てはめて考えることを教えてくれています。
こうして毎週記事を書いていても、昨日書いたことを翌日見直すと考え方が新たになっていたり、深まっていたり、日々生きていくうちに勉強になっていることを痛感しています。
*最近の、ラテン語にまつわるニュース*
イタリアメディアが5/28に報じたニュースで、「イタリア警察は、ラテン語の成績が悪かったとして16歳の娘をローマの高速道路に置き去りにした40歳の女を児童虐待容疑で逮捕・訴追した。」というものが。
イタリアでは現在も、大学進学のためのテスト(大学入試はない)の科目にラテン語があるそうです。
「スペイン・マドリードのプラド美術館で27日、イタリアの巨匠カラバッジョの新発見絵画が公開」というニュースがありました。
絵画は、イバラの冠をかぶった血まみれのキリストが描かれ、ラテン語で「Ecce Homo(この人を見よ)」と名づけられたそうです。
ラテン語は決して、「誰も話さず、使われなくなった言語」ではないのです。
名は体を表す
今週もお相撲の話しからです。
いま、わたしの一番のオシは、入門一年にして優勝した、元横綱稀勢の里の二所ノ関部屋の大の里
(相撲ファンでないと、早口言葉のような文字列ですね。)
大の里というしこ名は、大正から昭和初期に活躍し「相撲の神様」と呼ばれた元大関の大ノ里に由来しているそうです。
『名は体を表す』と言いますが、相撲力士のしこ名と取り組み方を併せて見ていると、その名のように成長していく様を感じるのはわたしだけでしょうか。
この言葉は、『名前にそのものの本当の姿が表れている』という意味を持つ慣用句です。
仏教用語の『名体不二(みょうたいふに)』(名前と体は一緒である、という意味)が由来であるとされています。
正教会やカトリック教会においては聖人を崇敬しており、わたしたちはそれぞれ洗礼名を持っています。
一方で、プロテスタント諸教派においては聖人崇敬を行わないため、特に洗礼名を付けないところが多いようです。
教皇フランシスコは、イエズス会出身であるのに『フランシスコ』という霊名を選びました。
アッシジの聖フランシスコを崇敬されて、というのはご存じかと思います。
成人洗礼であれば、わたしたちは自由に、じっくりと洗礼名を選ぶことができます。
幼児洗礼の場合は、ご両親などが「そのように育ってほしい」という想いを込めて選ばれるでしょう。
数名の成人洗礼の信徒の方に、その洗礼名の由来を伺いましたが、それぞれにエピソードがありました。
教会の広報誌に、受洗者、転入・転出などの方のお名前を洗礼名とともに掲載していますので、あらためて見返してみたら、そのエピソードをお伺いしてみたいと思うお名前がいろいろとありました。
先日ご帰天された、支援させていただいていた方は、ヨハネ(バプティスタ・ド・ラ・サール)という、( )付きの洗礼名でした。
彼がどうしてこの名前を選んだのか、お聞きできないままでした。
久留米教会で司牧実習をされていた古市神父様(現・東京練馬区 北町教会主任司祭)は、ヨハネ・マリア・ミカエルという、かなり贅沢な洗礼名です。
(神父様にお尋ねしたら、3つまでと言われたので、マリア様の両サイドに洗礼者ヨハネと大天使ミカエルを配置することにした、のだそうです。)
聖人を祝う記念日は、四旬節と待降節を除いてほとんど毎日あります。
聖人の祝祭日はその重要性に応じてランクがつけられており、重要性の順に「祭日」「祝日」「義務の記念日」「任意の記念日」とがあります。
5/22は聖リタの任意の記念日でした。
先日、妹がプレゼントしてくれたものです。
イエス様のご像のいばらの棘を額に受けたリタは、なんとなく、中年女性の雰囲気がリアルです。
若い頃の不幸な結婚生活を経て修道女となったリタ。
家庭内に問題のあるところでは彼女の忠告が喜ばれ、そのとおりにすると必ず幸福が帰ってきたと言われ、「望みのないときの助け手」とも言われています。
ウィキペディアには、「守護対象:絶望的状況、必死の状態、望みがない時、不可能な願いを抱く人、病気、怪我、母、結婚問題、不妊、虐待、子育て」とありました。
おそらく、しょっちゅうケガや病気をしているわたしのために、妹は聖リタを選んでくれたのでしょう。
なかなか重い任務を課せられた聖女です。
リタ、という洗礼名をお持ちの方がいらしたら、その方にもその名前を選んだ物語があるのでしょう。
わたしの洗礼名がインマヌエルになったのにも、物語があります。
『名は体を表す』
自分の日々を反省するとき、「インマヌエルの名に恥じないように」と心に鞭を打つ思いです。
人として足りないことの多い、同じ過ちを繰り返してばかりのわたしですが、困難に会った時に「あ、そうだ、インマヌエルだった。神様が共にいてくださっている、心配ないんだ。」という場面がこれまでに何度となくありました。
ですが、葬儀ミサで「彼女はホントにインマヌエルだったね」と言われるよりも、今現在の自分を「インマヌエル」に恥じない存在となるよう励みたい、と思っているのに、なかなかうまくできないのです。
26日のごミサ前に、告解をしました。
「まさにそれ!」というお言葉を神父様からいただき、心だけでなく身体までスッキリした気分になれました。
自分に与えられたもう一つの名前が、自分の体を表すのだ、と心を新たにできた日曜日でした。
・・・・・・・・・・・
「『神のインフルエンサー』の少年がカトリック教会の聖人に」、というニュースがありました。
2006年に15歳で亡くなった少年が、キリスト教カトリック教会で聖人となる見通し。
アクティスさんは、所属していた教区や学校のウェブサイトをデザインしたほか、報告されている全ての「聖体の奇跡」の記録を目的としたウェブサイトを立ち上げて有名になった。
https://www.bbc.com/japanese/articles/c0ddvr8dgm1o
これからは、洗礼名にカルロを選ぶ人も出てくるのかもしれませんね。
イエス様の教え
先週の記事のテーマについて引き続き考えながら、大好きな大相撲中継を見ていました。
教会の友人と、「改めて考えてみると、カトリックって決まり事が多いよね。。。」と話しをしたところでしたので、相撲の所作を改めて注意深く見てみました。
相撲好きの方はご存じのように、
「勝った力士は、勝ったという事実に縁起を担ぎ、次の取組の力士に力水をつけてあげる」
「勝った力士は、懸賞金を受け取るときに刀手を切る(右手で左側を切り、その後で右と中央を連続して切る)」
など、相撲は所作をとても大事にしています。
こうした所作が雑な力士は、たとえ横綱であっても評価が下がり、親方から叱責を受けるのです。
わたしたちも、ミサ中に決まった場面で十字を切り、立ったり座ったり、歌ったり祈ったり、決められた所作をしています。
何気なく、ではなく、ひとつひとつに意味があることも理解しています。
19日のごミサでは、お2人の方が受洗されました。
洗礼の秘跡の中では、司祭も受洗者も代父母も、決められた美しい所作を大切にします。
ルカ・シニョレッリ『使徒たちの聖体拝領』
Comunione degli apostoli
『初聖体拝領』パブロ・ピカソ
イエス様からパンをいただく使徒たちの姿は、司祭からご聖体を受け取る信徒に重なって見えます。
初聖体式は、子どもたちの晴れやかな笑顔が感動的で、幼児洗礼式、成人洗礼式と同じくらい、カトリックではとても大切な儀式です。
ご聖体自体の重要な意味(イエス様のからだをいただけるのは洗礼を受けているから)、はもちろんですが、わたしたちはその「拝領」する行為(所作)をも大切にしているのではないでしょうか。
幼児洗礼であっても、成人洗礼であっても、ご聖体拝領について学びの期間があり、どのような意味を持つものかをしっかりと教えられます。
ご聖体の受け取り方、口に含むタイミングも決められています。
永年の習慣にすぎないものになっていたとしても、身に沁み込んだ所作は、きちんとした学びがあって与えられた、わたしたちの信仰上の権利のようなものとも言えるのではないか、、、間違っているかもしれませんが、そう思っていました。
旧約の時代のユダヤ教徒たちも、様々な儀式やしきたり、所作を大事にしていました。
レビ記の第一部(1〜7章)には、守るべき掟がびっしりと書かれています。
今でも、厳格なユダヤ教徒であればモーセ5書(創世記〜申命記)を毎日繰り返し読み、頑なにこれらの教えを守っています。
(例:安息日に労働をしてはならない=エレベーターのボタンを押すことも、冷蔵庫の扉を開け閉めすることも、絶対にダメです)
先日、親戚の法事があり、お坊さんのお経を45分間も聞かされる、苦行のような体験(何を言っているのか全く分からないので)をしました。
そして驚いたのは、叔母がお経の冊子のようなものを見ながらお経をしっかりと聞いていたことでした。
同時に思い出したのが、母の葬儀ミサに参列してくれた友人が後に、「葬儀ミサは初めての経験だったけど、何を言ってるのか何をしているのか全然わからなかったから、仏教の葬儀よりもすごく長く感じた。。。」と聞かせてくれたことでした。
ユダヤ教、キリスト教、そして仏教でも、知らない人・理解していない人にとっては不思議なことを大真面目にやっているのです。
ヨハネ福音書には、イエス様の教えそのものが「パン」なのだ、と明確に書かれています。
わたしが命のパンである。
わたしの所に来る者は、決して飢えることがなく、わたしを信じる者は、もはや決して乾くことがない。
わたしは天から降ってきた、生けるパンである。
このパンを食べる人は永遠に生きる。
(ヨハネ33・35、51)
主は、乏しいパンと僅かな水しかお前たちに与えないことがあっても、お前の導き手はもはや隠れることはなく、お前の目はお前の導き手を見ている。
(イザヤ30・20)
イエス様は、この預言を成就した存在なのです。
初代教会は、聖体(エウカリスティア)の象徴的な先駆けをイエスが言葉と食べ物をご自分の民と分かち合おうとされたパンの奇跡のうちに見ていました。
事実、聖体祭儀の典礼の構造は、この奇跡に見られるのと同じ形式に従っています。
まず言葉の典礼で、聖書朗読に貫かれている教えと、その教えの意味を解き明かす説教によって、イエスは私たちを養ってくださいます。
それから感謝の典礼で、イエスは、私たちのために与えてくださるご自分の体と血である命のパンによって、私たちを養ってくださいます。
かごいっぱいになった残り物が、生き生きとした象徴になっているように、神がご自分の民を養われるとき、すべての人を十分に満たしても、それ以上の食べ物が常にあるのです。
その賜物は神ご自身なのですから、どうしてそれを知らずにいられるでしょうか。
(メアリー・ヒーリー著
カトリック聖書註解 マルコによる福音書より)
洗礼を受けたわたしたちは(なんとなくであったとしても)こうしたことを知っていて、理解しています。
ここを読んでくださっている方、あるいは、勇気を持って日曜日のミサに参列してくださる洗礼を受けておられない方にも、わたしたち信者がもっとこうした教えをお伝えしなければならないのでしょう。
そうでなければ、信仰への理解が広がることも深まることも、あり得ないのです。
教会の先輩が教えてくださった、教皇様のお言葉です。
「キリスト信者にとって最大の誘惑となるのは、神からの呼びかけを特権だと考えてしまうこと、それは全く違います」
洗礼を受けていることだけが、本当に神様からの特別なお恵みなのか。
あたらめてもう一度考え直さなければならないと思っています。
宮﨑神父様はお説教で、このようにおっしゃいました。
「 同じ信仰を持つものが、互いに集い、互いに磨き合う場、その集まりの一致の場が教会・エクレシアなのです。」
いつも、わたしたちの心に響くお説教をしてくださいます。
伝わる信仰
人の価値観や物事の受け取り方が予想とあまりにも違うと、驚いたり・気付かされたり、ということがありませんか?
最近、ごミサの中で気になっていることがあります。
「あの方はお見かけしたことがないな、初めて来られた方かな?」ということがよくあります。
そうした方のことは、気にかけて声をかけるようにしています。
そして、『初めて教会に来られた方へ』というパンフレット、聖書と典礼、聖歌集をお渡しし、質問も受けるようにしています。
ところが、中には知らずにご聖体を受け取り、口にしてしまう方がいらっしゃるのです。
並んで、信者の所作を真似てしまうようです。
「洗礼を受けておられない方は、司祭から祝福を受けることができます」、とアナウンスをしていますが、委員会でこのことが話題になりました。
「司祭から祝福を受ける」ということを、そもそも理解できないのではないか、と。
「洗礼を受けていないと聖体がもらえないなんて、差別されてる気持ちがする」とおっしゃった方もいたそうです。
「信じなければ救われない、というのがキリスト教ですか?」と聞かれたこともあります。
わたしたち信徒の価値観で、「洗礼を受けていないのにご聖体を口にするなんて!!」という気持ちが湧くことも。
このような一方通行では、信仰が人々に伝わるわけがありません。(反省)
わたしも、ここにこうして書く内容については1週間かけてじっくりと吟味していますが、やはり「難しい」「わからなかった」という感想を聞くこともあります。
「カトリックの信仰に関心を持っていただけるように」、「久留米教会に行ってみたいと思っていただけるように」と書き始めたのに、いつの間にか、「学んだことを多くの人に伝えたい」気持ちの方が先走ってしまうことも。
わたしの母校である大学は、とても熱心なプロテスタント教育でも知られる学校です。
イギリス国教会から独立したアメリカの聖公会。
ウィリアムズ主教は、まだキリスト教が禁止されていた江戸時代末期の1859年に米国聖公会の宣教師として来日し、日本聖公会初代主教となります。
1874年には、東京・築地に聖書と英学を教える私塾「立教学校」を設立し、これが後に立教大学となりました。
カトリックも多くの学校を創設し、いまでも日本中でカトリック教育を実践していますが、プロテスタントの教育の方が率直で分かり易くて力強い気がするのです。
大学の広報誌には、当時のトランプ大統領に祈りを捧げる様子が掲載されていて驚きました。
アメリカ聖公会は、福音派(エバンジェリスタ=いわゆるトランプ派)ととても深い結びつきがあるようです。
広報誌に書かれていた、「宗教を学ぶことは国際問題の理解や自己理解を深める」という文言には、納得するような違和感を抱くような、複雑な気持ちになりました。
カトリック信者であるわたしがこの大学に行ったように、生徒のほとんどは聖公会の信徒ではなかったように思います。
わたしにとって宗教は、頭で「学ぶ」もの、よりも先に心と身体で「感じる・信じる」もの、です。
信じたうえで、こうして「学び」を楽しんでいます。
同時に思うのは、プロテスタントの方々は本当によく聖書を学ばれている、ということ。
例えば、「あなたは、わたしに従いなさい」。というヨハネにある言葉を頼りに検索すると、たくさんの教会のホームページやコラムが表示されます。
それは、ほとんどがプロテスタントです。
横浜指道教会という、プロテスタントの教会のホームページで見つけた牧師さんの文章には、こうありました。
「私たちそれぞれには、それぞれなりの、主イエスに従う道が備えられています。
それは人によって全く違う道です。
私たちは、他の人にどのような道が備えられ、どのように導かれているのかに目を奪われるのではなくて、自分に与えられている道を見極め、そこをしっかり歩んで、主イエスに従って行くことが大切なのです。」
https://yokohamashiloh.or.jp/jn-fj-21-3/
とても分かり易く、勉強になります。
プロテスタントの牧師さんたちは、礼拝でのご自分のお話をホームページにまとめて発信する、ということにもとても熱心なように感じます。
知らずにふと入ってみた最初の教会が、カトリックかプロテスタントかは、信者でなければわかりません。
キリスト教の信仰を知りたい、と思う方が、カトリック教会のミサに参列しようと日曜の朝に教会に来てくださったのに、「これはダメです」と言われたら、、、、。
わたしたちの信仰がもっとわかりやすく伝わるように、もう少し工夫が必要かもしれません。
乙女峠への旅
津和野の乙女峠には、毎年5月3日に全国から巡礼者が集まります。
聖母月にあたり、聖母マリアと殉教者たちを讃えるお祝いのこの日は、コロナ禍も巡礼者が途絶えることはなく、今年も(おそらく)2500名ほどが津和野教会から乙女峠までの聖母行列、峠の記念聖堂でのごミサに与りました。
地元の方は「知っている限り、今までで1番多いような気がします」とおっしゃっていました。

このような、苔むした急な坂道を登ったところに記念聖堂と広場があります。
わたしは、この坂を登り降りることは難しかったので、麓でYouTubeの生配信をみながらごミサに与りました。
乙女峠のこと、ご存知でしょうか。
1867年、明治政府による浦上村の隠れキリシタン弾圧事件「浦上四番崩れ」では、およそ3400名ほどのキリシタンたちが見知らぬ土地に流刑されました。
全国22ヵ所に流された人々のうち、153名は津和野に辿り着きました。
激しい責苦を受け、37名が乙女峠で殉教しました。
1892年に、ビリオン神父が殉教者たちの遺骨を一つの墓に収めました。
1948年には、ネーベル神父が地域の方々の支援を受けて乙女峠に記念聖堂を建て、その周りの殉教地が祈りの場所にふさわしいものとなるように整備したのです。
彼が始めたのが、5/3の乙女峠まつりです。
今年の司式は、森山司教様
司教様は、お説教でこのようにおっしゃいました。
「今のわたしたちの信仰は、殉教したキリシタンの方々に負うところが大きいのです。
彼らは、自分たちを根底から生かしておられる方を信じました。
そして、見えないものにこそ真理が宿ることをも信じたのです。
わたしたちは「信仰を守る」という言い方をしますが、彼らは「信仰を生きた」人々です。
誰のために、どのように生きるべきかを知っていた人々です。
教皇様はこうおっしゃっています。
『何のために生きるか、ではなく、誰のために生きているか、が大事』だと。」
全国から多くの巡礼者が集まっていたことには、本当に驚きました。
特に印象的だったのは、津和野教会の副主任司祭である大西神父様が大勢の子どもたちを引き連れて、隣町から巡礼団として(徒歩で3時間半!)参列されていたことです。
今回の巡礼では、これまでにない感覚が生まれました。
巡礼地と言われる様々なところへ行ったことがありますが、今回のように、教会から峠までの道のりを大勢の信徒がロザリオを唱えながら歩き、全員でミサに与る、という巡礼は、とても特別なものでした。
久留米教会の子どもたちにもこのような体験をしてもらいたい、そして、今回わたしたちが経験できたように、楽しみながら信仰を分かち合うことができたら、と思うのです。
*乙女峠の聖母への祈り*
キリストの母マリアよ
あなたは乙女峠の証し人をはげましてくださいました。
神のみ旨に従って生きることができるようあなたの子供である私を助けてください。
私がなにを必要としているかは、母であるあなたがよく知っておられます。
神のみ前にあなたの取り次ぎは必ず聞き入れられると信じ特に今お願いします。
(あなたの願い)
聖母よ、私の母、取り次ぎ者としてあなたを慕う幸せを深く悟らせてください。
アーメン
・・・・・・・・・・・・・
津和野教会
山口ザビエル記念聖堂
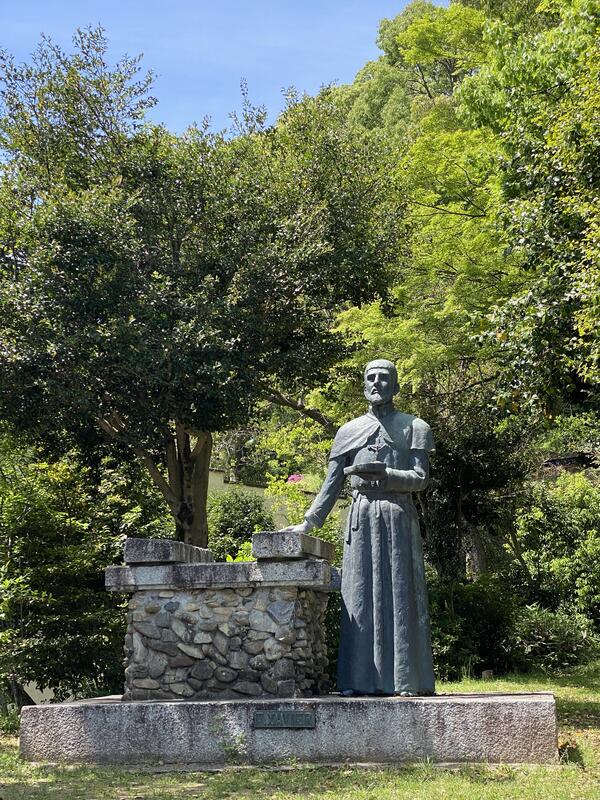
お二人の司教様と
(このお店、俵種苗店の先先代が、乙女峠の聖堂を作るための資金を出されました。
今は子孫であるお嬢さんが経営され、とても素敵なインテリアや食器のお店「SHIKINOKA」になっています。)
来年は、久留米教会の巡礼団として参加できたらいいな、と心から思いました。
マリア行列、峠への坂道の様子など、↓ こちらの記事でご覧いただけます。
https://www.sanin-chuo.co.jp/articles/-/569322
・・・・・・・・・・・・・
静かな津和野の街が賑わう乙女峠まつりだけでなく、5/3に復活したSL蒸気機関車を見に、これまた全国から人が集まっていました。
知的好奇心
以前書いた、聖書とキリスト教の教えについて学び始めた友人と、先日LINEでやりとりをしていました。
先週の記事を読んでもらい、意見交換をしていて、わたしが「この世はテンポラリーなもので、永遠の命のためにわたしたちはこの世を旅しているのよ」と伝えたところ、こう質問されました。
「永遠の命、とはどういうこと?」
皆さんは、そう尋ねられたらどうお答えになりますか?
昔、「マラナタ、ってどういう意味ですか?」と、年配の信者さんに質問したことがあります。
その時のお答えは、「心で理解していることなので、そういう風に聞かれたらうまく言葉にできない」と。
使徒信条は、このように締めくくられます。
聖霊を信じ、聖なる普遍の教会、
聖徒の交わり、罪のゆるし、からだの復活、
永遠のいのちを信じます。
二ケア・コンスタンチノープル信条では、
わたしは信じます。主であり、いのちの与え主である聖霊を。
聖霊は、父と子から出て、父と子とともに礼拝され、栄光を受け、また預言者をとおして語られました。
わたしは、聖なる、普遍の、使徒的、唯一の教会を信じます。
罪のゆるしをもたらす唯一の洗礼を認め、死者の復活と来世のいのちを待ち望みます。
この文章を使って友人に説明してもおそらく理解してもらえないでしょうし、わたし自身もいまいちピンとこないというのが正直なところです。
聖霊、聖徒の交わり、こうしたことは「信じています」と簡単に言えますが、「永遠のいのちを信じます」とは何を信じているということなのでしょうか。
「わたしは復活であり、命である。
わたしを信じる者は、たとえ死んでも生きる。
生きていて、わたしを信じる者はみな、永遠に死ぬことはない。
このことをあなたは信じるか」。
(ヨハネ11・25〜26)
愛していたラザロが墓に葬られ、嘆き悲しむ姉妹のマルタに対してイエス様はこうおっしゃいました。
フランシスコ会訳聖書の解説には、「イエスが死者を復活させる力をもち、永遠の命の源であることを意味する。イエスを信じるものは、この世の命に死んでも、永遠の命に生き続けることを意味する。」とあります。
うっすらと、疑問の霧が晴れてきたような気がします。
逮捕される直前、イエス様は数々の祈りをされます。
ヨハネ17章では、まずご自分のために祈りを捧げます。
あなたは、すべての人を治める権能を子にお与えになりました。
子が、あなたから与えられたすべての人に、永遠の命を与えるためです。
永遠の命とは、唯一のまことの神であるあなたを知り、また、あなたがお遣わしになったイエス・キリストを知ることです。
(1〜3)
続けて、弟子たちのために祈りを捧げます。
あなたが世から選んでわたしにお与えになった人々に、わたしはあなたの名を現しました。
彼らはあなたの言葉を守りました。
あなたがわたしにお与えになったものはすべて、あなたからのものであることを、今、彼らは知っています。
なぜなら、あなたがわたしにお与えになった言葉を、わたしが彼らに与え、そして、彼らはそれを受け入れ、わたしがあなたの元から出てきたことを本当に知り、あなたがわたしをお遣わしになったことを信じたからです。
(6〜8)
だいぶん視界が開けてきました。
以前ご紹介した、わたしの愛読書を開いて、さらなる答えを探してみました。
第3巻第47章は、タイトルが「永遠の命を受けるために、すべての労苦を忍ぶべきこと」となっており、その2節にはこう書いてあります。
あなたの為すべきことを忠実に行いなさい。
『わたしのぶどう園に行って働きなさい』(マタイ21・28)、そうすれば『わたしはお前の報い』(創15・1)となるだろう。
読み、書き、歌い、願い、沈黙し、祈り、勇気をもって苦しみを受け入れなさい。
永遠の命は、このような苦悩、いやそれ以上の苦悩に値するものである。
第49章「永遠の命への憧れと、そのために戦う人に約束された大いなる報いについて」の3、4節には、
あなたは、『神の子供の栄光の自由』(ローマ8・21)に入りたがっている。
またあなたは、永遠の住居と喜びに満ちた天の国を望んでいる。
しかしその時はまだあなたの上には来ていない。
今は、まだその時ではなく、戦いの時、苦労と試練の時だからである。
あなたはまだこの世で試され、さまざまに鍛えられなければならない。
たびたび慰めも与えられるが、しかしこの世に完全な慰めはない。
「キリストを生きる」トマス・ア・ケンピス(翻訳:山内清海)
深い霧が少しづつ晴れてきて、心が軽くなるような気持ちになります。
わたしたちのこの世での日々は、信仰があったとしても苦悩や試練の連続です。
それらに打ち勝ち、内的成長のための糧と捉えて前に進むことができるのは、イエス様の教えを「知って、理解して、信じている」からです。
現在の苦しみは、将来、わたしたちに現されるはずの栄光と比べると、取るに足りないとわたしは思います。
わたしたちは救われているのですが、まだ、希望している状態にあるのです。
目に見える望みは望みではありません。
目に見えるものを誰が望むでしょうか。
わたしたちは目に見えないものを望んでいるので辛抱強く待っているのです。
(ローマ8・18、24〜25)
と、ここまで書いたところで28日のごミサに与り、宮﨑神父様のお説教で目を見開かされました。
「永遠の命を得るということは、イエス様の求める生き方を追求して自分の人生を全うすること、とも言えるでしょう。」
わたしがこの記事を書いていることは、もちろん神父様がご存知なはずはないのに。
思わず、「今日のお説教素晴らしかったです!」とお伝えしました。
(「いつも、やろ」と返されました。)
「 永遠の命とは」と、こうして聖書の言葉などを紐解きながら、友人がもっと「教えを知りたい」という好奇心を掻き立ててくれることは、わたしにとっても喜びです。
内なる旅
「The Book」といえば、「聖書」を意味します。
2010年の映画「ザ・ウォーカー」(デンゼル・ワシントン主演)は、原題「The Book」です。
それが聖書とは知らずに、「本を西へ運べ」という心の声に導かれ、目的地も分からぬまま30年間アメリカを西に歩き続ける男の話しです。
先日、「星の旅人たち」という映画を観ました。
原題は「The Way」
The Bookが聖書であるように、The Wayは聖地サンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼路のことです。
旅の途中で出会ったジプシーの男が主人公に告げた、「息子の遺灰をムシーアの海に撒け」との言葉に従って、目的の聖地サンティアゴ・デ・コンポステーラに辿り着いた後も旅を続ける、父親の物語です。
父親役はマーティン・シーン、息子役はエミリオ・エステべス、2人は実の親子であり、息子のエミリオがこの作品の監督です。
(AmazonPrimeでご覧になれます。)
イスラエル、ローマ、サンティアゴ・デ・コンポステーラが、キリスト教の3大巡礼地と言われています。
スペイン語でEl Camino de Santiago(サンティアゴの道)と呼ばれ、El Camino(その道)、つまりThe Wayといえば、この巡礼のことを指します。
エルサレム、ローマと比べ、800キロ以上もの道のりを1か月ほど歩き続ける行程は、かなりハードルが高いものです。
そして、イスラエル、ローマへの巡礼とはかなり様子が違うのです。
つまり、「純粋なカトリックの信仰の故に歩く」のではない人の方が多いようなのです。
この映画の主人公もそうです。
旅を共にすることになる3人の仲間も、それぞれに「歩く理由」を持っていました。
巡礼者の中には、理由・目的をはっきりと自覚している人もいれば、それを捜すために歩く人もいます。
歩く理由、あるいは、生きる理由とも言えると思います。
わたしがイスラエル巡礼をした理由は、イエス様たちが生きた土地を自分で体感したいから、でした。
(実際には、足の不自由なわたしにとって灼熱のイスラエルを歩き回るのはかなり大変で、イエス様たちの生きた証を体感するなどという素敵な目的は、ほとんど忘れていましたが。。。)
歩く理由、生きる理由は本当に必要でしょうか。
男子はすべて、年に三度、すなわち除酵祭、七週祭、仮庵祭に、あなたの神、主の御前、主の選ばれる場所に出ねばならない。
ただし、何も持たずに主の御前に出てはならない。
(申命記16・16)
旧約時代の人々、熱心なユダヤ教徒たちは、この3つの祭りを厳格に祝うことを今で言う「巡礼」、と考えていました。
理由は、「主がエジプトからあなたを導き出されたから。エジプトで奴隷であったことを思い起こすため。すべての収穫、すべての働きの実を祝福してもらうため。」でした。
巡礼者であるとはどういう意味でしょう。
巡礼を始める人は、まず目的地をはっきりと設定し、それを心と頭につねに置いています。
ですが同時に、その目的地に達するには、目の前の一歩に集中することが必要で、足取りが重くならないよう無駄な荷を下ろし、必要なものだけをもち、疲れ、恐れ、不安、暗闇が、歩み始めた道の妨げにならないよう、日々頑張らなければなりません。
このように巡礼者であるとは、毎日新たに出発すること、再出発を続けること、旅路にあるさまざまな道を進むための熱意と意欲を新たにし続けるということです。
疲労や困難はあっても、それによってつねに新たな地平と、見たことのない光景とが広がるのです。
キリスト者にとっての巡礼の意義は、まさに次のとおりです。
わたしたちが旅に出るのは神の愛を発見するためであり、と同時に、内なる旅によって自分自身を見いだすためでもあります。
内なる旅とはいえそれは、多様なかかわりに刺激され続けるものです。
つまり、呼ばれているから巡礼者なのです。
神を愛し、互いに愛し合うよう呼ばれています。
ですから、この地上におけるわたしたちの旅が徒労に、あるいは無意味な放浪に終わることは決してありません。
その逆で、日々、呼びかけにこたえつつ、平和と正義と愛を生きる新たな世界に向かうはずの一歩を踏み出そうとしているのです。
わたしたちは希望の巡礼者です。
よりよい未来に向かおうとし、その道すがら、よりよい未来を築くことに全力を尽くすからです。
「第61回世界召命祈願の日」教皇メッセージより
記事を書くために色々と読んだり調べたりしていたら、この、教皇様のメッセージに出会いました。
現代のわたしたちが巡礼する意味が、明確に述べられています。
イスラエルやローマなどに行かずとも、わたしたちは巡礼者、旅人なのです。
内なる旅を続けながら、自分自身を見出す人生、それが巡礼なのでしょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・
この映画、とてもお勧めです。
歴史の評価
ローマに滞在中の聖書の師匠が、カラバッジョの作品の写真を送ってくださいました。
サンタゴスティーノ聖堂(ローマ)にある、カラヴァッジョの『ロレートの聖母(巡礼者の聖母)』
貧しい農民であろう老夫婦が、聖母子を拝む様子が描かれています。
聖母マリアは、33歳のカラヴァッジョが当時の公証人パスクアローネを襲撃し、大怪我を負わせる原因となった娼婦マッダレーナ・アトニエッティがモデルと言われています。
崇敬の対象である聖母マリアが普通の人々と同じように素足で描かれ、肩を出した露出の高い服、しかも巡礼者とかなり近い距離であることから、不敬だとしてライバルの画家に訴えられて裁判にかけられ、実際に投獄されています。
マリアの母性は、わたしたちを神の御父としての優しさに出会わせてくださる、もっとも直接的で、容易な道です。
聖母が、信仰の始まりとその中心へ導いてくださるのです。
それは、計り知れない賜物で、わたしたちを神に愛される子どもとし、御父の愛のうちに住まわせてくださるのです。
(教皇様の4/10のX)
そして、今観ているネットフリックスのドラマに登場したのが、次の作品です。
この『ゴリアテの首を持つダビデ』は、カラヴァッジョ最晩年の代表作です。
旧約聖書に登場する巨人兵士ゴリアテを倒し、斬り落とした首を持っている、羊飼いダビデの姿を描いた作品です。
彼は、このタイトルで3枚の絵を描きました。
マドリードのプラド美術館に所蔵されている絵は、初期の作品とされています。
他の2つのバージョンは、ウィーンの美術史美術館とローマのボルゲーゼ美術館にあり、これはローマにある作品です。
若きダビデと手に掴まれたゴリアテの首は、カラヴァッジョの若い頃と晩年の自画像だと言われています。
同情と愛を秘めた目でゴリアテの首を見つめているダビデの表情は、人間の複雑な心理描写であるように感じます。
「カラヴァッジョはこの作品を枢機卿に贈答することで、自らの罪を改悛している姿勢を示し、恩赦を得ることを画策した」
「ダビデの持っている剣に「H-AS OS」という文字が刻まれていおり、これはラテン語の「humilitas occidit superbiam(謙虚さは誇りを殺す)」の略語」
「旧約聖書の英雄ダビデをイエス・キリストに重ね合わせ、巨人ゴリアテを悪魔になぞらえて、イエスによって悪魔は葬られることを指す。」
「イエスは謙虚さであり、ゴリアテは誇りを意味する。」
などと説明されているサイトもありました。
https://note.com/ryuishi/n/nf836e5bb9e20
カラバッジョは、いわゆる「キレやすい」人物だったことはよく知られています。
頻繁に問題を起こし、人を切りつけ、絵画のモデルとして死体や娼婦を使っていたことも有名です。
彼が生きていた時は、作品よりも彼の問題行動や人間性の方が評判だったのかもしれません。
しかし今となっては、彼の作品は最高級の芸術品として崇め奉られています。
死がその評価を変える例としては、ゴッホなどとも通ずるものがあります。
イエスのご復活によって、悪は力を失いました。
失敗も、わたしたちがやり直すのを阻むことはできません。
死さえも、新たないのちの始まりへの通過点となったのです。
(教皇様の4/8のX)
・・・・・・・・・・・・・・
:余談1:
教皇様のX(旧ツイッター)のアカウント名は、@Pontifexです。
ラテン語で、pontifex maximus は教皇を意味します。
元々は、「最高神祇官」(古代ローマの公式な宗教行事を司る神官団に属する人)を指す言葉でした。
今では、pontifexはカトリックの司教を意味していて、英語のpontificate(尊大に話す、横柄な態度で話す)の語源になっています。(笑)
バチカンへの定期訪問のためローマを訪れた日本の司教らは、4月8日(月)より、教皇庁の各省・各機関を精力的に訪問し、日本のカトリック教会の現在の情勢を報告すると共に、具体的な情報の交換とより緊密な関係構築に努めた。
アド・リミナ(ad limina )とよばれるこの定期訪問では、「使徒たちの墓所へ」を意味するその言葉のとおり、初代教会を支え、宣教に尽くし、ローマで殉教した2人の使徒、聖ペトロと聖パウロの墓参りが行われる。
バチカンニュースより
・・・・・・・・・・・・・・・・・
:余談2:
「ゴリアテの首を持つダビデ」の絵が出てきたのは、ネットフリックスの「リプリー」というドラマです。
アラン・ドロン主演の映画『太陽がいっぱい』(1960)が新たにドラマ化され、先週から配信されています。
イタリアの美しい風景があえて全編白黒なところが、かえって美しさを際立たせているように感じました。
この作品もまた、何度もこうして映像化され、歴史に残る名作となっています。
行動する女性たち
4月の教皇様の祈りの意向は、「女性の役割」のために、とされています。
「女性の尊厳と価値があらゆる文化で認められ、さまざまな差別に終止符が打たれますように」。
ビヨンセ(アメリカの世界的アーティスト)の楽曲に、「Who run the world? Girls!」というのがあります。
誰が世界を動かしてる?女性たちよ!!
日本では女性管理職の数が少ない、議員になる女性が少ない、などと言われていますが、世界を見渡せば、女性たちがまだ旧約聖書の時代のような扱いを受けている国もあるのです。
聖書が書かれたのは、古くは今から4000年以上前であるにも関わらず、そして、当時は当然の如く女性蔑視(人数を数える際にはカウントされないですし)の時代であったにも関わらず、旧約にも新約にも、歴史を動かす女性や男性に怯まず行動する女性たちが描かれています。
イエス様が亡くなった時とその直後、すぐに行動したのは女性たちでした。
イエス様が息を引き取られた時に、百人隊長が「まことに、この方は神の子であった」。と言い、その様子を婦人たちが遠くから見守っていました。(マルコ15・40)
ジェームズ・ティソ(James Tissot)
『十字架上から見たキリストの磔刑』 1890年頃
この人たちは、イエスがガリラヤにおられたとき、イエスに従って、仕えていた婦人たちである。
なお、このほかにもイエスと一緒にエルサレムに上って来た多くの婦人たちがいた。
(マルコ15・41)
マグダラのマリアとヨセの母マリアとは、イエスが納められた場所を見ておいた。
(15・47)
安息日が終わるとすぐに、3人の女性たちは香料を買って墓に向かいます。
彼女たちは、遺体の腐敗が始まっているであろうことには気にも留めず、イエス様への献身の故に、最後の奉仕をしようと行動するのです。
十字架につけられたイエス様と一緒にいた彼女たちの誠実さは、その不在が際立っているペトロをはじめとする十二人の弟子たちの不誠実さとは対照的です。
「日が昇るとすぐ」(16・2)彼女たちは墓に向かいます。
マルコがわざわざ日の出を記したのは、旧約の最後の預言にあたるマラキ書の言葉を指し示しているのかもしれません。
わたしの名を畏れるお前たちには、正義の太陽が輝き、その翼には癒しがある。
お前たちは外に出て、肥えた子牛のように跳ね踊る。
(マラキ3・20)
正義の太陽とはまさにメシアを指しています。
そして、週の初めの日は、神が光を創造した日、つまり新しい創造の始まりを意味します。
7日のごミサで宮﨑神父様がおっしゃったように、週の初めの日、つまり日曜日から始まるわたしたちの日常は、イエス様の復活を記念して集うミサごとに新しくされます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
何度か紹介している画家、ジェームズ・ティソ(James Tissot、1836~1902)
晩年は、フランス東部のドゥー県シュヌセ=ビュイヨンにある修道院で聖書の挿絵に取り組みました。
先日のNY滞在の折、JewishMuseumで彼の連作を見てきました。
旧約聖書の物語を描いた作品は、どれも生き生きと描かれており、画集を買ったので今も時々開いて見ています。
「十字架上から見たキリストの磔刑」という作品は、BrooklynMuseumにありますが、次にご紹介する作品はJewishMuseumに収蔵されています。
旧約の中で主人公として描かれている女性は何人もいますが、このエステルはわたしのお気に入りです。
ユダヤ人であることを隠してクセルクセス王の妃となったエステルは、王の家臣であるハマンがユダヤ人の虐殺を計画していることを知り、機転を効かせて行動し、それを阻止するという物語がエステル記です。
この絵は、エステル記に書かれている豪奢な王宮の様子をよく表しています。
銀の輪と大理石の柱には、白い木綿の織物と緋色の幔幕が良質の亜麻布と紫色の織物でできた紐で結ばれていた。
また、まだら石や大理石、真珠貝やいろいろな宝石でモザイクを施した床の上には、金や銀の長椅子が置かれていた。
(エステル記1・6)
信念を持って行動する女性の姿は、いつの時代も鮮烈な印象を残します。
男性には武勇伝的なものが多いのに比べ、知恵と機転を効かせた女性の行動力は、あっぱれとしか言いようがないと思いませんか?
男性と女性は同じ、ではなく、女性にしかできない役割、能力というものがあると思っています。
教皇様のご意向のように、全ての女性たちの尊厳と価値が守られますよう、祈りましょう。
受難物語
聖週間は、わたしたちの信仰の基礎をなしています。
聖木曜日は洗足式が行われました。
聖金曜日、一年に一度この日だけ祭壇の布が取り外され、日中の祭壇にはステンドグラスが映り込みます。
聖土曜日、新しいロウソクが準備され、新しい一年が始まりました。
そして、御復活を祝う日曜日には、記憶にある限りこれほどまでに多くの参列があったのは初めてでは?というほどの人々が、ごミサに集いました。
5人の幼児洗礼式が執り行われ、お祝いは頂点に達した日曜日でした。
・・・・・・・・・・・・
4つの複音書で、受難物語の中の言い回しや出来事の順序が互いによく似ていることは、初代教会がイエスの受難の細部にどのような重要性を見ていたかを示しています。
その受難を、特にイザヤ書の苦しむ僕の歌を、苦しむ義人の詩編の観点から解釈しています。
受難の苦悩を言い繕うことはせずに、物語全体を復活の光で満たしているのです。
特にマルコは、読者にこの神秘の重要性をより深く理解してもらおうという点に集中しています。
つまり、ポンティオ・ピラトのもとで十字架につけられて死んだこの男は誰なのか、そしてこの男の死はわたしとどのような関係があるのか、という点です。
この日々の中でわたしがいつも特に気にかかるのは、イスカリオテのユダの心情です。
彼は自ら率先して、イエスを裏切ろうとして祭司長たちのところへ出掛けていきます。
ユダがイエスを「引き渡す」という言い表し方は、受難物語の中で大変重要な表現です。
かつてイエスがやがて自ら経験することになると言っていた(9・31、10・33)、一連の裏切りを表しています。
ユダは、弟子の一人でありながら、イエスをユダヤ人指導者たちに「引き渡し」、彼らはイエスを異邦人支配者に「引き渡し」、そして彼はイエスを十字架刑に「引き渡す」のです。
同時に、こう表現することもできます。
イエスはユダによって引き渡されます。
しかし、神の計り知れない計画で、神はご自分の御子を罪人たちに引き渡されましたが、それは彼らへの愛の故でした。
わたしたちすべてのために、ご自分の子をさえ惜しまずに死に渡された神が、どうして御子に添えてすべてのものをわたしたちにくださらないこちがありましょうか。
(ローマ8・32)
そして、イエスは同じ愛を持って自らを自由に引き渡しました。
マルコは、ユダが「十二人のうちの一人」であり(14・10、20、43)、イエスが特別な親しい関係をご自分と結ぶため、また自らの権能を分かち合うために選んだ一人であった(3・14〜15)ことを特に繰り返し記すことで、裏切ることがいかに痛みを伴うのかを強調しているのです。
マルコの中でのイエスは、自分を裏切ることになる者が誰なのか明確にしていません。
これには二つの理由が考えられます。
一つは、彼が告げたことは、他の弟子たちに落ち着いて語られた戒めであり、各人に自分たちの心を調べさせ、そのような行為をする何か冷酷な心の本質が内面にあるかどうかを識別させるためです。
もう一つは、イエスが告げたことが、誰にも知られることなく悪意ある計画を悔い改めて断念する機会をユダに与えるためです。
人の子であるイエスは苦しむメシアであって、彼の受難は神によってあらかじめ定められ、聖書の中で預言されてきました。イエスが述べているのは、ユダの裏切りが彼自身に引き寄せている酷な運命に、苦悩を表す警告なのです
主よ、どうかわたしを憐れみ、再びわたしを起き上がらせてください。
(詩編41・11)
イエス様が使徒たちに自らを顧みるチャンスを与えてくださったように、わたしたちにも、日々の生活の中でその機会が与えられています。
御復活の喜びに浸ったわたしたちは、この呼び覚まされた気持ちを忘れないように明日からの日々を生きていかねばなりません。

心の支え
枝の主日、あいにくの雨でしたが、大切な日を祝うことができました。
この枝は、久留米教会の敷地に育っているもので、有志の皆さんが丁寧に洗い、棘をとり、枝の主日のために準備してくださったものです。
・・・・・・・・・・
わたしたちカトリック信者は、占いやおまじないと言ったものを信じてはいません。
全ては神様の御旨の通り、お導きを信じていますから。
ですが、京都でお寺を巡ったり、神社でおみくじを引いたり、といったことは、日本人の習慣として楽しむことはあります。
占いやおみくじに書かれていることは、時には(都合のいい時には)わたしたちの心の支えとなります。
言葉に心を留める人は喜びを見出す。
主に寄り頼む人は幸い。
(箴言16・20)
心地よい言葉は蜂蜜のよう、
舌に甘く、体を健やかにする。
(箴言16・24)
人の歩みは主によって導かれる。
人間は、どうして自分の道を悟り得ようか。
(箴言20・24)
NYの妹が、仕事で東京に来ています。
彼女は、父と変わらない年齢の世界的アーティストのプロデューサー的な仕事をしており、その方の作品を昔売った方から買い戻す、外国の美術館で個展を開催する、など、大きなミッションを幾つも抱えています。
洗礼を受けている妹が今日引いたおみくじには。
わがおもう
港も近く なりにけり
ふくや 追手のかぜのままに
災自ら去り福徳集まり目上の人の助けを受けて喜事があります
行先利徳あり
売物買物損はなし
相場は好機です
プレッシャーのかかる案件を抱えた妹にとって、とても大きな心の支えになっているようです。
(おみくじの文面を考えている方のセンスに感動しました。)
自分の今の状況に応じた言葉を得ることができると、わたしたちは都合のいいもので、「『神様』がわかってくださっている!」と実感することができます。
よく宮﨑神父様がおっしゃるのが、「プロテスタントの方に比べて、カトリック信者はあまり聖書を読みません。もっと聖書に親しんでください。」
聖書を開くと(特に、わたしがいつもやるように、目をつぶって適当に開くと)、必ずと言っていいほど、目が開かれるような聖句に出会うことができます。
神がわたしを助けて、思いのままに語らせ、授かった恵みにふさわしい考えを起こさせてくださるように。
神こそ知恵の案内者であり、知恵ある者の指導者でもあるのだから。
わたしたちもわたしたちの言葉も、あらゆる分別と仕事の知識も神の手にある。
存在するものについての誤りないい知識をわたしに授けたのは神である。
(知恵の書7・15〜17)
わたしたちカトリック信者も、もっと聖書に心の支えを求めるべきでしょう。
ここを読んでくださっている方は、こうして毎週紹介している聖書の箇所を開いてくださっているのでしょうか。
ぜひ、この四旬節の間、それぞれにとっての心の支えとなる聖句を見つけてみてください。
・・・・・・・・・・
NYから来た姪が、「カトリックの教会素敵!」と宮﨑神父様と英語で話していた様子が、わたしにとっての今日のお恵みでした。
仕事と子育てを頑張っている妹たちと、4人の姪甥、そして、聖書に見出す言葉が、わたしの心の支えです。

天国とは
天国はどのようなところだろう、と思ったことはありませんか?
「天の国」はわたしたちが永遠に安らぐ場所、という感覚で理解していますが、「天国」は、大切な人々が旅立ったところ、というイメージです。
わたしはいつも、母が天国で後から来た後輩たちのお世話を焼いている姿を想像しています。
何度か書いたことのある、支援していた方が天国へ旅立たれました。
どうしてわたしが神に答えられようか。
言葉を選んで神と論議することができようか。
たとえ、わたしが正しくても、わたしは答えることができない。
わたしを裁く方に憐れみを乞うだけである。
たとえ、わたしが呼んで、神がお答えになっても、神がわたしの言い分をお聞きになるとは思えない。
わたしに息つく暇も与えず、苦痛でわたしを満たされる。
わたしはもう自分のことはどうでもよい。
わたしは生きることをいとう。
神でなければ、これは誰の仕業か。
(ヨブ記9・14~18、23、24)
なぜ、あなたはわたしを母の胎から引き出されたのですか。
わたしは誰の目にも触れずに息絶えていたらよかったものを。
あたかもこの世にいなかった者のように、母の胎から墓場へと運ばれていればよかったものを。
わたしの余命はいくばくもないではありませんか。
今、わたしから離れて、少しでもわたしを楽にさせてください。
わたしが、二度と帰って来られない所に、闇と死の影の国に行く前に。
暗黒のように真っ暗な国、秩序のない死の陰の国、そこでは、光すら暗黒のようです。
(ヨブ記10・18~22)
その方は、強い信仰のなかで、自分がなぜこれほどの苦しみの中を生かされているのか、いつもその意味を捜していました。
まさに、現代のヨブでした。
ヨブ記の著者は、苦しみの起源と意義について問題提起しています。
当時の因果応報的な世の中にあって、そのことに強い疑念を抱き、この物語で神がヨブに現れて語りかける様子を描きました。
MARC CHAGALL 'Job Praying'(シャガール:祈りを捧げるヨブ)
なぜこのような苦しみをお与えになるのですか。
どうしてわたしをこれほど辛い目にあわせるのですか。
その方も、病気で苦しみ続けたこの10数年は、自分に与えられた苦悩についてもがいていました。
それでも、彼のことを見放さずに支援してくださったある神父様の存在が、彼の希望の光でした。
家族の中でも孤立し、あまりうまく行っていなかったようです。
ですが、臨終には家族が立ち会い、最期を見送られたそうです。
「語りかけるが、苦しみの意義は明らかにされない。
それは神秘のまま留まる。
だが、重要なのはヨブが苦しんでいるときに神が現れたことである。
これによって、人は苦しんでいるときも、孤独ではなく、自分の傍らには神が常におられることを強く感じるのである。」
フランシスコ会訳聖書には、こう説明がありました。
「孤独ではない」
きっと彼も、ヨブの言葉を理解されたのではないか、そう思ってわたしは自分を慰めています。
わたしはあなたのことを耳にしていました。
しかし、今や、この目であなたを見ています。
それ故、わたしは塵と灰の上に座り、わたしの言葉を忌み、悔い改めます。
(42・5~6)
天の国は、このようなところではないか。
ヨブ記を読み返していて、そう強く感じました。
地上での自分の人生は決して孤独ではなかった、いつも、隣に神様がいてくださったのだ、そう強く理解できる場所、それが天の国なのかもしれません。
主はこう言われる。
わたしは恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。
わたしはあなたを形づくり、あなたを立てて、民の契約とし、国を再興して、荒廃した嗣業の地を継がせる。
捕らわれ人には、出でよと、闇に住む者には身を現せ、と命じる。
彼らは家畜を飼いつつ道を行き、荒れ地はすべて牧草地となる。
彼らは飢えることなく、渇くこともない。
太陽も熱風も彼らを打つことはない。
憐れみ深い方が彼らを導き、湧き出る水のほとりに彼らを伴って行かれる。
わたしはすべての山に道をひらき、広い道を高く通す。
見よ、遠くから来る、見よ、人々が北から、西から、また、シニムの地から来る。
天よ、喜び歌え、地よ、喜び躍れ。
山々よ、歓声をあげよ。
主は御自分の民を慰め、その貧しい人々を憐れんでくださった。
シオンは言う。主はわたしを見捨てられた、わたしの主はわたしを忘れられた、と。
女が自分の乳飲み子を忘れるであろうか。
母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。
たとえ、女たちが忘れようとも、わたしがあなたを忘れることは決してない。
(イザヤ49・8~15)
目に浮かぶようなこの光景。
天国がこのような場所であったら。
見送った大切な人たちがここで過ごしてくれていたら。
彼が、安らかな穏やかな顔で、「神様、ようやくお会いできましたね」と天の国で幸せに過ごしている様子を想像しています。
癒しの力
レコンキスタという言葉、ご存じでしょうか。
「失地回復」を意味するスペイン語です。
718年から1492年まで、イスラム教徒から南欧イベリア半島を奪還するために、ヨーロッパのキリスト教勢力が起こした戦争のことです。
当時、イスラム教徒だけではなく、多くのユダヤ人もスペインから追放されました。
最近は、プーチン大統領によるウクライナ侵攻は「レコンキスタ」であると表現されています。
1198年に選出されたローマ教皇インノケンティウス3世。
悪名高き行いや政策で、カトリック界のみならず、歴史に名を遺した教皇です。
カトリックの威信の発揚とイスラムの撃退を目指した教皇は、キリスト教諸国間の争いを停止し、対ムスリムで結束するように呼びかけます。
これに応えて、ヨーロッパでは第4回十字軍が結成されました。
これも、当時の彼らの意図としては「レコンキスタ」です。
イベリア半島でも、アルフォンソ8世を中心としたキリスト教連合軍が結成されることになり、ピレネー山脈を越えて多くの十字軍騎士が来援し、連合軍は総数6万を超えました。
レコンキスタは、「再征服」という言い方もされるようです。
取り戻す、ということでしょうか。
先日、テレビのインタビューでこうおっしゃっていた方が。
「東日本大震災の被災者もそうだったと思うが、能登地震で被害に遭った自分も、元の生活に完全に戻るということはあり得ないと思っている。
新しい生活を一から作っていかなければならないんだ。」
13年経ってようやく下水道工事が始まる、という福島の方は、こうおっしゃっていました。
「これから新しい街を作っていくのだから、いろんな夢がある。」
元々は自分たちの土地だとして「取り戻す」戦争は、現代の世界では容認できないものです。
自然災害などによって荒廃した故郷を、新しく「取り戻す」という、力強く前を向いた方々の姿には、敬意を表すことしかできません。
シャガールが故郷への愛をもっとも詩的に描いた作品「村と私」を、NYのMoMA(近代美術館)で見てきました。
「これは単なる風景画ではなく、親しんだ習慣に対するノスタルジーを反映した大きな世界を表現したものである。自身を緑色で描いているが、これは彼にとって、復活と喜びを象徴するものであった。」と解説されているサイトがありました。
聖書には、バビロン捕囚からの帰還後、エルサレムを復興する希望を書いた美しい文章がたくさんあります。
すでに捕囚から帰還し、なお苦しい生活をしている人々を奮い立たせようとする神の姿です。
わたしは囚われ人となっているお前の民を、水のない穴から助け出そう。
囚われの身にあっても希望を持つ人々よ、砦に帰れ。
(ゼカリヤ9・11~12)
万軍の主は子自分の羊の群れであるユダの家を訪れ、彼らを戦場で栄えある軍馬のようにされる。
この群れから隅の石が、
この群れから天幕の杭が、
この群れから戦いの弓が、
この群れからすべての指揮者が出る。
わたしはユダの家に力を与え、ヨセフの家を救う。
わたしは彼らを憐れむが故に、彼らを連れ戻す。
彼らは、わたしが見捨てたことのなかった者のようになる。
(ゼカリヤ10・3~6)
東日本大震災から13年
能登地震から3か月です。
同様に聞かれるのが、避難先から人々が戻らず、故郷が失われる不安や寂しさです。
そして同じように、故郷の再建のために隅の石となって指揮をされる人々の存在があります。
今なお、苦しい思いを抱えている方々に、少しでも癒しの時間がありますように。
復興への長い道のりを、諦めずに前進し続ける方々に、勇気と知恵、導きが絶えず与えられますように。
・・・・・・・・・・・・
マイケル・ジャクソンの名曲のひとつ、「ヒール・ザ・ワールド」は、直訳すると「世界を癒そう」という意味です。
歌の内容は「人間同士の争いで傷ついた世界を、愛で治癒しよう」というものです。
時代が変わっても、同じ行い、過ちを犯し、変わらぬ理想を持ち、癒しを求めるのが、わたしたち人間なのです。
Heal the world
Make it a better place
For you and for me and the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me
世界を癒そう
もっと素晴らしい世界にしよう
君にも僕にも、そして人類すべてにとって
死にかけている人々もいるんだ
君が命にちゃんと思いやりをもてば
君にも僕にも、より良い世界になる
新しい楽しみ
NYに聖書を持って行ったことを書きましたが、妹は友だちが来たとき、「姉は毎日聖書を読んでいる」と驚いた様子で話していました。
(毎日読んでいた訳ではないのですが、、、、)
その彼女から、「ボーイフレンドがプロテスタントの熱心な信者で、聖書を勉強してほしいと言われたの。Aki(わたしの妹)に聖書を借りて読んでるけど、眠くなるだけで全然意味がわからない。どうしたらいい?」と聞かれました。
「一人で家で聖書を読んでも、理解は難しいよ、、、。」
その時は、そう答えました。
『信仰が先か、聖書が先か。』その時は、そう思ったのです。
聖書をどこから読むかによっても、「面白くない」「意味がわからない」という感想だけに終わってしまいます。
福音宣教の3月号、高橋洋成さんのコラムに、
「マルコの福音書はせわしなく場面が切り替わる。導入部分のイエスの出現と洗礼、荒野の試練、宣教の開始、使徒たちとの出会いに至るまでの経緯を、マタイとルカでは4〜5章を費やしているのに、マルコはたったの1章で駆け抜ける。」
と書いてありました。
今では1番最初に書かれた福音書はマルコである、とわたしたちは認識していますが、実はこの福音書は他の3つの福音書に比べて軽視されていたという歴史があります。
マルコに関する注解書は、中世のはじめまで何一つ世に出ることはなかったのです。
マルコの661節のうち、90%がマタイの中に複製され、55%はルカにあります。
マルコは使徒たちの幾つもの欠点を赤裸々に描写しているのに、マタイとルカはそれを柔軟に扱っています。
そして、イエスのかなり人間臭いさまざまな活動と感情を描いているのに、マタイとルカはそれを削除しています。
そのような細かな研究が進む中で、20世紀になってようやく「マルコが最初に書かれた福音書である」と学者たちは結論づけるに至ったのです。
冒頭に書いた妹の友人に、この本を薦めようと思います。
この本は、聖書の師匠から「素晴らしいから、ぜひ読んで!」と教えてもらった、今年の1冊目です。
マルコを1章1節から、1節ずつ、様々な解説文を添えながら深く、それでいて分かりやすく解きほぐしていきます。
例えば、イエスの洗礼についての箇所
1・9の解説
「彼自らが、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けるために、悔い改める謙遜な人物の役目を担って現れるというのは驚くべきこと」
「キリストが洗礼を受けたのは、ご自分が水で聖化されるためではなく、水を聖化するためであり、ご自分が水で洗われることによって、ご自身が触れた川の水を清めるためだった。」
1・10の解説
「イエスが水から上がってくることに応えて、上から聖霊が降っています。神は恐らく、その民が不浄から清められた後に初めて、彼らのもとに降って来るのでしょう。イエスの上に霊が降るということは、十字架によって罪が取り除かれた後、聖霊降臨の時に教会にその霊が降ることを予示しています。」
11章のイエスのエルサレム到着の場面についての解説
「イエスの時代に、神殿は改修され、エルサレムはほとんど地上に存在する壮麗さの頂点を極めていました。
ユダヤ教の三大祝祭、過越祭、五旬祭、仮庵祭がそれぞれ祝われる頃になると、その町は巡礼者であふれ、通常4万人いる人口が三倍以上にもなりました。
さらに、イエスの言葉と預言的行為が明らかになるにつれ、その聖都は頽廃と宗教的偽善によって損なわれていきました。
この都が著しく荒廃することを彼は警告しましたが、紀元70年にエルサレムがローマ軍によって徹底的に破壊されたときに、それは悲劇的にも成就しました。(マルコ13・1〜30)」
とても具体的で深く、そしてわたしにとっては時折、とても新しい視点で解説されていて、読んでいて多くの発見があります。
マタイ、ルカ、ヨハネについても書かれているようですので、翻訳されるのが楽しみです。
・・・・・・・・・・・・・・・・
先日の記事で「日本人には知らない人に挨拶をする習慣はない」ということを書きましたが、飛行機を降りる時に「これが日本人」と思ったことがありました。
わたしはいつも、空港内は車椅子でのサポートを頼むため、一番最後に飛行機を降ります。
そのため、全員が下りるまで座席で待つのですが、乗客一人ひとりに「ご搭乗ありがとうございました」と挨拶するCAさんに対して、ほぼ全員の日本人乗客が頭を下げていたのです。
おそらく、皆さんは「礼節を重んじた」というような感覚ではなく、自然とそうされたのではないでしょうか。
心と身体に染みついた、そうした自然な振る舞いが、日常生活の中でもっと表現されれば、と思うのです。
普通のこと
今回の滞在は長かったため、いろいろなことをじっくりと考える時間がありました。
先日、クロイスターズ美術館に行ってきました。
ここはメトロポリタン美術館の別館になっていますが、セントラルパークの中央あたりにある本館からはかなり遠く、マンハッタンの上の方にあります。
1934年から1938年にかけて、ヨーロッパの4つの修道院と3つの礼拝堂が、石材のままニューヨークへ運ばれ、再建され、ひとつの建物として生まれ変わりました。
それが、このクロイスターズ美術館です。
クロイスターとは、修道院の内部にある回廊のことです。
9歳の姪、シャーロットは、父親が入学させたかった学校に入るために、0歳の頃から一緒にクエーカーのミーティングに行っていました。
(わたしたちが日曜日に集まるのをミサ、という代わりに、彼らは日曜日の集まりをミーティングと呼んでいます。)
今回、クロイスターズ美術館でカトリックの美術品に囲まれて圧倒されたようで、「わたしも大きくなったらカトリックになりたい!」と言っていました。
「ミーティングではいつも何をしてるの?」
「ただ静かにみんなでお祈りをするのよ。」
「どんなことを祈ってるの?」
「みんなが幸せに、平和に暮らせますように、って祈ってる。」
「今度から、家族それぞれの幸せについてもお祈りしてみて!」
そんな会話をしました。
カトリック学校に配布されている『よき家庭』という季刊誌の昨年12月号に、森山司教様が寄稿されており、こう書いてありました。
何を中心にし、どこに生活の基盤を据えるのかはとても重要な課題です。
グローバリゼーション、さらにコロナの影響により、その場にいなくとも、オンラインで会議ができ、必ずしも対面で話す必要はなく、自室にいて世界中の人々と交信できることは、一昔前からすれば驚くべきことです。
しかしながら人は、やはり直に相手の顔や表情を見、その声を聴いて安心したり、より互いの理解を深め合ったりします。
「家庭は社会生活の第一の細胞」(カテキズム2207番)なのですから、今一度、家庭からすべてが始まり、生まれることを再確認してみてはどうでしょうか。
こうして外国に暮らす家族を訪ね、それぞれがどのような価値観のもとで生活しているかを実際に確認し、来て良かったと心から思います。
四旬節にあたり、改めて家族の大切さ、普通のことですが、これが1番大切なことなのだと再確認できました。
主よ、あなたはわたしの心を調べ、わたしを知り尽くしておられる。
あなたはわたしが座るのも立つのも知り、遠くからでも、わたしの思いを見通される。
あなたはわたしが歩くのも休むのも見守り、わたしの道をことごとく知っておられる。
わたしの舌に言葉が上る前に、
主よ、あなたはすべてを察しておられる。
あなたは後ろからも前からもわたしを庇い、
その手をわたしの上に置かれる。
(詩編139・1〜5)
もしニューヨークに行く機会がありましたら、クロイスターズ美術館にぜひ行ってみてください。
個人的な旅の中で感じた、信仰にまつわることを書いてきた1ヶ月でした。
お読みくださって、ありがとうございます。
自分を持つ
わたしが今回ニューヨークに来たのは、家族の今と将来を、自分の目と心で確認するためです。
妹は、ニューヨークに住むようになって30年近くになります。
今ではこちらで会社を運営し、2人の娘がいます。
もちろん日本でもそうですが、働く母というのはとても大変です。
5年ぶりに来ましたが、日本と同じく、物の値段が上がり(と言っても、全てが日本の倍以上の価格です)、ますます暮らすのが大変になっていました。
妹も洗礼を受けていますが、教会からは遠ざかっており、それも心に引っかかっていました。
わが子よ、わたしの言うことをよく聞け。
わたしの言葉に耳を傾けよ。
それをお前の目から離さず、お前の心のうちに保て。
それを見出す者には、それは命となり、その全身を健やかにする。
用心深くお前の心を守れ。
そこから、命の水が湧き出る。
ひねくれたことを言う口を、お前から取り去り、曲がったことを言う唇を、お前から遠ざけよ。
お前の目は前を見つめ、お前の視線を、お前の前に注ぐようにせよ。
お前の足の歩みに心を配り、お前のすべての道を堅く固めよ。
右にも左にもそれるな。
お前の足を悪から遠ざけよ。
(箴言4・20〜27)
(フリックコレクションで見た、ヴァン・ダイク作の作品です)
わたしは二つのことをあなたにお願いします。
わたしが死なないうちに、それをかなえてください。
わたしを不実と偽りから遠ざけてください。
わたしに貧しさも富も与えないでください
ただ、わたしに割りあてられたパンだけで、わたしを養ってください。
満ち足りると、わたしはあなたを否み、「主とは誰か」と、言うようになるでしょう。
また、貧しくなると、わたしは盗みをし、わたしの神の名を汚すようになるでしょう。
(箴言30・7〜9)
世界中から人が集まっている人種のるつぼであるこの街は、さまざまな問題を抱えており、貧富の差、人種差別はますますひどくなっているように感じます。
先日書いたように、教会といってもとても多くのプロテスタント宗派がありますし、心に不安を抱えてセラピーを受けるのも(金銭的に余裕があれば)普通のことです。
「人を養うのはもろもろの収穫物ではなく、あなたに信頼する人々を守るみ言葉である」と知恵の書にあるとおり(16・26)、この街では特に、自分をしっかりと持っていないと、不安と不満に押し流されそうになります。
妹もですが、彼女の友人たちも、世界中を移動して仕事をしている女性が多く、仕事と生活、子育てを担うのは本当に大変そうです。
今回、こうして長い時間をこちらで過ごしているのは、旅行ではなく、共に生活をしてみて確認したかったからなのです。
彼女たちが、自分をしっかりと持ち、信念を持って強く逞しく生きている様子を確認でき、安心しています。
わたしが知り得ただけの感覚ではありますが、彼女たちに共通していると感じるのは、「人を羨まず」、「自分の役割が明確で」、「常に先を見据えている」、と言うことです。
もしわたしがこの街に住むとしたら、信仰がなければ自分を見失ってしまうかもしれませんが、彼女たちからたくさんのことを学ぶ毎日に感謝しています。
慎み深く自尊心を保ち、自分の真価を知って自らを評価せよ
(シラ書10・28)
あなたに感謝をささげるために、日の出前に起き、暁にあなたに祈らなければならない
感謝を知らない者の望みは、冬の霜のように解け、無用な水のように流れ去る
(知恵の書16・28〜29)
聖書を持ってきて、本当に良かった!
1日に一度は聖書を開き、今日の糧となる言葉を探すことで、心の底から落ち着くことができるのはお恵みです。
余談ですが、この街に住む人は多くが外国から移住している人で、苦労して生きているからか、人に優しいと感じます。
イスラエルに行った時に、みんなが「シャローム!」と声をかけてくれたように、毎日何人もの人が小さく微笑みながら「ハァィ」と会釈してくれるか、「ハブ ア ナイス デイ!」と言ってくれます。
日本では、知らない人に挨拶をする、なんて習慣はありませんね。
来週は、少し遠くに家族で旅に出るため、このコラムはお休みさせていただきます。
キリスト教の芸術
メトロポリタン美術館に行きました。
日本で有名な絵画展があっても、写真撮影は出来ないことが普通ですが、こちらではOKです。
もちろん、その美術館の収蔵品だから、と言うこともありますが、例えば小学生が課外授業でクラスごと訪れていて、座り込んで写生していたりするのも普通の光景です。
とても1日では見て回れない数の展示品がありますので、見たいポイントを調べてから行かないと、疲れ果てるだけに終わる贅沢な美術館です。
わたしはいつも、同じ絵を見るために行くのですが、今回はこれらのキリスト教にまつわる作品を初めて見ました。
カトリック教会が芸術に力を入れるようになったのは、宗教改革に端を発しています。
トリエント公会議で、芸術は崇拝の対象ではないとの判断がなされ、建築や絵画が重要な位置を占めるようになって行きます。
絢爛豪華で力強い教会の建築を推し進め、教義の重要性を絵画や彫刻で語ることに力を入れていきます。
1506年に着工されたローマのサン・ピエトロ大聖堂はその事情を反映している、とウィキペディアにありました。
「聖人崇拝に好意的ではないプロテスタントへの反動で、多くの聖人画も描かれるようになりました。
カトリック教会が宗教美術の力を利用したのは現代でいうメディア戦略であり、「宗教画=目で見る聖書」によって、わかりやすく、そして劇的に信者の宗教心に訴え帰依させようとしたのです。」
と書いてある記事も見つけました。
事情はどうあれ、現代のわたしたちにとってこうしたキリスト教の芸術は、信仰の助けというよりは心の滋養に最適なものではないでしょうか。
こちらは、ニューヨーク最大のカトリック教会、セントパトリック教会です。
五番街の真ん中にそびえ立つ、豪華絢爛な聖堂です。
平日の午後に行ったのですが、平日は毎日3回のミサがあり、ちょうどその最中でした。
どういう事情でかはわかりませんが(わたしが日曜に行く近くの教会も同じで)、聖歌はみんなで歌わず、一人のプロのような人(おそらく、音大の学生)が声高らかに歌い上げます。
神がほんとうに地上にお住みになるのでしょうか。
天も、天の天も、あなたを包むことはできません。
わたしが建てたこの神殿などなおさらです。
しかし、わたしの神、主よ、あなたの僕の祈りと願いを顧み、今日、あなたの僕がみ前にささげる叫びと祈りを聞き入れてください。
どうか、あなたの住まいである天でこれを聞き、聞き入れてお赦しください。
(列王記上8・27〜30)
8章は、「あなたは天にあってこれを聞き」と繰り返し書かれている、『ソロモンの祈り』という箇所です。
ソロモンが豪華絢爛な神殿を建て、そこに神の櫃を置いた時、雲が神殿に満ちます。
「主は密雲の中に住む」、とソロモンは悟ります。
豪華な神殿も教会も、建物そのものは、わたしたちにとっての一つの祈りの場所にすぎないのです。
自分磨き
先日の記事で、各所で人材が不足しているということについて書きましたが、ここアメリカでも危機に瀕している教会があることを知りました。
今、ニューヨークにいます。
犬の散歩で近所を歩いている時、姪が「あの古い教会は、維持できなくなって売られて、中は素敵なアパートに改装されてるのよ」と、教えてくれました。
↑この古い教会は、外観をそのままに、今はアパートになっているのです。
ブルックリンは、ニューヨークの中でもとても教会が多い地区で、2ブロックごとに様々な宗派の教会があります。
↓こちらは、フレンチバプティストの教会
そして、こちら↓が、わたしが滞在する時にいつもミサに行くカトリック教会です。
(妹の家から歩いて10分の距離です。
歩いている途中に、4つのプロテスタント教会があります。)
QUEEN of ALL SAINTS CHURCH
学校が併設されている、とても大きな教会です。↓
ご存知の通り、ニューヨークはとても物価が高く、不動産を維持するのはとても大変です。
エアライツ(空中権=近隣のビルからの眺めを阻害しないように、これ以上建物の上を高くしないという約束)を売って、維持費を得ている教会もあるそうです。
韓国では多くの召命があるのに、とも嘆いたことを書いていましたが、12/14発表の韓国統計庁によると、韓国の出生率は2023年は0.72となり、2025年には0.65まで低下するとの推計だそうです。
少子化が社会問題である日本でさえ、2022年の出生率は1.26ですので、いかに韓国が危機的な状況かがわかります。
つまり、韓国の召命が日本のようになるのは時間の問題なのです。
ある神父様に「もう久留米教会に神学生が実習に来てくれることもない。日本の教会はどうなっていくのだろう」という愚痴を話していた時、こうおっしゃいました。
「以前わたしが教えたように、信徒それぞれが『信仰のセンス』を磨いていくしかないのですよ」
信仰のセンスについては、前にもここに書きましたが、大切なことですのでもう一度書いておきます。
大まかに、2つのセンスが必要となります。
①能力としてのセンス
・聖霊によって与えられた、神からの霊的な事柄を感じる能力
・神からの救いへの働きかけを感じ取り、受け入れる能力
・日々の生活の中で、神、キリストの永遠の救いについて、自分なりの考えを見出す能力
②理解としてのセンス
・神の啓示について、各人が理解して得る意味
・人がそれを他者に表現するとき、信仰の知識として顕になるもの
どうですか?
難しい、と感じられたかもしれません。
でも、全てのセンスを持っている、と断言できなくとも、どれも薄っすらとは分かっているものではないでしょうか。
「今日、わたしがあなたに命じるこの命令は、あなたにとって難しすぎるものでも、遠く及ばぬものでもない。
それは天にあるのではなく、海の彼方にあるのでもないから、『誰がわたしたちのために天に昇り、海の彼方に渡り、それを取って来て、わたしたちが行うように、それを聞かせてくれるのか』と言うには及ばない。
実に、言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口と心にあるのだから、あなたはそれを行うことができる」。
(申命記30・11〜14)
ローマ10章に引用されている箇所です。
司祭の数が足りない、少子化が心配だ、と嘆く前に、「わたし」に授けられている「言葉」を自覚する必要がある、と言うことです。
信者としての自分のセンスを、それぞれが磨くのです。
信仰のセンスは、個人の生き方で現されるものです。
上に書いた5つのポイントを意識して生活してみるといいですね。
わたしたちの信仰のセンスが磨かれれば、自然とその背中を見た若者の気持ちが芽生えてくれるかもしれません。
人の痛み
いつも、ここに書くことの基礎は、その週に起こった出来事や考えたことを信仰に結びつけています。
皆様は、今週はどのような日々でしたか?
何か、考えさせられることや、気になることはありましたか?
わたしは、「病気」についてずっと思いを巡らせていました。
以前から何度か書いたことのある、ある神父様から依頼を受けて支援を続けている方のことです。
彼に何かあると、決まって『虫の知らせ』があり、心に引っ掛かるものが湧き、連絡を入れるのです。
また、負のスパイラルに陥っていました。
いくつかの身体的な病気を患っているのですが、根本的な問題は、アルコール依存症です。
身体に不調があると入院し、病院にいる間はお酒が抜けることで精神的に軽やかになります。
信仰を持っていること・神父様とわたしに気にかけてもらっていることへの感謝に満ち、お電話をくださり、優しい言葉で会話をすることができます。
家に戻ると、そのうちまたお酒に浸るようになり、生かされていることの意味を問うようになり、自暴自棄になってしまうのです。
弟子たちはイエスに尋ねて言った、「ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか。
この人ですか。それともこの人の両親ですか」。
イエスはお答えになった、「この人が罪を犯したのでもなく、この人の両親が罪を犯したのでもない。
むしろ、神の業がこの人のうちに現れるためである。
わたしをお遣わしになった方の業を、
わたしたちはまだ日のあるうちに行わなければならない。
誰も働くことのできない夜が来る。
世にいる間、わたしは世の光である」。
(ヨハネ8・2〜5)
その方が、わたしにこれまで何度もおっしゃいました。
「どうしてわたしを見捨てないんですか。」
わたしは、「神父様から頼まれているからよ。わたしはあなたのことを見捨てませんよ。」とお答えします。
彼のために働くこと、それはわたしに神様がお与えくださった、一つの使命だと思っています。
彼の痛みが、なんとなくですが、わかるのです。
恐らく、わたしたちは誰も、同じような罪を繰り返し犯しているのではないでしょうか。
アルコール依存症は病気です。
それは、罪ではありません。
生かされている意味を疑うこと、それが罪だと思うのです。
病気、それも、本人に治す気があれば治る病気なのに、、、、とずっと考えています。
以前、その神父様から教わったことの一つに、「ある宗教的な体験によって自分が変えられた、という誰かとの出会い。その時を持っていることは幸いだ」というものがあります。
イエス様が十字架の死を予告される場面でおっしゃる言葉があります。
『父よ、わたしをこの時から救ってください』
いや、このために、この時のためにこそ、わたしは来たのである。
(ヨハネ12・27)
「この時」
誰かとの出会いがその人を救う、そのことはイエス様にとっての「この時」である、と教えてもらいました。
その方が、わたしとの出会いをきっかけに変わってくれるのを何年も待っているのです。
旧約の「難解さ」が好きなので、いつも好んで旧約を読むのですが、今回はこの記事を書くにあたって、書簡を読み返してみました。
書簡はストレートに心に入ってくる文章が多く、読んでいてワクワクします。
律法全体は、「隣人を自分のように愛せよ」という一句を守ることによって果たされます。
わたしたちは霊の導きに従って、生きているとするなら、また、霊の導きに従って前進しましょう。
機会あるごとに、すべての人に、特に、信仰によっていわば家族となった人々に対して、善を行いましょう。
(ガラテヤ5・14、23、6・10)
聖霊が言っておられるように、「今日、もしあなた方が神の声を聞くなら、心を頑なにしてはならない」。
あなた方のうち誰一人罪にまどわされて、頑なになる者がないように、むしろ、「今日」という日が過ぎ去らないうちに、毎日、互いに励まし合いなさい。
「今日、もし、あなた方が神の声を聞くなら、心を頑なにしてはならない、神に背いた時のように」。
(ヘブライ3・7、13〜15)
「この時」
「今日」
いずれも、神様がわたしたちに語りかけ、働きかけてくださる瞬間です。
人の痛みを感じるならば、神様が「働きなさい」と背中を押しているのだ、ということを忘れないように。
・・・・・・・・・・・・・・
2年間、久留米教会で司牧実習をしてくれた神学生のホンくん。
28日が最後のミサでした。
いよいよ、3/20に長崎で助祭に叙階されます。
久留米教会からも、バスを借りてみんなで叙階式に参列させていただこうと計画しています。
ホンくんは、韓国から来て日本で神学校に行き、長崎教区で叙階されます。
彼のために祈りましょう。
(彼の送別会を兼ねたバーベキューだったのに、彼が1番働かされていました!)
人のちから
「人材不足」、経済活動において今一番重大な問題です。
「置き配」や、飲食店でのタブレットや携帯からのオーダーなど、さまざまな工夫で、業界とユーザー相互で解決できることもあります。
JALの次期社長が初の女性になることは、業界の人材不足解消の一助になるでしょう。
防衛省が、自衛隊の男性隊員への「丸刈りルール」・女性隊員への「ショートカット推奨」を廃止することを発表しましたが、これも人材不足の対策のひとつだそうです。
カトリック教会においても、司祭不足が懸念されています。
将来、「告解はAIが担当します」とお知らせに載る日が来たら、、、。
お隣の韓国では、毎年多くの神学生が召命を受け、司祭を日本に派遣していただけるほどです。
なにがこれほどの違いを生じさせているのでしょうか。
「1月15日、アメリカ大統領選挙の共和党公認候補のアイオワ州選挙でトランプ元大統領が圧勝」、というニュースがありました。
人口の約 90% が白人で、エヴェンジェリカル(福音派)が主流という土地柄の影響が大きいとはいえ、(能力や人柄は置いておくとして)(良くも悪くも)「あれほど分かり易くて、あれほどパワーがあれば、きっと何かやってくれるに違いない!」という期待を抱かせるのは、なんとなくわかる気がします。
歴史に残る時代は、その時を象徴するような人のちからによって形成されます。
世界が混沌とし、明るいニュースが聞かれない今、希望の光となる救い主が必要だ、と思うのは極端でしょうか。
現代社会に必要な人とは、どのような人でしょうか。
先週ご紹介した本には、アッシジの聖フランチェスコについても少し記述がありました。
フリードリッヒ2世と同年代に生きたフランチェスコのことを、塩野さんは「ルネッサンスの第一走者」と書いていらっしゃいます。
おそらくフランチェスコは、当時相当な変わり者として見られていたはずです。
(親からもらったものは置いていく、と着ていたものを脱ぎ捨てて家を出て、鳥と話していたんですもの・・・)
1182年生まれのフランチェスコの説いたことは、当時のキリスト教界では革命的なものでした。
教皇たちの豪華絢爛ぶりをよそに、清貧であることの尊さを説き、キリスト教の神は、これまでに言われてきたような厳しく罰を与える神ではなく、優しく包み込む愛の神であると初めて説いたのは彼です。
そして何より彼が行った革命は、利潤追求を目的とした工業、商業に専念する人々をも修道僧として受け入れ、組織としてまとめたということです。
修道僧だけでは社会は存続できない、そのためには資金が必要である。
貧しい人、不幸な人に精神的にも物質的にも援助を惜しまない商売人も、修道会へ寄付をすることで信者としての義務を果たし、時には修道僧として共に生活を送ればよい、というのです。
合理的な支援の仕方です。
彼自身が商人の息子であるから生まれた考えでしょうが、お金儲けをする『働く人』(当時の第三階級)が修道士としても『祈る人』(第一階級)となれる、という発想は、当時『働く人』が持っていた劣等意識を取り払ったのです。
塩野さんは、「資本主義はフランチェスコから始まった」とおっしゃいます。
2000年前に人々を導いたイエス様、800年前に活動した聖フランチェスコ、彼らは文字通りの救い主でした。
わたしたちの悪行がわたしたちに不利な証言をしても、
ああ、主よ、
あなたの名のために、何かを行ってください。
まことに、わたしたちの離反ははなはだしく、
わたしたちはあなたに罪を犯したのです。
ああ、イスラエルの希望、困難の時に救ってくださる方よ、
あなたはどうして、在留の他国の者のようにこの地におられ、
一夜だけ宿った旅人のようなのですか。
あなたはどうして無力で、
救うことのできない勇者のようなのですか。
それでも、主よ、
あなたはわたしたちのただ中におられ、
わたしたちはあなたの名によって呼ばれているのです。
わたしたちを見捨てないでください。
(エレミヤ14・7~9)
現代をバビロン捕囚の時代に例えてみると、現状を引き起こしたのは頑なで利己主義に陥ったわたしたちの問題であり、それを神様が嘆いておられる姿が浮かび上がってくるようです。
救い主をじっと待つのではなく、わたしたち一人ひとりのちからが試されているような気がします。
主は憐れみ深く正しい方、
罪人に道を示し、
貧しい人を正義に導き、
へりくだる者にその道を教えてくださる。
主よ、わたしの咎は大きいが
み名の誉れのために赦してください。
主は、その人に選ぶべき道を示してくださる。
(詩編25・8、9、11)
貧しく、へりくだる人
わたしたち一人ひとりが自分の罪を認めて、今自分が選ぶべき道を正しく進むことができますように。
聖なるもの
気温はマイナスでも、気持ちの良い青空の日曜の朝でした。
毎週日曜日の朝、教会で皆さんと言葉を交わし、一緒に歌い祈り、そうして過ごせることの喜びをひしひしと感じました。
被災地の教会の被害状況に心が痛みます。
1日も早く、被災された方、海保のパイロットの方に笑顔になれる時間が訪れますように。
・・・・・・・・・・・・・
去年からハマって読んでいるのが、塩野七生さんの本。
何冊か読んでみましたが、飛びぬけて面白く、皆さまにお薦めしたい本はこちら。
本好きの友人から、「現代のクリスチャンが、安全にイスラエルに聖地巡礼に行けるようになった基盤を作ったのは誰か知ってる?」と、この本を薦めてもらい、昨年の秋から読み始めました。
その時は、まだ現在の戦争状態が起きる前でしたので、まさか「もう二度と行けないかもしれない」という状況になるとは思ってもみませんでした。
塩野さんは、本を書く際にはかなり綿密な調査をされることでも知られています。
豊富な知識と徹底した資料収集から構築される中世ヨーロッパの歴史は、まるで彼女がその世界に生きていたのかと思わせるものがあります。
友人の質問、「誰がキリスト教徒の聖地巡礼を可能にしたのか」。
それが、神聖ローマ帝国皇帝のフリードリッヒ2世です。
当時のキリスト教世界には、ローマ教皇と神聖ローマ帝国皇帝という、2人の最高指導者がいました。
ローマ教皇は神の代理人とされ、精神上の最高位者
ローマ皇帝は、ヨーロッパのキリスト教世界における世俗の最高位者
『教皇は太陽、皇帝は月』という有名なフレーズは、悪名高き教皇、インノケンティウス3世の残した言葉です。
幼くしてシチリア王国の国王になったフリードリッヒの後見人が、この教皇でした。
(当時は各地方が自治権を持っており、イタリアやギリシャ、という国は存在していません。)
当時の歴代ローマ教皇は、長年にわたってイスラム教徒の支配下にあったエルサレムの奪還が最優先事項であると考え、執拗に十字軍を送ります。
一方で、フリードリッヒはあれやこれやと理由をつけて、十字軍への参加を拒み続けていました。
それは、彼の「平和裏に聖都返還を実現したい」という思いからでした。
1228年、フリードリッヒは第六次十字軍を率います。
軍を率いたのは、あくまでも抑止力としてでした。
その前の第五次十字軍には、アッシジのフランチェスコも修道士として参加していることをご存知でしょうか。
フランチェスコもまた、平和のうちに交渉しようとして、スルタンにキリスト教に改宗するよう迫ったのです。
もちろん、そのような言葉での外交がうまくいくはずは無く、その場で殺されてもおかしくなかったのに、笑い飛ばされて追い返されています。
それに対し、フリードリッヒは聖地でのキリスト教徒の存続の保障を話し合うために、軍を率いてヤッファ(現在のテル・アビブ)に向かいます。
対するスルタン、アル・カミールは、離宮のあったガザにて待ち構えます。
二つの街を双方の使者が行き来して、四か月で講和が成立しました。
その項目の一つが、「キリスト教側の領土であろうとイスラム側の領土であろうと関係なく、巡礼と通商を目的とする人々の往来は、双方ともが自由と安全を保証する」というものでした。
今では大都会であるテル・アビブとイスラム教徒のパレスチナ人が追いやられているガザが、この平和交渉の舞台であったという事実に驚きを感じませんか?
なぜ交渉が成立したか、その内容に教皇が激怒したこと、などはぜひお読みいただくとして、わたしたちキリスト教徒にとって聖なるものが、同じように、イスラム教徒にとっても聖なるものなのだ、ということを痛感させられる本でした。
まことに、教えはシオンから、主の言葉はエルサレムから出る。
主は、諸国の間を裁き、多くの民の仲裁を行われる。
彼らはその剣を鋤に、槍を鎌に打ち直す。
国は国に向かって剣を振りかざすことなくもはや戦うことを学ばない。
(イザヤ1・3〜4)
わたしたちの生きている現在も、いつか歴史として語られる大きな転換点かもしれません。
例えば、イスラエルの不安定な状況。
エルサレムがイスラム教・ユダヤ教・キリスト教のいずれかに独立支配されているわけではないのに、巡礼すらままならないということ。
元日の地震で、石川県の海岸では4メートルも隆起している箇所があり、これは数千年に一度の現象であること。
塩野さんの文章に、こんなことが書いてありました。
歴史を書きながら痛感させられることの一つは、情報とは、その重要性を理解できた者にしか、正しく伝わらないものであるということだ。
十字軍の歴史一つとっても同じで。この点では、キリスト教徒であろうとイスラム教徒であろうと、まったくちがいはない。
古代ローマの人である。ユリウス・カエサルも言っている。
「人間ならは誰にでも、現実のすべてが見えるわけではない。
多くの人は、見たいと欲する現実しか見ていない。」
情報を活用できるのは、見たくない現実でも直視する人だけなのである。
それでも、主はお前たちに厚意を示そうとして待っておられ、
それでも、お前たちを憐れもうとして立ち上がられる。
まことに、主は公正の神。
主を待ち望むすべての者は幸い。
主は、お前が大地に蒔く種のために雨を与え、大地が産み出す食物は豊かで滋養に富む。
その日、お前の家畜は広い牧場で草をはみ、大地を耕す牛やろばは、シャベルと三又で選り分けて発酵させた飼い葉を食べる。
大いなる殺戮の日、塔の倒れる時には、すべての高い山、そびえたつ丘の上に、水のほとばしる流れができる。
主が民の傷口を包み、その討たれた傷を癒やされる日、月の光は太陽の光のようになり、太陽の光は七倍にもなって、七日分の光のようになる。
(イザヤ30・18、23〜26)
弱った手を強くし、ふらつく膝をしっかりさせよ。
心に不安を抱く者たちに言え、
「強くあれ、恐れるな。
見よ、お前たちの神を。
報復が、神の報いがくる。
ご自身がこられ、お前たちを救ってくださる」。
(イザヤ35・3〜4)
宮﨑神父様がお説教で、「聖書にある言葉で1番好きなのは、恐れるな、というものです。わたしたちが選んで洗礼を受けたのではなく、神に選ばれたのだということを心に刻みましょう。」とおっしゃいました。
2024年の始まりに起きた日本の災害だけではなく、終わりの見えないウクライナの戦争とイスラエルの戦争、世界各地で起きている現実を直視し、今を生きる自分にできることは何かを自問自答したいと思います。
神様を探して
明けましておめでとうございます。
いつもお読みくださってありがとうございます。
今年も、日常の出来事の中から気づいたことや考えたことを基本に、聖書にその答えや解決のヒントとなる教えを見出していけるような記事を書いていきたいと思います。
年明け、「さて、今年最初の記事は抱負となるような聖書のことばを書こうかな」と思っていた矢先に、大きな災害が発生しました。
元日からこのようなことが起きるとは、驚きと苦しさで、何も考えられなくなっていたところ、2日の夕方のあの航空機事故による大火災の映像。
テレビで「共感疲労」を感じて辛くなっている人が多い、と言っていましたが、まさにわたしがその状態に陥っています。
主の公現のお祝いを迎えたわたしたちキリスト者は、神様を見つけたと喜びに満ちていますが、被害に遭われた方々は、「神はどこにいるのか」と辛い気持ちを抱えられているのではないでしょうか。
「今日もまた、わたしは反抗的に嘆き、神の手は、わたしの呻きの上に重くのしかかる
ああ、神に会える所が分かれば、わたしはそのみ座まで行きたい。
わたしは神の前にわたしの訴えを並べ立て、口を極めて論じたい。
わたしは神がわたしにお答えになる言葉を知り、何と仰せになるかを悟るだろう。
神は大いなる力をふるって、わたしと争われるだろうか。
いや、神はわたしの言葉をお聞きになるだけだろう。
そこでは、正しい者が神と論じ合う。
そうすれば、わたしはわたしを裁く者から永久に追放されるであろう。
だが、わたしが東に進んでも、神はそこにおられず、
西に進んでも、
わたしは神を見つけることができない。
北を探しても、わたしは神を見つけられず、
南に向きを変えても、
わたしは神を見ることができない」。
(ヨブ23・2〜9)
奥様と幼いお子さん2人を亡くされた方が、インタビューに答えてこうおっしゃっていました。
「目の前で命が絶えていく子どもを見ながら、何もできなかった父親の気持ちがわかりますか?
この怒りをどこにぶつけたらいいかわからない。
違うとわかっていても、人のせいにする気持ちしかわかない。」
神様なんかいない、きっとそういう心境になられているでしょう。
その方のために祈りたい、と心から思いました。
神はあなたを困難の中から誘い出し、
束縛のない広い所に導き、
あなたの食卓を脂ぎった物で整えられます。
(ヨブ36・16)
フランシスコ会訳聖書の解説によると、この箇所は、神がヨブにその苦しみ悩みから逃れて豊かになり、喜びの生活に戻る機会を与えてくださることを意味しているのだそうです。
被災された方々のうち、どのくらいの方が何かの宗教を信仰されているでしょうか。
祈る気持ちの余裕も気力も失われているかもしれません。
神か仏がいるのなら、自分たちがこんな目に遭うのはなぜなのか、という気持ちかもしれません。
わたしは今、家族、友人、そして家さえも失った方々のために祈ることしかできません。
適切な言い方ではないかもしれませんが、一人だけ生き残られた海上保安庁の飛行機のパイロットの方のためにも祈っています。
なぜ自分だけ生かされているのか、自分を責めてしまわれているのではないか、そう思うと、苦しくて心が張り裂けそうです。
1日のうち、ほんの少しでも笑顔になれる時間がありますように。
1日でも早く、心が落ち着く日が戻りますように。
神よ、あなたはわたしたちを見放され、わたしたちを打ち破られました。
あなたは怒っておられました。
わたしたちの所に戻ってください。
あなたは地を震わせ、それを裂かれました。
裂け目を直してください、地が揺れ動くのです。
あなたはご自分の民をつらい目に遭わせ、足をふらつかせる酒をわたしたちに飲ませられました。
あなたを畏れる者たちに旗を掲げ、彼らを弓矢からその旗のもとに逃れさせてください。
(詩編60・3〜6)
神よ、わたしの叫びを聞き、わたしの祈りを心に留めてください。
心が弱り果てるとき、わたしは地の果てから、あなたに呼び求めます。
わたしを高い岩に導いてください
あなたはわたしの逃れ場。
とこしえにあなたの幕屋にわたしを住まわせ、あなたの翼の陰に逃れさせてください。
(詩編61・2〜5)
神よ、わたしを救いに来てください。
主よ、急いで助けに来てください。
神よ、わたしのもとに急いでください。
あなたはわたしの助け、わたしの救い主。
主よ、ためらわないでください。
(詩編70・2、6)
・・・・・・・・・・・・・・・
今年は、2人の新成人のお祝いを執り行うことができました。
日本の将来を担う彼らの上に、豊かなお恵みが注がれますように。
救いの時
主の御降誕おめでとうございます。

主は、アハズに重ねて語られた、「お前の神、主に徴を求めよ。陰府の深みに、また天の高みに」。
しかし、アハズは言った、「わたしは求めません。主を試みるようなことはしません」。
そこで、イザヤは言った、「ダビデの家よ、開け。あなたたちは、人間を煩わせるだけでは足りず、わたしの神までも煩わせるのか。
それ故、主ご自身が、あなたたちに徴を与えられる。
見よ、おとめが身籠って男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。
(イザヤ7・10〜14)
インマヌエル、わたしの洗礼名です。
キリスト者であることを自覚するべく反省する時などには、この霊名を思い返すようにしています。
与えていただいた名前、これがわたしの誇りです。
神様がわたしたちに与えてくださった徴、それは救いの象徴です。
わたしのいとしい方は、わたしに語りかけて言われます、
「わたしの愛する人、立ちなさい。
美しい人、出ておいで。
冬はさり、雨はやんで、もう去った。
大地には花が咲き乱れ、歌の季節がやって来て、山鳩の鳴き声が、わたしたちの国じゅうに聞こえる。
いちじくの木は初なりの実をつけ、花を咲かせたぶどうの木は香りを放つ。
わたしの愛する人、美しい人よ。
さあ、立って、出ておいで。
(雅歌2・10〜13)
雅歌は、紀元前4〜3世紀の間に書かれたとされており、ヘブライ語本では「歌の歌」と言う表題で、数ある歌の中でも最も美しい歌であるという意味が込められています。
花婿はイスラエルの民を愛する主なる神で、花嫁は主を愛するイスラエルの民
あるいは、キリストと教会、神と聖母マリア、キリストとキリスト者を当てはめて解釈されることもあります。
そう思ってこの歌を読み返すと、その美しさがさらに増すように感じます。
祈り続け、ようやく身籠って産まれたサムエルを、ハンナは主に捧げます。
「祭司さま、あなたの命に懸けて申します。
わたしはここであなたの傍らに立って主に祈っていた女でございます。
この子が授かるようにと、わたしは祈り、主はわたしの願いを聞き入れてくださいました。
ですから、わたしもこの子を主に委ねます。
この子は生きているかぎり主に委ねられたものです」。
(サムエル上1・26〜28)
「主に委ねる」、という表現が心にしみます。
(聖書の表記で、「」。というのが好きです。
大切なことを語り終えて、。で心を止める、という感じがしませんか?)
以前、悩んでいたことを友人に相談したところ、彼女が「神様にすべてを明け渡すしかないよ」とアドバイスをくれました。
目が開かれる思いでした。
すべてを「主に委ねる」ことは、何もせずにほおっておくこととは違います。
以前も書いたように、自分にできることをしたうえで、神様のお導きを信頼して待つのです。
24日の朝のミサで、宮﨑神父様がおっしゃいました。
「どのようなことが起きても、いつでも全てを主に委ねると言うマリア様の信仰を思い、アベマリアの祈りを祈っていますか?
神に全てを委ねる信仰は、覚悟を持つと言うことです。」
今年のクリスマスは、なにか、心が落ち着かないままで迎えてしまいました。
ひとつには、イスラエルで起きていることのためです。
新聞報道によると、ガザで食料配布用のトラックが襲われ、人々がトラックの荷台に乗って食料を奪い、その場でむさぼるように食べていた、といいます。
避難所では水は1日1人当たり1.6リットル、トイレは486人に1つ、感染症も急増しているそうです。
犠牲者が増える一方で、同時に生存者も、食料・水・燃料がなく、生きる希望を失っています。
希望の季節を迎えたキリスト教会のわたしたちは、救いのない状況を強いられている人々の現状を、ニュースの世界のこととして傍観してはなりません。
このような時に、どうこの気持ちを表したらいいかと考えていたところ、ローマの船津神父様のFacebookにその答えをみつけました。
現在バチカンに展示されている「100の飼い葉桶」について、船津神父様はこう書いていらっしゃいました。
「様々あって面白い。
しかし一番強烈で心が痛むのは、今年、聖地ベツレヘムの教会に置かれている、瓦礫の中のイエス。
絶望、争い、悲しみ、恐れの世にイエスは生まれてくる。
希望、平和、喜び、愛として。」
みなさま、よい年末年始をお過ごしください。
ことば、沈黙
久留米教会の建物正面に、新しいステンドグラスが設置されました。
久留米市の市木のひとつである椿と、伝統工芸の久留米絣をモチーフにしたものです。
教皇フランシスコのお告げの祈りでのお言葉です。
沈黙と祈りを通してのみ、わたしたちは御父のみことばであるイエスに耳を傾け、空虚なことばやおしゃべりから自由になることができるだろう。
それは、キリスト教生活の本質的要素である。
声は、わたしたちの考えや心の思いを表す道具である。
ならば、それが沈黙と大変関連していることがわかるだろう。
なぜならば、声は自分の内部で成熟したもの、聖霊の促しに耳を傾けることで得たものを表現するからである。
沈黙できないならば、意味ある言葉を話すのは難しいだろう。
それに対し、より注意深く沈黙すればするほど、言葉はより力あるものになる。
さあ、自問しよう。
自分の一日において、沈黙はどういう位置を占めているだろうか。
それは虚しい、あるいは重苦しい沈黙だろうか、それとも傾聴と祈りの空間、心を守る場所だろうか。
わたしの生活は節度を保ったものか、それとも無駄な物ごとであふれているのか。
わたしは父との二人暮らしですので、実際に家の中が静寂に包まれる時間があります。
小さなお子様のいるご家庭では難しいことですが、そうした静寂の中で沈黙し、じっくりと自分を見つめることも好きな過ごし方です。
パパ様のおっしゃる、「声は、わたしたちの考えや心の思いを表す道具である」ということについて考えました。
最近は、人とのやり取りはもっぱらLINEで、というのが当たり前になっています。
わたしも、よほど緊急でなければ、友人との連絡はLINEばかりです。
もちろん、実際に会って顔をみて話をするのが、人と人とのコミュニケーションとしては理想です。
一方で、LINEに伝えたいことを書く際には、少し考えて、言葉を選びながら、できるだけ短く、と心がけることもできます。
現代社会においては、発することばもLINEに書いた文字も、それはわたしたちの「声」です。
わが子よ、わたしの言うことをよく聞け。
わたしの言葉に耳を傾けよ。
それをお前の目から離さず、お前の心のうちに保て。
それを見出す者には、それは命となり、その全身を健やかにする。
用心深くお前の心を守れ。
そこから、命の泉が湧き出る。
ひねくれたことを言う口を、お前から取り去り、曲がったことを言う唇を、お前から遠ざけよ。
お前の目は前を見つめ、お前の視線を、お前の前に注ぐようにせよ。
お前の足の歩みに心を配り、お前のすべての道を堅く固めよ。
右にも左にもそれるな。
お前の足を悪から遠ざけよ。
(箴言4・20〜27)
心を守れ、という表現には、とても深いものを感じます。
心は、わたしたちの生活を支配する中核であり、心の動きによって身体全ての活動が促されるのです。
ひねくれたこと、曲がったことをことばや文字にして発すれば、相手だけではなく自分自身にもダメージがあります。
箴言の著者は、「主の言葉に耳を傾け、常に前を見つめ、歩みを強固にすることで、命の泉が湧き出る」と教えてくれています。
口数が多ければ罪を避けられない。
しかし、口を慎む者は賢い人。
(10・19)
人は、その口から出る言葉によって、善いものに満ち足りる。
(12・14)
慰めの言葉は命の木。
乱暴な言葉は魂の痛手。
(15・4)
言葉に心を留める人は喜びを見出す。
主により頼む人は幸い。
(16・20)
言葉を慎む者は知識ある人。
冷静な心を保つ者は理性ある者。
(17・27)
直接会って、適切なことばで会話ができない不安があるならば、黙って見守ることも時には必要かもしれません。
わたしはかなりズバッと相手に言うタイプなので、この格言を書いた紙をお財布に入れて持ち歩いていた時期があります。
Wisdom has two parts,having words to say and not saying it.
知恵には二つの面がある。
言うべきことを持つこと、それを言わないこと。
どこで見つけたものかは忘れましたが、今思えば、おそらく聖書から来ているのではないかと。
本当に大切だと思うことは、一度沈黙し、言うべきことを相手に伝えるかどうかを吟味し、できれば顔を見て伝えるように心がけています。
率直な戒めは、ひそかな愛に勝る。
友人の与える傷は真実なもの、敵の口づけは偽り。
(27・5〜6)
マタイ26・48にある、ユダのイエスへの口づけを想起させる箇所だ、と教わりました。
自分に対して友人がそうしてくれるように、わたしも、相手に伝えるべきだと思ったことは丁寧に対応するようにしているつもりです。
冒頭のパパ様のお話を、是非もう一度お読みください。
空虚なことばやおしゃべりに支配されないよう、沈黙の時間を大切にしたいものです。

心に潤い
ネットのニュースで見つけたお話です。
1688年に建立された長崎の曹洞宗のお寺、天福寺。
貧しく、本堂の床は抜け落ちそうで、天井から雪が舞い込むほどで、檀家に修復費用を募っていました。
このお寺は、キリスト教が禁止され厳しい取り締まりがあった江戸時代に、危険を冒して潜伏キリシタンを受け入れ、マリア像を本堂に隠し、彼らを積極的にかくまっていた歴史があるそうです。
1978年、少し離れた地区に住むカトリック信徒の人々が訪れ、「私たちは潜伏キリシタンの子孫です。お寺のおかげで信仰と命をつなぐことができました。少しでも恩返しがしたい。」と、400万円ほどの寄付を申し出たというのです。
寄付を申し出たカトリック信者たちは30人ほど。
その理由をこう語ったそうです。
「天福寺に何かあったときは助けるようにと、いろり端で代々、伝えられてきたから」
見返りを求めずに、お互いが助け合ったのです。
先日、友人にこう言われ、ハッとしました。
「あなたは人に見返りを求めている。
見返りを求めずに、相手に与えることを喜びとしたら、
相手から優しい言葉と行動が自然と出てくるよ。」
その通りだと思います。
災いだ、悪を善、善を悪と言い、
闇を光、光を闇とし、
苦いものを甘い、甘いものを苦いとする者たちは。
災いだ、自らを知恵ある者とみなし、
自分一人で賢いと思っている者たちは。
(イザヤ書5・20~21)
マタイ5章の「幸いだ~」は、このイザヤ書が元となっています。
今のわたしは、まさにこの戒めがあてはまります。
自信過剰になりすぎ、人に認められたい、褒められたい、という傾向があるわたしを、この友人はハッキリと戒めてくれました。
その夜、開いた聖書にこのイザヤ書の文章を見つけ、さらに反省の念を深めたのでした。
おそらく以前のわたしでしたら、友人からこれほど鋭く指摘されたら、落ち込んでしまい、くよくよ考え込んでいたでしょう。
ですが、こうしてホームページの記事を書くために頻繁に聖書を開く習慣が根付いた今のわたしは、見つけた聖句から心に潤いを得ることができるようになりました。
耳の痛い指摘も、聖句を通して心に刻むようにしています。
求めていたことばを聖書に見つけた時の喜び。
心の眼が開かれる感覚。
気づかせてくださってありがとうございます、と湧きあがる気持ち。
新約聖書にも素晴らしい教えがありますが、旧約の面白さを教わったわたしは、聖書を開くときは旧約の、3000年前の人々の感覚に魅力を感じるのです。
わたしの日常に潤いを与えてくれるのは、聖書、芸術、音楽なのです。
もし目が見えるなら
お母さんの顔が見たいです
僕は目が見えないのに
お母さんは美術館に行って
絵のことをたくさん話してくれました
美しい空や美しいもの
風のささやきを心の眼で感じられるのは
母の影響です
目は見えなくても心の眼は見えているので満足している
だから、今から見えるようになりたいとは思わない
見えなくてもいい
だけどもし一瞬でも見えるなら
お母さんの顔が見たいです
ピアニスト辻井伸行さんのことばです。
母親が子どもに愛を無償で与えるのは当然かもしれませんが、これほど愛を注ぎ、子どもがそれを受け止めてタレントを広げている関係に、胸が震えます。
辻井さんが13年前の演奏会の時にアンコールで披露したオリジナル曲、「コルトナの朝」の演奏をお聴きください。
「イタリアの美しい田舎町、コルトナを旅した時に作った曲」というナレーションも、辻井さんだから、その景色が目で見えなくてもこれほどの美しい曲が生まれるんだ、と納得できます。
「みなさんに感動していただけで、僕も大満足です」という彼のことばが、今のわたしには特に感動的でした。
(アンコール曲の演奏は、ビデオ開始から1分ほどで始まります。)
残りの日々を
待降節が始まり、今年も残りひと月となりました。
今年のアドベントクランツは、このような感じに作りました。
2023年12月の教皇の祈りの意向は「障がい者のために」とされています。
わたしたちの間で、最も不安定な立場の人たちの中に、障がいのある方々がいます。
彼らの中には、無知や偏見に基づく拒絶にあい、疎外感を体験する人もいます。
社会制度は、教育、雇用、また創造性を発揮できる場所へのアクセスを通して、彼らの計画を支えなければなりません。
障がい者の受け入れを促進する計画やイニシアチブが必要です。
その中でも特に、付き添うことを望む人の大きな心が必要です。
それは、社会においても、また教会生活においても、様々な能力を持ったこれらの人たちの貢献と才能に対して開かれたものとなるように、わたしたちのメンタリティーを少し変える必要を意味しています。
それゆえに、完全にバリアフリーの小教区を作ることは、物理的なバリアを取り除くことを意味するだけではありません。それはまた、「彼ら」について話すのをやめて、「わたしたち」について話し始める必要があると理解することでもあるのです。
ちなみに、障害者、障碍者、障がい者、という日本語表記については、様々な意見があります。
わたしは、障害者のままで問題ないと思っています。
◆「障害」というのは障害者本人ではなく社会の側の障害のことであり、障害者は社会にある障害と向き合っている人たちだという考え
◆「障害者の気持ちを汲んで労る」という気遣いは、少々見当違いであり、現実的な社会の障害を取り除くことのほうが大事
英語では、disability(能力不全の意味)となります。

イエス様は、病気の人、障害のある人、やもめ、孤児など、社会的弱者であった人々を特に大切にされていました。
一般的に恵まれていた人よりも、恵まれていない人々の方がその恵みを受けていたのです。
わたし自身が身体に障害があるのであえて言うのですが、disability=できないことがあるから、周囲の人に助けてもらえる場面がよくあります。
いつも、知らない方が手を差し伸べ、肩を貸してくださり、心を配ってくださる方がどのような場面でもいてくれるのです。
わたしは本当に恵まれている、と思います。
障害がある、というのは、わたしのように誰が見てもわかる人とそうでない場合があります。
だれもが、必要に応じて、手を差し伸べ合うことが出来れば、と思うのです。
トビト記は、敬虔なイスラエル人のトビトと妻サラ、息子トビアの物語です。
トビトが息子に遺言のような話をする場面です。
息子よ、わたしが死んだら、丁重に葬ってくれ。
母を敬い、母がこの世にある間、その傍らを離れてはならない。
母の喜ぶことをし、何事にせよ、母の心を悲しませてはならない。
息子よ、お前がまだ胎内にいたころ、母がお前のために受けた多くの苦難を思い出しなさい。
そして母が死んだら、同じ墓に、わたしの傍らに葬ってくれるように。
(4・3~4)
息子よ、日ごとに主を思い出しなさい。
お前は一生を通じて日々、正義を行い、決して不義の道を歩んではならない。
お前の持ち物で施しをしなさい。施しをするときには、物惜しげな眼をしてはならない。
どんな貧しい人に対しても顔を背けてはならない。
そうすれば、神もまたお前に対してみ顔を背けないであろう。
(4・5~7)
子よ、すべての行いに注意し、すべての振る舞いに節度を守りなさい。
お前自身が嫌うことを他人にしてはならない。
(4・14~15)
この箇所は、旧約聖書の中ではじめて愛の黄金律が表現されたものです。
新約では「何事につけ、人にしてもらいたいと思うことを、人にもしてあげなさい」(マタイ7・12)と、より積極的になっています。
これは、わたし自身いちばん大切にしている黄金律です。
このような教えを、わたしたちが子どもたちや若い世代にきちんと伝えることが出来ているでしょうか。
親を敬い、人のためになることをし、人が嫌がることをしないで、自分がしてもらいたいことを人にもする。
これができれば、特に「障害があるから」という理由で人に特別に優しくするのではなく、困っている人には手を差し伸べる、助けが必要な人に肩を貸す、ということになるのではないでしょうか。
イエス様がおっしゃったように、最も小さな人びとにしなかったことは、すなわちイエス様にしなかったことなのです。
今年の残りのひと月を、悔いのないように過ごすためにも、「障害のある人」「困っている人」「助けが必要な人」のことをもっと普通に考え、自分もいつか人の助けが必要な時が来ることも同時に考えて、残りの日々を行動してみましょう。
https://www.vaticannews.va/ja/pope/news/2023-11/intenzioni-preghiera-dicembre-2023.html
。。。。。。。。。。。。
信徒会館の防水塗装工事が終わり、こんなに綺麗になりました。
信徒のみなさまの維持費、献金がなければこのような大規模な補修工事はできません。
これからも、どうぞご協力をよろしくお願いいたします。
死者への愛
死者の月、皆さんも天に召された大切な人を想って過ごしておられるのでしょうか。
毎晩、寝る前の祈りの際に、「天国のみなさんを安らかに過ごさせてあげてください」ということばを唱えます。
わたしが神様にお願いしなくても全く大丈夫なことではあるのですが、母をはじめとする、周囲の大切だった人たちが天国でどのように過ごしているのかを想像するのです。
その人たちは、いまでもわたしにとって大切な人々なのです。
デンマークの哲学者、宗教思想家に、実存主義の創始者と言われるキェルケゴールという人がいます。(1813~1855年)
実存という言葉を、「今ここに私がいる」という意味で初めて用いました。
熱心なキリスト教徒でしたが、同時に、形式にこだわりすぎる当時のデンマーク教会への批判もしています。
彼は、人間の自己生成の段階を3つの段階によって説明したことでも知られています。
実存は深化してゆき、人間は最終的に宗教的実存に至る、と。
「宗教的実存」とは、神と一対一で向き合うことで本来の自分を取り戻す、ということです。
彼は、その著書『愛の業』のなかで、隣人には死者まで含めなければならないと言っています。
なぜなら、死者に対してわたしたちは明らかに義務をまた負っているからである。
もしわたしたちが現に見ている人々を愛するべきであるならば、わたしたちが見たことはあるが、死によって奪い去られたゆえに今はもう見ることのできない人々をもおそらくまた愛すべきであろう。
ひとは死者を嘆きやわめきによって煩わせてはならない。
義務を負う、とは、わたしたちは死者からの愛によって生きているということです。
さらに、こう言っています。
わたしたちが愛において死者を想うということはもっとも無私なる愛の行為である
わたしたちが愛において死者を想うということはもっとも自由な愛の行為である
わたしたちが愛において死者を想うということはもっとも信実な愛の行為である
キェルケゴールの思想は、一見かなり難解に思いますが、この文章は心にスッと入ってくる気がします。
毎年この季節には、マカバイ記のこの箇所を読みます。
ユダヤ人とアラビア人の戦いによって亡くなった戦死者が、罪の故に犠牲になったと知り、弔う場面です。
彼がこのように、最も善良で、崇高な心を持って行ったのは、復活について思い巡らしたからである。
もし彼が戦死者の復活することを希望しなかったら、死者のために祈るのは余計なことであり、愚かしいことであったろう。
だが、彼は敬虔な心をもって眠りに就いた人々のために備えられた、素晴らしい報いについて思い巡らしていた。
その思いは清く、敬虔であった。
彼が、死者のためにこの贖罪の捧げ物をささげたのは、彼らが罪から解かれるためであった。
(2マカバイ12・44〜46)
死者のために祈るということが無駄なことではない、という言葉は、母を亡くして悲しみに暮れていたわたしにとって大きな救いとなりました。
この箇所では、死者のために祈ることは彼らの罪を解くためですが、わたしが死者のために祈るのは、わたしの罪を赦してもらうためです。
天国で安らかに過ごしてほしい、そして、生前わたしが足りなかったところを赦してほしい、そう思って祈っています。
キェルケゴールの言うように、「ひとは死者を嘆きやわめきによって煩わせてはならない」というのはもっともです。
悲しみ続けることは、天に召された人々を心配させるだけです。
23日木曜日の朗読箇所は、まさに今のことを言い当てたかのようでした。
都に近づき、イエスは都をご覧になると、そのためにお泣きになって、仰せになった、「もしこの日、お前も平和をもたらす道が何であるかを知っていさえいたら・・・・・・。
しかし今は、それがお前の目には隠されている。いつか時が来て、敵が周囲に塁壁を築き、お前を取り囲んで、四方から押し迫る。そして、お前と、そこにいるお前の子らを打ち倒し、お前のうちに積み上げられた石を一つも残さないであろう。
それは、訪れの時を、お前が知らなかったからである」。
(ルカ19・41〜44)
聖書で「イエス様が泣いた」と記述されているのはここだけ、と以前教わりました。
西日本新聞11/20の朝刊に、姜尚中さん(東大名誉教教授)のコラムが掲載されていました。
パレスチナ人もユダヤ人も平和的に共存していた地で建国されたイスラエルは、事実上核武装する、サムエル記に登場するペリシテ人の巨人兵士ゴリアテのような国家になってしまった。
イスラエルの占領地に対するパレスチナ人の抵抗運動は、投石も含めた「石の闘い」と呼ばれた。
しかし、イスラエルの苛斂誅求から「石の闘い」の無力さが浮き彫りになり、やがてテロをいとわない過激な民族運動が台頭したとすれば、それは憎しみをエンジンとする暴力の連鎖を生み出したと言える。
*苛斂誅求(カレンチュウキュウ)=税などを容赦なく取り立てること。また、そのような酷い政治のこと。
イエス様が今生きておられたら、この現状に涙されるのではないかと想像しています。
わたしたち、人というのは、何千年経っても同じ過ちを繰り返しています。
他者を犠牲にして自分の主義主張を満たそうとする。
神様が嘆き、涙されている様子が浮かぶようです。
この死者の月の間は特に、イスラエルの紛争によって犠牲になった方々のためにも祈りましょう。